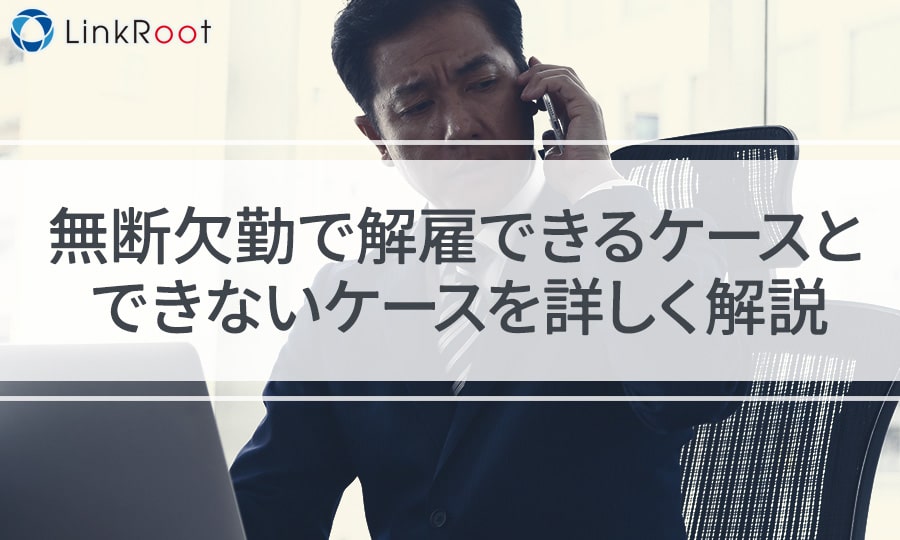無断欠勤は、チームワークの乱れや生産性の低下といった悪影響を与える行為です。そのため、企業側は適切に処分しなければなりません。とはいえ、簡単に解雇できるわけではないため注意が必要です。
解雇ができるかどうかは、無断欠勤の理由や従業員の反省状況などによって異なります。正しく判断しなければ不当解雇として訴えられる可能性もあるため注意しましょう。
この記事では、無断欠勤で解雇できるケース・できないケースや注意点について詳しく解説します。
無断欠勤とは?
無断欠勤とは、事前に連絡したり許可を得たりせずに、勝手に会社を休む行為のことです。法律などで明確に定義されているわけではありませんが、従業員には労働契約に従って働く義務があるため、無断欠勤をすると契約に違反することになります。
無断欠勤が発生すると、作業工程の遅れや生産性の低下、クライアントとの関係悪化など、さまざまな悪影響が生じます。そこで、無断欠勤に該当する行為や繰り返される場合の処分について就業規則に記載して、社内の秩序を維持している企業も多いでしょう。
従業員が無断欠勤する理由

従業員が無断欠勤する理由としては、以下のようなことが挙げられます。
- 遅刻や寝坊をしてしまったが叱責されるのを避けたい
- パワハラやセクハラなどが原因で出社を拒否している
- 精神疾患の影響により連絡できない
- 出勤中の事故や急病により出社できない
- 仕事や職場の雰囲気に適応できない
- 退職したいと考えており意図的に連絡していない
無断欠勤の理由は、従業員によって異なります。遅刻や寝坊など、従業員の自己都合の場合もありますが、出勤中の事故や急病といったやむを得ない事情があるかもしれません。一人暮らしの従業員の場合は、自宅で死亡している可能性もあります。
また、パワハラやセクハラなど、企業側に責任があるケースもあるため注意しなければなりません。従業員ごとの理由を明確にしたうえで、適切な対応を取ることが重要です。
無断欠勤を理由に解雇できる?
無断欠勤を理由に解雇できるかどうかは、状況によって異なります。解雇とは、企業側から一方的に労働契約を解除することです。普通解雇や懲戒解雇などの種類がありますが、どのような方法であっても従業員の生活に大きな影響を与える重い処分であるため、慎重に行わなければなりません。
一般的に、2週間以上の無断欠勤が続いており、繰り返し注意しても状況が改善されない場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、事前に就業規則に無断欠勤による解雇について記載しておく必要があり、正しい手続きを経て解雇しなければなりません。
逆に、パワハラやセクハラがあった場合や、長時間労働により精神疾患になった場合など、企業側に責任があるときは不当解雇と見なされる可能性もあります。
無断欠勤の理由を正確に把握したうえで、解雇するかどうかを判断することが大切です。
無断欠勤に対する基本的な対応方法
無断欠勤が発生した場合、まずは従業員へ連絡したうえで、適切な指導を行うことが重要です。指導や注意をしても状況が改善しないときは、解雇を検討しましょう。
以下、無断欠勤への対応方法を詳しく解説します。
1.従業員へ連絡する

従業員が無断欠勤をしたときは、すぐに電話連絡して状況を確認しましょう。前述のとおり、単純な寝坊が原因という場合もありますが、自宅で倒れていたり、事故で出社できない状態になっていたりする可能性もあります。
仮に従業員本人へ電話がつながらないときは、家族へ連絡することや自宅を訪問してみることも必要です。たとえば、出勤中に逮捕されたり緊急搬送されたりした場合、家族に連絡が入っているケースもあります。
また、自宅を訪問することで、急病で倒れている従業員を救える可能性もあるでしょう。
2.適切な指導を行う
無断欠勤の理由が判明したら、その内容に応じて適切な指導や注意を行いましょう。飲みすぎや夜更かしなど、従業員の自己管理に問題がある場合は、改善を促すことが大切です。
ほかの従業員やクライアントへ迷惑がかかること、就業規則のなかに無断欠勤に対する処分が記載されていることなどを伝え、反省を促します。
裁判などのトラブルが発生したときに備え、書面で指導を行って証拠を残すことも重要です。
一方でパワハラやセクハラ、人間関係による精神疾患や体調不良が原因の場合は、職場における事実関係を調査する必要があります。関係者から状況をヒアリングしたうえで、必要に応じて職場環境の改善や人事異動を検討しなければなりません。
また、パワハラやセクハラに関わった従業員が対応すると、無断欠勤を改善できないケースもあるため、人事担当者や別の同僚が対応しましょう。
3.解雇を検討する
適切な指導や対応を行っても無断欠勤が改善されないときは、解雇を検討します。ただし、いきなり解雇という重い処分を与えることは避けましょう。無断欠勤の理由や従業員の反省状況に合わせて、適切な処分を検討することが大切です。
以下のような段階的な処分を検討するとよいでしょう。
顛末書を提出させる
顛末書とは、無断欠勤に対する理由や詳しい状況を報告する書類のことです。従業員に書類を作成させることで、状況を客観的に理解させ、反省を促します。
軽い処分ではありますが、指導をした証拠としても役立つため、まずは顛末書を提出させるとよいでしょう。
出勤停止を命じる
繰り返し注意したり、顛末書を提出させたりしても状況が改善しない場合は、出勤停止を命じます。出勤停止を命じられた従業員は一定期間、仕事をすることができません。有給休暇とは異なり、出勤停止中は給与が発生しないため、比較的重い処分といえるでしょう。
減給を検討する
さらに重い処分として減給があります。減給とは一定期間、支給する給与を減らす処分のことです。出勤停止と同様、従業員の生活に大きな影響を与えるため、月給の10分の1以下まで、平均賃金1日分の半分以下まで、というルールがあります。
退職勧奨を行う
出勤停止や減給などの処分を行っても状況が改善しない場合、退職勧奨を実施します。退職勧奨とは、従業員に対して自主的な退職を促すことです。
企業と従業員で話し合い、双方が合意すれば退職が成り立ちます。ただし、退職を強要するとトラブルに発展するため注意しなければなりません。
以上のような段階的な処分を行ってから解雇を検討することで、解雇の正当性が認められやすくなります。適切な対応をせずにいきなり解雇すると、不当解雇と見なされる可能性もあるため注意しましょう。
無断欠勤による解雇が認められるケース
無断欠勤による解雇が認められるかどうかは、状況によって異なります。一般的に次のような要件を満たしている場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。
- 事前に就業規則に記載している
- 2週間以上の無断欠勤が続いている
- 無断欠勤を証明できる証拠がある
それぞれの要件について詳しく解説します。
1.事前に就業規則に記載している

無断欠勤を理由として従業員を解雇するためには、事前に就業規則に記載しておかなければなりません。無断欠勤を含め、どのような行為に対して解雇という処分が適用されるのか、解雇事由を具体的に定めておく必要があります。
基本的に従業員を10人以上雇い入れる場合は、就業規則を作成したうえで、労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、就業規則の内容を従業員へ周知し、いつでも確認できる状態にしておくことも大切です。
2.2週間以上の無断欠勤が続いている
目安として、正当な理由もなく2週間以上の無断欠勤が続いている場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。また、国家公務員については、21日以上勤務を欠いた場合は免職または停職とすると、人事院が規定しています。(※1)
仮に、就業規則のなかで「1週間の無断欠勤により解雇とする」などと厳しいルールを定めたとしても、短すぎる場合は解雇が認められないケースもあります。
3.無断欠勤を証明できる証拠がある
無断欠勤による解雇を行うときは、証拠を残しておくことが重要です。タイムカードや出勤簿、勤怠管理システムのデータなど、無断欠勤であることを客観的に示せるものを残しておきましょう。
さらに、従業員に提出させた顛末書、適切な指導を行ったことを示す書類、注意したときの議事録などを残しておくと、適切な手順で解雇を行った証明につながります。客観的な証拠が不足していると、従業員から訴えられた際に不利になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
無断欠勤による解雇が不当解雇になるケース
職場でハラスメントがあった場合や、長時間労働による精神疾患で出勤できない場合に解雇すると、無効と判断される可能性があります。
ここでは、不当解雇と見なされるケースについて確認しておきましょう。
1.会社でハラスメントなどがあった場合

パワハラやセクハラ、嫌がらせやいじめが原因で無断欠勤をしている場合、解雇することは認められにくいでしょう。無断欠勤の原因が企業側にあるからです。
企業は労働施策総合推進法に従ってパワハラや嫌がらせを防止し、働きやすい職場環境を整えなければなりません。パワハラなどが原因の無断欠勤が発生している場合は、従業員本人や関係者から事情を聞き、状況を改善するように努める必要があります。
2.長時間労働が原因である場合
長時間労働による疲労や体調不良が原因で無断欠勤をしている場合も、解雇は認められないでしょう。企業は法定労働時間や時間外労働の上限を守りながら、業務を指示しなければなりません。
仮に法律の範囲内であったとしても、過剰な残業が発生していたり、業務の偏りがあったりする場合は、人材の確保や業務の再配分によって長時間労働を是正する必要があります。
無断欠勤を従業員の責任と決めつけるのではなく、職場環境の改善により解決することも考えましょう。
3.精神疾患が原因である場合
精神疾患による無断欠勤には慎重に対応しなければなりません。うつ病や適応障害などの場合は、会社に連絡すること自体が難しいケースもあるからです。職場環境が原因による精神疾患も考えられます。
精神疾患が疑われる場合は、病院へ行くことを打診する、診断書を提出してもらうなど、従業員の心身の健康を維持できるような対応をすることが重要です。
また、いきなり解雇を検討するのではなく、休職させて様子を見るなど、他の方法も検討しましょう。適切な手順で解雇を行わないと、不当解雇と見なされる可能性もあります。
無断欠勤により解雇するときの流れ
無断欠勤により解雇するときの流れは以下のとおりです。
- 出社を促す
- 解雇予告をする
- 解雇通知書を送付する
以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
1.出社を促す
無断欠勤に対する正当な理由が見つからず、繰り返し指導しても改善されないときは出社命令を出しましょう。従業員へ電話やメールで連絡して出社を促します。
連絡が取れない場合は、書面を内容証明郵便で送ることも有効です。内容証明郵便を活用すれば、いつ誰がどのような内容を送ったのか、記録を残すことができ、裁判時の証拠としても役立ちます。
本人と連絡が取れた場合は、無断欠勤の理由や本人の言い分をヒアリングしたうえで解雇するかどうかを決定しましょう。
2.解雇予告をする
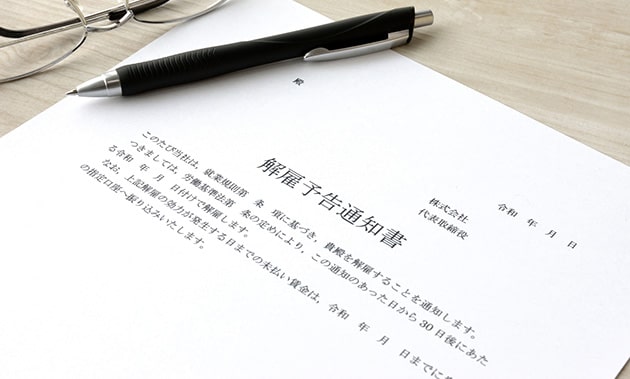
従業員を解雇するときは、解雇予告をしなければなりません。解雇予告とは、事前に解雇する日時を伝えることです。
基本的には、解雇する日の30日前までに解雇予告をする必要があります。30日を待たずして解雇するときは、解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当は、平均賃金×30日で算出できます。
また、労働基準監督署へ申請して解雇予告除外認定を受けることで、解雇予告が不要となります。ただし、従業員側に責任がある場合や行為が悪質な場合など、一部のケースに限定されているため、事前に労働基準監督署へ相談しておくとよいでしょう。
3.解雇通知書を送付する
解雇予告から一定期間が経ったら、解雇通知書を送付しましょう。解雇通知書には、従業員名や解雇の日時、解雇する理由などを明記する必要があります。口頭での解雇通知も認められてはいますが、証拠を残すためにも書面で交付することが重要です。
郵送する場合は、内容証明郵便で送りましょう。解雇通知書は従業員へ確実に届ける必要があるからです。本人が受け取ったことを証明できるような方法で送るようにしましょう。
無断欠勤した従業員を解雇するときの注意点
無断欠勤した従業員を解雇するときは、以下のような点に注意しましょう。
1.解雇事由が正当か検討する

解雇を検討するときは、解雇事由が正当かどうかを慎重に判断しなければなりません。解雇は減給や出勤停止よりも重い処分であるため、単純に無断欠勤をしているだけでは、解雇が認められない可能性もあります。
2週間以上の無断欠勤が続いており、注意をしても改善されないなど、正当性が認められる場合にのみ解雇が可能です。逆に、長時間労働による体調不良やハラスメントなどが原因の場合、不当解雇と見なされる可能性が高いため注意しましょう。
2.解雇以外の選択肢も含めて検討する
解雇は最も重い処分であるため、それ以外の選択肢を検討することも大切です。まずは簡単な注意や指導から行い、顛末書の提出や出勤停止、減給など、状況に応じて少しずつ重い処分を与えていきましょう。
指導をせずにいきなり解雇したり、状況に合わないような重い罰則を与えたりすると、処分が無効となるケースもあります。
3.必要に応じて専門家に相談する
判断に悩むときは、専門家に相談するのもおすすめです。無断欠勤による解雇が有効かどうかは、解雇事由の正当性はもちろん、過去の判例なども含めて総合的に判断されます。
法律や裁判に関する専門知識が必要となるため、社内の担当者だけで判断するのが難しいケースもあるでしょう。不当解雇によるトラブルを避けるためにも、必要に応じて弁護士などに相談することが重要です。
無断欠勤による解雇は慎重に判断しよう!
今回は、無断欠勤した従業員を解雇するときのポイントや注意点について解説しました。従業員が無断欠勤をすると、生産性の低下やクライアントとの関係悪化など、さまざまな悪影響が発生します。しかし、正当な理由なく簡単に従業員を解雇することはできません。
2週間以上の無断欠勤が続いている、繰り返し注意や指導をしても状況が改善されないなど、正当性が認められる場合に限って解雇が認められます。
職場におけるハラスメントや長時間労働による精神疾患など、無断欠勤の原因が企業側にある場合は、不当解雇として訴えられる可能性もあるため注意しましょう。