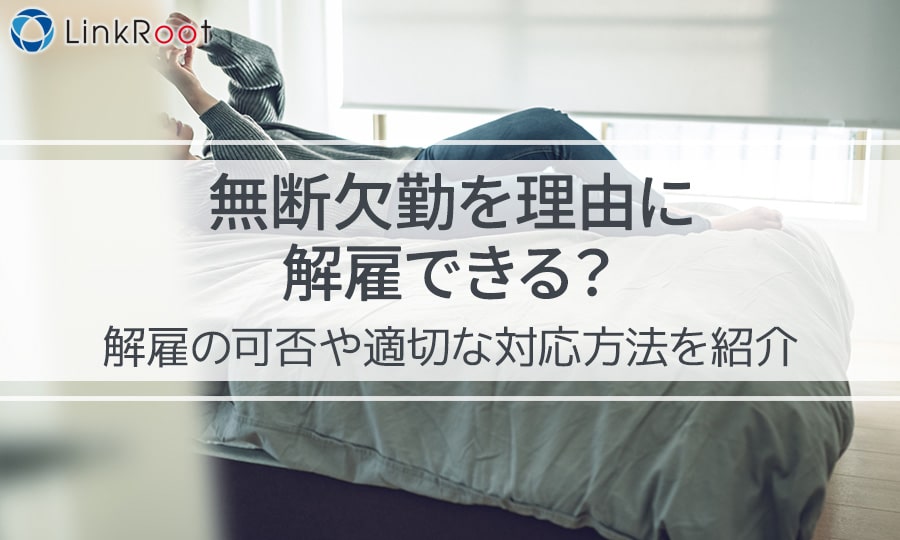無断欠勤を理由として従業員を解雇するときは、慎重に手続きを進めなければなりません。欠勤が多いからといって、必ず解雇が認められるとは限らないからです。
解雇の正当性については、無断欠勤の原因や就業規則の内容などによって異なるため注意しましょう。
この記事では、無断欠勤を理由とした解雇の可否や、欠勤が多い従業員への対応方法について詳しく解説します。欠勤を理由とした解雇を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
欠勤が多いことを理由に解雇できる?

頻繁に欠勤する従業員がいると、担当している仕事が進まなくなったり、真面目に働いている従業員が不満を感じたりするため、解雇を検討するケースもあるでしょう。ただし、解雇が可能なケースもある一方で、正当な理由のない解雇は無効となり、さまざまなトラブルにつながる可能性があるため注意しなければなりません。
ここでは、欠勤を理由とした解雇が難しいことや、解雇が可能となる事例を紹介します。
欠勤が多いだけで解雇することは難しい
欠勤が多いからといって、従業員を簡単に解雇することはできません。民法の第627条によると、期間の定めのない雇用契約を締結している場合、企業側から契約解除の申し入れをすることが可能で、申し入れから2週間が経過すると雇用契約は終了します。
しかし、解雇は従業員に対する重い処分であるため、労働基準法や労働契約法によって厳しく制限されています。
正当な理由のない解雇は無効となる
労働契約法の第16条によると、従業員を解雇するためには客観的に合理的な理由が必要です。また、社会通念上相当であることも求められます。
つまり、欠勤が多いというだけで解雇という重い処分を与えることは、社会通念上相当ではないと見なされ、処分が無効となる可能性もあるのです。
解雇の権利を濫用したとして処分が無効になると、従業員が戻ってくるだけではなく、未払いの賃金を請求されたり、企業のイメージが低下したりするため注意しましょう。
また、従業員を解雇するときは、労働基準法の第20条に従って、30日以上前に解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払わなければなりません。正しい手順で解雇手続きを進めなければ、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
まずは適切な指導を行う必要がある
頻繁に欠勤する従業員がいるときは、まずは適切な指導を行う必要があります。従業員本人や関係者から欠勤の理由をヒアリングし、本人に問題がある場合は注意や指導を行いましょう。
解雇に該当するような理由があったとしても、いきなり解雇することは難しく、注意や指導から始めるのが基本です。懲戒処分を行うときでも、戒告やけん責といった軽い処分から検討していきましょう。適切な処分を繰り返し与えることで、最終的に解雇をするとなったときに、正当性が認められやすくなります。
逆に、過剰な長時間労働やハラスメントなど、欠勤の原因が会社側にある場合は職場環境を改善しなければなりません。
欠勤した日の賃金を支払う必要はない
従業員が欠勤した日については、賃金を支払う必要はありません。ノーワーク・ノーペイの原則により、労働の対価としての賃金が発生しないと考えられるからです。欠勤日数に応じて、賃金を減らして支払うようにしましょう。
ただし、従業員が有給休暇を取得している場合は、賃金を支払わなければなりません。また、傷病休暇などの会社の制度を利用して休んでいる場合は、就業規則に従って賃金を支払う必要があります。
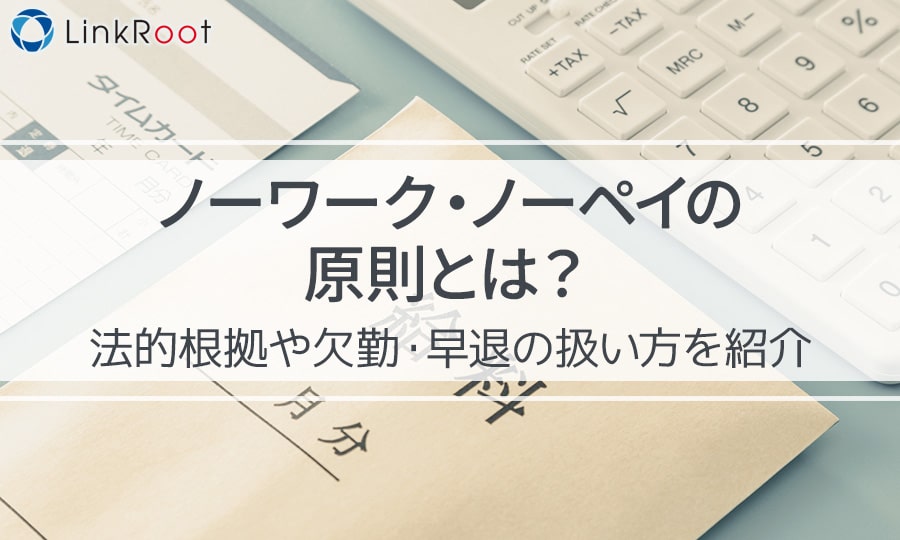
解雇が可能なケースもある

ここまで、欠勤を理由とした解雇が難しいことを紹介しましたが、解雇が可能なケースもあります。
以下のような条件を満たしている場合は、正当な解雇であると認められる可能性が高いでしょう。
- 正当な理由のない欠勤が頻発している
- 欠勤の原因が会社側にない
- 適切な注意や指導を繰り返し行っている
- 戒告やけん責などの処分を与えても状況が改善されない
- 就業規則に欠勤を理由とした解雇について記載されている
解雇の正当性については、さまざまな事柄を含めて総合的に判断されます。簡単に認められるわけではないため、適切な対応を行い、その証拠を残しておくことが大切です。
欠勤が多いときに考えられる理由
従業員の欠勤が多い理由としては、以下のようなことが考えられます。ヒアリングなどを通して、欠勤の理由を明確にしたうえで適切な対応を選択しましょう。
1.体調不良
体調不良を理由として、欠勤を繰り返す従業員もいるでしょう。風邪などで数日間休む程度であれば問題ありませんが、欠勤が頻発すると業務に支障が出たり、他の従業員の負担が増えたりしてしまいます。
体調不良で継続的に働けない状態の場合は、病院を受診してもらい、医師が作成する診断書を提出してもらうことが大切です。就業規則のなかに休職の規定があれば、ルールに従って休ませることも検討しましょう。
2.精神疾患

うつ病などの精神疾患により、欠勤を繰り返す従業員もいます。一人暮らしの従業員の場合、自分で会社へ連絡することすら難しく、結果として無断欠勤になってしまうケースもあるかもしれません。
精神的な症状は外から見えにくいため、単に怠けていると思われがちですが、放置しておくと症状が悪化して、取り返しのつかない状況になる可能性もあるため注意が必要です。精神疾患が疑われる場合は無理に働かせるのは避け、早めに病院を受診させるようにしましょう。
3.家庭の事情
介護や育児など、家庭の事情により欠勤が多くなってしまうケースもあるでしょう。他に対応できる家族がおらず、子どもが病気になったときや親の世話をするときなどに自分が対応しなければならない、という従業員もいるかもしれません。
必要に応じて業務を再配分する、在宅勤務を取り入れる、就業規則に従って特別休暇を利用させるなど、できる限り働き続けられるよう配慮しましょう。
4.職場環境
職場環境が原因で欠勤する従業員もいるかもしれません。ハラスメントやいじめなど、職場環境が原因のときは、まずは事実関係を確認する必要があります。従業員側の問題ではない場合、欠勤したからといって解雇することはできず、職場環境を改善しなければなりません。
また、長時間労働やハラスメントなどによる体調不良で休業する場合、休業期間中はもちろん、その後の30日間は解雇が禁止されています。無理に解雇すると、労働基準法違反として罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。
無断欠勤が多い従業員への対応方法
無断欠勤が多い従業員がいる場合は、理由を把握したり、適切な指導を行ったりすることが大切です。無断欠勤が多いからといって、すぐに解雇すると処分が無効となる可能性もあるため注意しましょう。以下、無断欠勤が多い従業員への対応方法を詳しく解説します。
1.無断欠勤の理由を聞く

まずは従業員本人から、無断欠勤の理由を聞く必要があります。体調不良や精神疾患など、連絡せずに休んでしまった理由を明確にしておくことが重要です。欠勤の原因が会社側にあるのかどうかも聞いておきましょう。必要に応じて、上司や同じ部署の同僚にヒアリングしておくことも大切です。
従業員本人と連絡が取れない場合は、家族へ連絡したり、近くに住んでいる同僚に訪問してもらったりするとよいでしょう。一人暮らしの従業員の場合、自宅で倒れている可能性もあるため、長期間連絡が取れないときは注意が必要です。
2.正当な理由がない場合は適切な指導を行う
単なる寝不足ややる気がないなど、正当な理由がない場合は、適切な注意や指導を行いましょう。生活習慣の見直しが必要なときは、産業医に相談して協力してもらうのもおすすめです。
また、注意や指導の方法に明確なルールはないため、口頭で行っても問題ありませんが、適切に行ったという証拠を残すために書面やメールで注意するとよいでしょう。
3.必要に応じて休職させる<
休職制度を設けている場合は、就業規則に記載された内容に従って休職させましょう。休職させるかどうかの判断に迷うときは、診断書を提出してもらい、医師の指示に従うことが重要です。
ただし、休職制度を設けることは義務ではないため、制度の有無や休職可能な期間などは企業によって異なります。休職させる場合は、社内のルールをしっかりと確認しておきましょう。休職期間が満了したら、復職できるかどうかを検討します。
4.退職勧奨をする
休職期間が満了しても復職できない場合は、解雇を検討することになります。ただし、いきなり解雇するのではなく、退職勧奨を検討するとよいでしょう。退職勧奨とは、会社と従業員で話し合いを行い、納得したうえで退職届を提出してもらうことです。
一方的に解雇するのとは異なり、合意のうえで退職してもらえるため、不当解雇などのトラブル防止につながります。とはいえ、退職届の提出を強制することはできません。働けないことを双方で確認し、自主的に退職を考えてもらうことが大切です。
5.解雇を検討する
退職勧奨に応じてもらえない場合は、解雇を検討することになるでしょう。解雇を行う場合は、就業規則を確認する必要があります。「休職期間満了時に復職できない場合は解雇する」といった規定がある場合は、ルールに従って解雇できる可能性が高いでしょう。
また、普通解雇の事由として「正当な理由のない欠勤を○回以上行った場合」などの記載があれば、基本的には解雇することが可能です。ただし、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇が無効となるため注意しましょう。
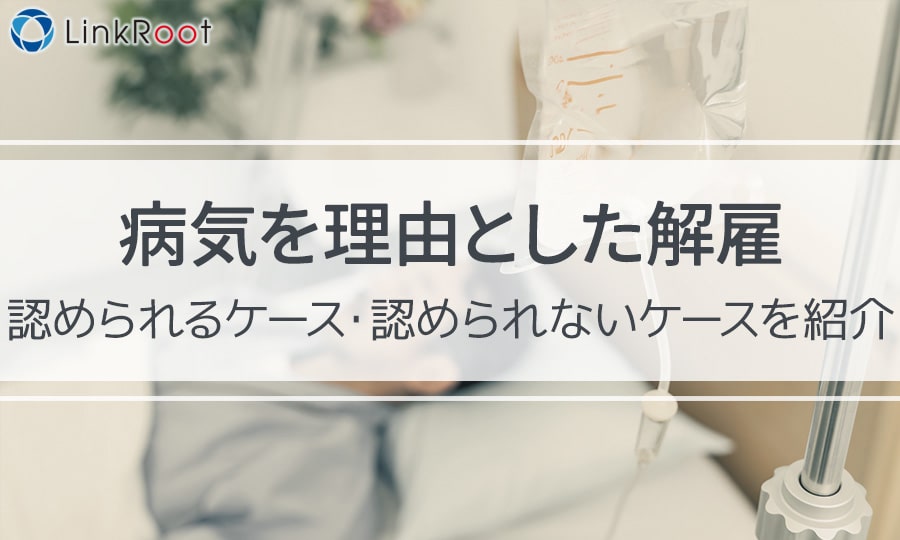
無断欠勤が多い従業員を解雇するときの注意点
無断欠勤が多い従業員を解雇するときは、以下のような点に注意しましょう。
1.無断欠勤でも解雇できない場合がある
無断欠勤の理由や原因、就業規則の内容によっては、解雇が認められない可能性もあります。
具体的には以下のようなケースにおいて、解雇ができないため確認しておきましょう。
- 無断欠勤の原因が会社側にある場合
- 無断欠勤に対する適切な注意や指導を行っていない
- 無断欠勤を理由とした解雇について就業規則に記載されていない
まずは無断欠勤の理由や就業規則の内容を確認し、解雇の可否を検討することが重要です。
2.無断欠勤の証拠が必要となる

無断欠勤を理由に解雇する場合、従業員が無断欠勤をしていたことを示す客観的な証拠を残しておかなければなりません。たとえば、タイムカードや出勤簿、勤怠管理システムのデータなどを残しておくことが重要です。
証拠がないと、裁判で会社側が不利になる可能性もあります。本当に従業員が無断欠勤をしていたとしても、それを立証できないと敗訴するケースもあるため、証拠をしっかりと残しておきましょう。また、適切な注意や指導を行ったという証拠を残しておくことも大切です。
3.適切に解雇通知を行う
従業員が無断欠勤している場合でも、解雇通知書を確実に届けなければなりません。従業員が解雇通知を受け取ったことを証明できなかったり、送付したのに返送されてしまったりした場合、解雇通知が成立していないと見なされる可能性もあります。
従業員が会社に来ないときは、解雇通知書が届いたことを証明するため、内容証明郵便で送るとよいでしょう。
4.判断に悩むときは弁護士に相談する
無断欠勤を理由とした解雇が可能かどうかの判断に悩むときは、弁護士に相談するのがおすすめです。ここまで解説したとおり、無断欠勤を理由とした解雇が認められるかどうかは状況によって異なります。無断欠勤の理由や就業規則の内容、対応方法などによって解雇の可否は変わるため、労務関係に強い弁護士に相談しておくと安心です。
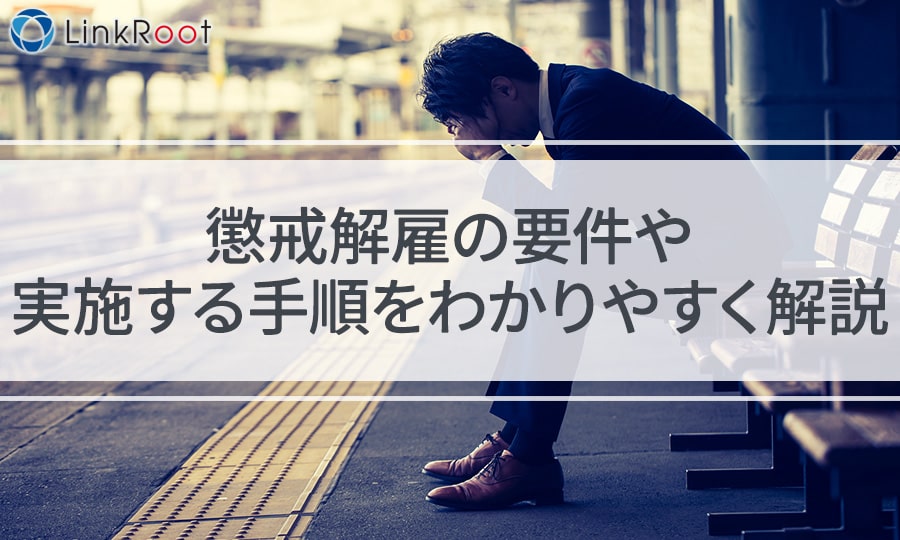
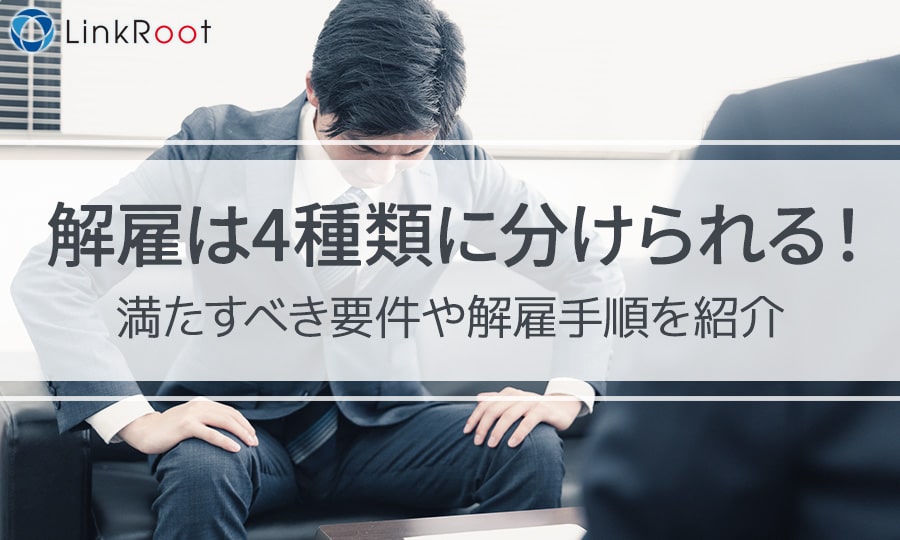
無断欠勤を理由とした解雇は慎重に進めよう!
今回は、無断欠勤を理由とした解雇の可否や、解雇を行うときの注意点などについて解説しました。解雇が認められるケースもありますが、無断欠勤の原因が会社側にある場合や、無断欠勤を理由とした解雇について就業規則に記載されていない場合は、原則として解雇できません。
また、解雇を進める場合は、適切なタイミングで解雇予告を行うことや、確実に解雇通知書を送付することが重要です。正しい手順で解雇の手続きを進めないと、処分が無効となる可能性もあるため注意しましょう。