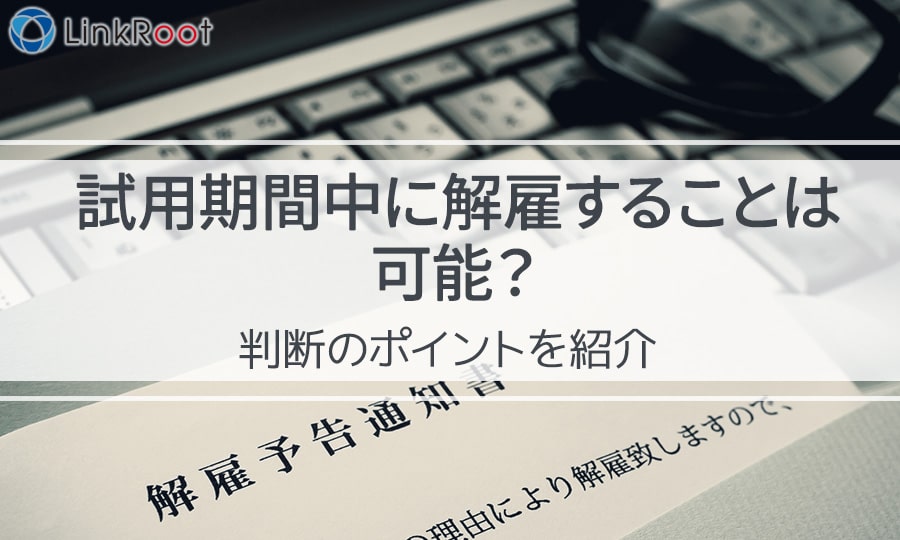試用期間のなかで従業員のスキルや人柄を見て、本採用を見送りたいと考えるケースもあるでしょう。ただ、試用期間だからといって簡単に解雇できるわけではありません。合理的な理由もなく解雇すると、不当解雇と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
そこでこの記事では、試用期間中に解雇することは可能なのか、解雇する場合の注意点や手順についてわかりやすく解説します。試用期間中の解雇を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
試用期間とは?途中で解雇することは可能?

試用期間とは、新しく入社した従業員に対して具体的な仕事を与え、スキルや適性を確認する期間のことです。研修的な業務を与えることもあれば、より実務に近い難易度の業務を担当させることもあるでしょう。
履歴書の確認や面接など、短い選考プロセスのなかだけで、従業員の本当の能力を見極めるのは簡単ではありません。そこで数ヶ月程度の試用期間を設け、本当に採用するかどうかを判断することが重要視されているのです。
試用期間を設ける法的な義務はなく、企業が自由に決定できます。試用期間を設ける場合は1~6ヶ月として、就業規則のなかに記載しておくのが一般的です。
以下、試用期間中の解雇について詳しく見ていきましょう。
試用期間中でも労働契約は成立しているが解雇は可能
試用期間中であっても労働契約は成立していると見なされます。解約権留保付労働契約と呼ばれ、企業側が契約を解除できる権利を持っている状態です。
試用期間は、従業員の実践的なスキルや仕事への適性を見極めるためのものであるため、従業員に何らかの問題があると判断した場合は契約を解除できます。ただし、どのような理由でも解雇が認められるわけではありません。
また、試用期間中の契約条件は、企業によってさまざまです。給与や労働時間などの契約条件について、本採用と同じにするケースと、給与を低くするなどの差をつけるケースがあります。特例許可申請を行えば、最低賃金の最大20%まで給与を減額することも可能です。特例許可申請は各都道府県の労働局長に対して行いましょう。(※1)
(※1)厚生労働省「最低賃金の減額の特例許可申請について」p1
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000785226.pdf
試用期間中の解雇には要注意
試用期間中の従業員を解雇することは可能ですが、正当な理由がなければ権利を濫用した不当解雇と見なされるため注意しなければなりません。正当な理由としては、病気やケガで継続的な勤務が不可能となった、繰り返し注意したにもかかわらず勤務態度が改善されない、といったことが挙げられます。
逆に、適切な指導を行っていない場合や、従業員側の言い分を聞いていない場合は、不当解雇に当たる可能性もあります。試用期間中の解雇が認められるケース・認められないケースについては、後ほど詳しく解説します。
通常の解雇よりはハードルが低い
試用期間中の解雇には正当な理由が求められるものの、通常の解雇ほどハードルは高くありません。前述のとおり解約権留保付労働契約を結んでいることから、能力が不足している、勤務態度が悪いなどの理由による解雇も認められる可能性が高いでしょう。
ただし通常の解雇と同様に、客観的で合理的な解雇理由を明確にして、正しい手順で解雇しなければ権利の濫用と判断されることもあります。試用期間だからといって自由に解雇できるわけではないことを覚えておきましょう。
試用期間中の従業員を解雇するときの2つの方法

解雇の方法としては、試用期間中の解雇と本採用拒否の2つがあります。意味や認められやすさはそれぞれ異なるため、状況に合った解雇方法を選択することが大切です。
以下、2つの方法の違いについて確認しておきましょう。
1.試用期間中の解雇
試用期間中の解雇とは、言葉のとおり、試用期間の途中で労働契約を解除することです。たとえば、6ヶ月の試用期間を設定している企業において、仕事を開始してから3ヶ月目に労働契約を解除する場合は、試用期間中の解雇に該当します。
2.本採用拒否
本採用拒否とは、試用期間が終わったタイミングで労働契約を解除することです。たとえば6ヶ月の試用期間がある企業において、仕事開始から6ヶ月後に労働契約を解除することは本採用拒否に当たります。「拒否」という言葉が使われていますが「解雇」と見なされるため、正当な理由がなければ認められません。
2つの方法を比較すると、本採用拒否のほうが認められる可能性は高いでしょう。試用期間は従業員の能力や適性を確認するための期間であり、その途中で解雇してしまうことは、試用期間の目的に反するからです。
基本的には試用期間のなかで従業員のスキルをしっかりと見極め、期間終了時に解雇するかどうかを判断しましょう。
ただし、学歴や職歴に関する重大な詐称が発覚した場合や、企業に大きな損害を与えた場合などは、試用期間中であっても解雇が認められます。
試用期間中の解雇が認められる理由
前述のとおり、試用期間中だからといって自由に解雇できるわけではありません。正当な理由を示さなければ従業員とのトラブルが発生したり、不当解雇として訴えられたりする可能性もあります。
解雇が認められるためには、次のような理由が必要です。
- 従業員の能力が不足している
- 勤務態度が悪い
- 病気やケガで勤務できない
- チーム内での協調性がない
- 経歴詐称をしている
上記のような解雇理由は就業規則に記載しておく必要があり、従業員の求めに応じて解雇理由証明書を発行しなければなりません。
以下、それぞれの解雇理由について詳しく見ていきましょう。
1.従業員の能力が不足している

従業員の能力が不足している場合や、期待していたほどの成果を出してくれない場合は、解雇を検討することになるでしょう。適切なサポートをしたものの、能力が向上しないときは、試用期間中の解雇が認められます。
ただし、企業側の指導や注意が不足している場合は、不当解雇に当たる可能性もあります。入社してすぐに能力を発揮できるとは限らないからです。とくに新卒社員や未経験歓迎などとして募集した従業員は、能力不足が前提となっているため、簡単に解雇することはできません。
継続的に指導したにもかかわらず改善されず、能力不足が許容範囲を超えている場合にのみ、試用期間中の解雇が認められます。
一方、中途採用や経験者の場合は、ある程度の即戦力を期待できるため、新卒社員よりは能力不足を理由とした解雇が認められやすいでしょう。とはいえ、仕事内容やルールは企業によって異なるため、適切なサポートを行わずに解雇することは不当解雇と見なされます。
2.勤務態度が悪い
勤務態度が悪いことも解雇を検討する理由のひとつです。仕事に対するやる気が見られない、正当な理由のない欠勤や遅刻が多いなど、勤務態度が悪い場合は試用期間中の解雇が認められるでしょう。
ただし、1〜2回の遅刻程度で簡単に解雇することはできません。また能力不足と同様、企業側が注意や教育を行っていない場合は、解雇が認められない可能性もあります。申告しにくい体調不良などで遅刻をしているケースもあるため、従業員の話を聞いてみることも重要です。
繰り返し指導したにもかかわらず勤務態度が改善されない場合にのみ、解雇が認められます。
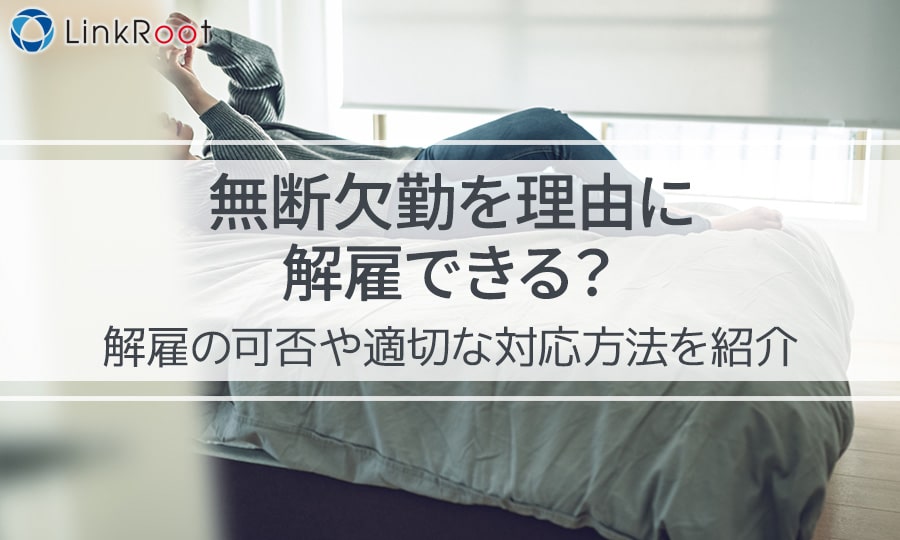
3.病気やケガで勤務できない

病気やケガで継続的な勤務ができない場合、状況によっては正当な解雇理由として認められます。当然ですが、数回の病欠やケガによる欠勤を理由として解雇することはできません。
次のようなポイントで、解雇できるかどうかを判断しましょう。
(1)病気やケガが仕事と関係している場合
仕事が原因で働けない状況となった場合は、療養期間を与える必要があり、その期間中と期間終了後30日間は解雇することが認められません。(※2)たとえば、仕事中の接触事故により骨折した、通勤中に交通事故に遭った、過労が原因でうつ病になった場合などは、休養期間を与えて復帰を待つ必要があります。
休養することで復帰できると医師が判断している場合に解雇すると、不当解雇と見なされるでしょう。休養しても復帰が困難な場合や、負担の少ない業務に変更しても継続的な勤務が難しい場合にのみ、解雇が認められます。
(※2)e-Gov法令検索「労働基準法」第十九条
(2)病気やケガが仕事と関係していない場合
病気やケガが仕事と関係していない場合は、就業規則に従うことが重要です。就業規則のなかに休職や休養に関する項目がある場合は、記載内容に従って休ませる必要があります。試用期間中だからといって安易に解雇せず、休職させたうえで雇用を継続するかどうかを判断しましょう。
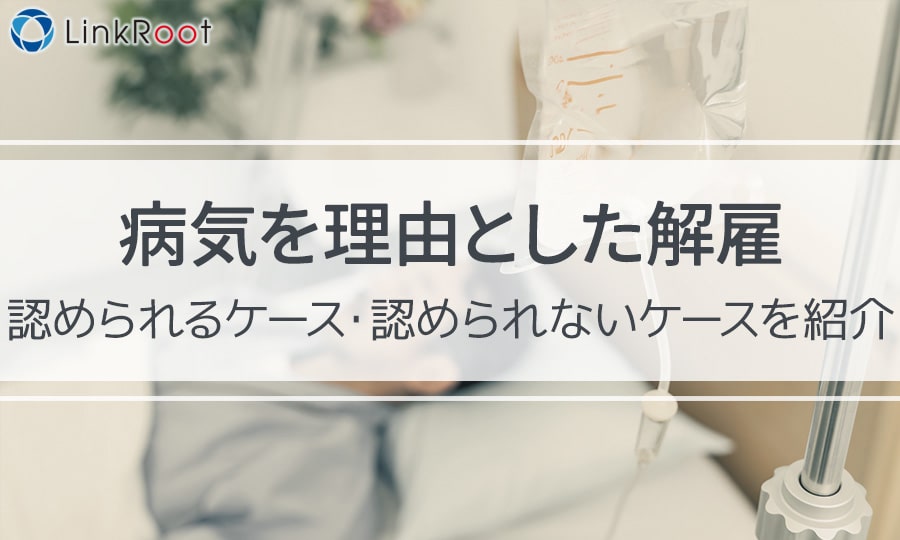
4.チーム内での協調性がない
仕事を進めるうえでは上司や部下、同僚とコミュニケーションを取りながら協力する必要があるため、極端に協調性がない場合は解雇を検討することになります。
ただし、能力不足や勤怠不良と同様、少し反抗的な態度だった、同僚との会話が少ない、といった程度で解雇することは認められません。指導したにもかかわらず状況が改善されない場合や、協調性がないことで重大なトラブルが発生している場合にのみ解雇が認められます。
5.経歴詐称をしている
経歴詐称も解雇を検討する理由のひとつです。学歴や職歴、資格取得などに関する嘘の申告が発覚し、事前に詐称を知っていれば採用していなかった場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、業務に大きな影響を及ぼさない場合や、採用・不採用の判断には関係なかった場合は、仮に詐称があったとしても解雇が認められないこともあります。たとえば、学歴の詐称があったとしても、そもそも学歴不問として求人を出していた場合は、解雇ができないケースもあります。
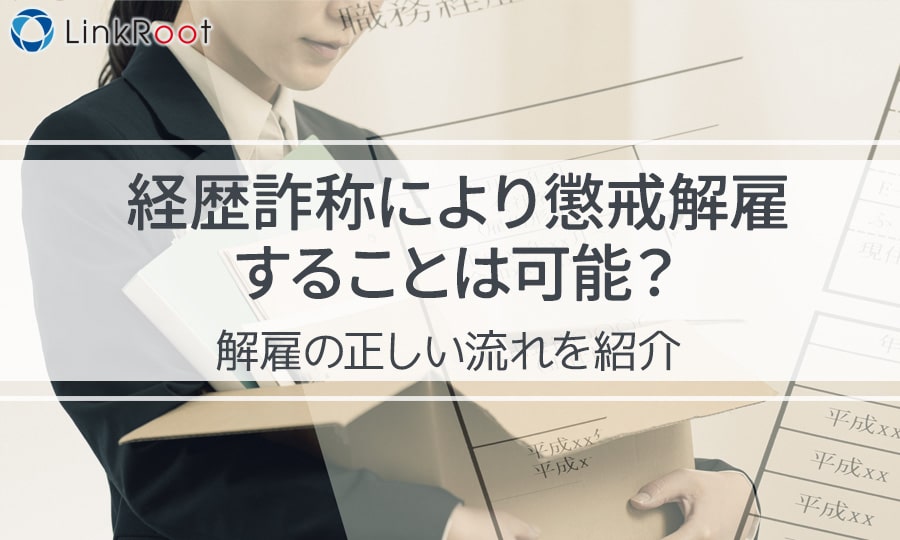
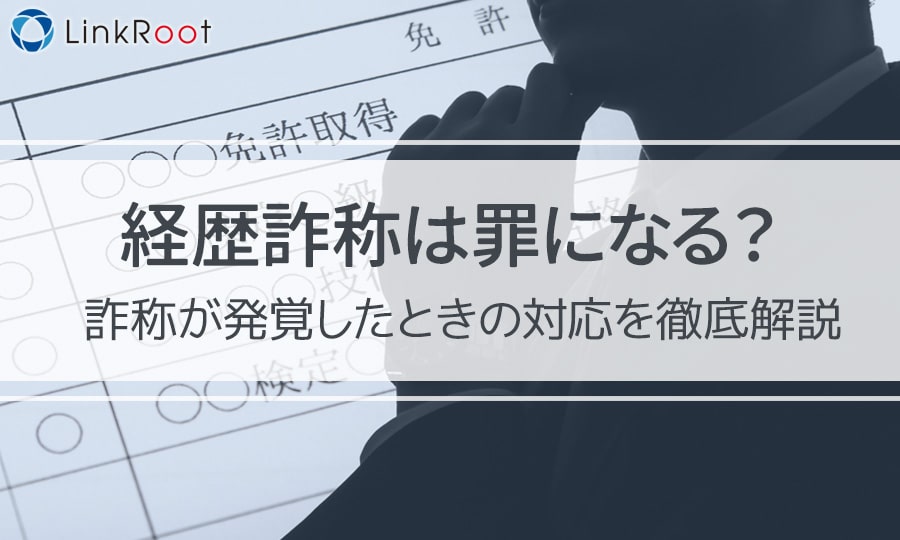
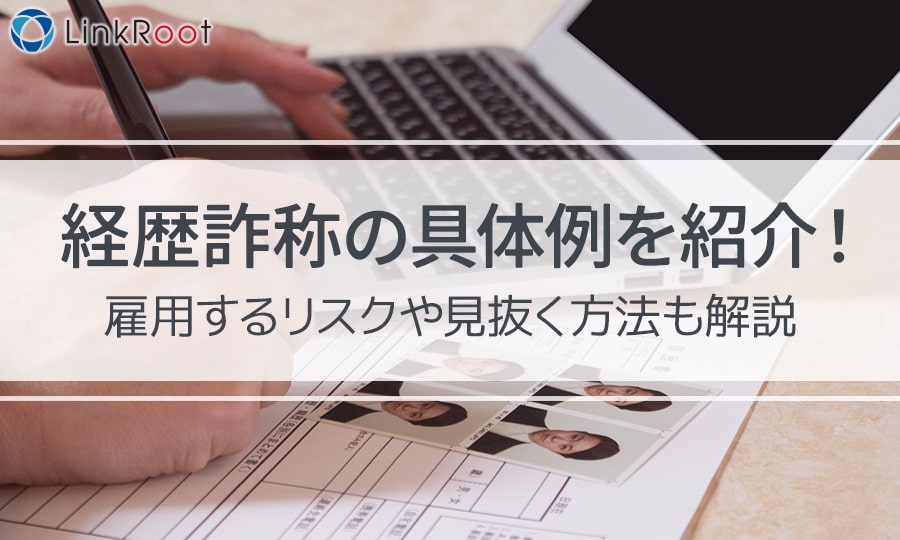
試用期間中の解雇が不当解雇に当たるケース
試用期間中の解雇は通常の解雇より認められやすいのですが、権利の濫用として不当解雇と見なされるケースもあります。以下のような場合は、不当解雇に当たる可能性があるため注意しましょう。
1.適切な指導を行っていないケース

適切な指導を行っていない場合は、不当解雇と見なされる可能性があります。能力不足や勤怠不良など、何らかの問題がある場合は指導や注意を行い、改善の機会を与えなければなりません。
口頭で行うことも可能ですが、書面での指導や注意も有効です。証拠を残すことにもつながるため、正当な理由のない遅刻や欠勤が多い、勤務態度が悪いなどの問題があるときは書面での指導を検討しましょう。
2.新卒採用者に対するサポートが不足しているケース
社会人経験のない新卒採用者は、当然、仕事をこなす能力が不足しています。まずは必要なサポートを行い、成長の機会を与えなければなりません。必要な教育や研修を実施せずに解雇することは、不当解雇と見なされる可能性が高いため注意しましょう。
また、能力不足で解雇を検討する場合は、客観的な数値で比較するなど、できる限り主観的な判断を避けることが大切です。
3.従業員側の言い分を聞いていないケース
試用期間中に解雇するときは、従業員の言い分をしっかりとヒアリングしましょう。従業員が何らかの事情を抱えているかもしれません。言い分を聞かずに解雇するとトラブルにつながったり、不当解雇として訴えられたりする可能性もあるため注意が必要です。
4.解雇予告を行っていないケース
試用期間がスタートしてから14日以上働いている場合は、解雇予告をしなければなりません。解雇予告とは、労働契約を解除する旨を事前に伝えることです。解雇予告は、30日以上前に行う必要があります。すぐに解雇したい場合は、平均賃金×30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
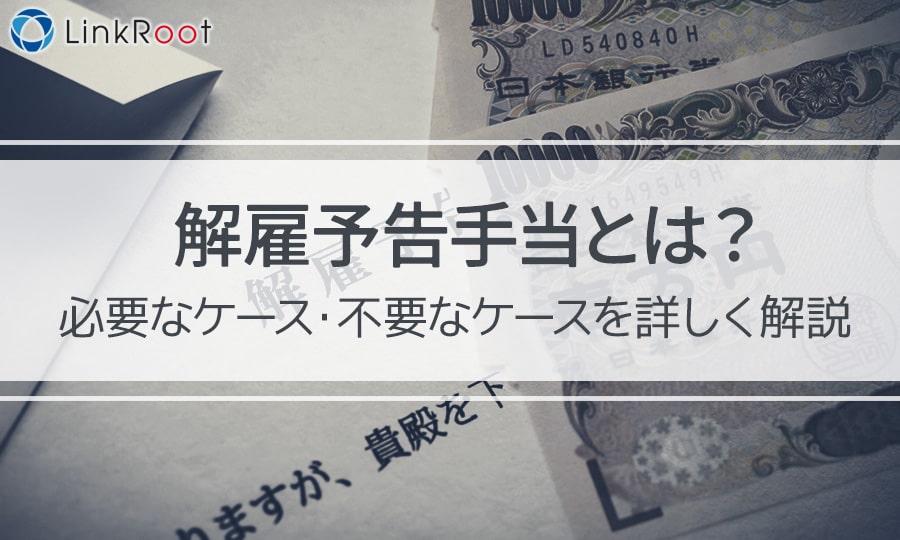
試用期間中に解雇するときの注意点
試用期間中の従業員を解雇するときは、解雇理由の正当性を確認することや適切なタイミングで解雇予告を行うことに注意しましょう。一般的な解雇と同様、社会保険の手続きも必要です。ここでは、試用期間中の解雇に関する注意点を解説しますのでチェックしておきましょう。
1.解雇理由が正当か慎重に判断する

繰り返しになりますが、解雇理由の正当性はとても重要なポイントです。そもそも解雇は従業員に対する最も重い処分であるため、試用期間中であっても本採用後であっても慎重に判断しなければなりません。
能力が不足している、経歴詐称があったなどの単純な理由だけではなく、業務や採用活動にどのように影響しているかも含め、総合的に判断したうえで解雇を検討することが重要です。
2.解雇理由証明書を求められるケースもある
解雇を告げた際に、従業員から解雇理由証明書を求められるケースもあります。解雇理由証明書とは、解雇することに決めた理由を明記した書類のことです。書類の提出を求められた場合、企業側は遅滞なく発行しなければなりません。
解雇理由証明書には、従業員名、作成日付、企業名、解雇理由を記載します。退職証明書には在籍期間や賃金なども記載しますが、解雇理由証明書には解雇理由のみを簡潔に記載しましょう。
3.適切なタイミングで解雇予告を行う
試用期間中の従業員を解雇する場合は、適切なタイミングで解雇予告を行う必要があります。試用期間がスタートしてから14日以上働いている場合は、30日以上前に解雇予告をするか、平均賃金×30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
14日以内であれば、解雇予告や解雇予告手当は不要です。ただし通常の解雇と同様、労働契約を簡単に解除できるわけではありません。正当な解雇理由を明確にしたうえで、正しい手続きで解雇しましょう。
4.社会保険などの手続きが必要になる
試用期間中であっても労働契約は成立しているため、一般的な企業で働く従業員は社会保険に加入することになります。パートやアルバイトなどの従業員についても、賃金や雇用期間が一定の条件を満たす場合は、社会保険に加入させなければなりません。
解雇する場合は社会保険から脱退することになるため、資格喪失の手続きを行う必要があります。国民年金や雇用保険など、社会保険ごとに必要な書類や提出先が異なるため、間違えないように注意しましょう。
試用期間中に解雇するときの流れ
試用期間中に解雇するときの流れは以下のとおりです。
- 本当に解雇すべきか見極める
- 解雇理由を明確にする
- 解雇予告を行う
- 解雇手続きを進める
それぞれの内容について簡単に解説します。
1.本当に解雇すべきか見極める
本来、試用期間は従業員の資質をチェックする期間であるため、すぐに解雇してしまっては意味がありません。まずは適切な指導や教育を行い、成長をサポートしながら、解雇すべきか継続的に雇用すべきかを判断しましょう。
部署異動や試用期間の延長など、解雇以外の方法を検討することも重要です。
2.解雇理由を明確にする
解雇する場合は、解雇理由を明確にしましょう。そもそも解雇理由は、就業規則に記載しておかなければなりません。
解雇を検討する際は、記載された解雇理由のうち、どの項目に該当するのかを明確にする必要があります。前述のとおり、従業員の求めに応じて解雇理由証明書を発行することも忘れないようにしましょう。
3.解雇予告を行う
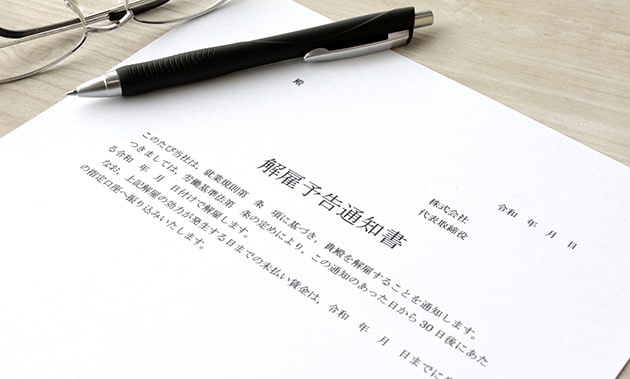
解雇することが決定したら、従業員に対して解雇予告を行いましょう。口頭で伝えると証拠が残らないため、解雇予告通知書という書面を作成するのが一般的です。タイミングによっては、解雇予告手当を支払う必要もあります。
4.解雇手続きを進める
解雇する際は、未払い賃金や退職金の支給、社会保険の資格喪失手続きなどを行う必要があります。ハローワークへ雇用保険喪失届と離職証明書を提出することも必要です。
従業員が退職するときとほぼ同じ手続きが必要となるため注意しましょう。
試用期間中の解雇以外の選択肢
解雇は従業員に対する最も重い処分であるため、他の選択肢を検討してみることも大切です。ここでは、解雇以外の選択肢を3つ紹介します。
1.退職勧奨を試す
退職勧奨とは、従業員に対して自主的な退職を勧めることです。試用期間中の勤務態度や従業員の能力を見て、自社に合わないと判断した場合は、退職勧奨を試してもよいでしょう。
ただし、退職勧奨には強制力がないため、従業員が応じてくれるとは限りません。無理やり退職させるような態度を取ると、退職強要としてトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
2.部署異動を検討する
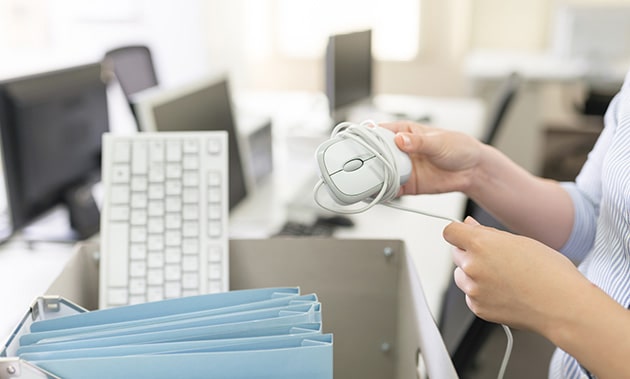
部署異動を検討することもよい方法です。最初に配属した部署の仕事には適性がなかったとしても、別の仕事ならうまくこなせる可能性があります。複数の部署がある場合は、従業員と相談のうえ、異動を考えてみるとよいでしょう。
3.試用期間を延長する
すぐに解雇せず、試用期間を延長して指導を行い、成長の機会を与えることも可能です。ただし、すべての場合において延長が認められるわけではありません。試用期間を延長する可能性について労働契約書や就業規則に記載している場合や、合理的な理由がある場合にのみ、延長が認められます。
試用期間中に解雇するときは正当な理由が必要!
今回は、試用期間中に解雇するときの注意点や手順について解説しました。試用期間中に解雇することは可能ですが、労働契約が成立しているため、簡単に解雇することはできません。従業員の能力が不足しており継続的に指導しても改善されない、重大な経歴詐称が発覚した、といった場合にのみ解雇が認められます。
不適切な理由で解雇を決めると、不当解雇と見なされトラブルに発展したり、訴えられたりするケースもあるため注意が必要です。正当な解雇理由を明確にしたうえで解雇予告を行うなど、適切な手順で手続きを進めましょう。