企業にとって自社に適した従業員を採用できるかどうかは大きなポイントです。自社に適した従業員を採用することで、生産性の向上や従業員のモチベーション向上が期待できます。
一方で自社に適していない従業員を採用をしてしまうと、企業のデメリットをもたらしてしまいます。このようなデメリットを避けるためには、採用候補者を口説き自社を採用しましょう。この記事では採用候補者を口説く理由や口説き方について解説します。
採用したい人材を口説く理由
自社が採用したい人材を口説く理由は大きく次の2つです。
- 採用ミスマッチを防ぐ
- 人手不足を解消する
いずれも自社の採用活動の効率化に欠かせない理由です。
採用ミスマッチを防ぐ

採用ミスマッチとは、自社にマッチしない従業員を採用してしまうことです。自社にマッチした従業員を採用するためには、自社が求める人材であることを伝えていかに口説けるかがポイントです。担当者からの口説きが足らなかった場合、せっかくの人材を採用できないかもしれません。
求職者を口説かずに採用ミスマッチが起きてしまうと、次のようなデメリットにつながりかねません。
- 従業員が早期離職してしまう
- 従業員採用のコストが無駄になってしまう
- 従業員のモチベーションが低下してしまう
- 生産性が低下してしまう
従業員が早期離職してしまう
採用ミスマッチが発生すると、従業員が早期離職する恐れがあります。入社したものの自分のスキルが発揮できない、企業風土に合わないといった場合、従業員は不満を抱き早期離職してしまうでしょう。
採用ミスマッチが続いて従業員の離職率が高いと、周囲からのイメージが悪化してしまいます。その結果、新たに求職者を採用するのが難しくなる可能性があります。
従業員採用のコストが無駄になってしまう
従業員の採用にはコストが発生するのが一般的です。そのため、採用ミスマッチによって採用した従業員が早期に離職してしまうと、採用コストが無駄になってしまいます。
厚生労働省の発表によれば、採用にかかるコストは正規雇用、非正規雇用、さらには利用する人材サービスによって異なります。(※1)
| 正社員 | 非正社員 | |
|---|---|---|
| 民間職業紹介事業者 | 85.1万円 | 19.2万円 |
| 求人情報誌・チラシ | 11.2万円 | 7.7万円 |
| インターネットの求人情報サイト | 28.5万円 | 10.8万円 |
| インターネットの求人情報まとめサイト | 6.4万円 | 3.2万円 |
| スカウトサービス | 91.4万円 | 44.0万円 |
| 新聞広告・屋外広告 | 7.1万円 | 4.5万円 |
| SNS | 0.9万円 | 0.2万円 |
| 知り合い・社員等からの紹介(縁故) | 4.4万円 | 3.4万円 |
| 自社HP等からの直接応募 | 2.8万円 | 2.7万円 |
上記のように正規雇用、非正規雇用に関わらず従業員を採用するとなると、方法によっては多額の費用がかかります。そのため、採用ミスマッチによる離職が繰り返されるたびに採用コストはかさんでしまうでしょう。
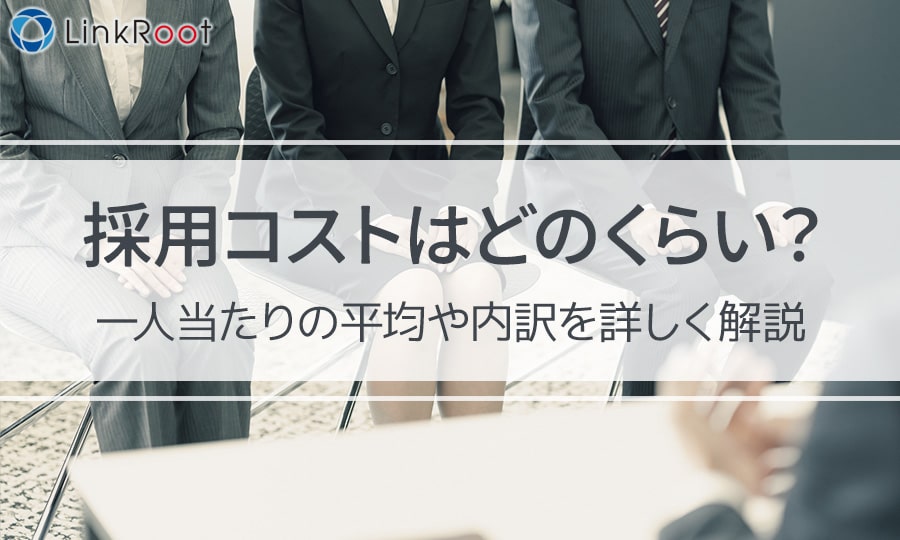
(※1)厚生労働省:採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査結果の概要」P8
従業員のモチベーションが低下してしまう
採用ミスマッチは組織のモチベーション低下につながってしまいます。入社したものの、自社が望むスキルを備えていない従業員の場合、周囲の従業員と連携が取れない可能性があります。
コミュニケーションコストがかさんでしまうと、周囲の従業員のモチベーションが低下しかねません。周囲の従業員のモチベーションが低下すると優秀な従業員が離職する恐れもあります。
生産性が低下してしまう
従業員のモチベーション低下は生産性低下にも関わります。モチベーションが低下してしまうと、ひとつの作業にかかる時間がかさんでしまい、生産性の低下がします。生産性の低下は自社の経営に大きく関わります。
求職者をしっかりと口説いて、採用ミスマッチを防ぎましょう。
人手不足を解消する

人手不足を解消するためにも採用時の口説きは大切です。
少子高齢化社会に突入している現在の日本は、求職者の方が多い売り手市場になっています。売り手市場の場合、企業は自社の魅力を求職者に伝えて口説くことが大切です。
求職者を口説かずにいると求職者が入社せず、人手不足に陥りかねません。人手不足を解消するために求職者を口説いて入社を後押ししましょう。
人手不足関連倒産件数の割合は増加傾向にある
少子高齢化社会の日本では15歳から64歳の生産年齢人口が減少傾向にあります。2020年には生産年齢人口が7,509万人だったのに対して、2070年には4,535万人にまで減少することが予想されています。
このように働き手が減少していることによって、人手不足関連倒産件数にも変化が現れています。厚生労働省の発表によれば、2013年に人手不足関連で倒産した会社の数は300件に達しませんでした。一方、2022年には485件にまで増加しています。倒産した企業のうち、人手不足関連で倒産した企業の割合は7.5%もありました。(※2)
人手不足は業務効率が低下し、従業員に負担がかかるだけではありません。人手不足が原因で倒産する可能性もあります。
そのため、採用候補となる求職者を口説いて人手不足を解消しましょう。
(※2)厚生労働省:「人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて~人材不足解消のカギは仕事と子育ての両立支援!~」P2,P7
人材を口説けない4つの理由
採用ミスマッチや人手不足を解消するために求職者を口説くことは大切です。しかし、求職者を口説けないケースもあります。
- 自社についての理解が足りていない
- 求職者との関係性を構築できていない
- 求職者のニーズを把握していない
- アプローチの工程を設計できていない
自社についての理解が足りていない

自社についての理解が足りていない場合、求職者を口説くのが難しいでしょう。例えば待遇や制度、キャリアプランなどは伝えられるかもしれません。
しかし、自社についての理解が足りていないと、現場でどのように業務を進めているのか、やりがいなどは伝えられないケースがあります。面接のなかでもオンライン面接は、対面よりも自社の魅力を伝えるのが難しい傾向にあります。
そのため、自社についての理解が足りていない場合、オンライン面接では十分な魅力を伝えきれない可能性があるでしょう。
自社について理解が足りていないと競合との差別化が図れない
自社について理解が足りていないと、競合との差別化が図れません。競合との差別化が図れていないと知名度、待遇などで他社と競う必要が出てきます。
競合と差別化を図るための自社の魅力は具体的にしましょう。例えば「働きやすい」と漠然と伝えるのでなく、残業時間は何時間までに抑えられているといったように具体的に伝えることが大切です。
求職者との関係性を構築できていない
求職者と関係性を構築していることも、口説くためには欠かせません。求職者を口説き自社に入社してもらうには、相手が何を考えているのか、どのようなキャリアプランを描いているのかなどを把握する必要があります。求職者から本音を引き出すためには、関係性を構築することが大切です。
求職者はまだ企業に雇用されているわけではありません。そのため、上下関係はありません。しかし、企業の担当者のなかには求職者に対して上から対応してしまう人もいるでしょう。このような態度を求職者に取ってしまうと、本音を引き出すのは難しくなります。その結果、採用したい求職者を口説けなくなってしまいます。
求職者との関係性構築のためには自己開示が大切
求職者との関係性を構築するためには自己開示が大切です。自己開示をすることで求職者との関係構築が期待できます。例えば新卒者を採用するのであれば、面接官が自身の学生時代の思い出などを話す必要があります。
求職者のニーズを把握していない

求職者のニーズを把握することも、採用で口説くうえでは大切です。面接官から質問するだけの画一的な面接では求職者がどのようなニーズを持っているのかを判断しづらいでしょう。求職者のニーズを把握するためにも、先述のとおり関係性の構築が欠かせません。
また、求職者のニーズが社内で共有されていないケースもあるでしょう。例えば一次面接、最終面接で担当者が異なる場合、一次面接で把握したニーズを最終面接の担当者に共有できていない可能性があります。
アプローチの工程を設計できていない
求職者に対するアプローチの工程が設計できていないケースがあります。
求職者のニーズに対してどのように自社の魅力を伝えるか、どのようなアクションを取っていくのかというアプローチを設計することで、求職者を口説きやすくなるでしょう。
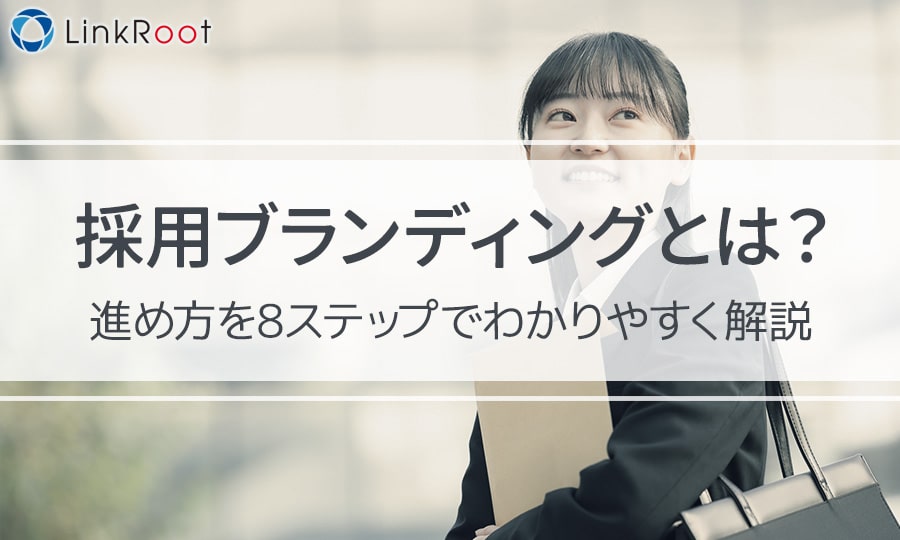
人材を口説くにはアプローチの設計が必要

求職者を口説くにはアプローチを設計しましょう。求職者を口説くためのアプローチ設計手法として以下が挙げられます。
- 3C分析
- プランの設計
- 実行
3C分析
3C分析とはマーケティング環境分析に用いられるフレームワークで、次の3つのCから成り立っています。
- Customer:市場・顧客
- Competitor:競合
- Company:自社
求職者へのアプローチにおいては求職者、求職者目線で捉えた自社、求職者目線で捉えた競合を分析します。求職者のアプローチ手段として3Cを用いる際は次のような情報を収集しましょう。
| 3Cの項目 | 質問例 |
|---|---|
| 求職者のニーズ | これまでどのような経験をしてきたか どのような企業に魅力を感じるか 会社選びについてアドバイスをくれる人がいるか 就職(転職)活動はどのような条件で終えるのか |
| 求職者目線で捉えた自社 | 自社に魅力を感じたポイントはどこか 入社したらどのようなことに取り組み・実現させたいか 働くにあたっての不安点はあるか 自社への入社希望度は100点満点中どれくらいか |
| 求職者目線で捉えた他社 | どの企業を受けているのか どのような事業の企業を受けているのか どのような職種に応募しているのか 選考状況と今後の予定 どれくらい他社に入社したいか |
上記のような情報を面接でヒアリングしてみましょう。面接だけでなくアンケートで調査することも可能です。
面接前であってもアンケートは取れます。しかし、面接後の方が求職者は自社に対してイメージを具体化しやすくなっているでしょう。具体的な意見を聞くためにも面接後にアンケートを取るのがおすすめです。
プランの設計
求職者へのアプローチを3C分析に落とし込んで求職者から情報を集めたら、次にプランの設計に進みましょう。プランを設計する際は、求職者のニーズに基づくことが大切です。
求職者から集めた情報から、どのようなニーズを抱えているかを分析しましょう。どれだけ自社の魅力を伝えたところで、求職者のニーズにそぐわなければ採用にはつながりません。
求職者へアプローチをする際のプラン設計として以下が挙げられます。
- 自社の魅力が伝わり切っていないのであれば伝え直す
- 求職者のニーズに合致し、競合に勝るほどの自社の魅力があれば強く打ち出していく
- 求職者のニーズに合致し、競合に劣る魅力は適度に伝える
自社の魅力を強く打ち出すためには、曖昧なことを伝えずに具体的な情報を伝えましょう。
実行
プランを設計したら実際に口説くアプローチをしていきます。求職者にアプローチする際は自社に入社することによってどのような未来を描けるか、どのように成長できるかを伝えましょう。
求職者へのアプローチは感情に訴える方法、理性に訴える方法の2つが軸となります。この軸にそれぞれ次の2つの方法が存在します。
- 夢の明確化
- 夢を実現できる確信へのアプローチ
つまり次のとおり合計4つのアプローチ方法があります。
| アプローチ方法 | 具体例 |
|---|---|
| 夢を実現できる確信を理性に働きかける | 社内の具体的なキャリアプランを詳しく説明する |
| 夢を実現できる確信を感情に働きかける | 夢を実現できるため一緒に働きたいと伝える |
| 夢の明確化を理性に働きかける | 漠然と将来を考えている求職者に自社ならではのキャリアプランなどを伝える |
| 夢の明確化を感情に働きかける | 漠然と将来を考えている求職者にやりがいなどを伝える |
4つのアプローチ方法を把握して、求職者の状況に合わせてどの方法がよいのかを選択しましょう。
人材の口説き方は新卒・中途で異なる
人材を口説く際は新卒採用や中途採用で異なります。ここでは新卒者、中途採用者それぞれの人材の口説き方について解説します。
新卒者の口説き方

新卒者を口説く際のポイントは次のとおりです。
- 採用プロセスから意識する
- スピーディに返答する
- 採用後の成長を意識させる
- 親族をも口説く
新卒採用の場合、中途採用よりも接する機会が多い傾向にあります。そのため、新卒者はさまざまな接点で口説いていくことが大切です。
採用プロセスから意識する
新卒者を口説く際は採用プロセスから意識しましょう。悠長に構えて、自社で望む人材が明確になってから対応するという場合、競合よりも遅くなってしまい優秀な人材の流出につながりかねません。
そのため、採用プロセスの最初からアプローチしていくことが大切です。例えば次のような施策を講じましょう。
- 採用専用のサイトを用意する
- 先輩の紹介をサイトに掲載する
採用専用のサイトやサイトでの先輩の事例紹介は一般的な施策です。しかし、いまだに用意していない企業もあるでしょう。
このような施策を用意しておかないと、採用者にネガティブな印象を与えかねません。
スピーディに返答する
求職者は企業にさまざまな質問をする可能性があります。企業は求職者から寄せられた質問に対してスピーディに返答しましょう。求職者が質問したのにも関わらず何日も返答しないでいると、求職者からの印象は悪くなってしまいます。
求職者のなかには返答が来ないことを不快に思い応募を見送る可能性があるでしょう。せっかくの求職者の応募を減らさないためにも、質問にはスピーディに返答することが大切です。返答はスピードだけでなく、クオリティにも配慮しましょう。横柄に感じられる返答をしてしまっては、スピーディであっても不快感を与えてしまいます。
スピーディかつ丁寧な返答を心がけるのであれば、チャットなど専用のツールを用いるのがおすすめです。専用のツールを用いることで自動返信が可能です。自動返信ができれば24時間365日、求職者からの問い合わせに対応できます。
採用後の成長を意識させる
新卒者の採用にあたっては成長を意識させましょう。成長を意識させる方法はいくつもあります。例えばキャリアだけではなく人生が成長することを伝えてみましょう。
先輩従業員のキャリアだけでなく、家族やライフステージ、プライベートを伝えることで成長を意識してもらえます。さらに成長によって得られることを伝えるのも効果的です。
親族をも口説く
新卒者を採用する際、新卒者本人だけでなく親族をも口説くケースがあります。なかには本人ではなく親を口説くという担当者もいるでしょう。例えば親のなかには業種や業務内容などに不満、不安を抱いている人がいる可能性があります。
このような親に対しては社長や管理職が説得しにいくことで納得してくれるかもしれません。
中途採用者の口説き方

新卒採用者に対して中途採用者は次のような方法で口説きましょう。
- 報酬や待遇で交渉する
- 直属の上司が自ら口説く
- 人材に応じた口説き文句を伝える
中途採用者は前職でさまざまな経験をしています。そのため、報酬や制度など、前職で不満い感じたところをケアすることで採用につなげられるでしょう。
報酬や待遇で交渉する
中途採用者を口説く際は報酬や待遇で交渉することがポイントです。中途採用者のなかには、前職の給与に満足せずに転職したという人もいるでしょう。
そのため、報酬で交渉して口説きを進めてみましょう。例えば「月収〇〇万円ということで進めていたものの、評価が高いためより高い月収〇〇万円でお願いしたい」といったように交渉することで、効果的なアピールが可能です。
直属の上司が自ら口説く
直属の上司が自ら口説くということも中途採用者に適しています。なんとしても中途採用者を採用したいという場合は、配属予定先の上司が直々に口説きに行きましょう。
上司が直接口説きに行く際は、役職が高ければよいというわけではありません。入社後に一緒に働く直属の上司が出向くことが効果的です。一緒に働く直属の上司からポジティブな言葉で口説かれれば、自社へ転職を決意してくれる可能性があります。
人材に応じた口説き文句を伝える
転職を検討している人は報酬や待遇だけでなく、やりがいやワークライフバランスなどさまざまな問題を抱えているケースがあります。そのため、求職者がどのような将来を描いているのかをヒアリングしましょう。
ヒアリングを行い、それぞれの人材に応じた口説き文句を伝えることで採用が期待できます。
採用候補者の口説き方を把握して自社の組織力を高めよう
採用候補者を口説くことで採用ミスマッチの防止や人手不足の解消が期待できます。しかし、自社についての理解が足りていない、求職者との関係性を構築できていない、求職者のニーズを把握していないなどの場合は、採用候補者をうまく口説けないでしょう。
採用候補者を口説く際は、3C分析を用いてアプローチ方法を設計しましょう。アプローチ方法を設計したら、新卒者・中途採用者それぞれに応じた方法で自社への入社を進めます。
採用候補者を口説けば自社が希望する従業員を採用可能です。ポイントを押さえて求職者を口説いて自社の組織力を高めましょう。




