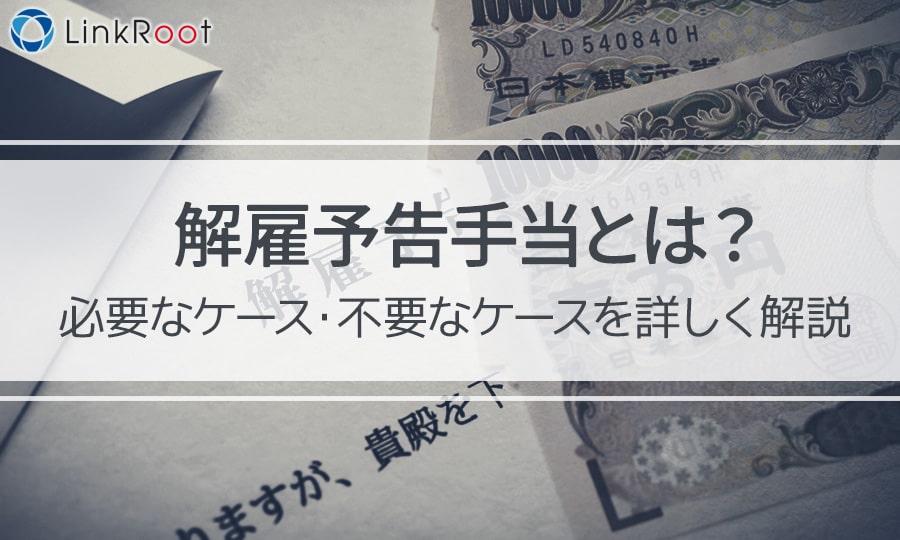従業員を解雇するときは、さまざまなルールに従う必要があります。解雇予告を実施することや解雇予告手当を支払うことも、企業が従うべき重要なルールです。ルールに違反すると、罰金や懲役などの罰則が科せられるケースもあるため十分に注意しましょう。
この記事では、解雇予告手当の意味や必要性、計算方法などについて詳しく解説します。従業員に重大な問題がある場合など、一部のケースを除き、解雇予告手当の支払いは必要です。適当な対応をすると従業員から訴えられたり、付加金が発生したりするため、解雇予告や解雇予告手当のルールについて理解を深めておきましょう。
解雇予告手当とは?

ここでは、解雇の意味や解雇予告手当の必要性について解説します。労働基準法に定められた内容であり、違反した場合の罰則規定もあるため、しっかりとチェックしておきましょう。
解雇や解雇予告手当に関するルール
解雇とは、従業員との雇用契約を終了させ、仕事や地位を失わせることです。能力が不足していたり勤務態度が悪かったりする場合、解雇を検討することになりますが、簡単に雇用契約を解約できるわけではありません。
仕事を失った従業員は生活ができなくなる可能性もあるため、ルールに従って解雇を進めることが必要です。従業員との雇用契約を解約するときは、解雇する30日以上前に通知しなければなりません。いつ解雇するのかを明確に伝えておくことで、従業員は退職の準備をしたり新しい仕事を探したりできます。
解雇の予告をしない場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当の金額は、30日分以上の平均賃金と決められています。解雇予告をするか、解雇予告手当を支払うか、どちらかの方法によって従業員の不利益が大きくなりすぎないように配慮することが必要です。
解雇予告手当に関する労働基準法の条文
解雇予告を行うべきことや解雇予告手当を支払うべきことは、労働基準法の第20条に記載されています。労働基準法に従った対応を行わないと、30万円以下の罰金、または6ヶ月以下の懲役が科せられるケースもあるため注意が必要です。(※1)
ただし、大きな災害によって事業の継続ができなくなった場合や、従業員側に重大な責任がある場合は、この条文は適用されません。解雇予告手当が不要なケースについては、後ほど詳しく解説します。
(※1)e-GOV法令検索「労働基準法」第二十条(解雇の予告)
解雇予告と解雇予告手当を組み合わせることも可能
解雇予告と解雇予告手当を組み合わせて対応することも可能です。たとえば、解雇する15日前に従業員に通知し、15日分の解雇予告手当を支払うという対応でも問題ありません。
基本的には30日以上前に雇用契約が終了することを伝える必要がありますが、解雇予告手当を支払うことで日数を補えます。すぐに解雇したい場合や、解雇予告が遅れた場合は、2つの方法を組み合わせて対応するとよいでしょう。
解雇するときは原則として解雇予告手当が必要
解雇予告手当が不要となるのは特定の条件を満たす場合のみで、ほとんどのケースにおいては適切に支払う必要があります。
以下のような場合は、解雇予告手当を支給する必要があるため確認しておきましょう。
1.パート・アルバイトに対しても解雇予告手当が必要

解雇予告手当を支払う必要があるのは、正社員だけではありません。パートやアルバイトとして働く従業員も雇用契約を結んでいるため、30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払う必要があります。雇用形態には関係なく、同様の対応をする必要があるため注意しましょう。
2.試用期間中でも解雇予告手当が必要
試用期間中の従業員を解雇する場合も、解雇予告手当を支払う必要があります。試用期間中であっても雇用契約は成立しており、一般の従業員と同様に労働基準法が適用されるからです。試用期間中だからといって、簡単に解雇できるわけではないため注意しましょう。
ただし、試用期間がスタートしてから14日以内であれば、解雇予告手当を支払う必要はありません。15日以上働いている場合は、解雇予告手当が必要です。
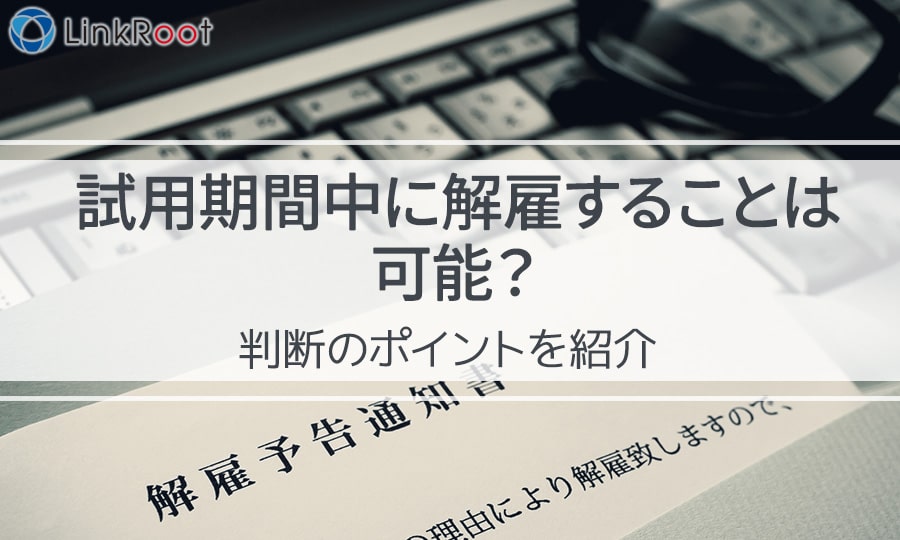
3.懲戒解雇の場合も解雇予告手当が必要
懲戒解雇とは、従業員による重大なルール違反や犯罪行為があったときに雇用契約を解約することです。さまざまな懲戒処分のなかで最も重い処分ではありますが、解雇予告を行わない場合は、基本的に解雇予告手当を支払わなければなりません。
ただし、労働基準監督署の認定を受けることで、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となります。窃盗や横領など、従業員に重大かつ悪質な行為があった場合に限られますが、解雇予告の除外認定を受けたいときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ申請書を提出しましょう。
申請すると労働基準監督署の調査が行われ、認められると解雇予告が不要となる認定書が交付されます。必ず認められるわけではなく、調査の結果、不認定となるケースもあります。
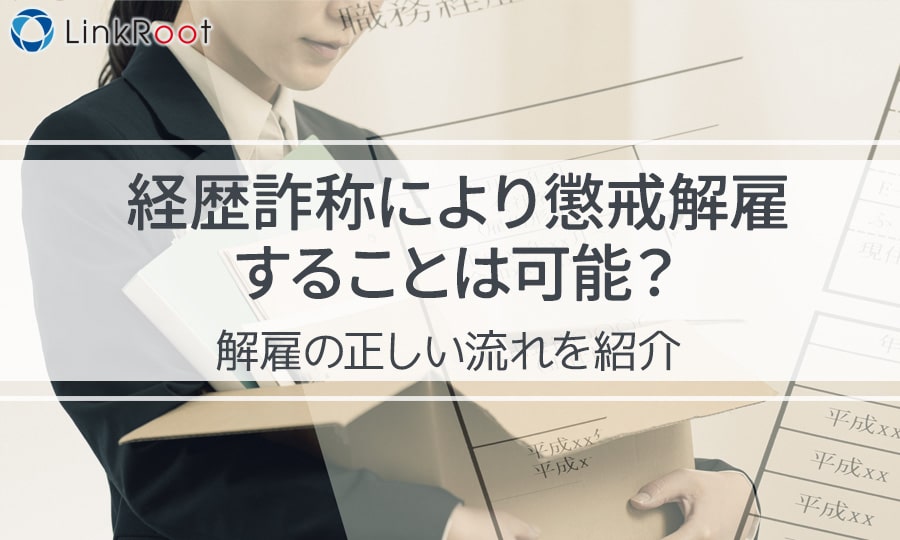
解雇予告手当が不要なケース
日雇労働者を解雇する場合や従業員に重大な責任がある場合など、例外的に解雇予告手当の支払いが不要となるケースもあります。
以下、それぞれのケースについて詳しく解説しますのでチェックしておきましょう。
1.日雇労働者などを解雇する場合
次のいずれかに該当する場合は、解雇予告を行ったり解雇予告手当を支払ったりする必要はありません。
- 日雇労働者(1日単位で雇用する労働者)
- 2ヶ月以内の雇用契約によって働く労働者
- 4ヶ月以内の雇用契約によって季節的な業務で働く労働者
- 14日以内の試用期間中の労働者
ただし、日雇労働者であっても1ヶ月を超えて継続的に雇用する場合は、解雇予告が必要です。上記の内容は、労働基準法の第21条に記載されているため、違反しないようにしっかりと確認しておきましょう。(※2)
(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第二十一条(解雇の予告)
2.従業員に重大な責任がある場合

従業員に重大な責任がある場合、解雇予告手当が不要となる可能性があります。ただし前述のとおり、重大なルール違反があったときに行う懲戒解雇であっても、基本的には解雇予告手当は必要となります。
解雇予告や解雇予告手当が不要となるのは、労働基準監督署へ申請して認められた場合のみです。解雇予告手当を支払いたくない場合は、労働基準監督署へ申請書を提出して調査を受ける必要があります。
解雇予告手当の除外認定を受けられるかどうかは個別の事情によって異なりますが、以下のような場合は認定を受けられる可能性が高いでしょう。
- 会社の金を横領した
- 窃盗や傷害事件に関わった
- 規律違反によって会社に大きな損害を与えた
- 重大な学歴詐称や職歴詐称が発覚した
- 無断欠勤が続いており出勤の督促をしても応じない
- 勤務態度が悪く繰り返し指導しても改善されない
認定を受けるためには、申請を出すだけではなく、労働基準監督署の調査にしっかりと対応することが重要です。
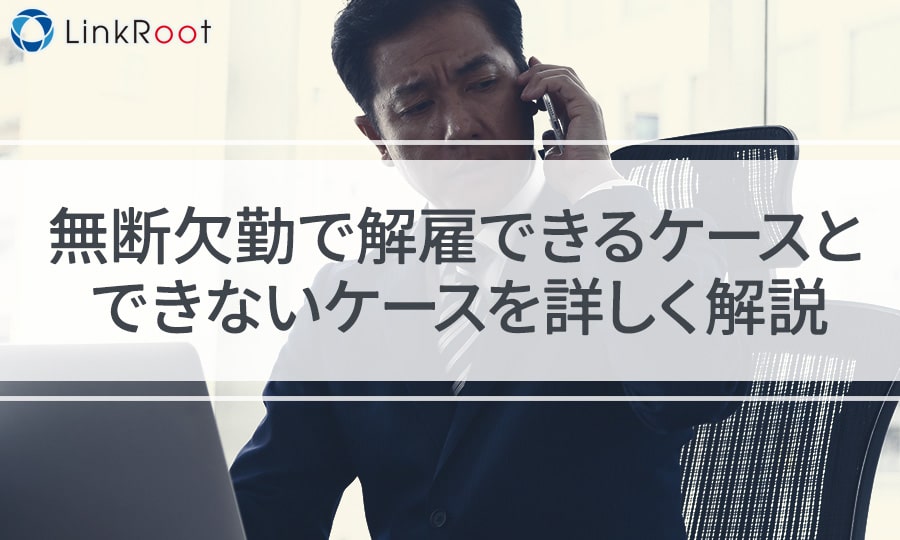
3.事業の継続が不可能になった場合
やむを得ない事情によって事業の継続が不可能になった場合も、解雇予告手当が不要となる可能性があります。ただし前項と同様、労働基準監督署へ申請して除外認定を受けなければなりません。(※3)
以下のような場合は、やむを得ない事情に該当すると判断され、解雇予告や解雇予告手当が不要になる可能性があります。
- 火災によって会社が焼失した
- 地震によって工場や事業所が倒壊した
ただし、故意や重大な過失による火災の場合は認められません。また、災害が発生したとしても、多少の復旧作業により事業を再開できるような場合は除外認定を受けられないため注意しましょう。
さらに以下のようなケースは、やむを得ない事情には該当せず、解雇予告手当の支払いが必要となります。
- 法令違反により事業主が強制収容された
- 法令違反により機械や資材を没収された
- 税金の滞納により事業廃止となった
- 取引先が休業となり依頼がなくなった
基本的に企業側に問題がある場合は、除外認定を受けることはできません。その場合は、すみやかに解雇予告手当を支払いましょう。
(※3)厚生労働省「解雇予告除外認定申請について」
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/kaikozyogai031025.pdf
解雇予告手当を計算する手順

解雇予告手当は「平均賃金×支給対象日数」という計算式で求めます。簡単な計算式ではありますが、それぞれの用語の意味を理解したうえで計算しなければ、正しい数値を求めることができません。
計算方法を間違えると、従業員が不利益を被るため注意が必要です。具体的には、次のような手順で計算しましょう。
- 支給対象となる日数を決める
- 平均賃金を算出する
- 解雇予告手当を計算する
以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
1.支給対象となる日数を決める
解雇予告手当を計算するときは、まず支給対象となる日数を決めましょう。解雇予告を行わない場合、支給対象日数は30日となります。
ただし、30日は最低基準であるため、それ以上の日数としても問題ありません。
解雇予告のタイミングが遅れた場合は、30日からその日数を差し引きましょう。たとえば、解雇する日の12日前に解雇予告をした場合は、18日が支給対象日数となります。
2.平均賃金を算出する
次に平均賃金を算出します。平均賃金とは、1日あたりに支給される賃金のことです。平均賃金は従業員ごとに異なり、直近3ヶ月間における賃金の合計をもとに計算しなければなりません。会社全体の平均賃金などではないため注意しましょう。
平均賃金を求める際は、以下2つの計算結果のうち、高いほうを採用します。
(1)直近3ヶ月の合計賃金 ÷ 直近3ヶ月の暦日数
(2)直近3ヶ月の合計賃金 ÷ 直近3ヶ月の労働日数 × 0.6
直近3ヶ月の考え方については、後ほど詳しく解説します。
暦日数とはカレンダー上の日数
(1)の計算式における暦日数とは、カレンダー上の日数のことです。平日はもちろん、土日や祝日を含む全日数となります。
たとえば7〜9月の暦日数はそれぞれ、31日、31日、30日です。よって、7〜9月の暦日数の合計は92日となります。
ただし、以下のような期間がある場合は日数から除外されます。
- 労働災害により休業した日数
- 産休・育休・介護休暇の日数
- 会社の都合により休業した日数
- 試用期間中の日数
従業員ごとの勤怠状況をよく確認してから日数を算出しましょう。
労働日数とは実際に働いた日数
(2)の計算式における労働日数とは、実際に働いた日数のことです。欠勤日は含まれないため注意しましょう。たとえば、7〜9月に実際に働いた日数がそれぞれ、20日、18日、21日だった場合、労働日数の合計は59日となります。
3.解雇予告手当を計算する
支給対象日数と平均賃金を算出したら、2つの数値を掛け合わせて解雇予告手当を求めましょう。たとえば、平均賃金が1万円、支給対象日数が30日の場合、「1万円 × 30日 = 30万円」が解雇予告手当となります。
解雇予告手当を計算するときのポイント
解雇予告手当を計算するときは、直近3ヶ月の考え方や賃金の合計に含まれるもの・含まれないもの、端数処理などについて理解しておきましょう。
以下、計算時のポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.直近3ヶ月の考え方
前述のとおり、平均賃金を算出する際は直近3ヶ月の合計賃金を求めなければなりません。この3ヶ月は、解雇予告日の直前の給与締日から遡って数えます。
たとえば、給与締日が毎月25日の企業において、9月15日に解雇予告をするケースを考えてみましょう。直前の給与締日は8月25日となり、そこから遡って3ヶ月の合計賃金を算出します。
つまり、5月26日〜6月25日、6月26日〜7月25日、7月26日から8月25日という3つの期間で支払った賃金の合計を計算することになります。
2.賃金の総額に含まれるもの
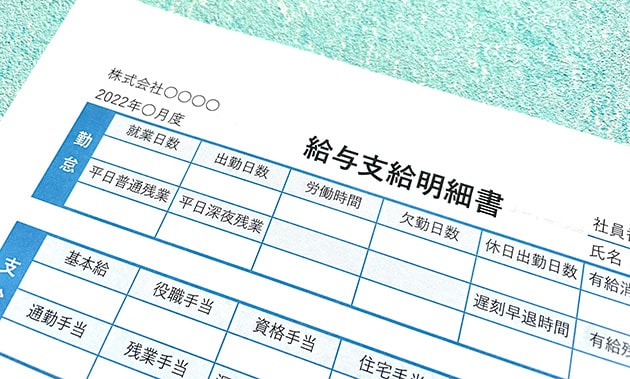
賃金の合計には、含まれるものと含まれないものがあるため注意が必要です。基本給のほか、以下のような手当は賃金の合計に含まれます。
- 基本給
- 時間外手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 役職手当
- 皆勤手当
- 家族手当
- 資格手当
直近3ヶ月に支払った基本給と各種の手当をすべて合計します。なお、所得税や社会保険料を控除する前の金額を合計することにも注意しましょう。
3.賃金の総額に含まれないもの
一方で以下のような手当は、賃金の合計に含まれません。
- 賞与
- 役員報酬
- 現物給与
- 臨時的な手当(出張手当・傷病手当・慶弔見舞金など)
- 退職金
ただし、3ヶ月以内ごとに支払われる賞与は、賃金の合計に算入します。また、以下のような期間に支払われる給与も除外されます。
- 労働災害により休業した期間
- 産休・育休・介護休暇の期間
- 会社の都合により休業した期間
- 試用期間
4.時給制や日給制の平均賃金
時給制や日給制で働く従業員の平均賃金についても、月給制の場合と同様に以下2つの計算式を用いて算出し、高いほうを採用します。
(1)直近3ヶ月の合計賃金 ÷ 直近3ヶ月の暦日数
(2)直近3ヶ月の合計賃金 ÷ 直近3ヶ月の労働日数 × 0.6
ただし、パートやアルバイトなどの場合、(1)の計算式を用いると平均賃金が極端に少なくなるケースがあります。よって(2)の計算結果が採用される場面も多いでしょう。(2)は労働基準法による最低保障額であるため、この結果を下回らないように注意しなければなりません。
5.解雇予告手当の端数処理
解雇予告手当を計算した結果、小数点以下の端数が発生したときは、四捨五入しましょう。また、平均賃金を計算した結果、小数点以下の端数がある場合は切り捨てます。
解雇予告手当を支払うまでの流れ
解雇予告手当の支払いは、正しい手順で行いましょう。具体的な流れは以下のとおりです。
- 適切なタイミングで解雇予告を行う
- 解雇予告手当を計算する
- 解雇予告手当を支払う
それぞれのポイントについて順番に解説します。
1.適切なタイミングで解雇予告を行う
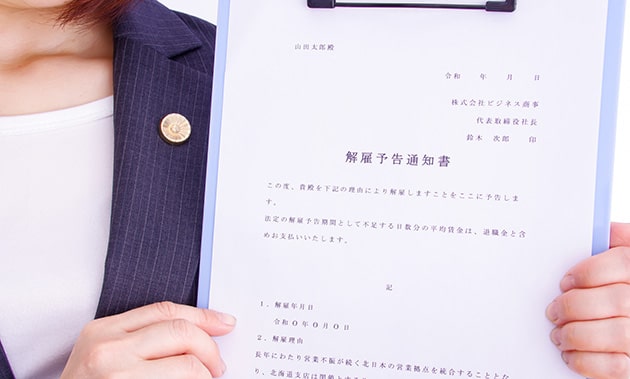
何らかの問題が発生し、従業員を解雇することを決定したら、適切なタイミングで解雇予告を行いましょう。できる限り早めに伝えておけば、従業員は新しい仕事を探すなどの対応が可能となります。
解雇予告の方法について絶対的なルールはないため、口頭で伝えるほか、メールや手紙、電話などで伝えても問題ありません。ただし、解雇予告をしっかりと行ったという証拠を残しておくことは重要です。
とくに口頭で伝えると記録が残らず、「言った・言わない」のトラブルが発生する可能性もあります。労使間の紛争を防止するためにも、解雇については書面で伝えるとよいでしょう。また、解雇予告をしない場合や解雇予告が遅れた場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。
2.解雇予告手当を計算する
解雇予告手当を支払うことになった場合は、前述の計算式を用いて正しく算出しましょう。支給対象日数や平均賃金を正確に算出したうえで、支払うべき解雇予告手当を計算しなければなりません。
まずは従業員の勤怠状況をしっかりと把握することが必要です。また、賃金に含まれない手当や労働日数の数え方などに注意しながら計算を進めましょう。
3.解雇予告手当を支払う
解雇予告手当を算出したら、従業員へ支払います。即日解雇する場合は、解雇する当日に支払いましょう。解雇予告を行ったときは、解雇する日までに支払えば問題ありません。
法律によって定められた支払い期限などはないため、最終の給与に上乗せする形で振り込むことも可能です。ただし、支払いが遅れると労使間のトラブルにつながるため、できるだけ早めに支払うとよいでしょう。
そもそも解雇された従業員は会社に対して不満を感じていることが多いため、すみやかに支払うことが大切です。
解雇予告手当に対する所得税
解雇予告手当は退職金と同様、給与所得ではなく退職所得に分類されます。退職所得からは、所得税と復興特別所得税を源泉徴収して、基本的に翌月の10日までに納付しなければなりません。ただし、社会保険料の控除対象ではないため間違えないようにしましょう。
源泉徴収する所得税の計算方法は、「退職所得の受給に関する申告書」の有無によって異なります。(※4)
(※4)国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されているケース
従業員から「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合は、勤続年数をもとに退職所得控除額を求めなければなりません。退職所得控除額は、勤続年数が20年を超える場合と、20年以下の場合で異なります。
次に、解雇予告手当から退職所得控除額を差し引き、課税対象となる退職所得金額を求めます。最後に、課税退職所得金額に応じて、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に従って源泉徴収する所得税を算出しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていないケース
従業員から「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合は、解雇予告手当に20.42%の税率を乗じて算出した所得税を源泉徴収しましょう。計算結果に1円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
解雇予告手当の未払いによる3つのリスク
解雇予告手当を適切に支払わないと、従業員から訴訟を起こされたり、刑事罰を受けたりする可能性があります。付加金が発生して大きな損害となるケースもあるため十分に注意しましょう。
ここでは、解雇予告手当の未払いによる3つのリスクを紹介します。
1.訴訟を起こされるリスク
解雇予告手当を適切に支払わないと、解雇された従業員から訴えられるリスクがあります。敗訴する可能性があるのはもちろん、裁判に提出する証拠書類を準備したり、出廷して証言したりするなど、多くの手間がかかってしまいます。
本来の業務が進まないことで、大きな損失が生まれるケースもあるため注意しましょう。
解雇予告を行うことや解雇予告手当を支払うことは、労働基準法によって定められた義務です。裁判などのトラブルに発展しないよう、適切な金額を支払いましょう。
2.刑事罰を受けるリスク
労働基準法に従って解雇予告手当を支払わない場合、30万円以下の罰金、または6ヶ月以上の懲役が科せられる可能性もあります。罰金という無駄な出費が増えるのはもちろん、懲役が科せられることによって、業務がストップしてしまうこともあるでしょう。
さらに、企業の社会的なイメージが悪くなり、取引先との関係が悪化したり、採用活動がうまく進まなくなったりするケースもあります。
コンプライアンスを強化しながら事業を進めることは、近年、とくに重要視されています。法律だけではなく、倫理的なルールを遵守しながら事業を展開していきましょう。
3.付加金が発生するリスク
付加金が発生することは、解雇予告手当の未払いによる大きなリスクです。解雇予告を怠ったり、解雇予告手当を支払わなかったりすると、解雇した従業員から付加金を請求される可能性があります。
請求された企業は、付加金として解雇予告手当と同額を支払わなければなりません。つまり、通常支払うべき解雇予告手当の2倍の出費が発生してしまいます。企業にとって大きな損失になるため、十分に注意しましょう。
なお、付加金は、従業員が訴訟を起こした際にのみ適用されます。
適切な金額の解雇予告手当を支払おう!
今回は、解雇予告手当の意味や必要なケース・不要なケースを紹介しました。解雇された従業員は仕事を失ってしまうため、不利益が大きくなりすぎないよう、適切なタイミングで解雇予告を行うことや解雇予告手当を支払うことが必要です。
従業員に重大な責任があり、労働基準監督署へ申請して除外認定を受けた場合など、一部の事例では解雇予告手当が不要となりますが、ほとんどのケースにおいては解雇予告手当を支払わなければなりません。
試用期間中の解雇や懲戒解雇であっても、基本的には解雇予告や解雇予告手当が必要です。労使間のトラブルを防止するためにも、判断基準をしっかりと理解しておきましょう。