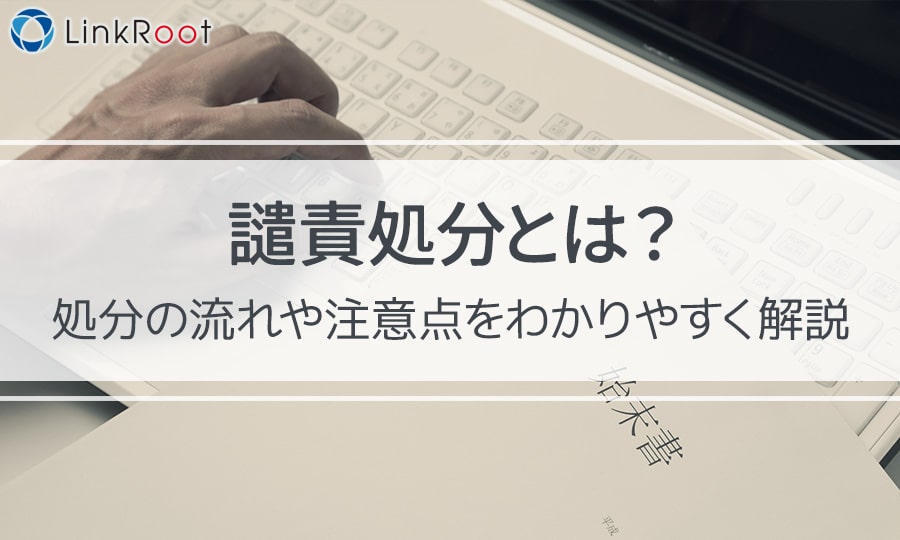従業員の軽度なルール違反に対して、譴責処分を検討するケースもあるでしょう。譴責処分は、懲戒処分のなかでは軽いものですが、対応を間違えると懲戒権の濫用と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、譴責処分の意味や他の懲戒処分との違い、実施するときの注意点などを詳しく解説します。不当な処分と見なされないよう、譴責処分を実施する前にポイントを把握しておきましょう。
譴責処分とは?
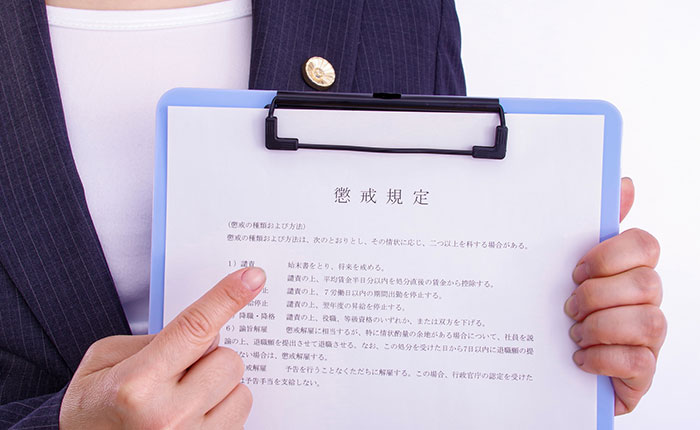
まずは、譴責処分の意味や戒告・訓告との違い、対象となる行為について確認しておきましょう。
譴責処分とは始末書を提出させて厳重注意を行うこと
譴責処分とは、ルール違反をした従業員に対して始末書の提出を命じ、厳重注意を行うことです。譴責という言葉には「不正や違反行為をとがめる」という意味があり、ビジネスの世界でもしばしば用いられます。
譴責処分は、懲戒処分のひとつであり、戒告・訓告の次に軽い処分として位置付けられます。ただし、譴責処分を設けることは法律上の義務ではありません。譴責処分を設けるかどうか、どのような行為に対して処分を与えるかは、企業が自由に決定できます。
譴責処分を設ける場合は、処分内容や対象となる行為について就業規則に明記しておきましょう。事前に従業員へ周知しておくことも重要です。
譴責処分と戒告・訓戒との違い
戒告・訓告も懲戒処分のひとつであり、違反行為をした従業員に対して口頭や文書で注意することを意味します。一般的には懲戒処分のなかで最も軽い処分であり、軽度のルール違反を対象として実施するのが基本です。
譴責処分との違いは、始末書を提出させるかどうかです。譴責処分では始末書を提出させるのに対し、戒告や訓告においては注意のみを行い、始末書の提出までは求めないケースが多いでしょう。ただし、戒告・訓告や譴責処分の内容は企業によって異なるため、就業規則を確認したうえで進めることが大切です。
譴責処分の対象となる違反行為
どのような行為に対して譴責処分を行うかは、企業によって異なります。一般的には、以下のような行為が譴責処分の対象となるケースが多いでしょう。
- 正当な理由のない遅刻や早退を繰り返した
- 正当な理由のない無断欠勤をした
- 軽度のハラスメント行為に関わった
- 業務命令に従わなかった
- 服務規定に違反した
- 社内の風紀を乱す行為をした
基本的には、比較的軽い違反行為に対して譴責処分を行います。会社に大きな損害を与えたり、重大な犯罪行為に関わったりした場合は、減給や出勤停止などの重い処分を検討しましょう。
譴責処分を受けた従業員はどうなる?

譴責処分を受けた従業員は、給与や退職金が減ったり、人事評価が下がったりするのでしょうか。ここでは、譴責処分を受けた場合の影響について詳しく解説します。
1.給与は減る?
一般的な譴責処分においては、厳重注意を行って始末書を提出させるだけであるため、給与が減ることはありません。譴責処分は、それほど重くない違反行為に対する処分であるため、給与が減るという大きな罰則はないのです。
従業員が大きな違反行為に関わっており、給与を減らしたり役職を下げたりしたい場合は、減給や降格といった別の懲戒処分を検討する必要があります。ただし、譴責処分を受けたことにより、社内の評価が下がることで昇進や昇格が遅れ、結果として給与が減るという可能性はあるでしょう。
2.人事評価は下がる?
譴責処分を受けたことで、人事評価が下がる可能性はあります。人事評価が下がった影響で、部署を異動することになったり、担当する仕事が変更になったりするケースもあるでしょう。さらに、給与が減少する可能性もあります。
もちろん、譴責処分を受けたとしても、大きな成果を出していたり、高い能力を保有していたりすれば、総合的な判断で人事評価は上がるかもしれません。ただし、譴責処分を受けた従業員として、上司や同僚からマイナスイメージをもたれる可能性はあるでしょう。
3.退職金は減る?
譴責処分を受けたからといって給与が減らないのと同様、退職金が減ることもありません。ただし、譴責処分によって人事評価が下がったり、結果として役職を失ったりすると、退職金が減る可能性もあります。人事評価や役職に応じて、退職金の支給額を決定する企業もあるからです。
退職金の計算方法や支給基準に関する法的な規制はないため、企業が独自に設定できます。人事評価や役職によって退職金が変動する制度を導入している場合は、受け取れる退職金が減ってしまうケースもあるでしょう。
4.転職で不利になる?
懲戒解雇などの重い処分とは異なり、譴責処分を受けたことによって転職で不利になるケースは少ないでしょう。比較的軽い処分であり、大きな犯罪行為に関わったわけでもないため、あえて履歴書に書く必要はありません。
ただし、面接などで懲戒処分を受けた経験について質問された場合は、正直に答えたほうがよいでしょう。転職先の企業がリファレンスチェックや素行調査を実施した際に、譴責処分を受けたことを知られる可能性もあるからです。面接で虚偽の回答をすると、経歴詐称と見なされるケースもあるため注意しましょう。
譴責処分を実施するときの流れ
譴責処分を実施するときは、正しい手順で進めましょう。具体的には、就業規則の内容を確認する、違反行為に関する客観的な証拠を確保する、弁明の機会を与えるなどの対応が必要です。
すぐに始末書の提出を命じられるわけではないため注意しましょう。以下、譴責処分の流れを詳しく解説します。
1.就業規則の内容を確認する
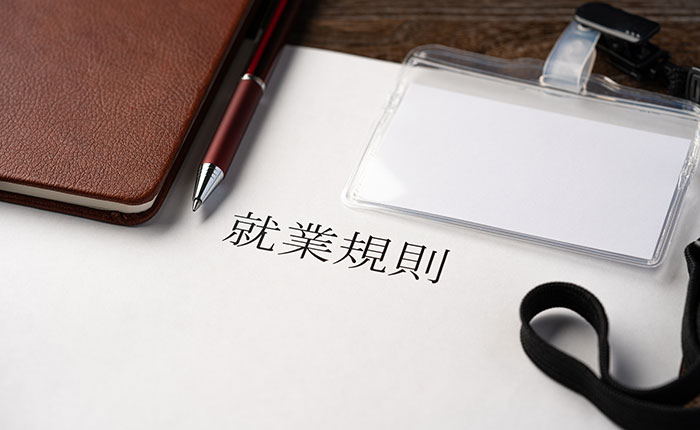
譴責処分を実施する前に、必ず就業規則の内容を確認しましょう。譴責処分の有無や対象となる行為、手続き方法は企業によって異なるからです。企業によっては、そもそも譴責処分についての記載がないかもしれません。
譴責処分の対象となる行為についても確認しておくことが大切です。従業員の行為が就業規則に記載された懲戒事由に該当していなければ、譴責処分を実施することは基本的にできません。懲戒事由に該当している場合は、正しい手続き方法で処分を実施しましょう。
2.客観的な証拠を確保する
譴責処分を含め、懲戒処分を行う場合は客観的な証拠が必要です。労働契約法の第15条には、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、処分が無効になると明記されています。(※1)
従業員が違反行為に関わったという具体的な証拠がなければ、客観的に合理的な理由がないと見なされ、処分が認められない可能性もあるでしょう。まずは従業員本人や関係者からヒアリングを行い、事実関係を確認することが重要です。ヒアリング内容を記録したり、業務命令の内容を示す文書やメールを保存したりすることも忘れないようにしましょう。
(※1)e-GOV法令検索「労働契約法」第十五条(懲戒)
3.弁明の機会を与える
譴責処分を実施するときは、処分の対象となる従業員に弁明の機会を与えることも大切です。従業員と話し合う場を設け、なぜ違反行為に関わったのか、反省の気持ちはあるのか、本人の言い分をしっかりと聞きましょう。話し合いの代わりに、弁明書と呼ばれる書面を提出させる方法もあります。
弁明の機会を設けないと、正しい手続きで処分を行っていないと判断されるケースもあるため注意が必要です。話し合いの内容によっては他の懲戒処分に変更したり、処分を中止したりすることも考えられます。弁明の機会を与えることで、過度な処分を防止するようにしましょう。
4.譴責処分通知書を交付する
譴責処分を実施することが決まったら、対象となる従業員に対して譴責処分通知書を交付しましょう。譴責処分通知書には、以下のような内容を記載します。
- 従業員名
- 会社名・代表者名
- 処分日
- 処分の種類
- 処分の内容
- 処分を行う理由
- 就業規則上の根拠条文
処分の種類については、譴責処分であることがわかるように記載します。始末書の提出を求める場合は、提出方法や提出期限も明記しておきましょう。
5.始末書を提出させる

始末書を提出させる場合、内容について会社側から指示を出すことは避けましょう。始末書は本人の反省を促すものであり、率直な気持ちを書いてもらわなければ意味がないからです。文章が下手であったり、体裁が整っていなかったりしても問題はありません。あくまでも本人の意思で作成させることが大切です。
始末書が提出されたときは、しっかりと反省しているかを確認しましょう。始末書の提出を拒否された場合は、就業規則に従って再度提出を命じたり、より重い懲戒処分を検討したりすることも必要です。
6.処分について公表する
譴責処分を実施した場合、社内で公表するケースもあるでしょう。譴責処分の事実を公表することで、同じような違反行為が発生することを防止し、社内の秩序を維持する効果が期待できます。
ただし、処分内容を公表することで、名誉毀損などとして訴えられるケースもあるため注意しなければなりません。譴責処分について公表するときは、客観的な事実のみを公表する、憶測による部分は公開しない、社外には公開しないなどの配慮をしましょう。
譴責処分以外の懲戒処分
譴責処分以外にもさまざまな懲戒処分が存在します。違反行為の内容に応じて、適切な懲戒処分を選択することが大切です。
以下、それぞれの懲戒処分について解説しますのでチェックしておきましょう。
1.戒告・訓告
戒告・訓告は、懲戒処分のなかで最も軽い処分であり、従業員に対して口頭や文書で注意することを意味します。正当な理由のない遅刻や早退が多い、業務命令に違反したなど、軽度の違反行為に対して実施されます。
譴責処分とは異なり、基本的には始末書の提出までは求めません。ただし、法律上のルールはないため、就業規則において始末書の提出を規定している企業もあるでしょう。
2.減給
減給とは、従業員の給与を減らす処分のことです。始末書の提出だけではなく、収入が減るという罰則を受けるため、譴責処分よりも重い処分として位置付けられます。
ただし、減給できる金額については制限があるため注意しなければなりません。具体的には、労働基準法の第91条に従い、以下の条件を満たす必要があります。(※2)
- 1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えない
- 総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えない
(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第九十一条(制裁規定の制限)
3.出勤停止
出勤停止とは、一定期間、仕事をさせない処分のことです。出勤停止とする期間は企業が自由に設定できますが、行為の内容に応じて1週間〜1ヶ月程度とするケースが多いでしょう。基本的に出勤停止の期間中は給与を支給せず、勤続年数としてもカウントしません。
4.降格
降格とは、従業員の役職やポジションを引き下げる処分のことです。例えば、部長から課長へと役職が変更となる、プロジェクトチームのリーダーではなくなるなどの処分が挙げられます。降格にともなって権限を失ったり、減給となったりすることもあるため、比較的重い処分といえるでしょう。
5.諭旨解雇

諭旨解雇とは、違反行為に関わった従業員に対して、自主的な退職を勧める処分のことです。会社側と従業員で話し合いを行い、納得してもらったうえで退職届の提出を求めます。
ただし、退職届の提出を強制することはできません。無理に提出させると懲戒権の濫用と見なされ、処分が無効となる可能性もあるため注意しましょう。諭旨解雇に応じてもらえない場合は、懲戒解雇を検討することになります。
6.懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員との雇用契約を一方的に解約する処分のことです。就業規則の内容によっては退職金が不支給となったり減額されたりするケースもあり、懲戒処分のなかで最も重い処分として位置付けられます。
懲戒解雇は、従業員の生活に大きな影響を与える処分であるため、簡単に実施することはできません。重大な違反行為があった場合や会社に大きな損害を与えた場合などに限って、懲戒解雇が認められます。
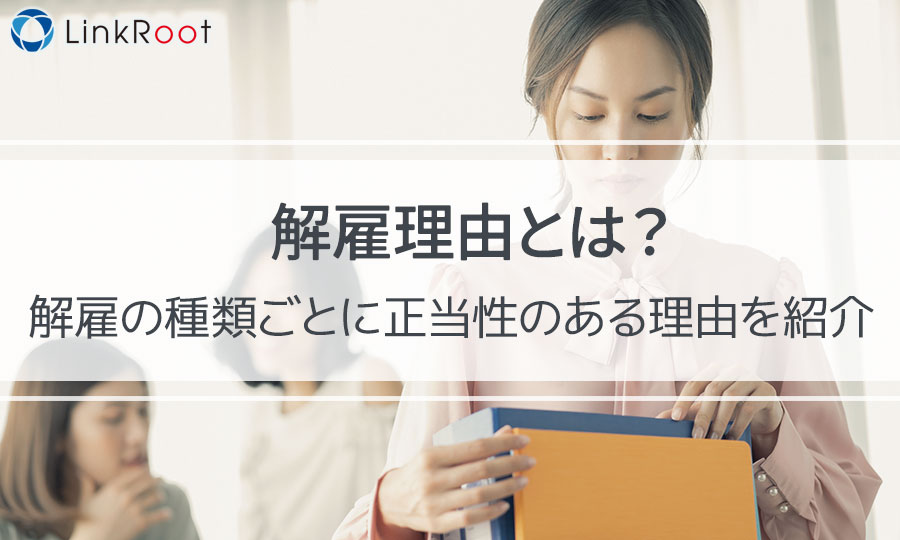
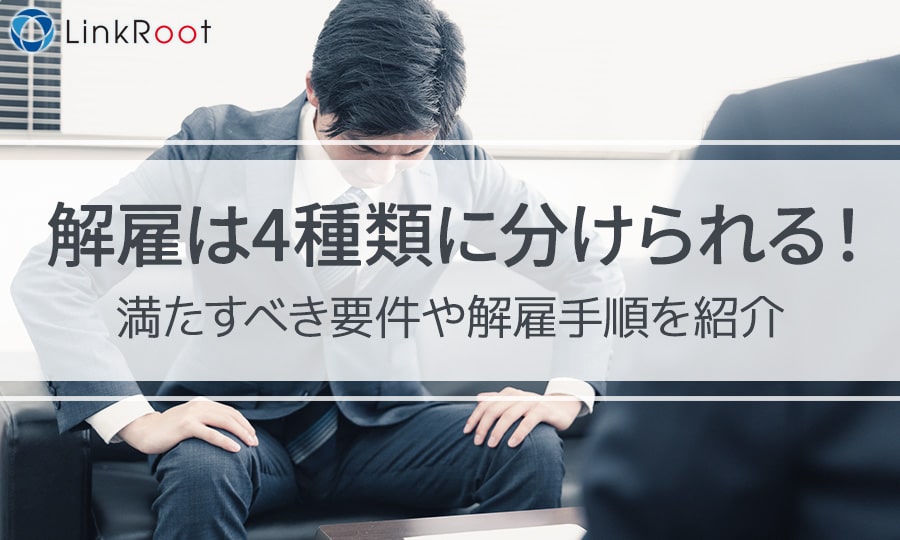
譴責処分が不当と見なされるケース
以下のようなケースにおいては、譴責処分が不当と見なされる可能性があるため注意しましょう。
1.就業規則に記載されていない
譴責処分は、就業規則に記載された内容に従って実施しなければなりません。どのような行為が譴責処分に該当するのか、どのような手順で処分が実施されるのか、といったポイントを就業規則に明記しておきましょう。
他の懲戒処分についても同様です。就業規則の内容を無視した処分を行うと、不当と見なされる可能性があります。
2.客観的に合理的な理由がない
譴責処分を実施する際は、客観的に合理的な理由が必要です。具体的な証拠がないにも関わらず譴責処分を実施すると、処分が無効となるケースもあるため注意しましょう。しっかりと事実確認を行い、証拠となる記録を残しておくことが大切です。
3.適切な手続きが行われていない
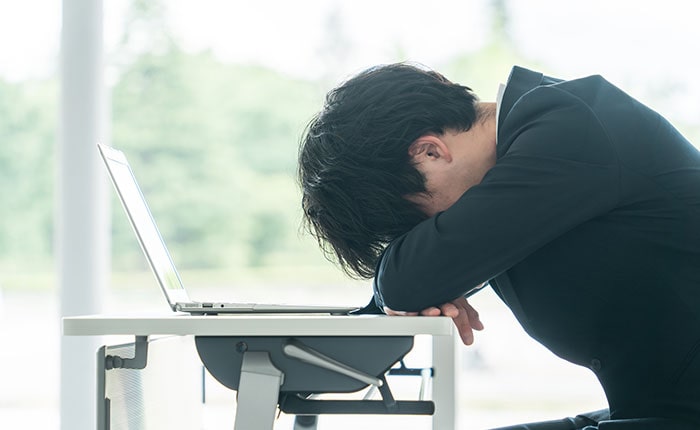
譴責処分は、適切な手順で実施しなければなりません。たとえば、弁明の機会を与えていない、始末書に書く内容を細かく指示した、といった場合は不当な処分と見なされる可能性があります。比較的軽い処分であるとはいえ、従業員へさまざまな影響を与える処分であるため、適切な手順で進めるようにしましょう。
4.1回の問題行動に対して複数回の処分を行う
1回の問題行動に対して、複数回の処分を行うことはできません。たとえば、業務命令を無視したことを理由として譴責処分を実施し、その後、同じ理由で減給などの別の処分を与えることは避けましょう。
このルールは「二重処罰の禁止」などと呼ばれています。問題行動の責任を問うことは大切ですが、ルールに従って処分を実施しなければなりません。
5.懲戒権の濫用に該当する
懲戒権の濫用に該当する場合、処分は無効と判断されます。軽い違反に対して重い処分を実施することなどは、懲戒権の濫用に該当します。
たとえば、数回の遅刻に対して譴責処分を行うことなどは、懲戒権の濫用と見なされるでしょう。問題行動の程度と懲戒処分の重さのバランスを考えながら、適切な対応を選択することが大切です。
正しい手順で譴責処分を実施しよう!
今回は、譴責処分の意味や対象となる行為、実施するときの流れなどを解説しました。譴責処分は、問題行動を起こした従業員に対して注意を行い、始末書を提出させる処分のことです。
懲戒処分のなかでは比較的軽い処分ですが、簡単に実施できるわけではありません。客観的な証拠を確保する、就業規則の内容を確認する、弁明の機会を与えるなど、適切な手順で進めることが大切です。ルールを無視して譴責処分を実施すると、処分が無効となるケースもあるため注意しましょう。