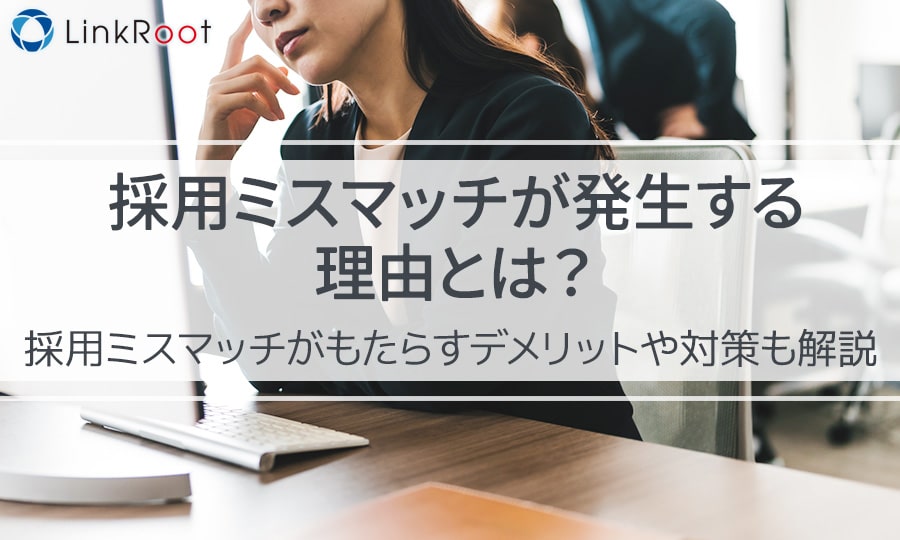自社が求めるスキルを備えていない求職者を採用してしまうことを採用ミスマッチと呼びます。採用ミスマッチの主な原因には、企業が自社の情報を十分に伝えていないことや求職者を見極められていないなどが挙げられます。
採用ミスマッチが発生してしまうと企業、求職者にさまざまなデメリットが発生しかねません。そのため、事前に対策を講じて採用ミスマッチを防ぎましょう。この記事では採用ミスマッチが発生する理由やデメリット、対策について解説します。
採用ミスマッチが発生する4つの理由

採用ミスマッチが発生してしまう理由は次のとおりです。
- 企業が情報を十分に伝えていない
- 求職者を見極められていない
- 面接や評価が属人化している
- 市場の労働力が少なくなっている
自社がこのような状況に陥っていないかを確認してみましょう。
企業が情報を十分に伝えていない
採用ミスマッチが発生してしまう理由のひとつとして、企業が自社の情報を十分に伝えきれていないという点が挙げられます。例えば求人を掲載するにしても、経験者のみが応募できるのか、未経験者でも応募できるのかは明確に伝えるべき情報です。
このような情報を十分に伝えきれていないと採用ミスマッチにつながってしまいます。
求職者を見極められていない
求職者がどのようなスキルを持っているのか、職歴なのかなどを見極められていないと採用ミスマッチの原因になります。求職者のなかには採用されるために自身のスキルや職歴を詐称している人もいます。
例えば次のような詐称例が挙げられます。
- 最終学歴が高校卒業なのに大学卒業にしている
- 前職で役職がなかったのに役職があったとしている
- 年収を前職より高くしている
採用担当者が求職者の経歴詐称を見抜けないと採用してしまい、採用ミスマッチにつながってしまうでしょう。
面接や評価が属人化している
面接や評価が属人化していると採用ミスマッチにつながります。面接や評価が属人化していると、面接官や採用担当者によって採用か不採用かの基準がバラバラになりがちです。
そのため、本来不採用だったはずの求職者を採用してしまうというミスマッチにつながりかねません。反対に本来採用したかった求職者を不採用にしてしまうケースもあるでしょう。
市場の労働力が少なくなっている
採用ミスマッチは自社の問題だけで発生するわけではありません。市場の労働力減少という外的な要因も挙げられます。内閣府が発表した『令和4年版高齢社会白書』では2021年には15~64歳の生産年齢人口が7,450万人だったと報告されています。ピーク時の1995年には8,716万人だったため、1,000万人以上減少したことになります。(※1)
市場の労働力が少なくなることにともない、企業が求めるスキルを備えた人材の確保も難しくなっていきます。その結果、自社で希望するスキルや職歴を持つ求職者を採用できず、採用ミスマッチが発生してしまいます。
市場の労働力は今後もより低下すると予想されています。『令和4年版高齢社会白書』によれば2065年の生産年齢人口の予想は4,529万人です。市場の労働力がより低下することで、採用ミスマッチのリスクも増加する可能性があるでしょう。(※1)
(※1)内閣府:令和4年版高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf
新卒・中途でもミスマッチの理由は異なる
採用ミスマッチが発生する理由は新卒採用、中途採用で異なります。ここでは新卒、中途で異なるミスマッチの理由について解説します。
新卒採用でミスマッチになる理由

新卒採用でミスマッチが発生してしまう理由は次のとおりです。
- 社風が合わなかった
- 入社前後にフォローをしなかった
- 学歴・面接の印象ばかりに意識を取られた
社風が合わなかった
新卒採用でミスマッチが発生してしまう理由のひとつが社風が合わなかったという点です。例えば、年功序列の考えが社風として根付いている企業では、成果主義を希望する新入社員が活躍するのは難しいでしょう。
このように新卒者の考えと企業の社風が合わなかったことで、採用ミスマッチが起こる可能性があります。
入社前後にフォローをしなかった
新卒者は当然、初めて社会に出て勤務する状況です。そのため、入社前後にフォローが欠かせません。入社前後のフォローをしなかった場合、新入社員はさまざまな不安を抱えてしまい退職をしてしまうかもしれません。
学歴・面接の印象ばかりに意識を取られた
新卒者を採用するにあたって、学歴や面接ばかりを意識してしまうと採用ミスマッチにつながる恐れがあります。新卒者の場合、前職がないためスキルや経験を判断材料にできません。そのため、学歴や面接の印象は大きな要素になるでしょう。
しかし、学歴や面接の印象ばかりに頼ってしまうと、実力を発揮できる候補者を見逃してしまう恐れがあります。例えば面接の印象が芳しくなくても、実際に働いてみたら高いスキルを発揮できる人もいるでしょう。一方、学歴や面接の印象が良くても求めるスキルを発揮できない人もいます。
中途採用でミスマッチになる理由

中途採用でミスマッチになってしまう理由は次のとおりです。
- 企業側の要件定義があまかった
- 求職者の詳細を把握できなかった
- 中途入社が働きづらい環境になっている
企業側の要件定義があまかった
中途採用の場合、どのような人材を求めているのか要件定義を明確にする必要があります。
要件定義とは、新たに働いて欲しい人材の能力や特性を定義することです。ただ人員が不足したから補充として求人を掲載するだけでは、要件定義が曖昧で採用ミスマッチにつながるでしょう。
求職者の詳細を把握できなかった
求職者がどのような経歴なのか、詳細を把握できなかったことでも採用ミスマッチが発生します。求職者が前職でどのような役職を担っていたのか、どのような資格を持っているのかなど詳細を把握しておくことで、自社で求める人材がどうか判断できるでしょう。
しかし、詳細を把握せずに採用してしまうと、ミスマッチの原因になってしまいます。
中途入社が働きづらい環境になっている
中途入社した社員が働きづらい環境になっていることも採用ミスマッチの要因です。例えば「うちでは~」といったように内向きな職場の場合、中途入社した社員が能力を発揮するのは難しいでしょう。
また、中途入社した社員に向けた研修やOJT制度が整備されていない職場も人材が定着しづらい環境です。中途入社だから経験豊富ですぐに戦力になると判断せずに、適切なフォローが必要です。
採用ミスマッチがもたらすデメリット
採用ミスマッチは企業に次のようなデメリットをもたらします。
- 内定を辞退されかねない
- 採用コストがかさんでしまう
- 入社後に活躍しづらい
- 社内のモチベーションが低下する
- 生産性が低下する
デメリットによっては採用活動の効率低下につながりかねません。それぞれのデメリットについて解説します。
内定を辞退されかねない
採用ミスマッチは求職者の内定辞退につながる恐れがあります。
採用選考のあいだに、企業は求職者にどのような役割や職務を任せたいのかを明確に伝えておくことが大切です。任せたいことを伝えきれていないと、求職者の意欲が下がってしまい内定辞退につながりかねません。
採用コストがかさんでしまう
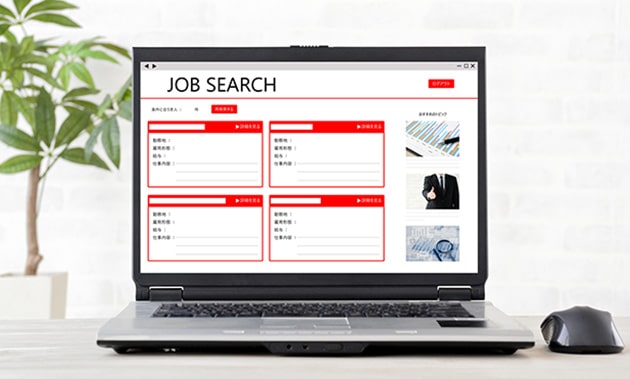
採用ミスマッチによって内定や離職が発生すると、改めて求人情報を掲載する必要があります。そのため採用コストがかさんでしまいます。
厚生労働省が発表した『採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査報告書』によれば、正社員、非正社員の1件あたりの採用平均コストは次のとおりです。
| 求人方法 | 正社員 | 非正社員 |
|---|---|---|
| 民間職業紹介事業者(紹介会社) | 85.1万円 | 19.2万円 |
| 求人情報誌・チラシ | 11.3万円 | 7.7万円 |
| インターネットの求人情報サイト | 28.5万円 | 10.8万円 |
| インターネットの求人情報まとめサイト | 6.4万円 | 3.2万円 |
| スカウトサービス | 91.4万円 | 44.0万円 |
多くの企業が利用している民間職業紹介事業者は、正社員で約85万円、非正社員で約19万円もの費用が必要です。さらに採用を担当する従業員の人的コストも発生します。(※2)
このように採用ミスマッチによって離職や内定辞退が発生すると、さまざまなコストがかさんでしまうでしょう。
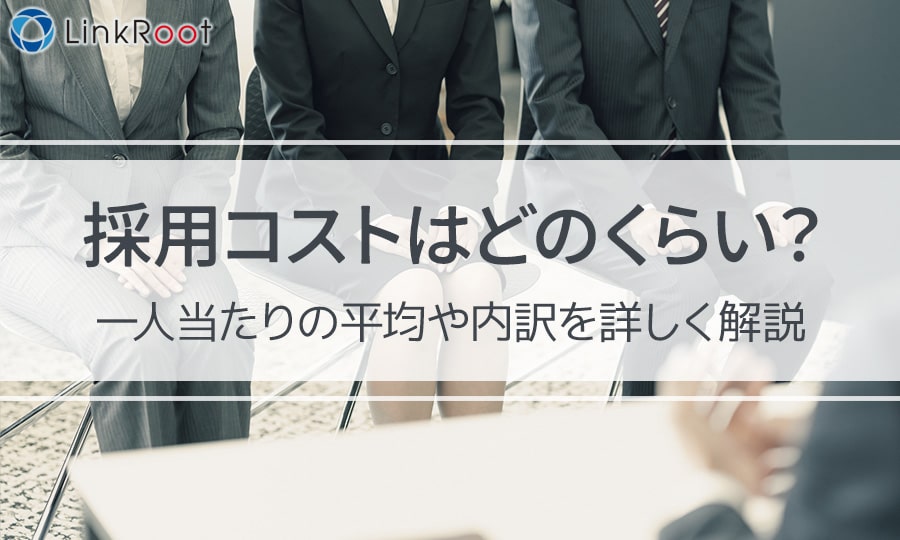
(※2)厚生労働省:採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000956216.pdf P95,96
入社後に活躍しづらい
採用ミスマッチは求職者が入社後に活躍しづらくなる原因にもなります。例えば企業が求めるスキルと求職者が持っているスキルとにズレがあった場合、入社後に活躍しづらくなるでしょう。
また、中途採用の従業員に対するケアがない職場も入社後に活躍しづらい環境といえます。
社内のモチベーションが低下する

自社が求める人材とミスマッチしている求職者を採用してしまうと、社内のモチベーションが低下する可能性があります。例えば同僚との関係性が構築できない、チームや社内の連携を妨げてしまうといったケースにつながりかねません。
チームや社内の連携が妨げられてしまうと、その他の従業員のモチベーション低下や離職が発生する恐れがあるでしょう。
生産性が低下する
採用ミスマッチによって入社した従業員は、スキルを身に着けるまでに時間がかかってしまいます。また、ミスも多発する可能性があるでしょう。
このような生産性の低下によってプロジェクトの遅延や顧客満足度の低下につながる恐れがあります。
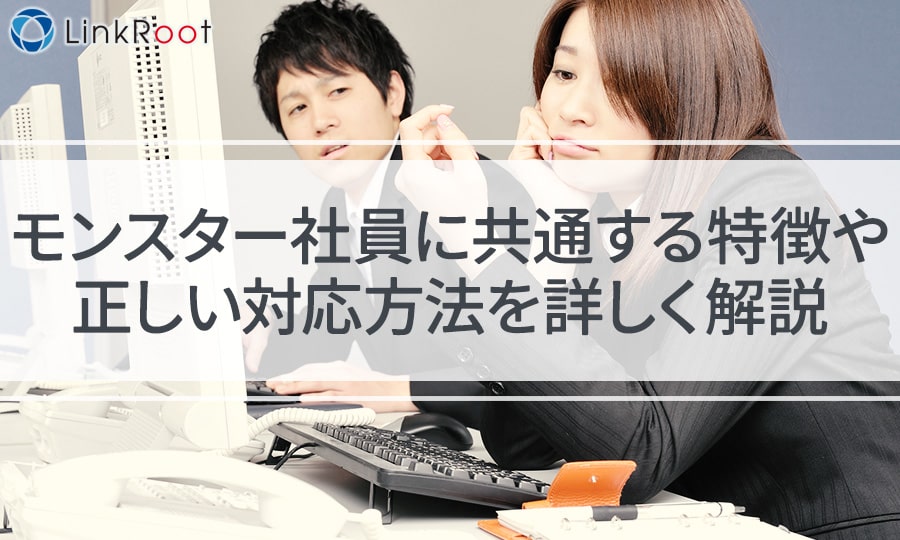
ミスマッチを防ぐ4つの方法
採用ミスマッチによるデメリットを発生させないためには、次のような方法での対策を検討してみましょう。
- リファレンス採用を導入する
- 企業の情報を適切に伝える
- 構造化面接法を導入する
- 採用前調査を検討してみる
リファレンス採用を導入する

採用にあたってリファレンスチェックを実施する、リファレンス採用を導入してみましょう。リファレンスチェックとは求職者の職歴をチェックする取り組みです。
採用活動では、求職者に履歴書や職務経歴書を用意してもらうのが一般的です。しかし、なかには履歴書や職務経歴書を詐称しているケースもあります。詐称の程度は人によってはさまざまですが、少しの詐称であっても採用ミスマッチにつながりかねません。
リファレンスチェックを導入すれば、前職でどのような職務や役職を担っていたかを調べられます。
リファレンスチェックは求職者に推薦者を紹介してもらいます。推薦者は前職の上司や同僚が一般的です。推薦者に求職者について質問することで、自社が求める人材かどうかを判断可能です。

リファレンスチェックのデメリット
リファレンスチェックは求職者について第三者の視点から意見を貰えるため、採用ミスマッチ防止に有効な取り組みです。しかし、リファレンスチェックの実施にはデメリットもあります。例えばリファレンスチェックは求職者から実施のための許可を得なければなりません。
求職者からの許可が得られなかったのであれば、リファレンスチェックは実施できません。さらに推薦者から拒否される可能性もあるでしょう。また、リファレンスチェックは自社で実施するとなると採用担当者の負担が増加しかねません。
企業の情報を適切に伝える
企業の情報が曖昧に伝わっていることで採用ミスマッチが発生してしまいます。そのため、企業の情報を適切に伝えて採用ミスマッチを防ぎましょう。どのような人材を求めているのか、どのようなスキルや経験が必要なのかなどを適切に伝えます。
さらに、自社のネガティブな情報も適切に伝えることが大切です。ポジティブな情報だけを伝えていると、求職者が入社後にネガティブな側面に触れたことで離職しかねません。例えば自社で抱えている課題や問題点を包み隠さずに伝えた後に、ポジティブなヴィジョンを話すことで意欲の低い求職者の足切りも可能です。
求職者が抱える不安もすくい上げる
面接では企業の情報を適切に伝えるだけでなく、求職者が抱えている不安もすくいあげることで採用ミスマッチを防止可能です。
例えば希望する条件や入社後のキャリアプランにおける不安などをヒアリングしておくことで、互いの希望をすり合わせられるため採用ミスマッチを防げます。
構造化面接法を導入する

構造化面接法とは事前に決めた質問項目を決まった順番通りに求職者に投げかける面接方法です。構造化面接法であれば面接官ごとに評価がバラつく可能性を抑えられます。
そのため、採用すべきだった求職者を落とし、自社が求めるスキルのない求職者を採用してしまうという採用ミスマッチリスクも抑制可能です。
構造化面接法のデメリット
構造化面接法は採用ミスマッチの防止に効果的ですがデメリットもあります。構造化面接法は質問事項が順番も含めてマニュアル化されているため、機械的な面接になりがちです。
すべての求職者に同じ質問をするため、求職者それぞれの特徴や発想を見つけづらい傾向にあります。
採用前調査を検討してみる
求職者の採用前調査(バックグラウンドチェック)も採用ミスマッチに効果的です。リファレンスチェックは求職者の前職での働き方や役職などを推薦者にヒアリングする方法です。対してバックグラウンドチェックは求職者の前職やスキルに詐称がないかを調査するだけでなく、次のような項目もチェックします。
- 学歴や職歴
- 勤務態度
- 反社会的勢力との関係
- 破産や民事訴訟歴
- SNSやインターネットメディアの調査
バックグラウンドチェックでは反社会的勢力との関係やSNSなどの投稿内容など、リファレンスチェックだけではカバーしきれない項目もチェック可能です。そのため、トラブルや信用低下につながる求職者を採用するリスクを抑えられます。
バックグラウンドチェックのデメリット
バックグラウンドチェックにもデメリットが存在します。バックグラウンドチェックもリファレンスチェックと同じく求職者から同意を得る必要があります。そのため、拒否されてしまってはバックグラウンドチェックを実施できません。また、バックグラウンドチェックを実施することを伝えると、求職者からの信頼が低下する恐れがあります。
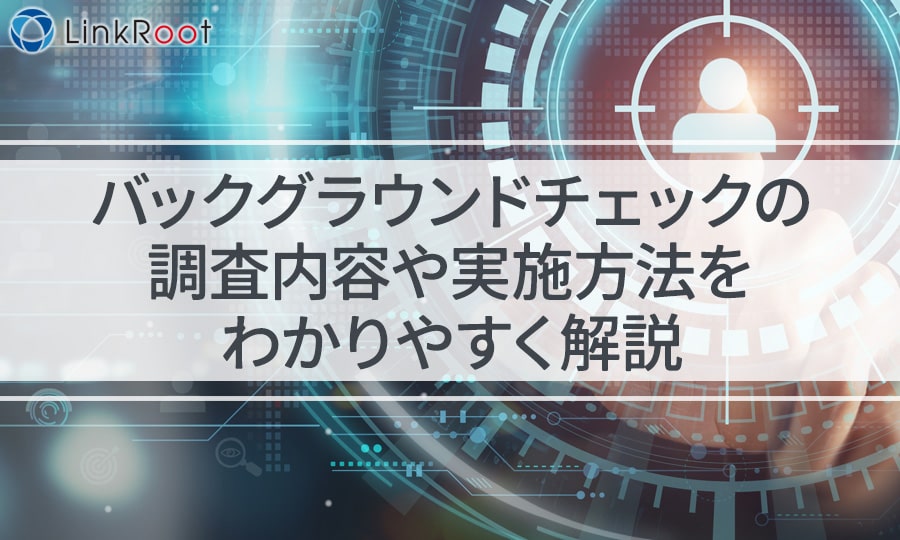
リファレンスチェックで採用ミスマッチを防ぐ
採用ミスマッチが発生してしまう理由は企業が情報を十分に伝えていない、求職者を見極められていない、面接や評価が属人化しているなどです。採用ミスマッチが発生してしまうと、内定辞退や採用コストの増加につながる可能性があります。
採用ミスマッチを防止するにはリファレンスチェックの実施が効果的です。リファレンスチェックによって候補者(求職者)の経歴・実績・スキルを把握することで、内定辞退や入社後のスキルギャップ、早期離職などを軽減し、採用コストの上昇や生産性の低下を防ぎましょう。