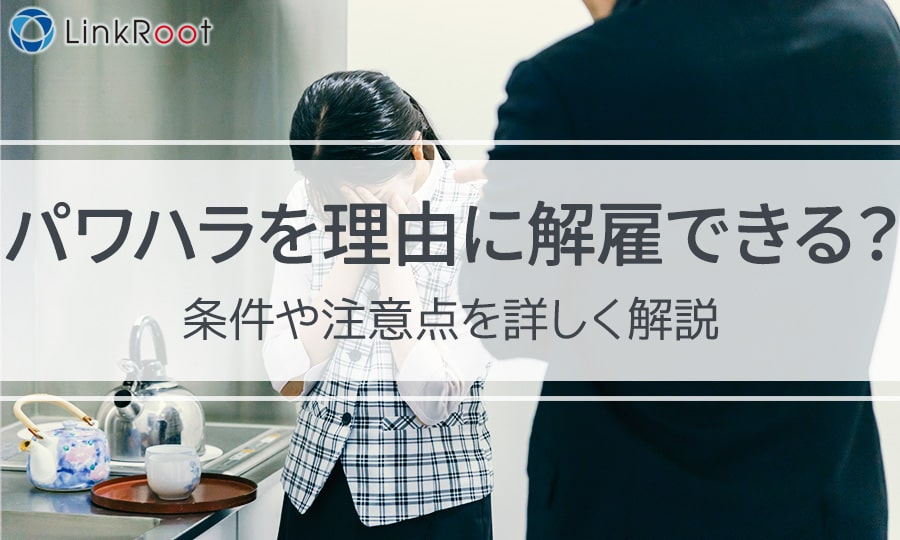パワハラとは、職場において優位な立場を利用し、業務上必要な範囲を超えた暴言や暴力によって受け手に身体的・精神的苦痛を与えることを指します。
パワハラは解雇の事由に当てはまるものの、考慮すべき条件が多く、容易に判断できるものではありません。企業が適切な対応を取らずに解雇処分を下した結果、不当解雇と見なされ裁判に発展した事例も少なくなく、トラブルを起こさないためには細心の注意を払う必要があります。
この記事では、パワハラを理由に解雇する際の条件や注意点を詳しく解説します。
パワハラに該当する行為

厚生労働省の『職場におけるハラスメント関係指針』では、以下の3つの定義をすべて満たすものがパワハラとされています。(※1)
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
これらの定義に当てはまるとされる行為には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、パワハラに該当する具体的な行為について詳しく解説します。
(※1)厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」
身体的な攻撃
身体的な攻撃には、以下のような行為があります。
- 殴る・蹴る・叩く
- 物を投げつける
- 腕や襟首を掴む
これらの暴力や傷害は、直接的・間接的問わず物理的な行為を伴います。刑法上の犯罪行為にも該当するため、刑事・民事事件につながるケースも少なくありません。
誤ってぶつかってしまったといった状況でなく、故意に危害を加えた場合、比較的軽度な行為であってもパワハラと見なされるのが一般的です。
精神的な攻撃
精神的な攻撃には、以下のような行為があります。
- 人格を否定するような言動をする
- 相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動をする
- 業務の遂行に関して、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
- 他の従業員の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う
- 能力を否定し、罵倒するような内容のメールを本人を含む複数の従業員宛に送信する
脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言といった相手に精神的な苦痛を与える言動は、精神的攻撃に当てはまります。「給料泥棒」「辞めてしまえ」といった言葉のほか、「お前はクビだ」「辞表を書け」といった解雇を匂わす言動も同様です。
職場内のいじめ
職場内のいじめには、以下のような行為があります。
- 集団で無視したり、別室に隔離し孤立させたりする
- 業務上明らかに必要のないことや遂行不可能なことを強制する
- 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする
- 私物を物色・撮影したり、私的なことに過度に立ち入り個人情報を暴露したりする
厚生労働省の『職場におけるハラスメント関係指針』によると、「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に当てはまる行為は、パワハラであると見なされます。
パワハラを理由に解雇できる?調査の流れを紹介
パワハラを理由に解雇したい場合、まずはパワハラの有無や内容を十分に調査する必要があります。
ここでは、パワハラを理由に解雇を行う前に必要な調査の流れを具体的に解説します。
被害者から事情を聞く

パワハラの被害を受けたとの申告があった場合、迅速に被害者へのヒアリングを行いましょう。
被害者は、被害によって負の感情を抱いていたり、話をうまく整理できなかったりすることもあります。事前に被害者との信頼関係を構築したうえで、メールやLINEでのやりとり、録音データや日記など、パワハラの証拠となり得るものはすべて提出してもらうよう努めましょう。ヒアリングの結果は詳しく記録しておく必要があるため、本人の同意を得てヒアリング内容を録音するのも有効です。
被害者へのヒアリングは、それだけでパワハラの有無を判断したり、加害者に指導を行ったりするためのものではありません。たとえ被害者の証言に疑問を持ったとしても、否定せずにそのまま記録しましょう。ヒアリングの記録に誤りがないかを被害者に確認してもらい、被害者の署名と捺印をもらいます。
加害者の言い分を聞く
被害者のみならず、加害者に対してもヒアリングを実施します。被害者の主張のみを信用して懲戒処分を行ってしまうと、不当な扱いを受けたとして加害者側から訴訟を起こされるケースもあるため注意が必要です。加害者へヒアリングする際は、必ず被害者の同意を得たうえで行いましょう。
加害者へのヒアリングでは、被害者から申告のあった被害内容についての事実確認や、被害者との関係性、パワハラと疑われる行為に至るまでの経緯といった内容を聴取します。被害者へのヒアリングと同様に、聴取内容は加害者の言い分を否定せずそのまま記録し、加害者の署名と捺印をもらいます。
食い違うポイントを検証する
被害者・加害者双方の言い分に食い違うポイントがあった場合、事実確認をする必要があるため、両者に対して再度ヒアリングを行いましょう。双方の言い分について質問し、もし以前と違う証言をするようであれば、その証言は信憑性に欠けます。聴取内容は記録を取り、本人に確認させ、署名と捺印をもらいます。
再度ヒアリングを実施しても事実関係が確認できない場合、目撃者や職場の同僚といった第三者へのヒアリングを実施することも有効です。パワハラについての客観的な証拠を得られるだけでなく、同じ加害者から同様のパワハラ被害を受けている人物がいた場合、被害者の主張が正しいと認められることもあります。
第三者への聴取を行う際も、事前に必ず被害者の承諾を得たうえで行いましょう。そのほか、メールやLINEの履歴を被害者・加害者の言い分と照合し、不自然な点がないかを確認することも重要です。
パワハラを理由に懲戒解雇するときの流れ
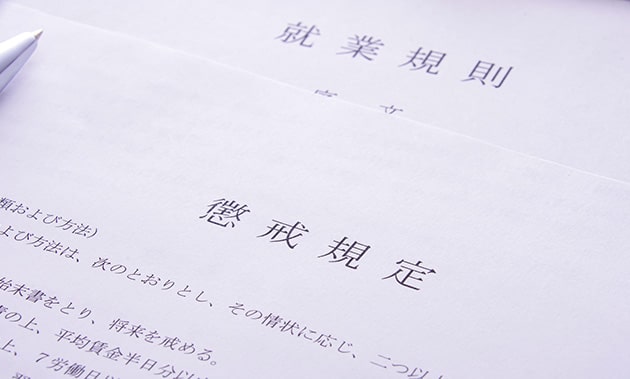
パワハラを理由に懲戒解雇をする場合、どのような流れで進めていけばよいのでしょうか。
ここでは、パワハラを理由に懲戒解雇するときの具体的な流れを解説します。
事実確認を行う
先述したとおり、パワハラの被害を受けたとの申告があった場合、まずはパワハラの有無を調査し、事実確認を行う必要があります。
この調査を怠ると、パワハラであるか否かの判断を誤ってしまうこともあり、当事者との間で裁判に発展したり損害賠償責任を負ってしまったりしたケースも少なくありません。
当事者および第三者へのヒアリングや、メールやLINEの履歴といった情報をもとに、パワハラであるかを判断することはもちろん、加害者への処分対応として懲戒解雇が適切であるかを見極める意味でも重要な役割を果たします。
就業規則を確認する
パワハラによって懲戒解雇とする場合、自社の就業規則にパワハラや懲戒解雇に関する規定が記載されていなければいけません。
厚生労働省のモデル就業規則第12条では、職場のパワハラ禁止に関する規定の記述があり、第68条では、第12条に違反し、かつ、その情状が悪質と認められる場合、懲戒解雇事由に該当するとされています。(※2)
自社の就業規則を確認し、定められた手続き通りに懲戒処分を進めていきましょう。
(※2)厚生労働省「モデル就業規則」
弁明の機会を与える
懲戒解雇に先立ち、加害者に弁明の機会を与えます。弁明の機会とは、懲戒処分の内容を加害者に通達し、それに対しての本人の言い分を聴取することです。パワハラの有無を調査するヒアリングとは別に実施され、最終的に下す懲戒処分の内容が妥当であるかを判断する場でもあります。
弁明の機会を与えなかった場合、不当解雇として裁判に発展してしまうこともあります。あらかじめ加害者の言い分を聞いておくことで、トラブルの発生を未然に防ぐことが可能です。
解雇通知書を作成する
弁明の機会を与えたうえで懲戒解雇することが決定したら、解雇通知書を作成します。解雇通知は口頭にて行うことも可能ではあるものの、証拠が残らずトラブルにつながる恐れもあるため、必ず書面で通知することが重要です。
また、作成前に社内の幹部や加害者本人の直属の上司に懲戒解雇する旨を共有し、承諾を得ておくとよいでしょう。
解雇について公表する
加害者への解雇通知後、社内で懲戒解雇について公表します。パワハラの相談対応では、被害者や加害者に関する個人情報を多く取り扱います。過去には、加害者の氏名や懲戒処分の内容を事細かに公表したことで、名誉毀損として訴訟を起こされた事例もあるので注意が必要です。
懲戒処分の内容が事実であっても当事者の氏名は明かさず、社内の規律維持に必要な範囲での内容にとどめ、当事者のプライバシーに配慮して公表しましょう。懲戒解雇の公表は、あくまでも加害者に対する見せしめのために行うものではありません。パワハラといった問題行動に対し懲戒処分を科すことを明確に示すことで、他の従業員による問題行動を防ぎ、社内の規律を高める目的があります。
パワハラを理由に解雇するときの注意点

パワハラを理由に解雇する場合、加害者との間でトラブルが発生しないよう、以下の注意点を考慮する必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
加害者に対する指導を行う
パワハラの事実が発覚した場合、会社はまず加害者に対して指導を行い、再発防止のために改善を促す必要があります。
一般的にパワハラによる懲戒解雇が認められるのは、会社が加害者にパワハラをやめるよう指導してもパワハラを繰り返したケースや、加害者が反省していないケースであるとされています。
会社がパワハラを認識していたにもかかわらず指導をしなかったり、指導をしても加害者に反省する機会を与えずに解雇したりした場合、不当解雇と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
正当な指導であるケースもある
一見厳しい指導であっても、正当な指導であればパワハラには該当しません。指導理由が嫌悪や退職に追い込みたいといった感情から来るものでなく、目的や経緯が指導として正当とされる場合であっても、パワハラを受けたと認知してしまう人は少なからずいるでしょう。
その際に、被害を受けたとされる従業員の主張だけを判断材料として、パワハラと認定するのは誤りです。先述したパワハラの定義にもあるように、業務上必要かつ相当な範囲を超えた指導であるかどうかが、パワハラか正当な指導かの線引きとなります。
会社側に責任があるケースもある
厚生労働省の『職場におけるハラスメント関係指針』には、企業がパワハラ防止のために必ず講じなければならない措置が明記されています。パワハラが発生しないよう努めることはもちろん、万が一パワハラが発覚した際に迅速な対応を取らなかった場合、企業として安全配慮義務違反や使用者責任を問われることになるでしょう。一般的に、これらは損害賠償責任を伴います。
パワハラをめぐる問題からさらにトラブルを招かぬよう、厚生労働省が示す指針をもとに日頃から適切な対応を取っておくことが重要です。
証拠がない場合は不当解雇と見なされる
パワハラの有無を判断するのに必要な調査を実施し、結果的に十分な証拠を得られなかった場合、加害者を解雇することはできません。証拠が不十分な解雇は不当解雇と見なされ、裁判に発展した際は企業側が敗訴することになります。
パワハラの申告を受けたとしても、録音データや動画およびLINEやメールの履歴といった信用性の高い証拠を得られない場合、当事者の配置転換をするなど懲戒処分以外の対応を検討するのがよいでしょう。
事前に就業規則に記載しておく
先述したとおり、パワハラを理由に懲戒解雇を行う場合、パワハラや懲戒処分に関する規定が自社の就業規則に記されていることが前提となります。
法律では、パワハラの加害者を厳正に対処する旨の方針とその対処の内容を、就業規則などの文書に規定し従業員に周知・啓発することを義務化しています。中小企業にかかわらず、自社の就業規則にパワハラが懲戒解雇にあたる旨の記載がない場合、早急に規準を定めましょう。
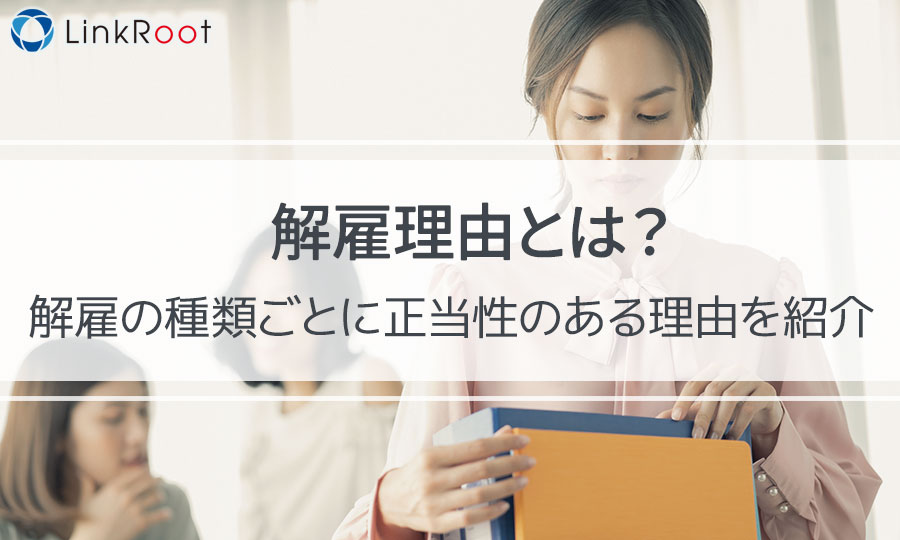
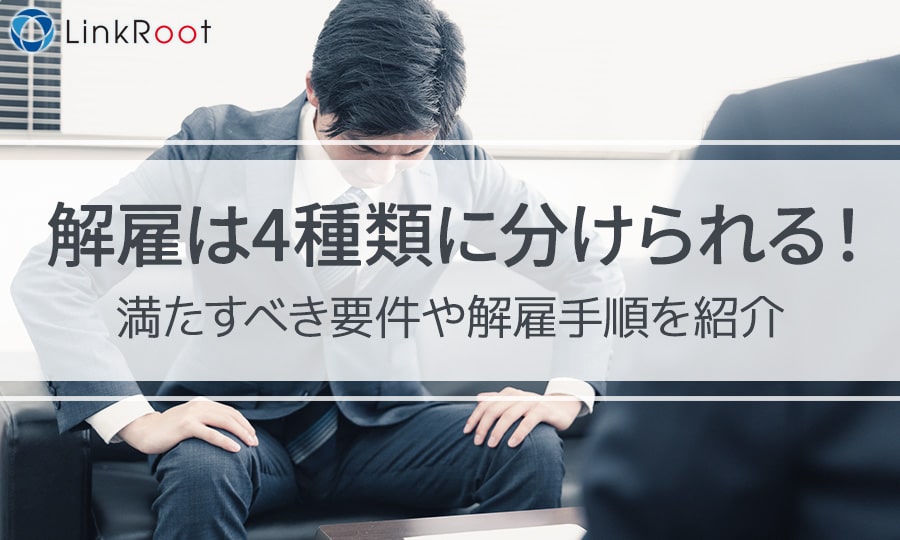
パワハラの有無や解雇の妥当性を慎重に判断しよう!
今回は、パワハラを理由に解雇する場合の条件や注意点について解説しました。パワハラで加害者を解雇できるのは、調査や指導を適切に実施し、事実確認ができている場合に限ります。安易な解雇や重すぎる処分は不当解雇と見なされ、損害賠償といったトラブルに発展しかねません。
企業として、パワハラ防止指針といったルールを日頃から遵守していなかった場合も同様です。パワハラに該当するか、懲戒解雇が妥当であるかの判断は、専門的な知識を要することもあるため、弁護士に相談するなどして慎重に行いましょう。