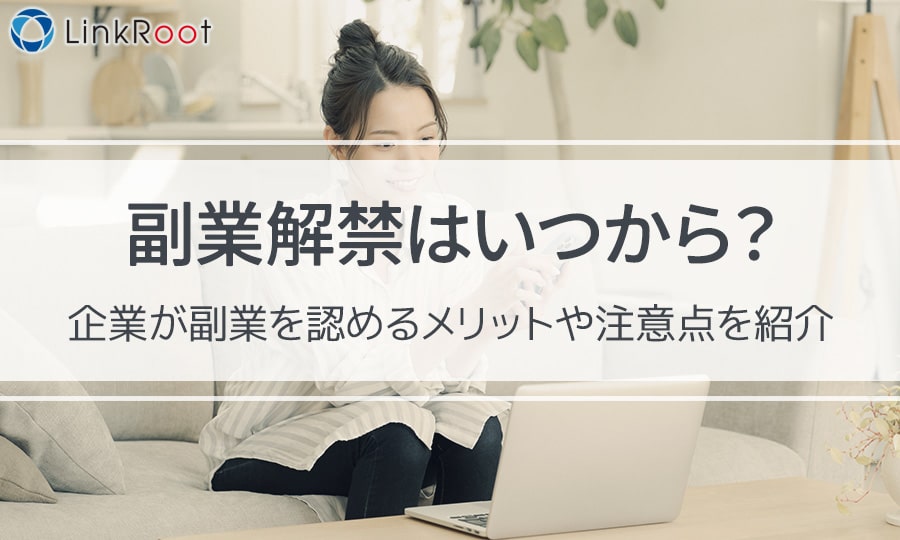副業を解禁することは、働きやすい職場環境を構築するための手段のひとつです。従業員が自分のスキルや経験を活かせる場を広げることで、優秀な人材の確保や離職率の低下を期待できるでしょう。
今回は、副業解禁に関する政府のガイドラインや、副業を認めるメリット・デメリットなどを紹介します。副業解禁を進めるときのポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
副業解禁の義務化はいつから?

2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表したことをきっかけとして、副業を解禁する企業も増えてきました。(※1)ただし、副業解禁は法律などで義務化されているわけではありません。副業を認めるかどうかは企業が自由に判断できるため、依然として就業規則などで副業を禁止している企業も存在します。
一方で、副業を禁止する法律も存在しません。従業員は、仕事以外のプライベートの時間を基本的に自由に使えます。就業規則などで副業を禁止していない場合は、従業員の副業や兼業を認めることになるでしょう。
ただし、自由に副業ができる状態にしておくと、本業に支障が出るなどのトラブルが発生する可能性もあります。副業を認めるなら、事前に申請してもらうようなルールを設定しておくことが重要です。
1.副業に関する政府のガイドライン
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、副業や兼業を希望する人が増加している状況を受けて策定されました。副業の解禁を義務化するものではありませんが、ガイドラインのなかには、従業員の希望に応じて副業解禁を検討すべきこと、副業を認める際は安全配慮義務に注意すべきことなどが記載されています。
また、同時にモデル就業規則も改定され、副業を禁止する項目が削除されました。その代わりに「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」という内容が第70条に記載されています。(※2)労務提供上の支障がある場合や企業秘密が漏洩する場合には、副業を禁止したり制限したりできる旨も記載されているため、就業規則を作成する際の参考にしましょう。
2.政府が副業解禁を推進している理由
同ガイドラインのなかで、副業解禁を推進すべき理由として以下のようなことが挙げられています。
- 優秀な人材の確保
- イノベーションの創出
- 地方創生
副業を解禁することで柔軟に働ける職場環境を構築すれば、優秀な人材を集めやすくなるでしょう。また社会全体として見ると、副業解禁によって社内外のアイデアやスキルを企業間で共有できる状態をつくれます。イノベーションや地方創生にもつながるため、政府としては副業解禁を積極的に進めています。
3.従業員が副業解禁を望む理由
一方、以下のような理由から、副業解禁を望む従業員も増えています。
- 収入を安定させたい
- スキルアップを図りたい
- 活躍の場を広げたい
- 新しい人間関係をつくりたい
- プライベートな時間を有効活用したい
業種や事業内容によっては副業を認めるのが難しいケースもありますが、できる限り従業員の要望に応じることで、働きやすい環境を構築できるでしょう。
企業が副業を解禁するメリット
企業が副業を解禁することには、以下のようなメリットがあります。
1.従業員のスキルアップを期待できる

従業員のスキルアップや成長を期待できることは、副業を認める大きなメリットです。日々の業務のなかで従業員の成長をサポートすることには、コスト的にも時間的にも限界があります。教育・研修制度があったとしても、同じ職場で働いていると幅広いスキルを身につけることは難しいでしょう。
一方で副業を解禁すれば、普段担当している仕事以外に関われるため、幅広い経験を積んだり、新しいスキルや知識を習得したりできます。副業を通して習得したスキルや経験を活かして、職場でより活躍してくれることも期待できるでしょう。副業はプライベートな時間に従業員が自主的に行うものであるため、企業側が教育費用を支払う必要もありません。
2.優秀な人材を確保できる
副業を解禁すれば、優秀な人材の確保につながります。少子高齢化による労働力不足が進むなか、人材を確保することは企業の大きな課題です。副業を認めることで能力が発揮できる場所を広げておけば、優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。
また、副業解禁によって人材の定着率を高めることも可能です。副業を禁止していると、従業員が他の仕事にチャレンジしたいと思ったときの選択肢が離職しかありません。しかし、副業を認めれば現在の仕事を続けながら新しい分野に挑戦できるため、離職されるケースを減らせるでしょう。
3.事業の拡大につながる
副業を解禁することで事業を拡大できるケースもあります。従業員が副業をすることで人脈が広がり、新たな事業パートナーを得たり、新事業を展開できたりする可能性もあるからです。副業で得た情報やアイデアをもとに、新しい商品やサービスを考案できるケースもあるでしょう。
ここまで紹介したように、副業を解禁することにはさまざまなメリットがあります。企業の成長につながる可能性もあるため、ルールの整備も含めて副業解禁を検討していくことが重要です。
企業が副業を解禁するデメリット
多くのメリットがある一方、離職率が高まったり、本業に支障が出たりする可能性もあります。以下のようなデメリットについても理解したうえで、副業解禁を検討しましょう。
1.離職率が高まる可能性もある
副業を解禁すると、離職率が高まる可能性もあります。副業によって身につけたスキルや知識を利用して、転職や独立を考える従業員もいるかもしれません。また、副業で関わっていた企業に引き抜かれてしまう可能性もあります。
優秀な従業員ほど転職のためのスキルを習得するのが早く、他の企業が採用したいと考える可能性も高いため注意が必要です。
2.本業に支障が出るケースもある

従業員によっては、副業に注力するあまり、本業に支障が出てしまうケースもあります。たとえば、プライベートな時間を副業に使いすぎ、疲労が蓄積したり、本来の業務の効率が低下したりする従業員もいるかもしれません。
従業員のスキルアップなどを目的として副業を解禁しても、本業の生産性が低下してしまっては意味がないでしょう。副業を解禁するなら、本業に支障が出ないようなルールを設定しておくことが重要です。
3.情報漏洩のリスクがある
情報漏洩のリスクがあることも、副業を解禁するデメリットのひとつです。社内の機密情報や顧客情報、ノウハウなどが流出すると、大きな損害が発生する可能性もあります。とくに同業他社に情報が流れると、顧客を奪われたり、競争に負けてしまったりするケースもあるでしょう。
上記のようなリスクを防止するために、情報の扱いに関するルールを設定したり、同業他社での副業を禁止したりする企業も存在します。機密情報や顧客情報などは企業の知的財産であるため、流出することのないよう、しっかりと管理することが重要です。
副業を解禁するときのポイント
実際に副業を解禁するときは、就業規則の改定や勤怠管理の徹底が必要です。状況に応じて社会保険の見直しも行いましょう。ここでは、副業を解禁するときのポイントを紹介しますので参考にしてください。
1.就業規則を改定する
副業を解禁するときは、就業規則を改定しましょう。とくに現在の就業規則のなかで副業を禁止している場合は、文言を変更しなければなりません。厚生労働省のモデル就業規則などを参考にしながら、副業を認める旨を記載しましょう。
また、必要に応じて副業を制限できるケースについても明記しておくことが大切です。就業規則を変更したら、従業員に周知する必要があります。同時に副業の申請ルールなども明確にして、従業員へ説明しておきましょう。
2.勤怠管理を徹底する

副業解禁を進めるなら、勤怠管理を徹底することも重要です。従業員に副業を認めると、労働時間が長くなってしまいます。休息時間が短くなり、体調を崩してしまう従業員もいるかもしれません。
本業に支障が出ないよう、過剰な残業が発生していないか、有給休暇をしっかりと消化できているか、今まで以上に勤怠管理を徹底することが大切です。
3.社会保険を見直す
状況によっては、社会保険の見直しが必要です。従業員が副業先でも社会保険の適用対象となる場合は、自社における賃金と副業先における賃金を合計し、按分したうえで社会保険料を算出しなければなりません。複雑な計算が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
4.健康状態を管理する
勤怠状況と同様、従業員の健康状態の管理も徹底する必要があります。過剰な労働により疲労やストレスが蓄積し、本業の生産性が低下したり、休職する従業員が増えたりするケースもあるからです。
従業員のスキルアップや定着率向上を目的として副業を解禁しても、働けなくなっては意味がありません。また、本業に支障が出ないよう、従業員に注意喚起したり、自己管理を促したりすることも重要です。
ルールを明確にしたうえで副業解禁を進めよう!
今回は、副業解禁に関する政府のガイドラインやメリット・デメリットなどを紹介しました。副業を解禁することは、法律によって義務化されているわけではありませんが、働きやすい職場環境を構築するために副業を認める企業も増えてきています。
副業解禁を進めることで、優秀な人材の離職を防止できる、従業員のスキルアップにつながるなどのメリットを得られるでしょう。一方で、副業に注力するあまり本業に支障が出たり、体調を崩したりする従業員もいるかもしれません。副業を解禁するなら申請ルールなどを明確にしたうえで、勤怠管理や健康管理も徹底しましょう。
(※1)厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
(※2)厚生労働省「モデル就業規則」