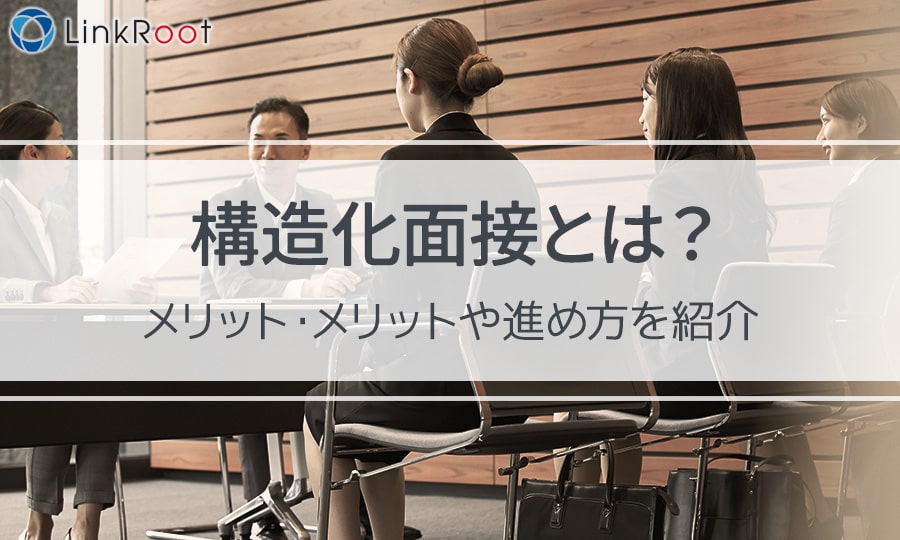構造化面接は、自社に合った人材を効率よく採用する方法のひとつです。事前に質問項目を決めておくため、誰が面接を担当しても同じような結果を得られるでしょう。
今回は、構造化面接の特徴やメリット・デメリットなどを紹介します。導入するときの注意点や具体的な質問例についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
構造化面接とは?

構造化面接とは、事前に決めておいた質問項目に沿って、応募者との会話を進めていく採用手法です。評価基準についても事前に設定しておき、一定の基準に従って合否を判定します。誰が面接官であっても同じ質問項目と評価基準を用いるため、主観を排除でき、面接や評価を安定させることが可能です。
構造化面接はもともと臨床心理学の分野で活用されてきた手法ですが、Google社が取り入れたことをきっかけとして注目されるようになりました。近年は、面接官による評価のブレを防止したり、面接の公平性を高めたりすることを目的として、構造化面接を実施する企業も出てきています。
構造化面接と非構造化面接の違い
非構造化面接とは、応募者に対して面接官が自由に質問を投げかける採用手法です。基本的にそれぞれの面接官が質問項目を決めるため、面接の自由度が高く、会話の流れに合わせて幅広い内容を質問できます。質問内容によっては、応募者の本音や考え方を詳しく把握することも可能です。
一方で、面接官の主観が入りやすく、評価がブレやすいというデメリットもあります。面接官が自分の好みで合否を決定するケースもあるため、ミスマッチが発生したり、求める人材像と異なったりすることもあるでしょう。
構造化面接と半構造化面接の違い
半構造化面接とは、事前に決めておいた質問と、自由な質問を組み合わせる採用手法です。構造化面接と非構造化面接の中間的な手法といえるでしょう。面接のなかで必ず質問すべき項目を決めておくことで、面接官によるブレを最小限に抑えつつ、自由な質問を通して幅広い内容を把握できます。
評価を安定させながら柔軟な面接を実施したい場合は、半構造化面接を選択するとよいでしょう。ただし、半構造化面接を実施するときは、面接が長くなりすぎないよう注意する必要があります。決められた質問と自由な質問を投げかけるため、適度な時間で面接が終わるよう調整することが大切です。
構造化面接のメリット
構造化面接には、面接官の違いによるブレを減らせる、ミスマッチを防止できるなどのメリットがあります。以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.面接官の違いによるブレが少なくなる
面接官の違いによるブレを減らせることは、構造化面接の大きなメリットです。質問項目と評価基準が固定されているため、面接官の技量や経験によって合否の判断が変わることは少ないでしょう。たとえば、ベテランの面接官と新人の面接官のどちらが担当しても、基本的には同じ結果を得られます。
また、面接官の主観を排除できるため、公平な評価を実施することが可能です。応募者から不採用になった理由を聞かれた場合でも評価基準を明確に示せるため、不満が出る可能性を減らせるでしょう。
2.ミスマッチを防止できる

ミスマッチを防止しやすいことも構造化面接のメリットのひとつです。構造化面接を実施するときは、事前に求める人材像を明確にします。具体的には必要なスキルや経験、コミュニケーション能力などを明確にしたうえで、それぞれの有無や程度を把握するための質問を決定します。決められた質問を投げかけることで、自社に合う人材かどうかを効率よく見極められるでしょう。
その結果、自社に合わない人材を採用したり、逆にマッチする人材を見逃したりする可能性を減らせます。せっかく人材を採用してもミスマッチにより早期に退職されると、コストや時間が無駄になってしまいます。ミスマッチを減らして効率よく人材を確保したい場合は、構造化面接を取り入れるとよいでしょう。
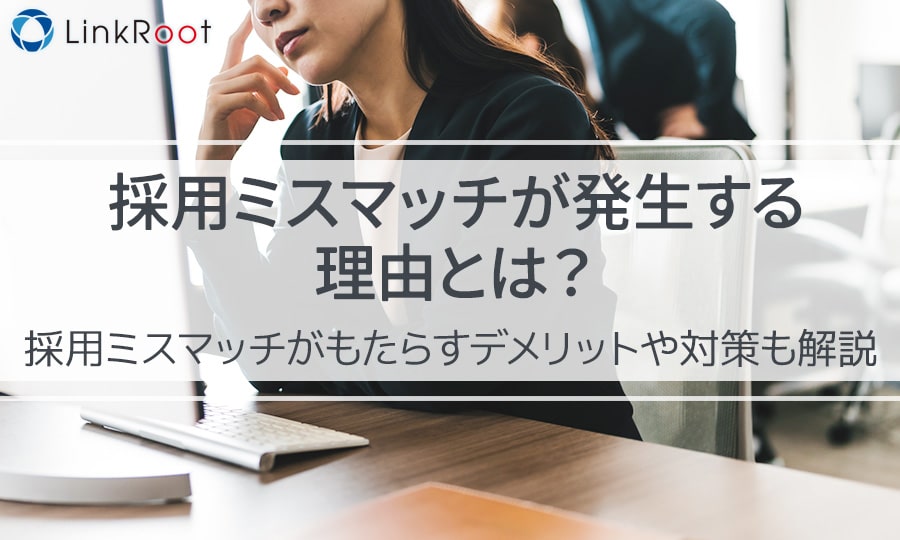
3.面接を効率よく進められる
構造化面接を実施すれば、面接を効率よく進めることが可能です。事前に質問項目と評価基準を決めておくため、関係のない会話をしたり、合否の判断に悩んだりするケースを減らせます。応募者が増えてもテンポよく面接を実施できるため、多くの人材を採用するときは構造化面接が適しているでしょう。
ただし、面接を効率化したい場合は、質問項目を厳選しておくことが重要です。詳細な内容を把握したいからといって質問項目を増やしすぎると、面接にかかる時間が長くなってしまうため注意しましょう。
4.無意識の偏見を排除できる
構造化面接を取り入れれば、面接官の無意識の偏見を排除できます。無意識の偏見とは、自分の経験や価値観の影響によって、偏った思考や判断に陥ってしまうことです。たとえば、自分と同じようなスキルをもつ人を高く評価したり、性別によって仕事の向き・不向きを判断したりすることが挙げられます。
このような無意識の偏見に注意しておかなければ、応募者の能力を客観的に評価できないでしょう。優秀な人材を見逃したり、ミスマッチが発生したりする可能性もあるため、構造化面接によって無意識の偏見を排除することが大切です。
構造化面接のデメリット
構造化面接には、似たような回答が増えやすい、機械的な面接になりやすいなどのデメリットがあるため注意しましょう。各デメリットの詳細は以下のとおりです。
1.面接の準備に時間がかかる
構造化面接のデメリットとして、準備に時間がかかることが挙げられます。事前に質問項目や評価基準を細かく設定しておく必要があるため、自由に質問をする面接手法より準備に時間がかかるケースも多いでしょう。決定した内容を面接官と共有し、すり合わせを行う時間も必要です。
また、質問項目や評価基準は定期的にアップデートしなければなりません。期待していたような人材が集まらない場合や、求める人材像が変わった場合は、その都度、質問項目や評価基準を変更する必要があります。時間のかかる作業であるため、担当者が負担を感じることもあるでしょう。
2.似たような回答になりやすい
応募者の回答が似たようなものになりがちな点も構造化面接のデメリットです。どの応募者に対しても同じ質問をするため、同じような回答ばかりが集まってしまうケースもあるでしょう。その結果、応募者の個性を把握できなくなったり、回答の違いが少ないために評価が難しくなったりする可能性もあります。
また、構造化面接における一般的な質問事項がインターネットなどで出回り、模範的な回答を準備されてしまうケースもあります。合格するために本音を隠して回答する応募者が出てくる可能性もあるため、内面を知れるような質問を組み合わせることが重要です。
3.機械的な面接になりやすい

構造化面接を実施すると、面接官のスキルによっては、人間的な会話ではなく機械的な会話になるケースもあるでしょう。とくに決められた流れに沿って次々に質問を投げかけると冷たいやり取りになり、圧迫面接のような印象を与えてしまう可能性もあります。
応募者が必要以上に緊張してしまい、本音を話せなくなることもあるため注意しなければなりません。アイスブレイクを取り入れる、ゆっくりとした口調で質問するなど、面接の雰囲気が固くなりすぎないよう配慮しましょう。
4.潜在的な能力を見極めにくい
応募者の潜在能力を見極めにくいことも構造化面接のデメリットのひとつです。事前に決めておいた質問をすることで、合格基準を満たしているかどうかを客観的に把握することは可能ですが、それ以上の能力や個性を見極めるのは難しいでしょう。
応募者の能力をより詳しく把握するためには、一次は構造化面接、二次は非構造化面接にするなど、複数の手法を組み合わせる必要があります。グループワークやアセスメントツールを活用するのもよい方法です。
構造化面接を実施するときの手順
構造化面接を実施するときは、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。具体的には、以下のような手順で進めましょう。
1.採用したい人材像を明確にする

構造化面接に限った話ではありませんが、まずは採用したい人物像を明確にすることが重要です。求める経験やスキル、資質や性格などを明確にしましょう。具体的には、主体的に仕事を進められる人、コミュニケーション能力が高い人、プロジェクトマネジメントの経験がある人、といったペルソナを設定します。
部署や役職によって採用したい人物像が異なるケースもあるため、それぞれの課題や不足している人材を把握したうえでペルソナを設定しましょう。
2.質問項目・評価基準を決める
採用したい人物像かどうかを見極められるよう、質問項目と評価基準を設定します。先に評価項目と評価基準を決めてから、質問項目を検討するのが基本です。
たとえば、評価項目のひとつとして「コミュニケーション能力」を設定した場合、「チームで仕事をするうえで大切にしていることは何ですか?」といった質問を準備するとよいでしょう。具体的な質問の例は、後ほど紹介します。
3.起点となる質問をする
実際に構造化面接を実施するときは、起点となる質問からスタートしましょう。起点となる質問とは、評価項目に関して大まかな内容を聞くための質問です。まずは起点となる質問を投げかけ、応募者の特性をざっくりと把握しましょう。
4.フォローアップとなる質問をする
起点となる質問に対する回答を得られたら、フォローアップとなる質問をして、応募者の特性を詳しく把握していきましょう。フォローアップの質問をするときは、評価項目や起点となる質問とズレすぎないように注意することが大切です。
たとえば、起点となる質問への回答について、その理由や具体例、周囲の反応や自身の反省点などを聞いてみるとよいでしょう。
5.合否を判定する
面接が終了したら合否を判定します。構造化面接を行うときは、面接官の主観をできる限り排除し、事前に決めておいた評価基準に沿って合否を検討することが重要です。応募者の回答を記載した面接シートを作成しておけば、面接官以外の人事担当者なども評価に参加できます。
また、良い回答例や悪い回答例などを記録しておけば、今後の採用活動に役立てられるでしょう。
構造化面接における質問例

ここでは、構造化面接における質問例を紹介します。構造化面接では客観的な評価項目と評価基準を設けるため、応募者の行動や仮定の状況に関する質問をするのが一般的です。以下、具体的な例を紹介しますので、質問を作成するときの参考にしてください。
1.過去の行動に関する質問
過去の行動に関する質問例は、以下のとおりです。
- 前職ではどのような作業を担当していましたか?
- 上司や同僚と関わる際、どのようなことを意識していましたか?
- どのような目標を設定していましたか?
- 成果を出すためにどのような行動をしましたか?
- 職場でどのような評価をされていましたか?
過去の行動について質問することで、応募者のスキルや経験、性格などを見極められます。
2.仮定の状況に関する質問
仮定の状況に関する質問では、特定の状況下でどのように行動するかを応募者に問いかけます。具体例は以下のとおりです。
- システムのトラブルが発生したら、どのように対応しますか?
- クライアントから知らない内容を聞かれたら、どのように回答しますか?
- 新サービスの開発を依頼されたら、どのように行動しますか?
仮定の状況を設定して質問することで、応募者の考え方や本音、価値観などを把握できるでしょう。
構造化面接を導入するときの注意点
ここまで解説したように、構造化面接は評価のブレを防止できる便利な手法ですが、うまく導入しなければ期待していたほどの効果を得られない可能性もあります。
ここでは構造化面接を導入するときの注意点を解説しますので、チェックしておきましょう。
1.模範的な回答が増える可能性がある

構造化面接を導入するときは、模範的な回答が増えすぎないように注意しなければなりません。とくに、どのような企業でも質問するような一般的な内容ばかりを設定すると、模範回答が出回ってしまう可能性が高まります。自社の事業内容に合わせてオリジナルの質問を作成するなど、対策を検討しておきましょう。
2.誘導質問をしないようにする
構造化面接では誘導質問をしないように注意しましょう。誘導質問とは、面接官が期待している回答を、応募者が簡単に予測できてしまう質問のことです。たとえば、「残業は可能ですか?」といった質問は誘導質問に該当します。「はい」と答えたほうが合格しやすいと、簡単に判断されてしまうからです。
誘導質問をすると、ほとんどの人が同じ回答をするため、応募者ごとの特性や考え方を把握することはできません。応募者の本音を把握できなくなり、ミスマッチが発生する可能性もあるため注意が必要です。
3.状況に応じて質問内容を変更する
構造化面接における質問内容は、適宜、変更する必要があります。求める人材像や事業内容、採用活動の方針が変わった場合などは、状況に合わせて質問内容を見直しましょう。
また、前述のような模範回答が多い場合、質問内容が不適切である可能性もあります。質問内容を見直して、応募者のスキルや特性をしっかりと把握できる状態をつくりましょう。
4.面接官のトレーニングを実施する
構造化面接に慣れていない場合は、面接官のトレーニングを実施することも重要です。面接官が不慣れな状態では、質問を淡々と投げかけるだけになってしまうかもしれません。面接が固い雰囲気になり、本音を引き出せないケースもあるでしょう。
このような状況を防ぐためにも、実際の面接を想定したロールプレイングを行うのがおすすめです。たとえば従業員に応募者の役をしてもらい、面接の流れや雰囲気づくりに慣れてもらえば、採用活動をスムーズに進められます。
構造化面接のメリット・デメリットを把握したうえで取り入れよう!
今回は、構造化面接の特徴やメリット・デメリットなどを紹介しました。構造化面接では事前に質問項目と評価基準を設定するため、面接官の主観を排除でき、客観的な評価を実施できます。面接時のやり取りも最小限で済むため、応募者が多い場合でも採用活動を効率よく進められるでしょう。
ただし、似たような回答が増えやすい、面接が機械的な雰囲気になりやすいなどのデメリットもあります。応募者の本音や潜在的な能力を把握できないケースもあるため、必要に応じて別の面接手法を組み合わせることも重要です。構造化面接を導入するなら、デメリットへの対応方法も検討しておきましょう。