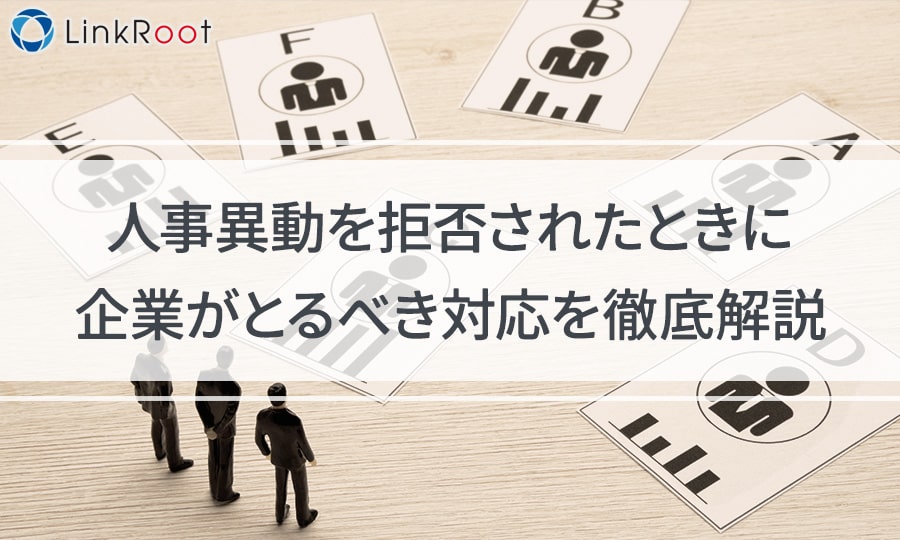人員配置の最適化や業務効率化などを目的として人事異動を行うとき、従業員に拒否されて困るケースもあるでしょう。企業側には人事異動を行う権利があるものの、無理に進めると労使間のトラブルが発生したり、優秀な人材が離職したりする可能性もあります。
そこで今回は、人事異動を拒否されたときに企業が取るべき対応について詳しく解説します。人事異動を拒否されないためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
人事異動は拒否できる?
まずは、人事異動の意味や企業がもつ人事権について確認しておきましょう。
人事異動とは?

人事異動とは、企業側が従業員の所属部署・役職・地位・勤務エリアなどを変更することです。従業員のスキルアップを図ること、適材適所を実現すること、業務を効率化することを主な目的として実施します。
以下のように、人事異動にはさまざまな種類があります。
- 部署異動:所属する部署・チームを変更する
- 昇格・降格:役職・地位・ポジションを変更する
- 転勤:所属する事業所・営業所を変更する
- 出向:雇用契約を維持しながら関連会社などへ異動する
- 転籍:雇用契約を解除してから関連会社などへ異動する
企業の目的に合わせて適切な方法で人事異動を行うことで、人件費を最適化したり、組織力を強化したりすることが可能です。
従業員は原則として人事異動を拒否できない
従業員は、企業側が決定した人事異動を拒否することは原則としてできません。企業には人事権があるからです。人事権は就業規則などで定められていることが多く、企業はこの権利に従って人事異動を実施します。
就業規則には、「業務上必要がある場合、就業場所や業務内容の変更を命じることがある」旨を記載しておくのが一般的です。厚生労働省のモデル就業規則にも人事権に関する項目があるため、上記のような内容を就業規則に記載している企業が多いでしょう。(※1)
就業規則のなかで人事権が定められている場合、基本的には従業員は人事異動に従う必要があるのです。ただし、後述するように正当な理由がある場合は、人事異動の拒否が認められるケースもあります。
人事権の規定がない場合は強制的な人事異動を実施できない
就業規則や雇用契約のなかに人事権に関する記載がない場合は、原則として強制的な人事異動を実施することはできません。ただし、労使間の合意があれば人事異動を実施することは可能です。
また、明確な規定がなくても、人事異動を実施することが企業の慣習となっている場合は「黙示の同意」があると見なされ、人事異動が認められるケースもあります。とはいえ、無理に人事異動を命じると労使間のトラブルに発展する可能性もあるため、基本的には就業規則や雇用契約のなかに規定を設けておくとよいでしょう。
内示であれば拒否できる?
人事異動を正式に伝える「辞令」だけではなく、前段階で行う「内示」についても、従業員は原則として拒否できません。内示は辞令と同様、企業が人事権に基づいて行うものだからです。
ここまで解説したとおり、企業には人事権が広く認められています。この背景には終身雇用制度の存在があり、従業員は安定して働ける一方で、企業側には事業を継続するために一定の権限が与えられているのです。
人事異動の拒否を認めるべき正当な理由
基本的に従業員は人事異動を拒否できませんが、企業側の都合だけを考えて無制限に命じられるわけでもありません。人事異動は従業員の生活に大きな影響を与えるため、一定の制約はあります。ここでは、人事異動の拒否を認めるべきケースについて解説しますのでチェックしておきましょう。
1.人事権の濫用に該当する

人事権の濫用に該当する場合は、従業員は人事異動を拒否できます。業務上の必要性がない場合や目的・根拠が不明確な場合は、人事権の濫用と見なされる可能性が高いでしょう。
当然ですが、従業員に対する嫌がらせや退職に追い込むことを目的とした人事異動も不当です。人事異動が無効となったり、人事権の濫用やパワハラとして訴えられたりする可能性もあるため注意しましょう。
2.雇用契約に違反している
雇用契約に違反した人事異動の場合は、従業員の拒否権が認められます。たとえば、雇用契約によって勤務エリアや職種などが限定されている場合、その範囲内でのみ人事異動を命じることが可能です。仮に就業規則に人事異動の規定があったとしても、雇用契約の範囲外の人事異動を命じると契約違反となってしまいます。
また、雇用契約のなかに特別な記載がなくても、長期間同じ勤務エリアや職種で働いている場合、「勤務エリアや職種の限定について黙示の合意があった」と見なされるケースもあります。人事異動を検討するときは、事前に従業員ごとの雇用契約や勤務状況を確認しておきましょう。
3.合理的な理由もなく賃金が減額される
人事異動の際は、賃金を変更しないのが基本です。賃金については雇用契約のなかで定められているため、人事異動を理由に減額することは原則としてできません。
たとえば、本社から支社への異動、都市部から地方への転勤という理由で、賃金を減額することはできません。合理的な理由もなく賃金を減額すると、人事異動の拒否が認められるだけではなく、裁判に発展したり、差額分の賃金の支給を命じられたりするケースもあります。ただし、合理的な理由による降格などにおいて、適切な手続きが行われている場合は、賃金の減額が認められるでしょう。
4.育児・介護などの事情がある

育児や介護などの事情を抱えている従業員が人事異動を拒否したときは、慎重に対応しなければなりません。育児・介護休業法に則り、適切な対応が求められるからです。(※2)
同法第26条には、勤務地の変更により育児や介護が難しくなる従業員がいる場合は、その状況に配慮すべきことが記載されています。たとえば、従業員本人以外に介護を行える家族がいない場合や、子どもの送り迎えができなくなる場合は、遠隔地への転居を伴う人事異動は避けるべきでしょう。
5.男女雇用機会均等法などに違反している
男女雇用機会均等法に違反している場合も、従業員は人事異動を拒否することが可能です。性別を理由とした部署異動や、結婚・妊娠・出産を理由とした降格などは、同法に違反するため認められません。
また、以下のような人事異動は、労働基準法や労働組合法などに違反するため避けましょう。
- 国籍・信条を理由として職務を変更する
- 労働組合の活動に参加したことを理由として遠隔地に異動させる
- 育児・介護休業や有給休暇を取得したことを理由として降格させる
6.うつ病の診断を受けている
うつ病の診断を受けている従業員が人事異動を拒否した場合は、慎重に対応することが必要です。たとえば、仕事内容や勤務地が変わることで病状の悪化が懸念される場合は、人事異動を避けるべきかもしれません。また、転勤により同じ病院に通えなくなる場合も無理強いは避けるべきでしょう。
無理な人事異動を実施したことによって病状が悪化した場合、安全配慮義務を果たしていないと判断される可能性もあります。損害賠償責任を問われるケースもあるため、医師の診断書や意見を確認するなど、慎重な対応をすることが重要です。
人事異動を拒否されたときの対応方法
従業員に人事異動を拒否されたときは、理由をヒアリングしたり、異動の必要性を説明したりすることが大切です。ここでは、人事異動を拒否されたときの対応方法を紹介します。
1.人事異動を拒否する理由をヒアリングする
従業員が人事異動を拒否している場合、まずは理由をヒアリングすることが大切です。介護や育児、雇用契約の内容など、正当な理由で人事異動を拒否しているかもしれません。無理に人事異動を実施すると大きなトラブルに発展する可能性もあるため、面談などを通して丁寧に話を聞きましょう。
2.人事異動の目的や必要性を説明する

従業員に対して、人事異動の目的や必要性を説明することも重要です。業務上の必要性やその従業員を選んだ理由などをしっかりと説明することで、納得してもらえるケースもあります。また、不安感から人事異動を拒否している可能性もあるため、異動後の仕事内容やフォロー体制についても説明しておくとよいでしょう。
3.待遇などを見直す
待遇を見直すことで、人事異動に納得してもらえる可能性もあります。たとえば、生活環境の大きな変化や経済的な負担増加を理由に人事異動を拒否している場合は、賃金の増額、転居費用の補助、単身赴任手当の支給などを検討するとよいでしょう。家庭の事情などがある場合は、人事異動のタイミングを調整したり、転勤先を見直したりすることも大切です。
4.懲戒処分を検討する
さまざまな対応を行っても、正当な理由のない拒否を続けている場合は、懲戒処分を検討する必要があります。懲戒処分とは、会社のルールに違反した従業員に与える罰則のことです。具体的には、戒告・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇などがあるため、状況に応じて適切な処分を科しましょう。
ただし、懲戒処分を実施するためには、就業規則に懲戒事由や処分内容を明記しておくことが必要です。就業規則に記載せずに懲戒処分を行うと、措置が無効になるケースもあります。
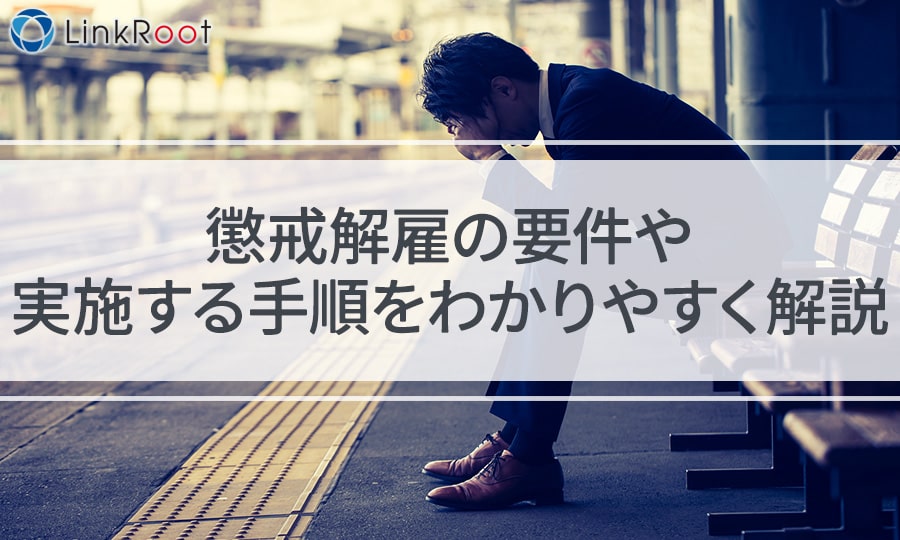
人事異動の拒否を認めないことのリスク

人事異動の拒否を認めないことには、以下のようなリスクがあります。
- 法律違反として罰則を受ける
- 優秀な人材が退職する
以下、詳しく見ていきましょう。
1.法律違反として罰則を受ける
育児や介護、健康上の問題など、従業員が正当な理由で人事異動を拒否している場合は、異動先について再検討したり、状況によっては異動を取りやめたりすることが必要です。
もちろん、好みの勤務地ではない、通勤時間が長くなる、といった従業員のわがままを受け入れる必要はありませんが、無理に人事異動を進めると、人事権の濫用として罰則を受ける可能性もあります。
2.優秀な人材が退職する
無理な人事異動を実施することには、優秀な人材が退職してしまうリスクもあります。転勤することを家族に反対された、自身のキャリアアップにつながらない、といった理由で人事異動を拒否しているケースもあるでしょう。
拒否の理由を聞かずに人事異動を進めると、仕方なく転職を考える従業員が出てくるかもしれません。優秀な人材の離職は企業にとって大きな損失となるため、人事異動は慎重に進めるようにしましょう。
人事異動の拒否による退職は自己都合?会社都合?

退職が自己都合になるか、会社都合になるかは状況によって異なります。以下、判断基準を紹介しますのでチェックしておきましょう。
1.自己都合になるケース
個人的な理由により人事異動を拒否して退職する場合は、自己都合による退職と見なされるでしょう。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 就業規則の規定に基づく正当な人事異動である場合
- 好みの仕事内容ではないなど、従業員のわがままと考えられる場合
冒頭で紹介したとおり、企業には人事権があるため、人事異動の拒否による退職は自己都合であると見なされます。ただし、以下のように会社都合の退職となるケースもあるため注意しましょう。
2.会社都合になるケース
就業規則に人事権の規定がない場合は、会社都合による退職と見なされることがあります。そのほか、会社都合となる可能性が高いケースは以下のとおりです。
- 雇用契約による勤務エリア以外への異動である場合
- 合理的な理由もなく賃金が減額される場合
- 業務上の必要性がなく、異動の目的・根拠が不明確な場合
- 育児・介護休業法や男女雇用機会均等法などに違反している場合
退職が自己都合になるか、会社都合になるかの最終的な判断は、公共職業安定所が行います。退職の経緯をしっかりと説明できるよう、関連する書類などを保管しておきましょう。
人事異動を拒否されないようにするポイント
従業員に人事異動を拒否されないために、以下のようなポイントを意識しましょう。
1.採用時に人事異動について説明する
人事異動をスムーズに進めるためには、採用時に人事異動の可能性について説明しておくことが重要です。とくに新入社員は、人事異動についてよく理解できていないケースもあります。面接や会社説明会のなかで転勤や部署異動があることを伝えておけば、実際に辞令を出したときに受け入れてもらいやすいでしょう。
2.人事異動の目的を丁寧に伝える
人事異動の目的や必要性を丁寧に伝えることも大切です。企業側は人事権をもっているため、基本的に従業員は辞令に従う必要があります。しかし、自身のキャリアプランや家庭の事情などもあるため、できれば部署異動を拒否したいと考えることもあるでしょう。
人事異動を命じるときは、異動先の部署で従業員のスキルや経験が必要であること、成長につながることなどを丁寧に伝える必要があります。個人面談などを通してしっかりとコミュニケーションを取れば、転勤や部署異動に納得してもらえることも多いでしょう。
3.雇用契約や就業規則を見直す
そもそも人事異動に関するルールが曖昧になっている場合は、雇用契約や就業規則の内容を見直さなければなりません。企業の人事権に関する規定がない場合は、強制的な人事異動を実施することが難しくなってしまいます。
現在の雇用契約や就業規則を確認し、企業の人事権や人事異動の可能性について明記しておきましょう。ルールを変更したときは、従業員へ周知することも必要です。
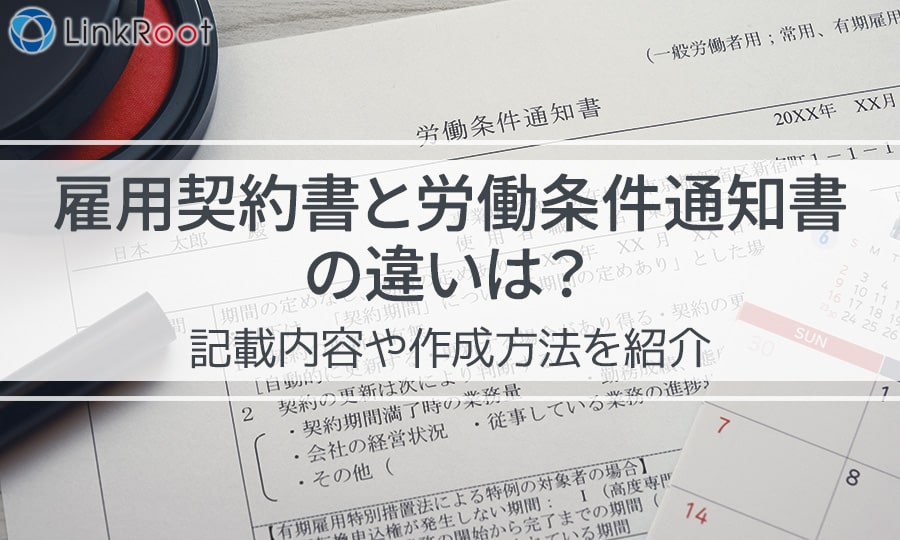
4.人事異動後のフォローを徹底する

人事異動後のフォロー体制を整えることで、転勤や部署異動をスムーズに進められるケースもあります。新しい場所へ異動する不安から、人事異動を拒否している可能性もあるからです。
新しい部署で仕事を教える担当者を決めておく、定期的にフォローアップ面談を行うなど、安心して働ける環境を整えておくことで、人事異動を受け入れてもらいやすいでしょう。事前に異動先での仕事内容や人間関係、異動の期間などを伝えておくことも有効な方法です。
人事異動を拒否されたときは丁寧なコミュニケーションを心がけよう!
今回は、人事異動を拒否されたときの対応方法や、拒否されないためのポイントなどを紹介しました。企業には人事権があるため、原則として従業員は辞令に従う必要がありますが、人事権の濫用に該当する場合や雇用契約に違反する場合は人事異動を拒否することも可能です。
従業員に人事異動を拒否されたときは、拒否の理由をヒアリングしたうえで、異動の目的や必要性をしっかりと伝えましょう。転勤や部署異動について納得してもらえるよう、フォロー体制を整えたり、待遇を見直したりすることも重要です。無理に人事異動を進めると、優秀な人材が離職してしまう可能性もあるため注意しましょう。
(※2)e-Gov法令検索「育児・介護休業法」