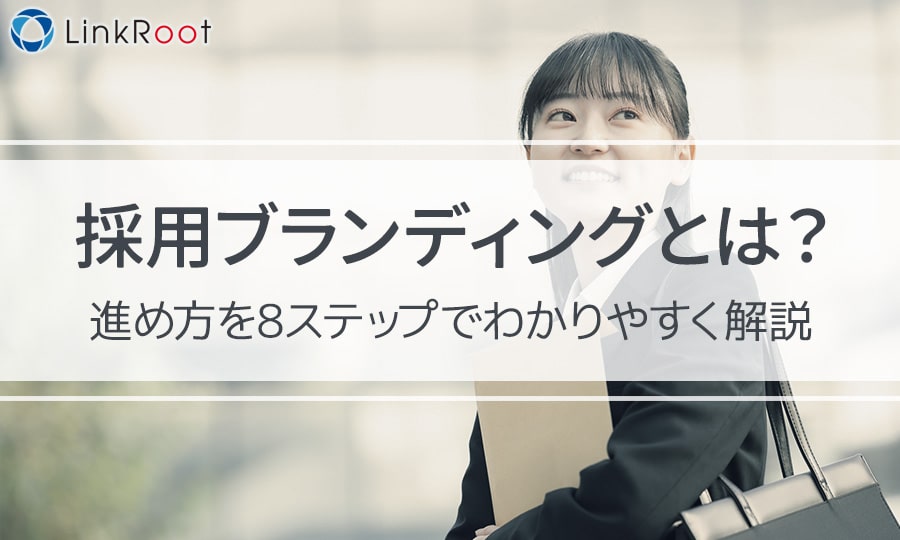求人票を出しても応募者がなかなか集まらない、採用してもすぐに離職してしまうなど、採用活動の悩みを抱えている企業は多いでしょう。採用活動がうまく進まないと、手間やコストばかりが発生し、事業をスムーズに展開できなくなることもあります。
採用ブランディングは、上記のような悩みを解決するための手法のひとつです。少子高齢化による労働力不足や求職者の価値観の多様化に対応するため、採用ブランディングに取り組む企業も増えてきました。
今回は、採用ブランディングのメリットや進め方について解説します。
採用ブランディングとは?

採用ブランディングとは、自社の理念に共感した優秀な人材を確保するために、企業の魅力を発信し、価値を高める取り組みのことです。そもそもブランディングという言葉はマーケティングの分野でよく使われており、デザインやキャッチコピーなどを活用して、自社の商品・サービスの認知度や人気を高める活動を指します。
同じような取り組みを採用の分野で行うのが採用ブランディングです。採用ブランディングにおいては、WebサイトやSNS、企業説明会などで仕事のやりがいや働きやすさを積極的に発信し、自社の認知度や人気を高めます。
採用ブランディングの目的
採用ブランディングの目的は、単純に自社の人気を高め、応募者を増やすことだけではありません。採用ブランディングの大きな目的は、企業の理念や価値観に共感した人材を採用することです。
いくら多くの人材を採用しても、ミスマッチにより早期退職されては意味がありません。採用活動や教育にかかる費用も無駄になってしまいます。また、企業の理念や価値観に共感していなければ、積極的に働いて業績アップに貢献してくれる可能性は低いでしょう。
採用ブランディングでは、経営理念や事業戦略、求める人材像を明確にしたうえで採用活動を進めます。その結果、企業の目標を達成するために必要な人材や、理念に共感している人材を確保できるでしょう。
採用ブランディングと採用マーケティングの違い
採用ブランディングと似た言葉として、採用マーケティングがあります。採用マーケティングとは、Webサイトに求人票を掲載したり、SNSで情報を発信したりして、応募者を増やす取り組みのことです。
一方の採用ブランディングは、応募者の増加だけではなく、企業価値の向上や理念に共感した人材の採用なども目的としているため、採用マーケティングよりも大きな概念といえるでしょう。
採用ブランディングに注目が集まっている理由

社会状況の変化に合わせて、採用ブランディングに力を入れる企業が増えてきました。採用ブランディングが注目される理由として、以下のようなことが挙げられます。
1.少子高齢化による労働力不足
少子高齢化により生産年齢人口が減少しているため、多くの企業が労働力不足に悩んでおり、採用活動における競争は激化しつつあります。求職者が多かった時代とは異なり、待っているだけで人材が集まってくるわけではありません。ライバル企業に優秀な人材を取られてしまうこともあるでしょう。
このような状況のなか、採用ブランディングを通して自社の価値を積極的に発信し、求職者にアピールすることが求められているのです。仕事のやりがいや魅力をうまく伝えなければ、人材を確保しつつ、事業を継続的に展開していくことは難しいでしょう。
2.求職者の価値観の多様化
求職者の価値観が多様化していることも、採用ブランディングに注目が集まる理由のひとつです。求職者は、月給やボーナスが高い、福利厚生が充実している、といったポイントだけを見て仕事を選ぶわけではありません。
とくに近年は働き方改革の影響などにより、自分が成長できる、社会に貢献できる、ワークライフバランスを確保できるなどのポイントを重視して、仕事を選ぶ人も増えてきました。企業としては求職者の価値観の変化に合わせ、月給や福利厚生を示すだけではなく、達成感を得られることや社会貢献につながることなどをアピールする必要があります。
3.インターネットの普及
インターネットやSNSの普及により、誰でも気軽に情報を発信できる世の中になりました。以前は企業説明会や求人情報誌などで自社の魅力を伝えるのが一般的でしたが、WebサイトやSNSを駆使して採用ブランディングを進める企業も増えてきています。
自社サイトに先輩社員のインタビューを掲載したり、SNSで普段の職場の様子を投稿したりして、求職者に魅力を伝える企業も増えてきました。一方で、SNSによって悪い評判が拡散され、企業のイメージが一気に悪くなるケースもあるため注意しなければなりません。
採用ブランディングに取り組むメリット
採用ブランディングに取り組むメリットとして、企業の認知度が向上することや、ミスマッチによる早期離職を防止できることなどが挙げられます。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.企業の認知度が向上する
企業の認知度が向上することは、採用ブランディングの大きなメリットです。魅力的で働きがいのある企業であっても、求職者に知られていなければ、なかなか応募者が集まらないケースも多いでしょう。
とくに中小企業やBtoB企業は、普段の生活のなかで求職者と接する機会が少ないため、まずは認知度を高めなければなりません。有名企業の場合は、求人票を出すだけで多数の応募者が集まることを期待できますが、認知度が低い企業の場合は、採用ブランディングを通して自社の存在を積極的にアピールすることが重要です。
2.応募者が増加する

採用ブランディングによって企業の認知度が向上すれば、応募者が増加するでしょう。仕事を通して得られる成長や達成感をうまくアピールし、他社との差別化を図れば、自社を選んで応募してもらえる可能性が高まります。母集団を形成できれば、そのなかから優秀な人材に出会える確率もアップするでしょう。
また、採用ブランディングが成功すれば、その後も自然と応募者が集まるようになります。企業に対するよいイメージは、消費されてなくなるものではなく、長く継承されていくものだからです。ブランディングには時間がかかりますが、一度成功すれば、長期的に採用活動を効率化し、採用コストを削減することにつながるでしょう。
3.ミスマッチによる早期離職を防止できる
ミスマッチを防止できることも採用ブランディングのメリットのひとつです。せっかく優秀な人材を採用しても、企業理念に共感していなかったり、仕事へのやりがいを感じていなかったりすると、早期に離職してしまう可能性があります。離職に至らないとしても、モチベーションや生産性が低下してしまうケースもあるでしょう。
採用プロセスのなかで、経営理念や今後のビジョンなどが伝わっていないと、ミスマッチが発生しやすくなります。前述のとおり、求職者の価値観は多様化しています。月給や福利厚生に関する情報だけではなく、企業の価値観や目標、仕事を通して得られる充実感など、求職者が気にしている情報を丁寧に伝えていくことが重要です。
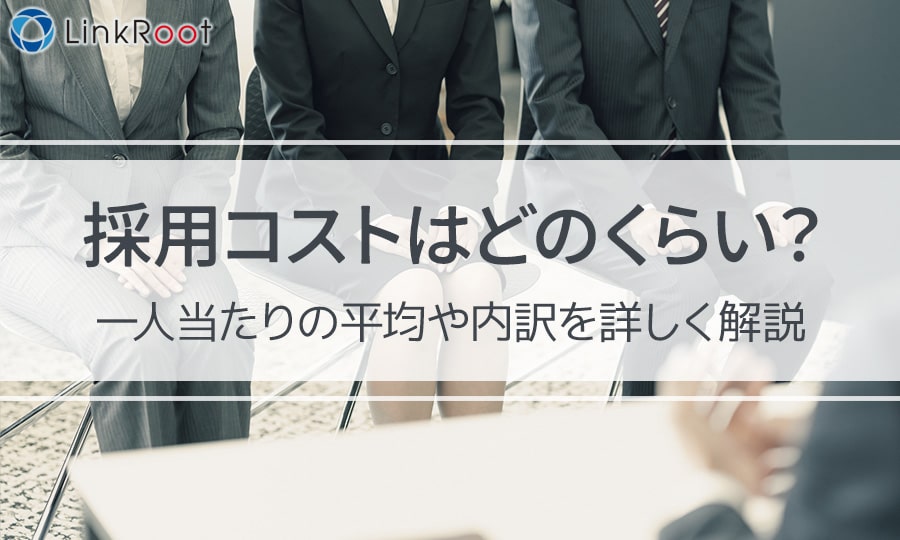
採用ブランディングの進め方を8ステップで解説
採用ブランディングは以下のようなステップで進めましょう。
1.課題と目標を明確にする
まずは採用ブランディングによって解決したい課題や、達成したい目標を明確にしなければなりません。取り組みを始める前に、採用活動をしても応募者が集まらない、入社しても定着せずに早期に離職してしまう、といった課題を把握しましょう。
そのうえで、目標とする採用人数や定着率を設定します。内定を辞退する人を減らしたいなど、採用プロセスにおける定性的な目標についても明確にしておきましょう。採用担当者から意見や悩みをヒアリングするのもよい方法です。
2.自社の魅力や価値観を把握する

採用ブランディングを成功させるためには、自社の魅力や価値観を把握することが重要です。まずは経営理念や社是などを再確認し、自社が大切にしている価値観を明確にしましょう。
また、仕事内容や働き方、給与や福利厚生などの基本的な項目を整理しておく必要があります。とくに自社独自の福利厚生や働き方を導入している場合は、アピールポイントになるため、しっかりと確認しておくことが大切です。
3.他社との差別化を図る
ライバル企業についても調査しておきましょう。ライバル企業の働き方や給与、職場の雰囲気など、どのような強みがあるかを調べておくことが大切です。また、採用活動の方法や特徴を調べておくことで、差別化を図りやすくなります。
他社の情報を集めたら、自社の強みについて再確認し、どのようにアピールすべきかを検討しましょう。自社で働くことでどう成長できるのか、どのような充実感を得られるのか、さまざまな視点から検討することで、他社との差別化を図りつつ、自社の魅力を明確化することが可能です。
4.ペルソナを設定する
次にペルソナを設定しましょう。採用活動におけるペルソナとは、自社が求める具体的な人材像のことです。ペルソナを設定する際は、「30代で営業職を希望している人」といった大まかなイメージではなく、以下のように特徴や属性を細かく決めていきます。
- 35歳
- 独身
- 営業職希望
- 首都圏在住
- 前職は食品会社の営業担当
- 趣味はスポーツ観戦
もちろん、ペルソナに100%合致する人材を探す必要はありません。ペルソナは、求める人材像を社内で共有するために設定します。できる限り具体的なペルソナを設定しておくことで、採用に関わるメンバーでイメージを共有しやすくなり、採用プロセスにおける認識のズレを防止できるでしょう。
5.採用コンセプトを考える
設定したペルソナに合わせて、採用コンセプトを考えていきます。採用コンセプトとは、採用方針や求める人材像をわかりやすく言語化したものです。キャッチコピーやスローガンのような形で設定することが多いでしょう。
採用コンセプトを検討する際は、アピールしたい魅力を盛り込みつつ、ペルソナの共感を得られるような適切な表現を選ぶことが大切です。経営理念などをそのまま用いることも可能ですが、時代やペルソナに合っていない場合は、再検討する必要があります。
6.情報発信の手段を検討する
次に、自社の魅力や採用コンセプトを伝えるための方法を検討しましょう。具体的には、企業説明会を開催する、SNSを活用する、自社サイトに情報を掲載するなどの方法が挙げられます。
どの方法を選ぶべきかは、ペルソナによって異なります。ペルソナがよく接する方法を選ぶことで、効率よく情報を伝えられるでしょう。また、いくつかのメディアを併用するなど、複数の方法で情報を発信するのがおすすめです。
7.採用活動を開始する
準備が整ったら採用活動をスタートします。計画に従って、SNSでの情報発信や企業説明会の開催などを進めましょう。求職者と接触できるときは、積極的にコミュニケーションを取り、自社の魅力を伝えていきます。
求職者の反応がいまいちな場合は、情報発信の方法を見直したり、アピールポイントを変更したりすることも重要です。計画に従って採用ブランディングを行うことは重要ですが、状況に応じて柔軟に対応していきましょう。
8.効果を検証する
一定の期間、採用ブランディングを行ったら、効果を検証することが重要です。応募者数や採用人数、定着率などがどう変化したのかを定量的に把握し、取り組みの効果を分析しましょう。
採用ブランディングによる効果が見られない場合は、アピール内容や戦略が間違っていた可能性もあります。次の採用活動に向けて、改善点を明確にしたうえで新しい戦略を練り直しましょう。
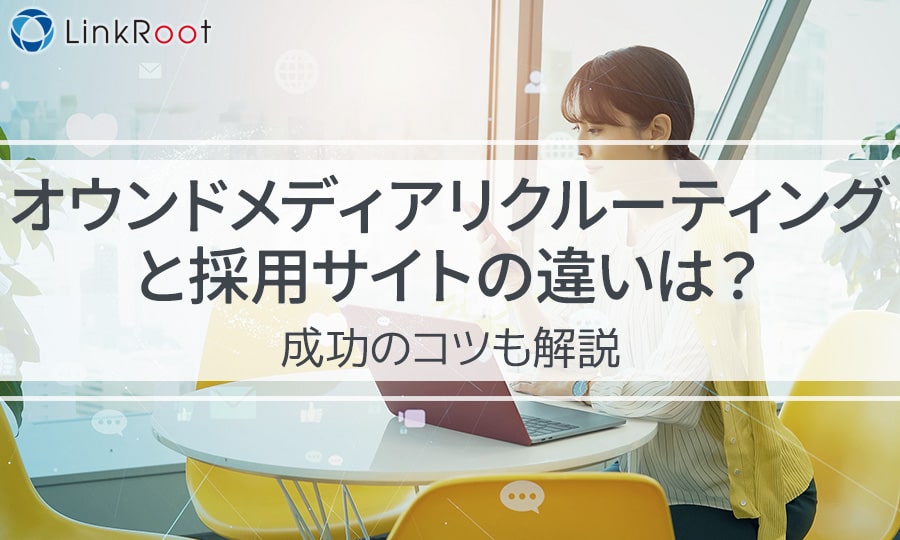
採用ブランディングを実施した会社の成功事例

ここでは、採用ブランディングの成功事例を紹介しますので、戦略立案の参考にしてください。
1.株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、現場の社員が採用に関わる仕組みを導入することで、採用ブランディングを成功させました。人事担当者だけではなく、実際に働く社員がリアルな情報を発信することで、「メルカリらしさ」を伝えることに成功したのです。
また、採用ブランディングを目的とした「People Branding」チームを立ち上げ、オンライン・オフラインで積極的に魅力を発信したことも成功の要因といえるでしょう。
2.ダイドードリンコ株式会社
ダイドードリンコ株式会社では、採用ターゲットを明確にすることで、自社に合う人材の確保を目指しています。具体的には「必要なスキルを備えるだけでなく、チャレンジングで努力を惜しまない人材」「チームワークを大切にしながら、リーダーシップを発揮し、周囲を巻き込む人材」という表現でターゲット像を打ち出し、ミスマッチを防止しています。
また、社風や働き方、活躍している社員のインタビューなどをWebサイトに掲載していることも大きな特徴です。企業の魅力をさまざまな形で発信することで、採用ブランディングを成功させています。
採用ブランディングに関する本

最後に、採用ブランディングについて学べる本をピックアップして紹介します。
1.人が集まる中小企業の経営者が実践している、すごい戦略 採用ブランディング
主に中小企業向けに、採用ブランディングのテクニックを紹介してくれる書籍です。社長が採用活動に関わることで差別化を図る、ペルソナは超理想的に描くなど、さまざまな手法が紹介されています。応募者が少ない、内定辞退が多いなどの悩みを抱えている場合は、解決策が見つかるかもしれません。
2.採用ブランディングのためのデザイン&コンテンツ
採用ブランディングを成功させるためのデザインやコンテンツ作成について学べる書籍です。Webサイトやパンフレットのデザインはもちろん、PR動画の作成方法まで学べます。採用ブランディングのプロが成功のコツを丁寧に解説してくれるため、実践的なスキルを習得できるでしょう。
採用ブランディングを通して優秀な人材を確保しよう!
今回は、採用ブランディングの意味やメリット、具体的な進め方などを解説しました。少子高齢化による労働力不足などを背景として、採用ブランディングに力を入れる企業が増えてきました。応募者が増える、ミスマッチによる早期離職を防止できるなどのメリットがあるため、採用活動で苦労している企業はひとつの戦略として取り入れてみるとよいでしょう。
ただし、採用ブランディングがすぐに成功するとは限りません。企業の認知度や人気を高めるためには、ある程度の時間がかかるため、長期的な視点で取り組むことが重要です。また、自社の魅力や価値を把握したうえで、うまく言語化する必要があります。ライバル企業との差別化を図りつつ、求職者にしっかりと伝わるような表現を選ぶことで、採用ブランディングの効果が高まるでしょう。