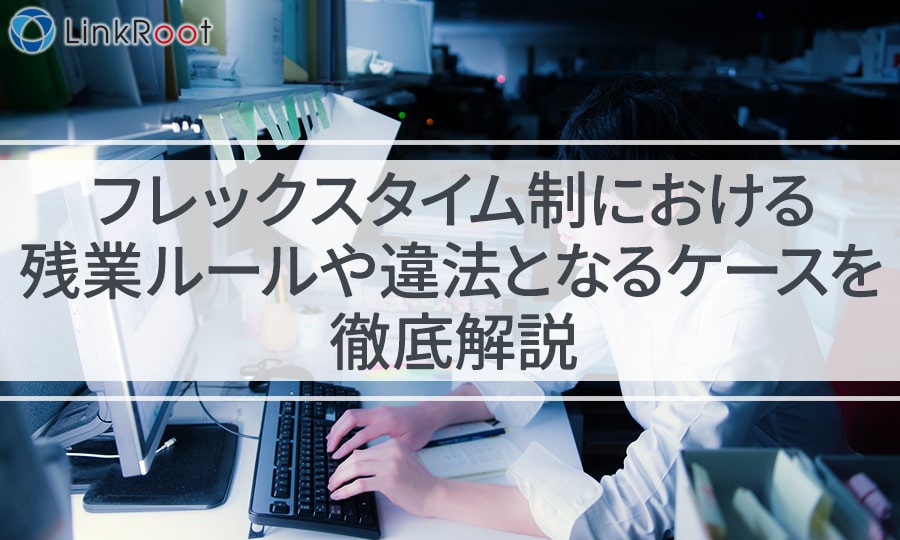フレックスタイム制は、従業員の自由な働き方を実現するための仕組みのひとつです。多様な人材を確保するために、フレックスタイム制の導入を検討している企業も多いでしょう。
ただし、フレックスタイム制を導入するなら、残業の取り扱いについて理解しておかなければなりません。通常の勤務形態とは異なるルールもあり、間違えると労働基準法違反として罰則を受けるケースもあります。
この記事では、フレックスタイム制における残業ルールや、違法となるケースについて解説しますので、ぜひチェックしておきましょう。
フレックスタイム制の残業ルールに関する基礎知識
ここでは、フレックスタイム制の残業ルールを理解するうえで重要な基礎知識を確認しておきましょう。
フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、一定期間において決められた総労働時間の範囲内で、従業員がある程度自由に働ける仕組みです。労働基準法第32条の3で規定されています。(※1)フレックスタイム制のルールは会社によって異なりますが、必ず労働しなければならないコアタイムと、始業・終業時刻を自由に決められるフレキシブルタイムを設定することが多いでしょう。
フレックスタイム制の大きなメリットは、プライベートの状況や仕事の進捗などに合わせて、従業員が柔軟なスケジュールで働けることです。家事や育児との両立もしやすいため、働き方改革の一環として取り入れる企業も増えてきました。
フレックスタイム制を導入するためには、労使間で協定を結ぶ必要があります。労使協定のなかで清算期間や総労働時間、対象となる従業員の範囲などを定め、就業規則に記載したうえで運用をスタートしましょう。
清算期間
フレックスタイム制における清算期間とは、従業員が働くべき時間を定めた期間のことです。最長で3ヶ月まで設定できます。後述するとおり、1ヶ月を超える清算期間を設定すると、残業時間の管理が複雑になるため注意が必要です。
総労働時間
総労働時間とは、清算期間内で働くべき労働時間の合計のことです。フレックスタイム制においては、この総労働時間を超える労働が発生した場合に、残業と見なされます。
法定外残業と法定内残業
残業は、法定外残業と法定内残業の2つに分けられます。法定外残業とは、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えた労働のことです。従業員に対して法定外残業を命じる場合は、事前に36協定を締結しなければなりません。また、法定外残業が発生した場合は割増賃金を支払う必要があります。
一方の法定内残業とは、法定労働時間の範囲内で発生した残業のことです。たとえば、所定労働時間が10〜18時の7時間(休憩1時間)の企業において、19時まで働いたケースを考えてみましょう。18〜19時の労働については、所定労働時間を超えてはいますが、1日8時間という法定労働時間内であるため、法定内残業と見なされます。法定内残業の場合は、割増賃金は発生しません。
フレックスタイム制を導入しても残業代が減るとは限らない
残業時間や残業代の削減を目的として、フレックスタイム制の導入を検討している企業も多いでしょう。しかし実際のところ、フレックスタイム制を導入したからといって、残業時間や残業代が減るとは限りません。
前述のとおり、設定した総労働時間を超えてしまった場合は残業代が発生します。フレックスタイム制を導入すれば従業員の自由度は高まりますが、ダラダラと働いていたり、マネジメントが不足していたりすると、労働時間は長くなってしまうでしょう。その点は、通常の勤務形態と同じです。フレックスタイム制において残業が減るかどうかは、従業員の意識やマネジメントの方法にかかっています。
フレックスタイム制における残業の考え方

フレックスタイム制の場合も通常の勤務形態と同様、36協定を締結しておくことで法定外残業を命じることが可能です。ただし、フレックスタイム制においては、総労働時間の範囲内で柔軟に働くため、1日8時間・週40時間を超えたからといって、ただちに法定外残業になるとは限りません。
通常の勤務形態においては、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えた労働が発生した場合、ただちに法定外残業と見なされます。
一方、フレックスタイム制の場合は、月曜に11時間、火曜に5時間といったイメージで柔軟に働くことが可能であり、1日単位ではなく清算期間内に何時間働いたかによって残業に該当するかどうかを判断します。また、法定労働時間の総枠が以下のように変わるため注意しましょう。
1.清算期間が1ヶ月の場合
フレックスタイム制における法定労働時間の総枠は、次の式で算出できます。
法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間)×(清算期間の暦日数÷ 7日)
この式を利用して、暦日数が31日の月における法定労働時間を考えてみましょう。
法定労働時間の総枠 = 40時間 ×(31日÷7日)= 177.14時間
つまり、暦日数が31日の月における法定労働時間の総枠は177.14時間となり、1ヶ月間でこの上限を超えた場合に法定外残業と見なされます。たとえば、1ヶ月の総労働時間を150時間と設定しており、実労働時間が180時間だったケースを想定してみましょう。合計で30時間の残業が発生していますが、そのうち27.14時間は法定内残業、2.86時間は法定外残業となります。
暦日数が30日の場合や28日の場合は法定労働時間の総枠が異なるため、勤怠管理や給与計算の際は注意しましょう。
2.清算期間が1ヶ月を超える場合
清算期間が1ヶ月を超える場合は、以下の条件に該当するときに法定外残業と見なされます。
- 1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えている
- 清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えている
清算期間を1ヶ月に設定する場合とは異なり、管理が複雑になるためルールをしっかりと覚えておきましょう。
フレックスタイム制における残業代の計算方法
法定外残業が発生した場合、従業員に対して割増賃金を支給しなければなりません。正しい割増率を用いて、以下の式で計算する必要があります。
残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間
詳しい計算手順について確認しておきましょう。
1.1時間あたりの基礎賃金を求める
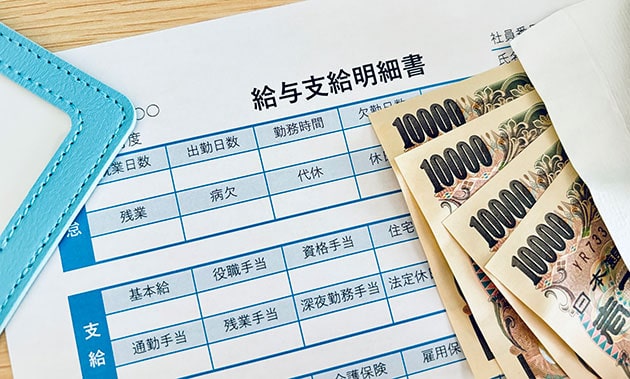
まずは、1時間あたりの基礎賃金を算出しなければなりません。時給制の場合、時給額がそのまま1時間あたりの基礎賃金となりますが、月給制の場合は以下の式で算出しましょう。
1時間あたりの基礎賃金 = 基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間
式中の基礎賃金には、月給や各種の手当が含まれます。ただし、以下のような手当については、基礎賃金に含まれません。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記のような手当は、従業員ごとの事情に応じて支給するものであるため、基礎賃金から除外しましょう。ただし、家族手当や通勤手当という名称であっても、全従業員に対して一律で支給している場合は、基礎賃金に含める必要があります。基礎賃金に該当するかどうかは、名称ではなく実態で判断する必要があるため注意しましょう。
2.割増率を確認する
割増率は、労働が発生した状況によって異なります。状況ごとの割増率は以下のとおりです。
- 法定外残業:25%
- 60時間を超える法定外残業:50%
- 深夜労働:25%
- 休日労働:35%
また、状況によっては割増率が加算されるケースもあります。たとえば休日に深夜労働が発生した場合は、休日労働の割増率35%と深夜労働の割増率25%が加算され、60%の割増率が適用されます。
3.残業時間を確認する
残業時間を確認しましょう。残業時間は、清算期間内の実労働時間から、設定している総労働時間を差し引くことで算出できます。たとえば、清算期間が1ヶ月であり、実労働時間が180時間、総労働時間が150時間だった場合、残業時間は30時間です。
ただし、30時間分の残業すべてに割増率が適用されるわけではありません。割増率が適用されるのは、法定外残業のみです。
前述のとおり、仮に暦日数が31日の月の場合、法定労働時間の総枠は177.14時間であるため、30時間のうち27.14時間は法定内残業、2.86時間は法定外残業となります。つまり、2.86時間分の法定外残業にだけ割増率が適用されます。27.14時間分の法定内残業に対しては、通常の賃金を支払えば問題ありません。
ここまで解説したように、1時間あたりの基礎賃金、割増率、残業時間を把握できたら、すべてをかけ合わせて残業代を算出しましょう。
フレックスタイム制における残業が違法になるケース
フレックスタイム制を導入している場合でも、従業員に対して残業を命じることはできます。しかし、以下のような場合は、労働基準法違反として罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。
- 36協定を締結していない
- 残業時間の上限規制を超えている
- 適正な残業代を支払っていない
- 残業時間を次の清算期間に繰り越している
それぞれのケースについて詳しく解説します。
1.36協定を締結していない
そもそも法定労働時間を超える残業を命じるためには、36協定を締結しなければなりません。36協定を締結せずに、法定外残業をさせることは違法です。また、労働基準監督署への届出も必要なため、忘れずに手続きを行いましょう。さらに、フレックスタイム制に関する労使協定の締結と届出も必要です。
2.残業時間の上限規制を超えている
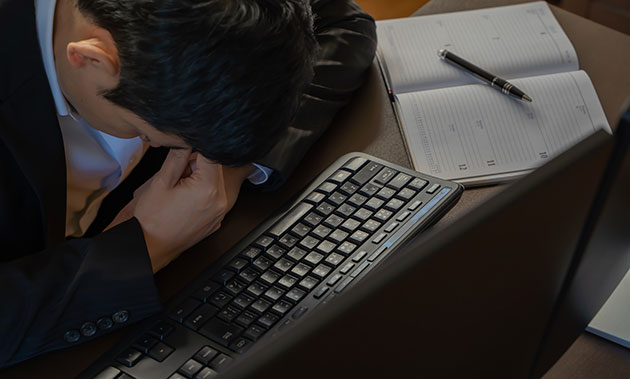
事前に36協定を締結すれば法定外残業を命じることは可能ですが、原則として月45時間以内・年360時間以内という基準を守らなければなりません。(※2)上限を超えると、30万円以下の罰金や6ヶ月以下の懲役が科せられるケースもあります。フレックスタイム制であっても、通常の勤務形態と同様に上限規制が適用されるため注意しましょう。
また、臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項付きの36協定を締結することで、上記の上限規制を超えることが可能です。ただし、無制限に残業を命じられるわけではなく、以下の基準を満たす必要があります。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
- 月45時間を超えるのは年6ヶ月まで
過剰な長時間労働は、従業員の心身の健康に悪影響を与えるだけではなく、モチベーションの低下や人件費の増加にもつながるため、できる限り減らしていきましょう。
3.適正な残業代を支払っていない
残業が発生した場合は、従業員に対して適切な割増賃金を支払わなければなりません。計算方法の項目で紹介したとおり、割増賃金は、残業が発生した状況に応じて異なる割増率を用いて算出する必要があります。計算方法を間違えると、正しい割増賃金を支給できなくなるため注意しましょう。
未払いの残業代が発生すると、労使間のトラブルが発生するだけではなく、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、実際に罰則が科せられたりします。企業の社会的なイメージが悪くなり、大きな損害が発生する可能性もあるため、正しい計算方法を理解しておくことが大切です。
4.残業時間を次の清算期間に繰り越している
フレックスタイム制の場合、清算期間内において、実労働時間が総労働時間に達しなかったときは、不足している労働時間を次の清算期間に繰り越すことが可能です。
しかし、総労働時間を超えて働いたときは、超過している労働時間を次の清算期間に繰り越すことはできません。残業が発生した場合は、その清算期間内で残業代を算出する必要があるため注意しましょう。
フレックスタイム制を導入するなら残業ルールを理解しておこう!
今回は、フレックスタイム制における残業ルールや、残業代の計算方法などを紹介しました。フレックスタイム制を導入している場合でも、36協定を締結することで法定外残業を命じることは可能です。残業が発生したときは、法定内残業と法定外残業を明確に分け、法定外残業に対しては割増賃金を支給しましょう。
また、法定労働時間の総枠や法定外残業に該当する基準は、通常の勤務形態とは異なります。フレックスタイム制の清算期間によっても基準が異なるため、ルールをしっかりと理解しておかなければなりません。残業代の計算ミスや支給漏れが発生すると、労使間のトラブルにつながるだけではなく、労働基準法違反として罰則を受けるケースもあるため十分に注意しましょう。
(※1)e-GOV法令検索「労働基準法」第三十二の三条
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_32_3
(※2)厚生労働省「時間外労働の上限規制」