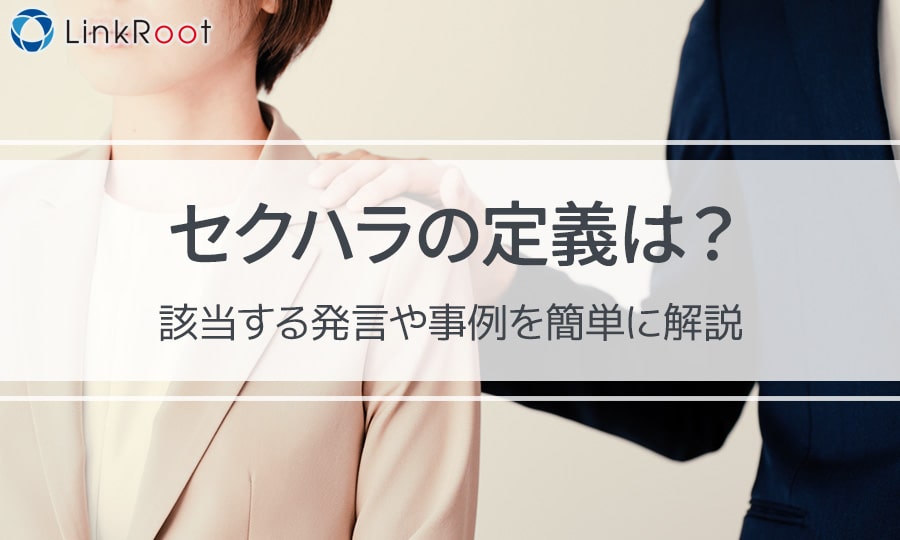セクハラを防止することは、企業に課せられた責務のひとつです。セクハラが発生すると、労働者が肉体的・精神的な被害を受け、働けなくなる可能性もあるため厳正に対応しなければなりません。
今回は、セクハラの定義や関連する法律、セクハラに該当する言動などを紹介します。セクハラを防止するために企業が講じるべき措置についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
セクハラ(セクシャルハラスメント)の定義

セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、職場において労働者の意に反して行われる性的な言動のことです。労働者が不利益を受けたり、働きにくくなったりする場合、その性的な言動はセクハラに該当します。
セクハラに該当するのは、男性が女性に対して行う言動だけではありません。女性から男性への言動や同性への言動も、セクハラと見なされる可能性があります。
また、性的な言動の受け止め方は労働者によって異なるため、同じ言動を行ってもセクハラになるケースとならないケースがあります。しかし、受け手が不快に感じた場合はセクハラに該当するため、職場における性的な言動には注意しなければなりません。
セクハラに関する法律
セクハラを禁止したり、セクハラに対して罰則を与えたりする直接的な法律は存在しません。ただし、セクハラに対する規制は、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)のなかに記載されています。(※1)
具体的には同法の第11条において、職場においてセクハラが発生しないよう、防止対策を講じることを企業に義務付けています。被害を受けた労働者の相談に応じるなど、適切な措置を講じるべきことも明記されているため、労働者同士の問題として片付けず、企業の責任と考えて対応することが必要です。
(※1)e-GOV法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
セクハラ以外のハラスメント
そもそもハラスメントとは、相手を不快にしたり不利益を与えたりする行為全般のことです。職場における代表的なハラスメントとしては、セクハラ以外にパワハラ(パワーハラスメント)やマタハラ(マタニティハラスメント)などが挙げられます。
パワハラ
パワハラとは、職場での優位な立場を利用して、業務上必要な範囲を超えた言動を行うことです。パワハラについては、2019年に労働施策総合推進法が改正され、パワハラ防止措置を講じることが企業に義務付けられました。
マタハラ
マタハラとは、妊娠・出産・育児などを理由として不当な扱いをすることです。マタハラについては、育児・介護休業法のなかで、労働環境が害されないよう適切な対応をすることが企業に義務付けられています。
以上のように、職場におけるハラスメント対策について、企業の責任が重要視されているため、労働者が快適に働けるようにしっかりと対応していきましょう。
セクハラとはどこから?セクハラに該当する3つの要件を紹介
セクハラに該当する要件は、男女雇用機会均等法の第11条に記載されています。ここでは、3つの要件を紹介しますのでチェックしておきましょう。
1.職場で行われている

職場での言動であることは、セクハラに該当するかどうかを判断する基準のひとつです。職場で性的な発言をしたり、身体を触ったりすると、セクハラに該当する可能性が高いでしょう。
ここでの「職場」とは、普段仕事をしている事業所や店舗に限られません。以下のような場所であっても労働者が業務を行っていれば、職場に含まれる可能性があります。
- 取引先の事務所や店舗
- クライアントの自宅
- 出張先
- 移動中の車内や飛行機の中
- 打ち合わせを行う飲食店
- 社員旅行中の宿泊施設
勤務時間外に開催される飲み会や懇親会など、実質的に業務の延長であると考えられる場合も職場に含まれます。職場に該当するかどうかは、業務との関連性や参加者、開催形式などに応じて個別に判断されるため注意が必要です。
2.労働者の意に反している
労働者の意に反して行われる性的な言動は、セクハラに該当します。他の人が気にしないような発言であっても、受け手が不快に感じたり労働環境が害されたりすると、セクハラと見なされる可能性があるため注意しましょう。
また、ここでいう「労働者」には、正社員はもちろんパートやアルバイト、契約社員なども含まれます。派遣社員に対しても、セクハラが起きないよう同様の措置を講じなければなりません。派遣元企業だけではなく派遣先企業にも責任が発生するため、慎重に対応することが重要です。
3.性的な言動である
性的な言動とは、性的な内容を含む発言や行動のことです。性的な関心や欲求による言動や、性的指向に関する言動なども幅広く含まれます。具体的には、労働者の容姿について言及したり、性的な関係を強要したりすると、セクハラと見なされる可能性が高いでしょう。
仮に行為者に性的な意図がないとしても、受け手が性的な内容であると感じた場合はセクハラに該当するケースもあります。何気ない一言がセクハラになることもあるため注意しましょう。また、社内の上司や同僚だけではなく、取引先の関係者なども行為者になり得ます。行為者が社外の人であっても、社内で起きたセクハラと同様の対応が求められるため、適切な防止対策を講じることが重要です。
セクハラの種類
セクハラは、対価型と環境型の2つに大きく分けられます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
1.対価型セクハラ
対価型とは、性的な言動を受けた労働者の対応によって、利益や不利益が生じるセクハラのことです。セクハラに抵抗したことを理由として不当に解雇したり、逆にセクハラを受け入れたことで昇格させたりした場合、対価型セクハラに該当するでしょう。そのほか、以下のような例が典型的です。
- 性的な関係を拒否したことを理由に降格させる
- 性的な言動について抗議したことを理由に減給する
- 身体を触ったことに抵抗したために不利益な配置転換を行う
セクハラを拒否したことを理由として、解雇や降格、雇用契約の更新拒否など、客観的に見て不利益な対応を行うと対価型セクハラに該当します。また、セクハラを受け入れたことを理由に昇進や昇格などを行うと、セクハラが横行する環境につながるため注意が必要です。
2.環境型セクハラ

環境型とは、性的な言動によって労働環境が害されるタイプのセクハラのことです。労働者が不快に感じることで能力が発揮できなくなったり、肉体的・精神的な苦痛によって働く意欲がなくなったりした場合、環境型セクハラに該当するでしょう。そのほかの典型的な例は、以下のとおりです。
- 同僚が会社のパソコンでアダルトサイトを見ていることで苦痛を感じる
- 上司が繰り返し性的な発言をするため職場にいるのが苦しい
- 取引先の担当者が身体を触るため仕事への意欲が低下している
環境型セクハラに該当するかどうかは、個別の状況を考慮して判断されます。一般的には、抗議しているにもかかわらず状況が改善されない場合や、心身に重大な影響が出ている場合などは、労働環境が害されているものと見なされ、環境型セクハラであると認められるでしょう。
セクハラに該当する発言や事例
職場において以下のような発言や行動をすると、セクハラに該当する可能性が高いため注意しましょう。
1.労働者の容姿について言及する
労働者の容姿について言及することは、典型的なセクハラの事例です。以下のような発言は、セクハラと見なされるケースもあるため避けるべきでしょう。
- 背が高くてスタイルがいいね
- 少し太ったね
- 痩せて美しくなったね
- イケメンだからモテそう
仮に褒め言葉のつもりであっても、受け手が不快に感じるとセクハラになってしまいます。労働者との関係性や場面によっては、労働環境が著しく害されることもあるため注意しなければなりません。
2.同意なく身体を触る

相手の同意なく身体を触る行為は、セクハラの代表例です。髪や肩などであっても、同意なく触ることは避けましょう。具体的な例は以下のとおりです。
- 応援するつもりで肩をたたく
- 作業を教えるふりをして身体を触る
- 飲み会の席で身体を接触させる
性別に関係なく、身体を触れられることを不快に感じる人もいるため、適切な配慮をしましょう。
3.性的指向について言及する
性的指向とは、恋愛や性的感情の対象についての指向のことです。性的指向は人によって異なり、異性が対象となる人、同性が対象となる人、異性・同性の両方が対象となる人、どちらも対象とならない人などが存在します。
異性のみが恋愛対象であると決めつけて話をすると、受け手が不快に感じる可能性もあります。たとえば、男性の労働者に対して好みの女性のタイプを聞くと、人によっては苦痛を感じるため注意しましょう。
4.性自認について言及する
性自認とは、自分の性別に関する認識のことです。性的指向と同様、性自認も人によって異なります。自分は男性であると思う人、女性であると思う人、どちらでもないと思う人、どちらでもあると思う人など、性自認は人によってさまざまです。
性自認について否定し たり、差別的な発言をしたりすることはセクハラに該当する可能性があります。労働者が働きにくくなるため、性的指向や性自認への理解を深め、良好な職場環境を構築しましょう。
5.性的な冗談を言う
性的な冗談を言うこともセクハラに該当します。相手の容姿をバカにしたり、自分の性的な体験談を語ったりすると、セクハラと見なされる可能性もあるでしょう。
また、会社内はもちろん、飲み会の席での発言もセクハラに含まれます。友人との会話なら許容される内容であっても、職場の同僚や部下に話すとセクハラになり得るため注意が必要です。
6.性別について言及する
不用意に性別について言及すると、セクハラに該当する可能性があります。たとえば、以下のような発言には注意しましょう。
- 男のくせに根性がない
- 女性なのに優秀だね
- この荷物は重いから男性が運んでください
- 女性は結婚したら退職する
7.ヌードポスターなどを職場に貼る
ヌードポスターを職場に貼るなど、労働者が不快に感じるような行為はセクハラに該当します。以下のような行為は避けるようにしましょう。
- 休憩時間中に卑猥な雑誌を読む
- インターネットで卑猥な写真を閲覧する
- 職場で卑猥な会話をする
8.しつこくデートに誘う
食事やデートにしつこく誘うなど、付き合いや性的な関係を強要することはセクハラに該当します。以下のような行為もセクハラに含まれるため、注意が必要です。
- 仕事以外の用事でしつこく電話をかける
- 性的な内容を含むメールや手紙を送る
- 飲み会への参加を強要する
9.飲み会でお酌を強要する
飲み会でお酌を要求するなど、何気ない行為もセクハラと見なされる可能性があります。そのほかの例は以下のとおりです。
- カラオケでデュエットを強要する
- 飲み会で上司の隣の席を指定する
セクハラによって生じる責務
セクハラが発生した場合、企業や行為者には次のような責務が生じます。
1.企業の責務
職場でセクハラが発生した場合、企業側に債務不履行責任が生じるケースもあります。前述のとおり、男女雇用機会均等法によって、セクハラ防止対策を講じることが企業に義務付けられているからです。
ハラスメント防止研修の実施や相談窓口の設置を怠ると、セクハラ防止義務に違反したとして指導や勧告を受ける可能性があります。勧告に従わないと企業名が公表され、社会的なイメージが悪化するケースもあるためしっかりと対応しましょう。
2.労働者の責務

セクハラを行った労働者は、刑事責任や民事責任を負うことになります。たとえば強制的に身体を触った場合、刑法に従って不同意性交罪や不同意わいせつ罪が適用され、5年以上の懲役など、重い罰則が科せられる可能性もあります。
また、セクハラを受けた労働者が休業したり、精神的な病気にかかったりした場合、行為者は損害賠償責任を負わなければなりません。治療費や通院交通費、慰謝料や逸失利益などを含めて多額の損害賠償が発生するケースもあります。
セクハラに対して企業が講じるべき措置
セクハラを防止するために、企業は次のような措置を講じる必要があります。
1.セクハラ防止に関する啓発を行う

職場におけるセクハラを防止するためには、労働者全員に対して啓発を行うことが重要です。セクハラがあってはならないこと、セクハラに該当する行為、セクハラ行為者は厳正に処分することなどを労働者に周知しておけば、セクハラ防止につながるでしょう。
啓発や周知の方法としては、セクハラ防止研修の実施やポスターの掲示などが挙げられます。セクハラ行為者に対する懲戒処分の内容を、就業規則に記載しておくことも効果的です。
2.相談窓口を設置する
相談窓口を設置して、セクハラを受けた労働者の話を聞くことも企業の義務です。人事部や総務部などに相談窓口を設置して、適切な対応ができるように体制を整えましょう。
中小企業などで社内に相談窓口を設置するのが難しい場合は、外部の弁護士や社会保険労務士に相談業務を委託したり、労働基準監督署が運営する総合労働相談センターを掲示したりすることも可能です。
3.セクハラが発生したときに早急に対応する
実際にセクハラが発生したときや相談を受けたときは、早急に対応しなければなりません。報告や相談を受けたにもかかわらず放置していると、セクハラ防止義務に違反したと見なされる可能性があります。
まずは関係者からヒアリングを行い、事実関係を確認したうえで適切な対策を講じましょう。さらに、再発を防止するための措置を検討することも大切です。
4.労働者のプライバシーに配慮する
セクハラに対応する際は、労働者のプライバシーに配慮することも必要です。プライバシーが保護されないと、労働者がセクハラについて相談しにくくなる可能性もあります。
また、セクハラの相談や報告をしたことによって、不当な取り扱いをすることも避けなければなりません。労働者のプライバシーを守りつつ、相談したことで働きにくい状況にならないよう配慮しましょう。
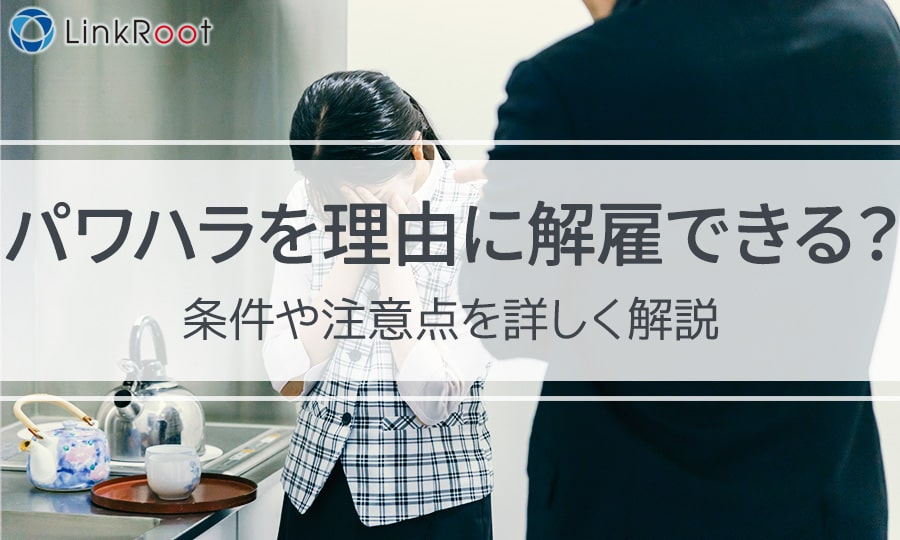
職場におけるセクハラが発生しないよう対策を講じよう!
今回は、セクハラの定義や、セクハラに該当する言動の例などを紹介しました。職場でセクハラが発生すると、労働者が不利益を受けたり、働きにくくなったりします。優秀な労働者が離職する、企業のイメージが悪くなるなどの問題につながる可能性もあるため、しっかりと対応しなければなりません。
セクハラの発生を防止するためには、ハラスメント防止研修を開催したり、相談窓口を設置したりすることが重要です。社会的な責任を果たしつつ、働きやすい環境を構築するために、企業として適切な対応を検討していきましょう。