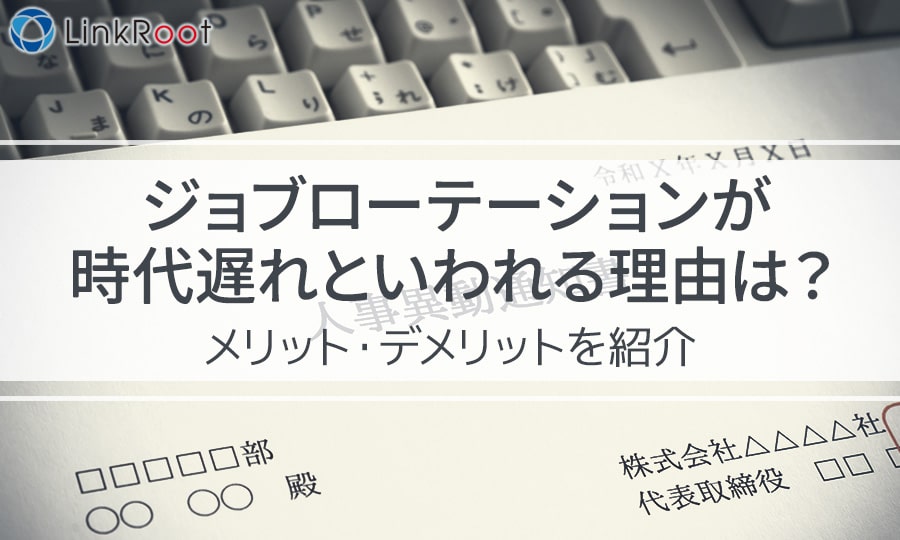ジョブローテーションは、社員を育成する方法のひとつですが、時代遅れといわれることも増えてきました。実際のところ、ジェネラリストを育成することは可能ですが、スペシャリストの育成には適しておらず、ジョブローテーションがうまく機能しないケースもあります。
今回は、ジョブローテーションが時代遅れといわれる理由や、導入するメリット・デメリットなどを紹介します。ジョブローテーションの導入を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
ジョブローテーションとは?

ジョブローテーションとは、社員を特定の部署に固定せず、定期的に配置変更を行ってさまざまな仕事を経験させる仕組みのことです。営業部・人事部・設計部・企画部・総務部など、社内で多くの部署を経験させることで、それぞれの業務内容を把握できたり、会社全体の経営環境を理解できたりします。社内全体で相互理解が深まり、協力体制の構築や組織力の向上にもつながるでしょう。
ジョブローテーションの目的
ジョブローテーションの大きな目的は、社員に幅広い知識とスキルを習得してもらうことです。総合的なスキルと柔軟な思考力を身につけてもらい、ゆくゆくは管理職やプロジェクトリーダーとして活躍できるよう、戦略的な人事育成を行います。
たとえば新入社員の場合、1〜3年ごとに違う部署へ異動させるケースが一般的です。さまざまな部署の仕事内容を知ることで会社全体の業務フローを理解でき、多面的な視点で仕事を捉えられるようになります。時間はかかりますが、ジョブローテーションをうまく行うことで優秀な人材を育成でき、事業を継続的に展開できるでしょう。
ジョブローテーションと人事異動の違い
人事異動とは、社員を他の部署に異動させることです。ジョブローテーションと同様、社員を異動させることですが目的はそれぞれ異なります。人事異動の目的は、会社側のニーズを満たしたり、組織の課題を解決したりすることです。たとえば、新しいプロジェクトを立ち上げるためにスキルのある社員を配置する、既存の社員が離職したために人員を補充する、といった目的が挙げられます。
一方、ジョブローテーションの主な目的は人材の育成です。短期的な目的で実施される人事異動とは異なり、ジョブローテーションにおいては長期的な計画を立て、社員にさまざまな部署を経験させます。両者の違いをしっかりと理解したうえで、目的に合った施策を実施しましょう。
ジョブローテーションが時代遅れといわれる理由
多くの企業が実施してきたジョブローテーションですが、以下のような理由から時代遅れといわれることもあります。
- 終身雇用制度が廃れつつある
- 定着率が低下する可能性がある
- スペシャリストを育成しにくい
- 教育コストがかかる
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
1.終身雇用制度が廃れつつあるから

そもそもジョブローテーションは、最初に入社した会社で定年まで働き続ける終身雇用制度を前提としている仕組みです。終身雇用制度においては退職するまでに何十年も働くため、ジョブローテーションのように長期的な教育が可能でした。教育に時間がかかったとしても、その後の勤務期間で活躍してくれることでコストを回収できたのです。
しかし、仕事に対する価値観の変化や転職市場の活発化などにより、終身雇用制度は廃れつつあります。雇用の流動化が進む状況においては、ジョブローテーションにより時間をかけて教育したとしても、長く勤務してくれるとは限りません。社員が早期に退職してしまうリスクを考え、時間のかかるジョブローテーションに代わる教育を実施する企業も増えてきました。
2.定着率が低下する可能性があるから
定着率低下の可能性があることも、ジョブローテーションが時代遅れといわれる理由のひとつです。ジョブローテーションにおいては、社員の希望や適性とは関係なく、1〜3年程度のスパンで部署異動を繰り返します。興味や適性のない部署に異動することに不満を感じ、離職を考える社員もいるでしょう。
また、適性のある部署で長く働けないことでモチベーションが低下し、転職する社員もいるかもしれません。少子高齢化による労働力不足が進むなか、人材を確保することは多くの企業が抱えている課題です。優秀な社員を他社に取られるリスクを考慮し、ジョブローテーションを取りやめる企業も増えてきました。
3.スペシャリストを育成しにくいから
ジョブローテーションが時代遅れといわれる理由として、スペシャリストを育成しにくいことが挙げられます。特定の分野に詳しいスペシャリストは、人手不足が進むなか、とくに少数精鋭の企業において必要な人材です。
しかし、ジョブローテーションはスペシャリストを育成することには向いていません。幅広い部署を経験させることでジェネラリストを育成することは可能ですが、スペシャリストが育成できないため、他の教育手法にシフトする企業も増えてきています。
4.教育コストがかかるから
教育コストがかかることも、ジョブローテーションが時代遅れといわれる理由です。新しい部署に異動した社員は、すぐにひとりで仕事を進めたり、成果を出したりできるわけではありません。まずは仕事内容や手順、部署の人間関係やクライアントの名前などを覚えてもらう必要があります。
上司や先輩社員による教育やサポートも必要となるため、配属先の部署が大きな負担を感じるケースもあるでしょう。教育のための時間やコストを削減するため、即戦力となる中途社員を採用するなど、別の方法で人材を確保しようとする企業も増えてきています。
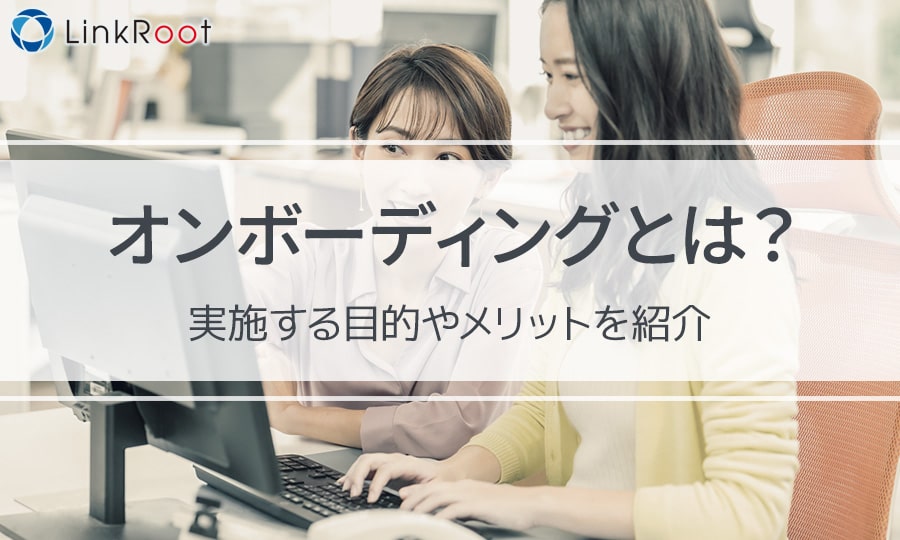
ジョブローテーションは本当に時代遅れ?メリットもある?
時代遅れといわれることが多いジョブローテーションですが、キャリアパスを多様化できる、社員の適性を見極められる、といったメリットもあります。ここではジョブローテーションのメリットを紹介しますので、チェックしておきましょう。
1.キャリアパスを多様化できる

社員のキャリアパスを多様化できることは、ジョブローテーションの大きなメリットです。社員にさまざまな仕事を経験させることで、総合的なスキルが身につきます。対応力や柔軟性も高まり、将来的にどのような部署でも活躍してくれるでしょう。
また、経営的な視点も含めて幅広い知見を身につけることで、管理職やリーダー的なポジションへ配置することも可能です。教育のための時間は必要ですが、将来的に組織を牽引する人材を育成できます。配置の選択肢が増えるため、人事異動の際に困ることも減るでしょう。
2.社員の適性を見極められる
ジョブローテーションを実施すれば、社員の適性を見極めることが可能です。面接時の質問や履歴書の内容だけで、社員の適性を判断することは簡単ではありません。本人の希望とは異なる部署で強みが見つかったり、意外なスキルが発揮されたりするケースもあるでしょう。
ジョブローテーションを導入すれば、さまざまな業務を担当させながら、社員の適性をじっくりと探せます。最終的に社員の適性に合った部署に配置することができれば、能力を遺憾なく発揮してもらえ、生産性の向上や利益アップを期待できるでしょう。ミスマッチによるストレスを減らせるため、離職防止にもつながります。
3.モチベーションの維持につながる
モチベーションの維持につながることも、ジョブローテーションのメリットのひとつです。ずっと同じ部署に所属し、同じ作業を繰り返していると飽きてしまい、モチベーションが低下するケースもあるでしょう。ついつい惰性で作業をこなすようになり、生産性が低下したり、新しいアイデアが生まれなくなったりする可能性もあります。
ジョブローテーションを実施すれば、定期的に新しい部署へ異動するため、社員は常に新鮮な刺激を受けることになります。知らなかった知識を吸収できることで、モチベーションが高まるケースもあるでしょう。気持ちが引き締まり、業務効率や生産性が向上することも期待できます。
4.社内のコミュニケーションが活性化する
ジョブローテーションをうまく行えば、社内のコミュニケーション活性化を図れます。同じ部署で働いていると特定の人としか関わらなくなり、他の部署にどのような人がいるのか、どのような仕事をしているのかを把握することができません。
一方でジョブローテーションを実施すれば、複数の部署を異動しながら、多くの人と関係性を構築できます。人柄や仕事内容をより深く理解できるため、業務がスムーズに進むことや、会社全体の協力体制が構築されることにつながるでしょう。
5.業務の属人化を防止できる
業務の属人化を防止できることもジョブローテーションのメリットです。属人化とは、社内でノウハウが共有されておらず、特定の社員しか業務を行えない状態のことです。業務の属人化が進むと、特定の社員の負担が増えすぎたり、社員が退職したときに業務を引き継げなかったりします。
ジョブローテーションを導入すれば、同じ業務を複数の社員が経験することになるため、属人化を防ぐことが可能です。担当者が退職や休職した際に、他の社員がフォローできるケースも増えるため、業務が滞りなく進むでしょう。
ジョブローテーションのデメリット
さまざまなメリットがあるジョブローテーションですが、以下のようなデメリットもあるため注意しなければなりません。
1.社員の負担が大きい
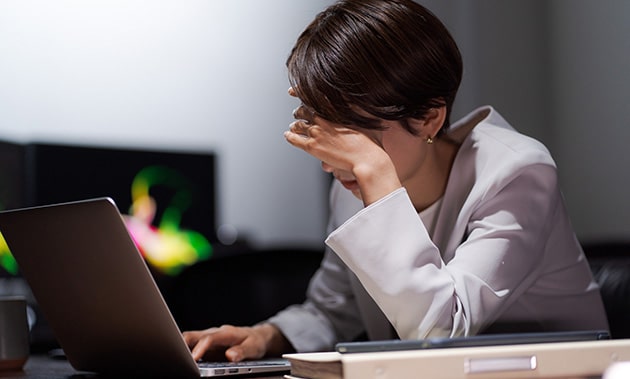
ジョブローテーションを行うことで、社員が大きな負担を感じるケースもあります。新しい部署へ異動すると、仕事を覚え直したり、人間関係に適応したりしなければなりません。また、社員を受け入れる側の負担も増えます。教育やサポートのために先輩社員や上司の手間が増えることも、ジョブローテーションのデメリットといえるでしょう。
2.新しい部署で活躍するまでに時間がかかる
新しい部署へ配属されたからといって、すぐに活躍できるわけではありません。前述のとおり、仕事内容や作業の流れを覚える必要があるため、一人前になるまでには、それなりに時間がかかるでしょう。一時的に部署の生産性や業務効率が低下してしまうことも考えられます。
3.専門性が身につかない
幅広いスキルを習得できる一方で、専門性が身につかないこともジョブローテーションのデメリットのひとつです。せっかく知識やスキルを習得しても一定期間で別の部署へ異動するため、業務について深く学ぶことはできません。ジェネラリストではなく、スペシャリストを育成したい場合、ジョブローテーションは向いていないでしょう。
4.モチベーションが低下する可能性もある
ジョブローテーションを間違った形で導入すると、社員のモチベーションが低下する可能性もあります。社員の適性や希望とかけ離れた部署に配属すると、ストレスを感じ、離職してしまうケースもあるでしょう。
また、プロジェクトの開始直後や完了直前に異動するとモチベーションが失われる可能性もあるため、ジョブローテーションのタイミングにも注意しなければなりません。
ジョブローテーションが適していない企業の特徴
ジョブローテーションは、すべての企業に適しているわけではありません。以下のような特徴のある企業には適していないため注意しましょう。
1.専門的なスキルが必要な企業

専門的なスキルが必要な企業には、ジョブローテーションは適していないでしょう。前述のとおり、ジョブローテーションはスペシャリストではなく、ジェネラリストを育成する仕組みだからです。短期間で異動することにより、知識やスキルを蓄積できなくなり、優秀な人材を育成できないでしょう。
たとえば、クリエイター職や研究職などが多い職場には、ジョブローテーションは不向きです。短期的な異動を避け、継続的なトレーニングを行う必要があります。
2.中長期的なプロジェクトが多い企業
中長期的なプロジェクトが多い企業にもジョブローテーションは向いていません。短期間でメンバーが入れ替わることで引き継ぎの手間がかかり、プロジェクトがスムーズに進まなくなるからです。また、担当者が変わることでクライアントに迷惑がかかったり、関係性の再構築に時間がかかったりするケースもあるでしょう。
3.中途採用の社員が多い企業
中途採用の社員に対して、ジョブローテーションを実施する必要性は低いでしょう。中途採用の社員はすでに専門的なスキルや知識を有しており、特定の部署での即戦力として採用するケースが多いからです。部署異動をさせず、スペシャリストとして育成するとよいでしょう。
4.少数精鋭の企業
少数精鋭の企業にもジョブローテーションは向いていないでしょう。たとえばベンチャー企業やスタートアップ企業などの場合、短期的な人事異動により職場が混乱する可能性もあります。それぞれの社員が集中して仕事をこなせる環境を整えるほうがよいでしょう。
ジョブローテーションを成功させるポイント
ジョブローテーションは時代遅れといわれないよう、実施する場合は以下のような点に注意しましょう。
1.目的を明確にする
ジョブローテーションを導入するなら、まずは目的を明確にすることが大切です。社員の適性を見極めたうえで人員配置を進めたい、将来リーダー的なポジションを任せる人材を育成したいなど、仕組みを導入する目的を明確にしましょう。また、社員と目的を共有することで、仕組みを導入することへの納得感が高まります。
2.長期的な計画を立てる
ジョブローテーションを成功させるためには、長期的な計画を立てることが重要です。配属する部署の順番や異動のスパンなどを計画しておけば、効率よく人材を育成できるでしょう。無理のないスケジュールを組むことで、配属先の部署も適切な準備を行えます。
3.フィードバックを行う

ジョブローテーションを実施したら、フィードバックを行うことも必要です。しっかりとスキルを習得できているか、サポート体制に無理はなかったかなど、対象の社員や関係者からヒアリングを行い、課題を解決していきましょう。繰り返し改善を行うことで、より効果的なジョブローテーションを実施できます。
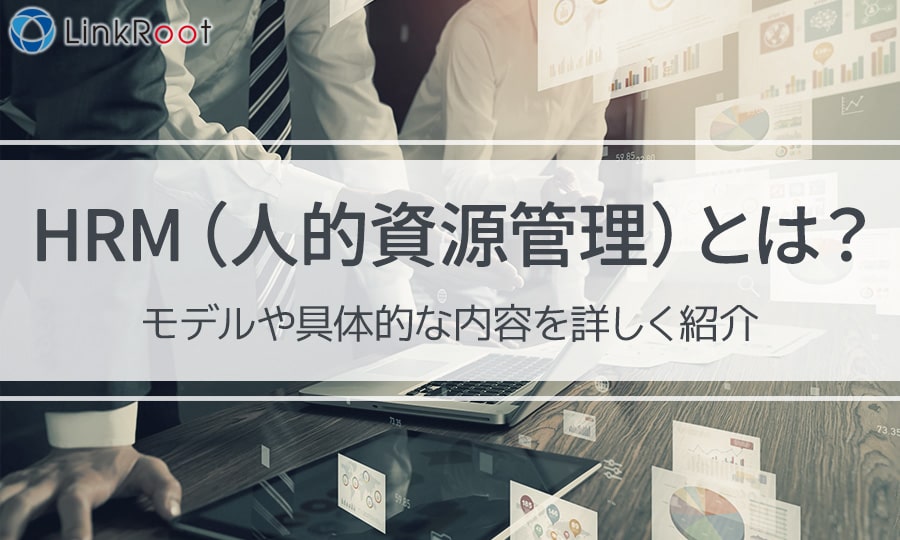
ジョブローテーションは時代遅れといわれないよう注意しよう!
今回は、ジョブローテーションが時代遅れといわれる理由や、導入するメリット・デメリットなどを紹介しました。終身雇用制度が廃れつつある、スペシャリストを育成しにくいなどの理由から、ジョブローテーションは時代遅れといわれることもあります。
ただし、うまく実施することで、社員のキャリアパスを多様化したり、適性を見極めたりすることも可能です。ジョブローテーションを導入する場合は、社員の負担が大きくなる、専門性が身につきにくいなどのデメリットを理解したうえで効果的に実施しましょう。