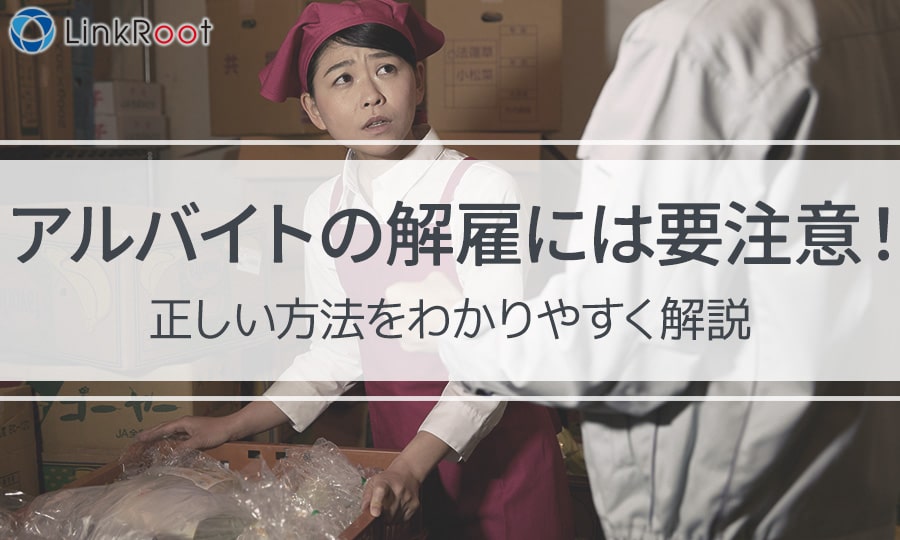アルバイトやパートの従業員は簡単に解雇できると勘違いされがちです。しかし、正社員と同様、正しい方法で解雇手続きを進めなければ不当解雇と見なされる可能性があります。解雇理由として認められるものも限られているため注意しましょう。
この記事では、アルバイトを解雇するときの方法や不当解雇によるリスクなどについて解説します。解雇の正しい流れについても解説しますので、アルバイト従業員とのトラブルを防止するために、しっかりと理解しておきましょう。
アルバイトを解雇する3つの方法
アルバイトを解雇する方法としては、以下の3つが挙げられます。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
1.解雇予告をしてから解雇する
アルバイトやパートに何らかの問題があったとしても、すぐに解雇することはできず、事前に解雇予告を行うのが基本です。解雇予告については労働基準法の第20条に記載されており、解雇しようとする日の30日以上前に行わなければなりません。(※1)
解雇予告の方法は口頭でも問題ありませんが、「言った・言わない」のトラブルを防止するために書面を交付するとよいでしょう。
解雇予告をしたあと、アルバイトから請求があった場合は、解雇理由証明書を発行しなければなりません。希望がない場合は発行する必要はありませんが、適切に対応しないと30万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため注意が必要です。(※2)
(※1)厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法20条」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-1.pdf
(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第百二十条
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_120
2.解雇予告手当を支払って解雇する
解雇予告をせず、すぐに解雇したい場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。30日分の解雇予告手当を支払えば、アルバイトやパートを即日解雇できます。
また、解雇予告と解雇予告手当を組み合わせることも可能です。たとえば、解雇する日の10日前に解雇予告を行い、20日分の解雇予告手当を支払うという方法で解雇することもできます。
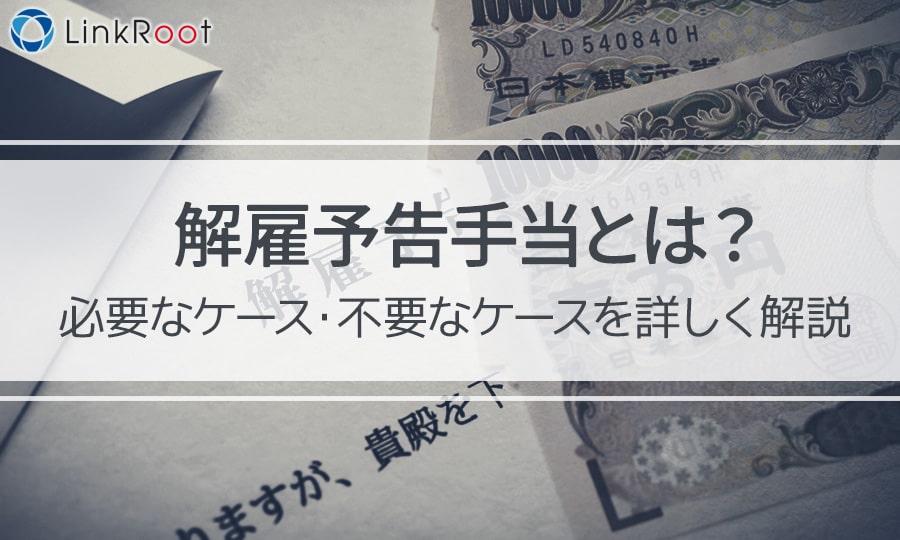
3.契約更新をしない
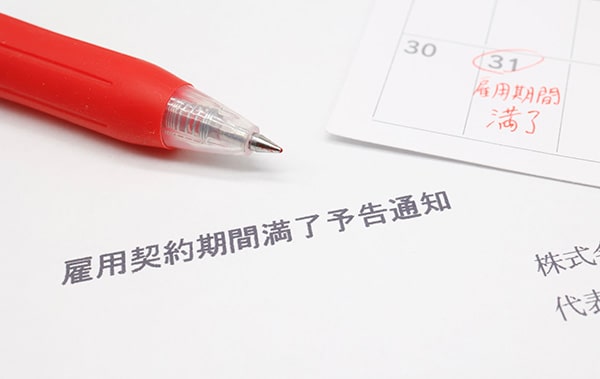
アルバイトやパートと期間の定めのある雇用契約を結んでいる場合、期間満了時に契約更新をしないことも可能です。この場合、期間満了を理由とした契約終了となるため、解雇とは見なされません。会社側から一方的に雇用契約を解約する解雇とは異なり、比較的スムーズに雇用関係を解消できるでしょう。
ただし、契約更新をしないことが認められないケースもあるため注意が必要です。過去に繰り返し契約が更新されている場合や、日常的な会話のなかで契約更新を示唆するようなやり取りがある場合は、引き続き雇用することが求められます。
また以下のようなケースにおいては、30日以上前に契約更新をしない旨を伝えなければなりません。
- 雇用契約が3回以上更新されている
- 雇用契約の期間が1年を超えている
- 雇用契約の更新により通算1年以上の契約となっている
アルバイトの解雇理由として認められるもの
アルバイトを解雇するためには、客観的で合理的な理由が必要です。また、解雇理由について、事前に就業規則に記載しておかなければなりません。就業規則に記載がないと、解雇が無効となる可能性が高いため注意しましょう。具体的には、以下のような理由が必要です。
1.重大な犯罪行為があった
アルバイトやパートが犯罪行為に関わった場合は、解雇を検討することになるでしょう。正当な解雇理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 会社の資金を横領した
- 店舗の備品や商品を盗んだ
- 設備や備品を破壊した
- 暴力行為に及んだ
- ハラスメントに関わった
上記のような行為は、刑法に定められている横領罪や傷害罪などに該当します。会社との信頼関係を破壊する行為でもあるため、解雇の有効性は認められやすいでしょう。
2.バイトテロなどにより大きな損害を与えた

バイトテロにより会社に大きな損害を与えた場合、解雇が認められる可能性が高いでしょう。バイトテロとは、不適切な行動を起こし、会社や店舗の評判を損なう行為のことです。行為の様子を撮影して、SNSや動画共有サイトなどに投稿するケースも多く見られます。代表的なバイトテロの事例は以下のとおりです。
- 飲食店において不衛生な行動を取る
- 店舗の設備を破壊してSNSに投稿する
- 口コミサイトに自社の悪い評判を書き込む
バイトテロが発生すると、企業のイメージが著しく低下してしまいます。最悪の場合、閉店などに追い込まれる可能性もあるため、解雇の有効性は高いといえます。
3.経営状況が悪化した
経営状況が悪化した場合は、整理解雇としてアルバイトとの雇用契約を解消することが認められます。ただし、整理解雇は簡単に実施できるわけではなく、以下の要件を満たさなければなりません。
- 人員削減の必要性がある
- 解雇を回避するための努力をしている
- 人員選定の基準が合理的である
- 正しい手順で解雇手続きを進めている
経営不振により人員を削減する必要がある場合でも、業務改善による経費削減など、まずは解雇以外の方法を検討しなければなりません。また、整理解雇を行ったのに新規アルバイトを募集するといった矛盾した対応があると、解雇が無効と判断されます。
実際に解雇を実施するときは、従業員への説明や協議を徹底するなど、正しい手順で進めなければなりません。
アルバイトの解雇が不当であると判断されるケース
ここまで紹介したような理由があったとしても、アルバイトへの指導が不足していたり、就業規則に記載がなかったりすると、不当解雇と見なされる可能性があります。
以下のようなケースでは、不当解雇と判断される可能性が高いため注意しましょう。
1.指導が不足している場合

仕事をこなすための能力が足りない場合や勤務態度が悪い場合であっても、簡単に解雇することはできません。とくに採用したばかりのアルバイトやパートの場合、職場に慣れていないために仕事をうまくこなせないケースもあるでしょう。
まずは適切な指導を行い、仕事ができるようにサポートする必要があります。繰り返し指導をしても状況が改善しない場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。万が一、裁判に発展した際にスムーズに対応するため、メールや文書で指導をしたという証拠を残しておくことも大切です。
2.数回の遅刻や欠勤で解雇する場合
数回の遅刻や欠勤、仕事上の小さなミスを理由として解雇することは、基本的に認められません。解雇はアルバイトに対する重い処分であるため、小さな問題に対して適用すると、社会通念上相当ではないと判断されます。
正当な理由のない無断欠勤が続いている場合や、ミスが多発しており大きな被害が出ている場合などは解雇が認められます。しかし、その場合でもまずは注意や指導を徹底しなければなりません。
また、解雇という重い処分を与える前に、出勤停止や減給といった処分を段階的に与えることも重要です。
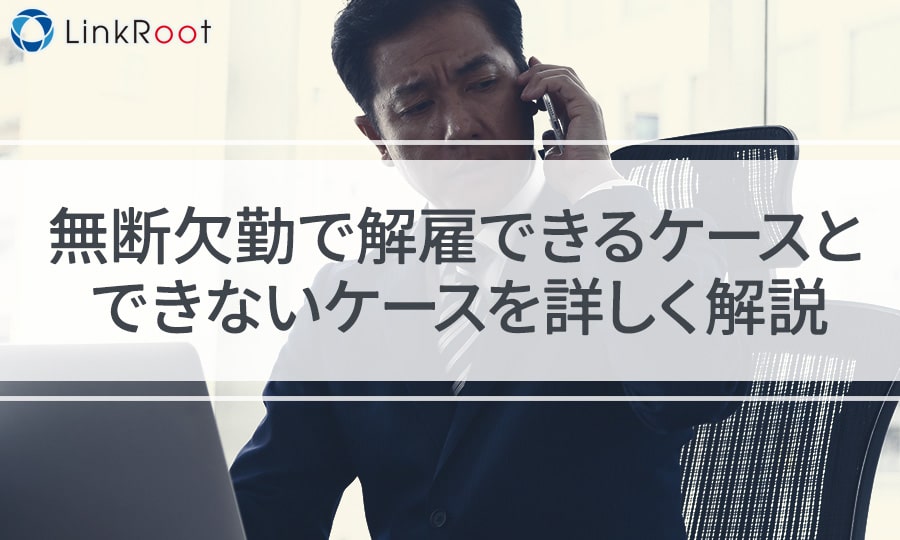
3.解雇理由が就業規則に記載されていない場合
解雇理由については、就業規則に記載しておかなければなりません。どのような行為に対して解雇という処分が実施されるのかを具体的に記載し、アルバイトを含む全従業員へ周知しておきましょう。
就業規則への記載を忘れると、不当解雇と見なされる可能性もあります。
就業規則に記載する際は、解雇に該当する理由を具体的に列挙するだけではなく、「その他、例示した状況に準ずるやむを得ない理由がある場合」などと記載しておきましょう。幅広い状況に対応できるようにしておくことで、解雇に関するトラブルの防止につながります。
アルバイトを不当解雇することによるリスク
アルバイトを不当解雇することには、次のようなリスクがあります。
- バックペイが発生する
- 従業員のモチベーションが低下する
- 企業のイメージが悪くなる
それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
1.バックペイが発生する
裁判により解雇が不当であると判断されると、アルバイトに対してバックペイを支払わなければなりません。バックペイとは、解雇した日から解決時までの給与のことです。解雇が無効になると、雇用関係が継続していることになるため、アルバイトが出勤していなくても、本来は発生していたはずの給与を支払う必要があります。
解雇した日からの期間が長くなるほど、多額のバックペイが発生するため注意しましょう。さらに慰謝料を請求されるケースもあります。また、労働基準法に違反した解雇を行うと、30万円以下の罰金や6ヶ月以下の懲役が科せられる可能性もあります。
2.従業員のモチベーションが低下する

従業員のモチベーションが低下することも、不当解雇を行うリスクのひとつです。不当解雇と見なされた場合、解雇されたアルバイトが戻ってくることになりますが、会社との関係が悪化しており意欲的に働いてくれないケースが多いでしょう。
さらに、他の従業員が自分も解雇されるのではないかという不安を感じ、モチベーションが低下する可能性もあります。離職する従業員が増えてしまうと、残る従業員の負担が増えたり、新規のアルバイトを募集するコストが発生したりするため注意が必要です。
3.企業のイメージが悪くなる
不当解雇を行うことは、企業のイメージ悪化につながります。裁判の結果は一般に公開されるため、不当な解雇を行うような企業として悪いイメージが付いてしまうケースもあるでしょう。SNSで悪評が広がる可能性もあるため注意しなければなりません。
企業のイメージが悪くなると、取引先との関係を構築しにくくなったり、採用活動がうまく進まなくなったりします。さまざまな場面で影響が出るため、不当な解雇は絶対に行わないようにしましょう。
アルバイトを解雇するときの流れ
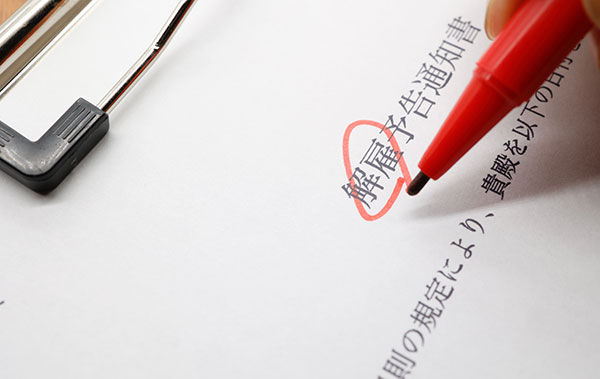
正しい手順で解雇の手続きを進めなければ、トラブルが発生する可能性もあります。アルバイトを解雇するときは、以下のような流れで進めましょう。
1.退職勧奨を行う
アルバイトを解雇する前に、退職勧奨を行うとよいでしょう。退職勧奨とは、アルバイトに対して退職してほしい理由を伝え、自主的に退職してもらうことです。
話し合いを通して納得したうえで退職してもらえるため、一方的に解雇するよりスムーズに問題が解決することもあります。ただし、退職を強要することは避けましょう。
2.解雇理由を明確にする
退職勧奨に応じてもらえなかった場合は、解雇を検討することになります。解雇する際は、理由を明確にしなければなりません。何度注意しても勤務態度が改善されない、無断欠勤が頻発しているなど、解雇が認められる理由を明確にしましょう。
解雇理由が就業規則に記載されているか確認することも重要です。また、解雇の正当性を証明できるよう、アルバイトの勤怠情報や、注意した際の記録を残しておくとよいでしょう。
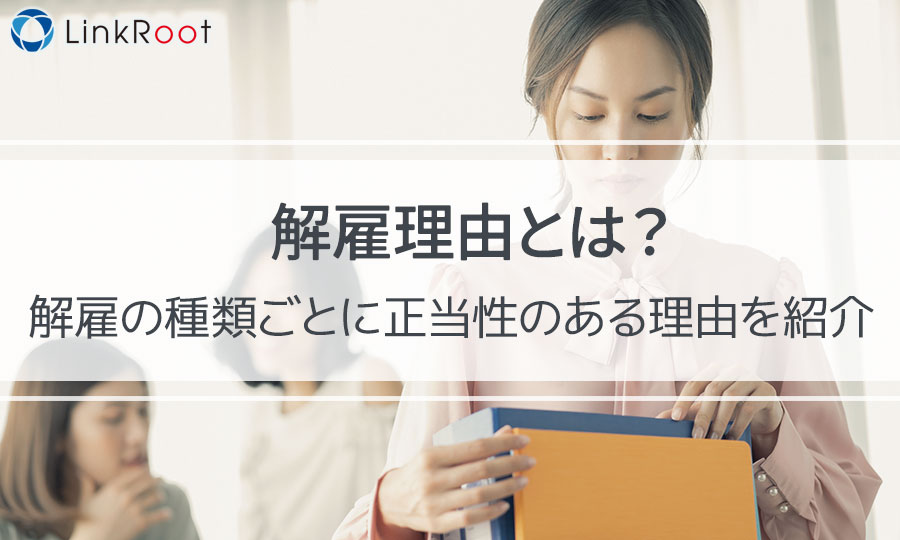
3.弁明の機会を与える
解雇するアルバイトに対して弁明の機会を与えることも必要です。弁明の機会とは、アルバイト側の事情や言い訳を聞くことです。
問題行動を起こした経緯や反省の気持ちなどを聞くことで、解雇という重い処分を見直すこともできます。解雇に踏み切る場合でも、弁明の機会を通してガス抜きをしておくことで、トラブルの発生を防止できるでしょう。
4.解雇予告を行う
前述のとおり、アルバイトを解雇する際は解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払わなければなりません。法律で定められた内容であるため、忘れないようにしましょう。
5.社会保険の手続きを進める
アルバイトを解雇するときは、社会保険の手続きを進める必要があります。健康保険や厚生年金の対象者ではなくなるため、資格喪失届を作成して年金事務所へ提出しましょう。
雇用保険については、資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出する必要があります。それぞれ提出期限が定められているため、遅れないように注意しなければなりません。
アルバイトの解雇は正しい流れで進めよう!
今回は、アルバイトを解雇する方法や解雇するときの流れについて解説しました。アルバイトやパートだからといって簡単に解雇することはできません。正社員を解雇するときと同様、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければ、解雇は無効となります。
アルバイトを不当解雇することには、バックペイが発生する、会社のイメージが悪くなるなどのリスクがあるため注意しましょう。まずは解雇理由を明確にし、就業規則に記載があるかどうかを確認することが大切です。正しい手順で解雇を進め、トラブルを防止しましょう。