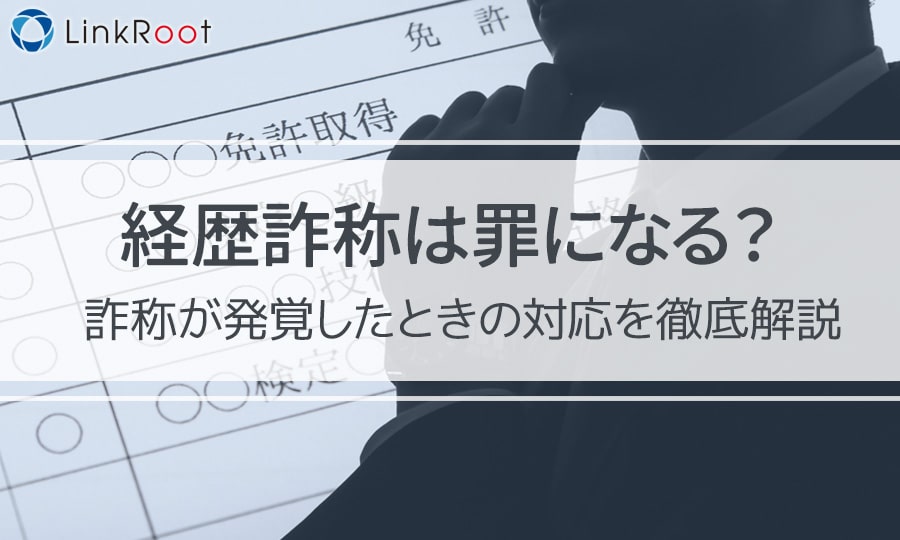経歴詐称は必ずしも罪になるわけではありませんが、詐称の目的や悪質性によっては詐欺罪や軽犯罪法違反と見なされるケースもあります。また、経歴詐称した人を採用するとコンプライアンス上の問題が発生するなど、企業にとって大きなリスクとなるため注意しなければなりません。
この記事では、経歴詐称により問われる可能性がある罪や、発覚したときの対処方法などを解説します。経歴詐称を見抜くポイントについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
経歴詐称とは?
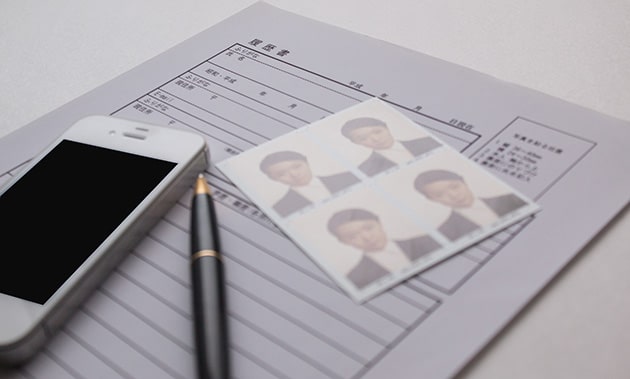
経歴詐称とは、職歴や学歴について虚偽の申告をしたり、事実を隠したりすることです。採用候補者は選考を有利に進めたいといった思いから、経歴を詐称することがあります。
経歴詐称した人を雇用すると、正確なスキルや経験を把握できず、適切な人材配置や業務配分ができません。その人の能力に見合わないような高い賃金を支払ってしまうこともあるでしょう。企業としては採用前に経歴詐称を見抜けるよう、提出書類のチェックや面接時のヒアリングを強化することが大切です。
経歴詐称の具体例
経歴詐称には、さまざまな種類があります。代表的な経歴詐称は以下のとおりです。
- 学歴詐称:卒業学校名・学部名や卒業年度について虚偽の申告をする
- 職歴詐称:過去の勤務先や担当業務について虚偽の申告をする
- 犯罪歴詐称:犯罪歴を聞かれた際に嘘の回答をする
- 病歴詐称:治療中の病気や健康状態について嘘の報告をする
- 免許・資格詐称:取得していない免許・資格を履歴書に記載する
上記のような経歴詐称は、面接時のヒアリングで採用候補者が嘘の回答をすることや、履歴書や職務経歴書に虚偽の内容を記載することで発生します。
早期退職してしまった企業について記載しない、卒業年度を偽って浪人したことを隠すなど、さまざまなパターンがあるため、申告内容をチェックする際は注意しましょう。
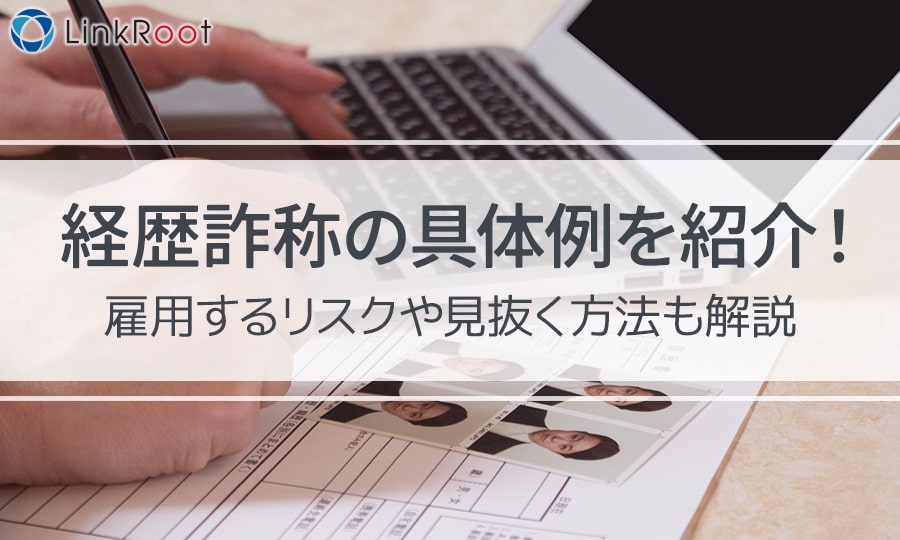
詐称と偽称の違い
詐称と似た言葉として偽称がありますが、両者の意味は少し異なります。詐称とは、事実を隠したり異なる申告をしたりすることで、自分の評価を高めようとする行為です。経歴詐称、学歴詐称、年齢詐称といった形で使われます。
偽称とは、事実とは異なる申告をしたり、存在しない事実を勝手につくって報告したりすることです。裁判で証人が嘘の発言をすることなどは、偽称に当たります。
経歴詐称は罪になる?
学歴詐称や職歴詐称をしたからといって、必ずしも罪に問われるわけではありません。ただし、経歴詐称の内容や悪質性によっては罪になることもあります。たとえば、経歴詐称をすることで金銭を騙し取ったり、補助金や手当金を不正に受給したりすると、詐欺罪になる可能性があります。
また、他人の名義を勝手に使用すると私文書偽造罪、学位を詐称すると軽犯罪法違反になる可能性もあるため注意が必要です。詳しくは次の項目で見ていきましょう。
経歴詐称により問われる可能性のある罪
経歴詐称により問われる可能性のある罪としては、詐欺罪、軽犯罪法違反、私文書偽造罪などが挙げられます。そのほか、民事責任を問われるケースもあるため注意しましょう。
それぞれの罪の詳細は以下のとおりです。
詐欺罪

詐欺罪とは、相手を欺くことにより財産を奪ったり、不当に利益を得たりする犯罪のことです。学歴詐称や職歴詐称により金銭を得ている場合は、詐欺罪が成立する可能性もあります。
たとえば簿記や行政書士など、特定の資格を取得している従業員に対して、資格手当を支給している企業もあるでしょう。仮に従業員が資格詐称をして、保有していない資格に対する手当を不正に受け取っているなら、詐欺罪に当たります。
詐欺罪に対する罰則は、10年以下の懲役です。罰金刑はありません。(※1)
ただし、経歴詐称をした人が通常の給与を受け取るだけでは、一般的に詐欺罪は成立しません。給与は労働の対価であり、経歴詐称とは関係なく支払われるべきものだからです。不正に資格手当を受け取るなど、経歴詐称によって金銭を受け取る行為が詐欺罪に該当します。
(※1)e-Gov法令検索「刑法」第246条
軽犯罪法違反
軽犯罪法は、日常生活のなかで発生する比較的軽い犯罪を取り締まるための法律です。軽い違法行為に対して罰則を与えることで、重大な犯罪の発生を防ぐことも目的としています。
たとえば、医師や建築士、弁護士などの資格を保有しているように見せかけることは、称号詐称として軽犯罪法違反に当たります。学位や職歴について詐称することも、軽犯罪法違反に当たる可能性があるため注意が必要です。(※2)
(※2)e-Gov法令検索「軽犯罪法」第一条15号
私文書偽造罪
私文書とは公的な立場にない一般人が作成した書類のことで、履歴書や契約書などは私文書に含まれます。私文書偽造罪とは、他人の名義を勝手に使用して履歴書などを偽造する犯罪のことです。
たとえば、他人の卒業証明書の氏名を書き換えて自分のもののように見せたり、実在する資格証明書に似せて自分のものを作成したりする行為は私文書偽造罪に当たります。私文書偽造罪による罰則は3カ月以上5年以下の懲役で、罰金刑はありません。
また、自分の履歴書に嘘の卒業学校名や勤務先を記載する行為は、他人の名義を使用しているわけではないため、一般的に私文書偽造罪には該当しません。
民事責任
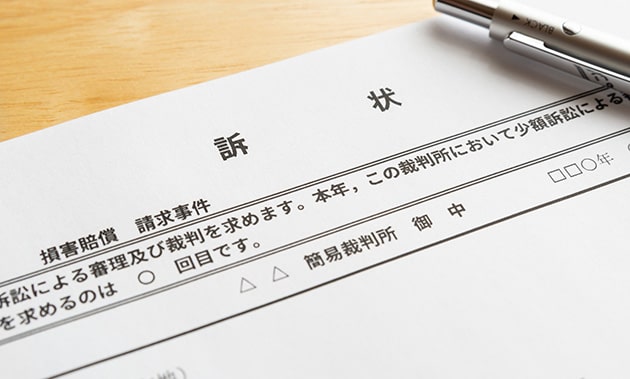
詐欺罪や私文書偽造罪といった刑事責任ではなく、民事責任を問われる可能性もあります。企業の採用選考において経歴詐称が発覚したときは、解雇や減給といった懲戒処分を科すケースも多いでしょう。
懲戒処分の内容については、企業の就業規則にて定めておくのが一般的です。正しい手続きによって懲戒処分を進めなければ、処分内容が認められないケースもあるため注意しなければなりません。
経歴詐称によって損害が発生した場合は、損害賠償請求をすることもあります。詐称によって本来は得られない手当を得たり、取引先との関係が悪化したりした場合は損害賠償請求をすることが可能です。
なぜ経歴詐称が発生するのか?
採用候補者が経歴詐称をしてしまうことには、さまざまな理由があります。企業側としては経歴詐称が発生する理由を把握しておくことで、適切な対応を取ることが可能です。
具体的な理由としては、他の候補者より就職活動を有利に進めたい、より高い給与をもらいたい、単純な記載ミスなどが挙げられます。
以下、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
就職活動を有利に進めたい

採用候補者は、就職活動を有利に進めたい、内定を勝ち取りたい、といった考えから経歴詐称をすることがあります。
すぐに辞めてしまった会社を書くと印象が悪くなると考えて、履歴書に書かなかったり、面接で犯罪歴を聞かれたときに虚偽の申告をしたりするケースもあるでしょう。
基本的には、自分の評価を高めたいという気持ちが根底にあります。嘘が発覚することはないだろうと考え、軽い気持ちで虚偽の申告をしている可能性もありますが、経歴詐称は犯罪に該当することもあります。
また、コンプライアンス上の問題や企業の信用性の低下など、事業に関わる大きなリスクもあるため、経歴詐称には厳しく対応しなければなりません。
高い給与をもらいたい
より高い給与をもらいたいと考えることも、経歴詐称が発生する原因のひとつです。過去の職場で難しい業務を担当してきた、管理的な役職を経験してきたなどと嘘の報告をして、上のポジションや高い給与を得ようと考える候補者もいるでしょう。
また、資格手当を支給している企業の場合、候補者が本来は取得していない資格名を履歴書に記載している可能性もあります。
資格や職歴の詐称が発生すると、本来は担当させられない業務を任せてしまったり、期待していた成果が出なかったりするケースもあるため注意が必要です。
単純な記載ミス
単純な記載ミスにより、意図せずして経歴詐称が発生することもあります。たとえば、以下のような記載ミスが考えられます。
- 学校の入学年度や卒業年度を間違えてしまう
- 派遣元企業を書くべきところに派遣先企業を書いてしまう
- 資格の等級や取得年月日を間違えてしまう
- 免許の有効期限が切れている
悪質なものではありませんが、従業員の正確なスキルを把握できない、免許がない人に免許が必要な業務を任せてしまう、といったリスクもあるため注意しなければなりません。
経歴詐称が発覚するパターン
経歴詐称はさまざまな場面で発覚します。面接や書類チェックなど、採用選考の途中で発覚することもあれば、採用後に発覚することもあるでしょう。
具体的には、源泉徴収票や卒業証明書などの内容から発覚するパターンが挙げられます。そのほか、タレコミやSNSの投稿から発覚することもあります。
以下、経歴詐称が発覚するパターンについて解説しますので、チェックしておきましょう。
1.面接での回答に矛盾がある

面接時の回答に矛盾があることで、経歴詐称が発覚することがあります。履歴書の内容をもとに質問したときに話が噛み合わなかったり、記載内容とは異なる発言をしたりすることで、学歴や職歴の詐称が発覚するケースもあるでしょう。
採用側としては経歴詐称を見抜くためにも、面接時にしっかりとヒアリングしておくことが大切です。
2.源泉徴収票の内容から発覚する
前職の源泉徴収票から経歴詐称が発覚することもあるでしょう。源泉徴収票には、企業名や退職日などが記載されています。前の職場で発行してもらうため、採用候補者が偽造することは難しく、内容をチェックすることで詐称を見抜けるケースもあるでしょう。
記載内容から、収入などに関する詐称が発覚することもあります。
3.卒業証明書の内容から発覚する
卒業証明書には、学校名や学部名、卒業年月日などが記載されています。履歴書の記載内容や面接時の回答と矛盾があることで、経歴詐称が発覚することもあります。
経歴詐称が気になる場合は、採用候補者に卒業証明書を提出してもらうとよいでしょう。
4.SNSの投稿から発覚する

採用候補者がSNSを使っている場合、投稿内容やプロフィールから経歴詐称が発覚することもあります。学歴や職歴の詐称が疑われるときは、SNSやインターネット上で採用候補者に関する情報を探してみるとよいでしょう。
5.タレコミが入る
珍しいパターンとしては、採用候補者の関係者や自社の取引先からのタレコミで経歴詐称が発覚するケースもあります。タレコミとは、関係者からの情報提供のことです。
たとえば、取引先の担当者が採用候補者のことを知っていた、社内に採用候補者と同じ学校出身の従業員がいる、といったケースが挙げられます。情報提供を求めることで、経歴の詐称が発覚することもあるかもしれません。
経歴詐称が発覚したときの対処法
経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇を検討する、引き続き雇用する、自主退職を促す、といった対処法が考えられます。どのような対処をすべきかは、経歴詐称の程度や社内のルールによっても異なります。
以下、それぞれの対処法について解説しますので、状況に合った対策を選択しましょう。
1.懲戒解雇を検討する
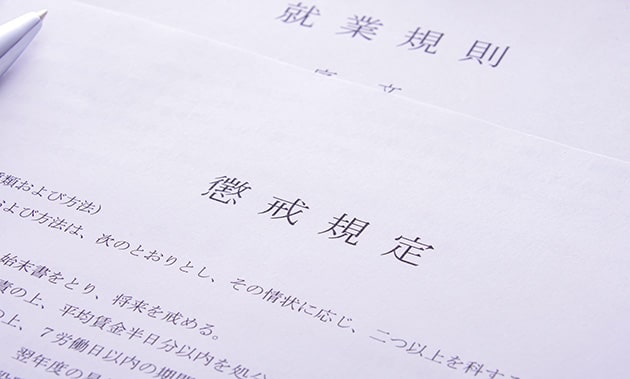
懲戒解雇とは、従業員との労働契約を解約する処分のことで、経歴詐称に対する最も厳しい対処方法といえるでしょう。
懲戒解雇は、懲戒処分のひとつです。懲戒処分は、会社の規約に違反したときに与える罰則であり、懲戒解雇のほか、訓告、減給、出勤停止、降格などの処分があります。
懲戒処分を行うためには、就業規則に記載したうえで従業員へ周知しておかなければなりません。どのような経歴詐称に対して、どのような処分が与えられるか明記しておきましょう。
懲戒処分を言い渡すときは、事実関係を確認したうえで、弁明の機会を与えるなど、正しい手続きで進めなければなりません。手続きの流れを無視すると、懲戒処分が無効になるケースもあるため注意しましょう。
また、合理的な理由がなければ、懲戒処分が無効と判断される場合もあります。たとえば学歴詐称が発覚したとしても、そもそも募集要項にて「学歴不問」としていた場合は、懲戒解雇が認められない可能性もあります。
減給や訓告など、経歴詐称の程度に合った懲戒処分を与えることが大切です。
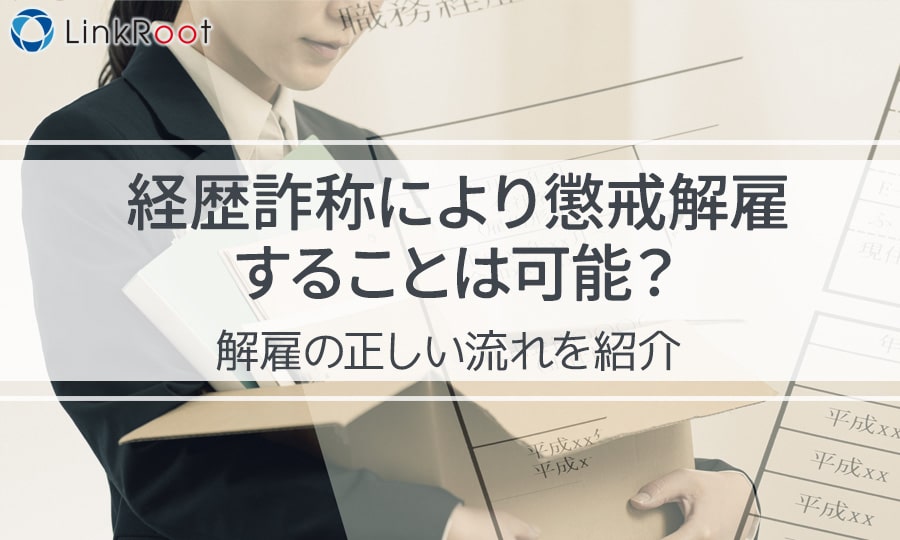
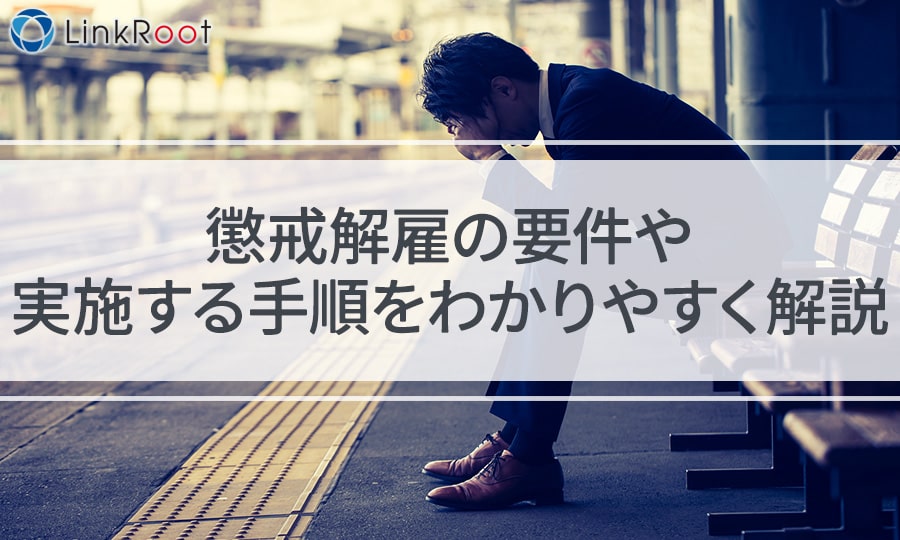
2.引き続き雇用する
状況によっては経歴詐称が発覚したあと、引き続き雇用しても問題ありません。たとえば、職歴詐称があったとしても「経験不問」「未経験歓迎」などと記載していた場合は、業務への影響が少ないと考えて継続雇用してもよいでしょう。
ただし、実際のスキルに合わせて担当業務を再検討したり、必要な知識を習得させたりすることは必要です。また、就業規則にて経歴詐称に対する処分を定めている場合は、内容に沿って訓告や出勤停止などを実施しなければなりません。
ルールを定めているにもかかわらず処分を実施しないと、会社の秩序が乱れるだけではなく、他の従業員から不満が発生する可能性もあります。
経歴詐称をした従業員を引き続き雇用する場合は、コンプライアンス上のリスクにも注意しましょう。学歴や職歴について嘘の申告をするのと同様、業務上の報告についても虚偽の内容があるかもしれません。社内の信頼関係が崩れてしまったり、クライアントとの関係性が悪化したりする可能性もあるため注意が必要です。
3.自主退職を促す
自主退職を促すことも、経歴詐称が発覚したときの対処方法のひとつです。自主退職とは、会社側から解雇を言い渡すのではなく、従業員自らの意思で退職してもらうことを意味します。
自主退職を促す場合は、まず経歴詐称の事実を確認したうえで、従業員本人の言い分や事情を聞きましょう。本人に自主退職の意思があるかヒアリングし、退職を希望している場合は退職手続きを進めます。
自主退職をする気がないときは、就業規則に則って懲戒処分を言い渡したり、減給などの処分を科したうえで継続雇用したりすることを検討しましょう。
経歴詐称を見抜くための5つのポイント
経歴詐称した人を雇用することにはさまざまなリスクがあるため、採用前にしっかりとチェックすることが大切です。
経歴詐称を見抜くためのポイントとしては、提出時の書類チェックや面接時のヒアリングを強化すること、リファレンスチェックを実施することなどが挙げられます。
以下、それぞれの方法について詳しく解説しますので確認しておきましょう。
1.履歴書の賞罰欄をチェックする
採用候補者から提出してもらう履歴書をチェックすることで、経歴詐称を見抜けることがあります。記載されている学校や会社が実在するか、職歴のなかに空白の期間はないかなどを確認することで、怪しい点を見つけ出すことが可能です。
履歴書に賞罰欄がある場合は、とくに注意しましょう。賞罰欄には、受賞した賞や犯罪歴などの罰を記載しなければなりません。賞罰欄があるのに犯罪歴を書かないことは、犯罪歴詐称に該当します。
職歴詐称とは異なり業務上の影響がないケースもありますが、他の従業員が不安を感じることもあるため、しっかりとチェックしましょう。
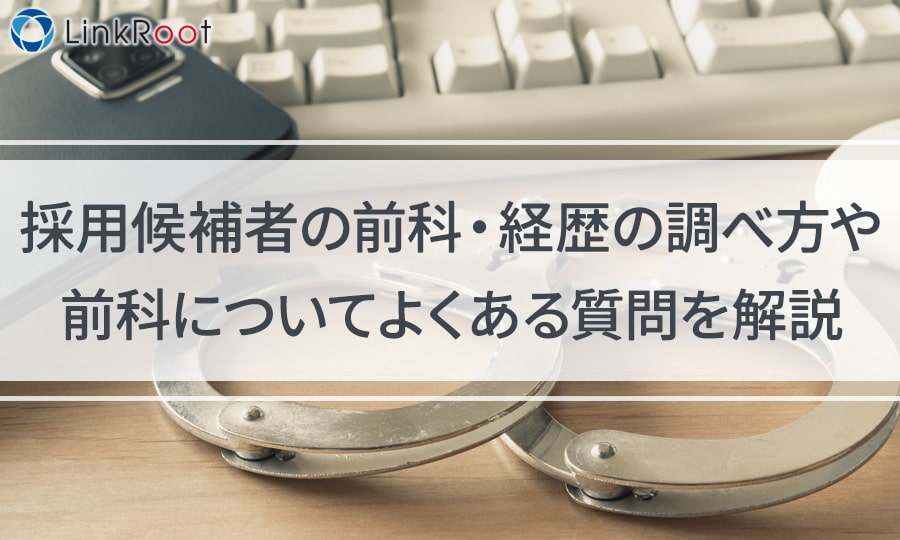
2.面接時に細かく質問する

面接時のヒアリングを強化することも経歴詐称を見抜くポイントのひとつです。とくに履歴書の内容で気になる点がある場合は、面接でさまざまな角度から質問してみるとよいでしょう。
所属していた部署や担当していた業務、学校での活動などについて回答できなければ、何らかの経歴詐称をしている可能性もあります。
学歴や職歴から考えると当然知っているはずの専門用語を出してみるのもおすすめです。知識がなかったり回答が矛盾していたりする場合は、虚偽の申告をしている可能性もあるでしょう。
3.証明書を提出してもらう
学歴や資格を証明できる書類を提出してもらうことも大切です。履歴書だけではなく、必要に応じて以下のような書類を提出してもらいましょう。
- 卒業証明書
- 保有資格の合格証
- 雇用保険被保険者証
- 退職証明書
- 源泉徴収票
- 年金手帳
卒業証明書を提出してもらえば、履歴書に記載されている学校を本当に卒業したのか、いつ卒業したのかを確認できます。また、年金手帳には社会保険加入日や退職日が記入されているため、職歴の確認にも役立ちます。
4.インターネットの調査を実施する

経歴詐称を見抜くためには、インターネットの調査を実施することも大切です。SNSや個人ブログの投稿内容から、学校での活動内容や研究内容を把握できるケースもあります。
履歴書の内容と異なる場合は、面接で詳しく聞いてみるなど、対策を取るとよいでしょう。
5.リファレンスチェックを強化する
リファレンスチェックは経歴詐称がないかどうかを確認するための重要な手法です。リファレンスチェックは、面接や履歴書だけでは把握できない、採用候補者の人柄や経歴、対人関係の問題などを調査する目的で実施します。
過去に所属していた会社の同僚や上司から、対人関係や勤務態度をヒアリングすることが一般的です。リファレンスチェックを通して、経歴詐称の有無を確認できるのはもちろん、採用候補者を多面的に評価できます。

経歴詐称は罪になる場合もある!
今回は、経歴詐称により問われる可能性のある罪や、詐称が発覚したときの対処方法を紹介しました。
経歴詐称の内容によっては、詐欺罪や軽犯罪法違反、私文書偽造罪などに該当する可能性もあります。経歴詐称した人を雇用することには企業側のリスクもあるため、採用前にしっかりとチェックすることが大切です。
経歴詐称を見抜くためには、履歴書のチェックや面接時のヒアリングを強化するだけではなく、リファレンスチェックを実施するとよいでしょう。本人や面接担当者以外の人物から情報を得ることで経歴詐称を見抜けると同時に、採用候補者を客観的に評価できます。