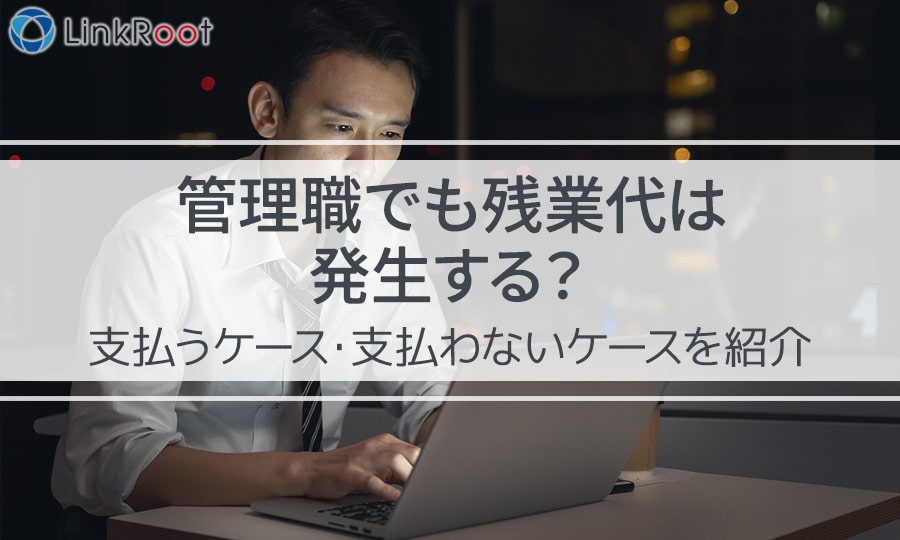管理職には残業代を支払う必要がないと誤解されがちですが、残業代が必要かどうかは状況によって異なります。残業代を正しく支給しないと、労働基準法違反となり、罰金や懲役が科せられる可能性もあるため注意しましょう。
この記事では、管理職へ残業代を支払うべきケース・支払わなくてよいケースを紹介します。判断基準を具体的に解説しますので、労使間のトラブルを防止するためにもしっかりと理解しておきましょう。
管理職へ残業代を支払うべきケース

1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合は、労働基準法の第37条に従って割増賃金を支払うのが基本です。割増賃金とは、いわゆる残業代のことで、通常の賃金の1.25倍以上に設定しなければなりません。割増賃金を正しく支給しないと、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるケースもあるため注意しましょう。(※1)
「管理職に対しては残業代を支払う必要はないのでは?」と考えている人もいるかもしれません。実は管理職であっても、残業代を支払うべきケースと支払わなくてよいケースがあります。以下のような場合は、残業代の支給が必要となるため、労働基準法に違反しないようチェックしておきましょう。
(※1)e-GOV法令検索「労働契約法」第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1.管理監督者に該当しない場合
管理監督者に該当しない場合は、管理職であっても残業代を支払う必要があります。管理監督者とは、労働条件や権限などが経営者と同じような立場にある従業員のことです。つまり、部長・課長・店長などという肩書きがあったとしても、とくに権限を与えられていないような従業員は、管理監督者には該当しません。
いわゆる「名ばかり管理職」の場合は、一般の従業員と同様の扱いとなり、残業代を支払う必要があるため注意しましょう。管理監督者の定義については、労働基準法の第41条2号に明記されています。(※2)また、管理監督者に該当するかどうかは、職務内容や与えられた権限などをもとに総合的に判断されます。
具体的な判断基準については、後ほど詳しく解説しますので参考にしてください。
(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第四十一条の二(労働時間等に関する規定の適用除外)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_41_2
2.深夜労働が発生した場合
管理監督者に該当する従業員に対しては、残業代や休日出勤手当を支払う必要はありません。ただし、深夜労働が発生した場合は、深夜労働手当が発生します。深夜労働とは22時~翌5時の時間帯における労働のことで、深夜労働手当は通常の賃金の1.25倍以上に設定しなければなりません。
管理監督者であったとしても、深夜に及ぶ労働は一般的な仕事の範囲を超えていると見なされるため、割増賃金の支払いが義務付けられているのです。割増賃金を正しく支払わないと労働基準法に違反することになり、罰則が科せられるため注意しましょう。
管理職へ残業代を支払わないケース
従業員が管理監督者に該当する場合は、残業代を支払う必要はありません。支給すべき給与を正しく計算できるようチェックしておきましょう。
また、仮に就業規則に残業代を支給しない旨を記載している場合は、どうなるのでしょうか。以下、それぞれのケースについて詳しく解説します。
1.管理監督者に該当する場合

前述のとおり、従業員が管理監督者に該当する場合は、残業代や休日出勤手当を支払う必要はありません。管理監督者は、経営者と一体的な立場にあり、労働時間や休日などの規制に関係なく働くことが求められているからです。
また、一般の従業員とは異なり大きな責任を負っており、重要な事項を決定する権利をもっています。重要なポジションに就いているため、相応の待遇を受けているケースも多いでしょう。
ただし、管理監督者に残業代を支払う必要がないからといって、何時間でも働かせてよいわけではありません。過度な労働は心身に悪影響を与えるため、適切に休ませることも重要です。残業代は不要ですが、深夜労働手当は発生することも忘れないようにしましょう。
2.就業規則に残業代を支給しない旨が記載されている場合は?
就業規則のなかに「管理職に対しては残業代を支給しない」と記載している企業もあるかもしれません。しかし、基本的には就業規則の内容よりも法律が優先されます。仮に就業規則で会社独自のルールを定めていたとしても、法律に違反している場合はその部分が無効となるのです。
つまり、就業規則の内容にかかわらず、従業員が管理監督者に該当しない場合は、残業代を支払わなければなりません。一方、管理監督者に該当する場合は、残業代の支払いは不要です。
管理職が管理監督者に該当するかどうかの判断基準
部長や店長といった肩書きがあるからといって、管理監督者に該当するとは限りません。管理監督者として認められるためには、以下のような基準を満たす必要があります。
- 経営に関わる職務を担当している
- 権限と責任を与えられている
- 一般の従業員とは異なる待遇を受けている
- 勤務形態についての裁量が与えられている
それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
1.経営に関わる職務を担当している
経営に関わる職務を担当していることは、管理監督者に該当するかどうかを判断する重要な基準です。自分の部署における業務の進捗管理や部下の指導だけではなく、経営者と一体となって経営に関わる職務を担当している場合は、管理監督者に該当するでしょう。
たとえば、経営方針を決定する会議に参加したり、人材採用や解雇に関する重要な決定に関わったりする場合は、管理監督者として認められます。このような職務を担当していると、労働時間や休日の規制範囲を超えて働く必要があるため、残業代は発生しません。逆に、部署内の一般的な業務のみを担当している場合などは管理監督者には該当せず、残業代を支払う必要があります。
2.権限と責任を与えられている
管理監督者として認められるためには、一定の権限と責任を与えられていることが必要です。部署内の業務の進め方に関して、ある程度は自由に決定できるような立場であれば、管理監督者として認められるでしょう。
一方、部長や店長などの肩書きがあっても、業務を進めるために必ず上司の承認を得る必要がある、経営陣が決めた方針を部署内に伝えるのみ、という状況の場合は、管理監督者には該当しません。
3.一般の従業員とは異なる待遇を受けている

管理監督者として認められるためには、その責任に見合う待遇を受けていることが必要です。管理監督者は、一般の従業員とは異なる職務を担当しており、大きな責任を負っているため、待遇についても扱いが異なっている必要があります。
一般の従業員よりも高い給与・賞与や役職手当が支給されているような場合は、管理監督者として認められるでしょう。一方、肩書きがあっても給与は変わらない、残業代が発生しないために収入が減った、という場合は管理監督者として認められない可能性もあります。
4.勤務形態についての裁量が与えられている
勤務形態や勤務時間に関する裁量が与えられていることも、管理監督者に該当するかどうかを判断する基準のひとつです。管理監督者は時間を問わず、経営上の重要な仕事をこなしたり、大きな判断をしたりする必要があります。
就業規則のルールに縛られずに出社・退社時刻を自由に決定できる、仕事量や勤務時間をある程度自由に調整できる、という状態であれば管理監督者として認められるでしょう。
また、管理監督者は、遅刻や早退をしたり、欠勤をしたりしても基本的に人事評価が下がることはありません。一方、残業をするために上司の承認を得る必要がある、仕事量の調整がまったくできない、という状態の場合は、管理監督者に該当しないと見なされるでしょう。
管理職から未払いの残業代を請求されたときの対応方法
管理職から未払いの残業代を請求された場合は、適切に対応しなければなりません。ここでは対応のポイントを紹介しますので、労使間のトラブルを防止するためにも理解を深めておきましょう。
1.管理監督者に該当するかを確認する
未払いの残業代を請求された際は、その従業員が管理監督者に該当するかどうかを確認する必要があります。前述のとおり、管理監督者として認められるためには、肩書きがあるだけではなく、職務内容や権限について一定の基準を満たさなければなりません。
具体的には以下のような調査を実施して、管理監督者に該当するかどうかを判断します。
- 雇用契約書や勤怠データのチェック
- 就業規則や組織図の確認
- 管理職の上長へのリアリング
- 経営者会議への出席状況の確認
上記のような調査を行い、管理監督者に該当すると判断できる場合は、残業代を支払う必要はありません。逆に、管理監督者に該当しないと判断されたときは、残業代や休日出勤手当を支給する必要があります。
2.判断に迷う場合は弁護士へ相談する

未払い残業代の請求に応じるかどうかの判断に迷う場合は、弁護士へ相談するとよいでしょう。判断を間違うと、労使間のトラブルに発展するだけではなく、労働基準法違反と見なされ罰則を受ける可能性もあるからです。
労働問題に強い弁護士に依頼すれば、そもそも残業を禁止していたかどうか、労働時間は正しく記録されていたか、残業代請求の時効が過ぎていないかなど、さまざまな視点から適切な判断をしてもらえます。残業代の支払いを拒否できる可能性もあるため、悩む場合は一度相談してみるのがおすすめです。
管理職と36協定・有給休暇などの関係
ここでは、管理職にも36協定は適用されるのか、有給休暇は発生するのか、といったポイントについて確認しておきましょう。
1.管理職にも36協定は適用される?
管理監督者に該当する従業員には、36協定は適用されません。36協定は、正式には「時間外・休日労働に関する協定書」と呼ばれ、一般の従業員に対して時間外労働や休日出勤を命じる場合は、事前に労使間で36協定を締結する必要があります。36協定を締結すれば、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて働かせることが可能です。
ただし、一般の従業員とは異なり、管理監督者には残業や休日出勤の概念がないため、36協定も適用されません。とはいえ、過度な残業や度重なる休日出勤が発生すると、心身の健康に悪影響が出るケースもあるため、適切な労務管理や健康管理を行うことが重要です。
2.管理職にも有給休暇を付与すべき?
管理監督者にも法律に従って有給休暇を付与しなければなりません。有給休暇の付与日数や付与条件は、一般の従業員も管理監督者も同じです。雇入れの日から6ヶ月継続勤務しており、全労働日の8割以上出勤している場合は、継続勤務年数に応じた日数の有給休暇を付与する必要があります。
管理監督者から有給休暇の申請があった場合、基本的には拒否できないため注意しましょう。また、年10日以上の有給休暇が付与される場合、そのうち5日は確実に取得させなければなりません。管理監督者だからといって、有給休暇の付与や取得状況の確認を怠らないようにしましょう。
3.管理職が遅刻・早退した場合は?
管理監督者が遅刻や早退をしても、その時間分の賃金を給与から控除することはできません。管理監督者には労働時間に関する規定が適用されず、ある程度自由に働けるからです。
一般の従業員の場合は、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、遅刻や早退をした時間分の賃金を控除できますが、管理監督者の給与からは控除できないため注意しましょう。控除すると、一般の従業員と同様であると見なされ、管理監督者として認められない可能性もあるため注意が必要です。
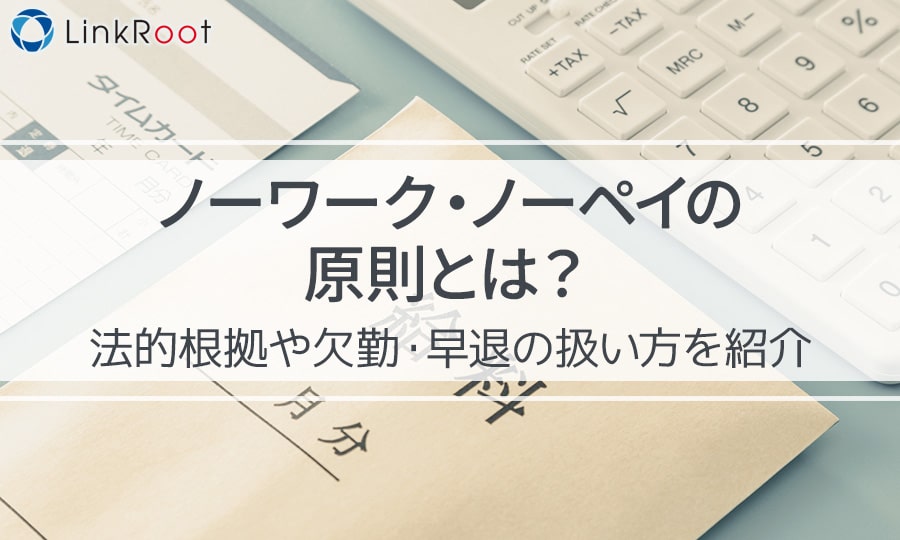
4.管理職手当は残業代と見なせる?
部長や課長などに支給する管理職手当を、残業代と見なすことは基本的にできません。法定労働時間を超えた場合に支払う残業代は、通常の賃金の1.25倍以上に設定する必要があり、企業が独自に設定する手当とは計算方法が異なるからです。
ただし、以下の要件を満たしている場合は、管理職手当を残業代と見なせます。
- 実態として、管理職手当が固定残業代として支給されている
- 基本給と管理職手当が明確に区別されている
- 残業代に相当する部分が、何時間分か明確になっている
- 残業代に相当する部分が、法定の割増賃金率の基準を満たしている
- 固定残業時間を超えた場合は、追加で支給される
管理職の残業を管理するときのポイント
管理職の残業を管理するときは、以下のようなポイントに注意しましょう。
1.客観的記録を残す必要がある

管理監督者に該当する場合、残業代を支払う必要はありませんが、勤怠状況を把握して客観的な方法で記録することは必要です。また、労働時間に関する記録は3年間保存しなければなりません。一般の従業員はもちろん、管理監督者も対象となるため、忘れないようにしましょう。
具体的には、タイムカードや勤怠管理システムなどを用いて記録を残すことが求められます。従業員ごとに日々の始業時刻と終業時刻を記録し、適切に管理することが必要です。
2.月80時間の時間外労働が発生したら医師の面接指導が必要となる
管理監督者は労働時間に関する規制を受けることはありませんが、月80時間以上の時間外労働が発生した場合は、医師の面談指導を受けさせる必要があります。適切に面談を受けさせなかった場合は、50万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため注意しましょう。
管理監督者を含め、従業員が安全かつ健康に働けるように配慮することは企業の義務です。従業員からの申請があった場合だけではなく、時間外労働が増えているときは、会社側から面談を受けるよう促す必要もあります。適切な配慮ができるよう、労働時間をしっかりと管理しておきましょう。
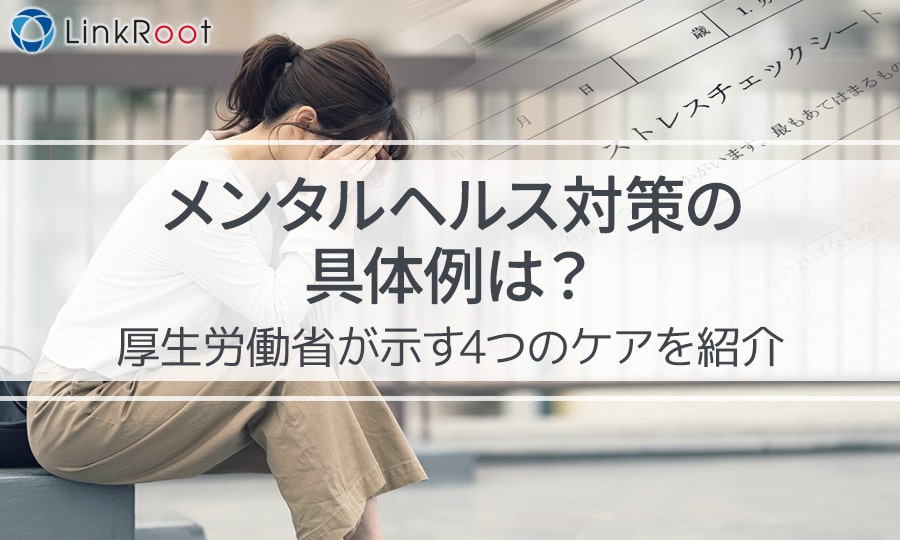
3.管理監督者に該当するか慎重に判断する
ここまで解説したとおり、管理監督者に該当するかどうかは、担当している職務内容や受けている待遇などによって異なります。肩書きがあるからといって、管理監督者に該当するとは限らないため注意が必要です。不当に残業代を支払わないと、労使間のトラブルに発展したり、労働基準法に違反したりするため慎重に判断しましょう。
管理職の残業代が発生するかどうかはケースバイケース!
今回は、管理職に対して残業代を支払うケース、支払わなくてよいケースを紹介しました。従業員が管理監督者に該当する場合は、残業代を支払う必要はありません。逆に、管理監督者に該当しない場合は、一般の従業員と同様、残業代や休日出勤手当を支給する必要があります。
また、管理監督者だからといって、無制限に働かせてよいわけではありません。過度な残業や休日出勤が続くと、体調を崩したり休職して働けなくなったりする可能性もあります。管理職の勤怠状況をしっかりと把握して、長期的に活躍してもらえるようなサポートをしていくことが大切です。