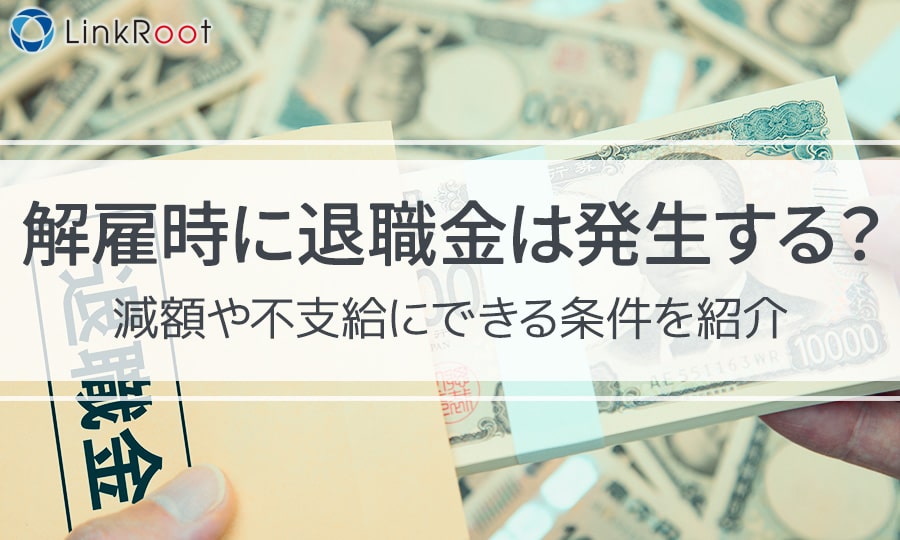従業員に何らかの問題があり、解雇をする場合、退職金を支払う必要はあるのでしょうか。実は、退職金制度の導入については法律上の定めはないのですが、制度を運用していくうえでは一定のルールに従う必要があります。
この記事では、解雇時に退職金が発生するケースや、減額・不支給にできる条件などを詳しく解説します。不当な理由で退職金を不支給にすると、労使間のトラブルが発生したり、裁判に発展したりする可能性もあるため十分に注意しましょう。
解雇や退職金の意味
解雇時の退職金について考える前に、それぞれの定義について確認しておきましょう。
解雇とは?
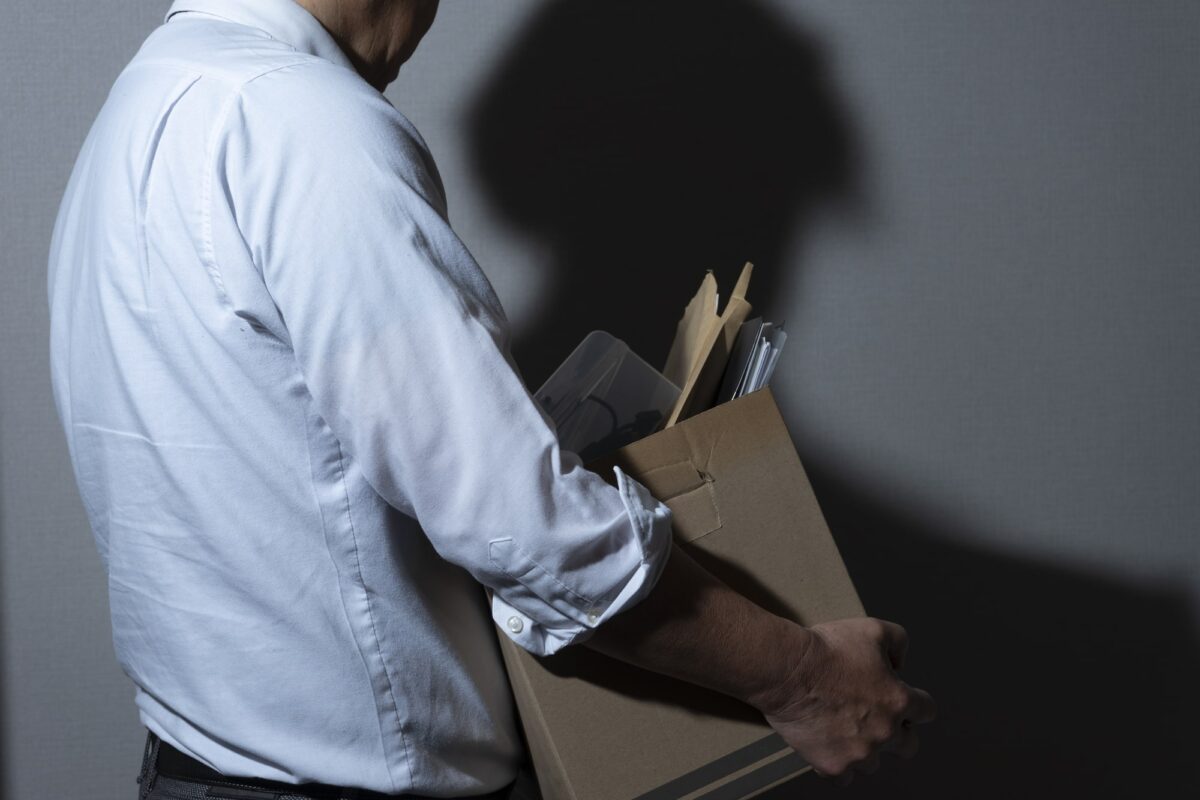
解雇とは、従業員の職を奪い、会社を辞めさせることです。従業員の意思で会社を辞める「辞職」とは異なり、企業側から一方的に雇用契約を解約します。
解雇については民法の第627条1項に記載されています。この条文によると、期間の定めのない雇用契約を締結している場合、企業と従業員どちらからでも契約解除の申し入れをすることが可能です。解約の申し入れがあった場合、2週間を経過すると雇用契約が終了します。(※1)
ただし、簡単に解雇できるわけではありません。合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇が無効となるケースもあるため注意しましょう。
また、解雇予告を行うことや解雇予告手当を支払うことなども義務付けられているため、適切な対応をすることが重要です。
(※1)e-GOV法令検索「民法」第六百二十七条1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
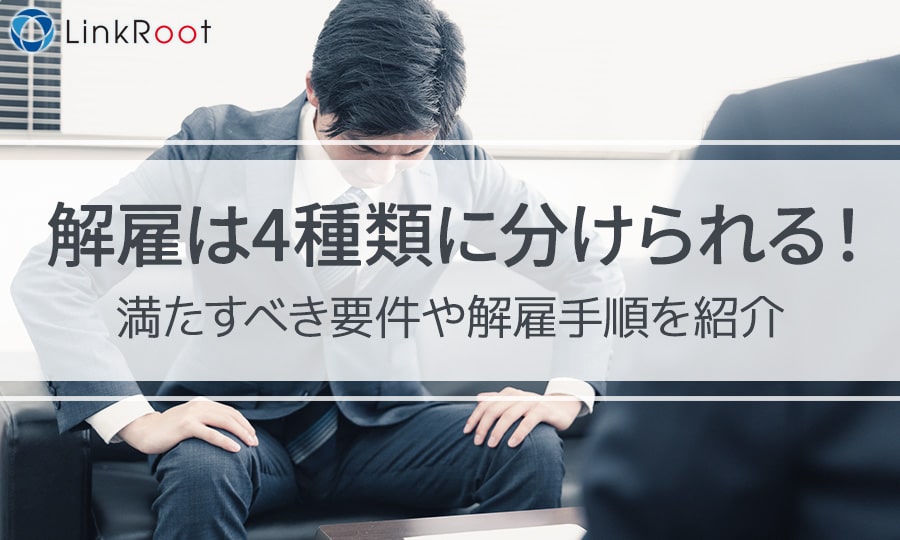
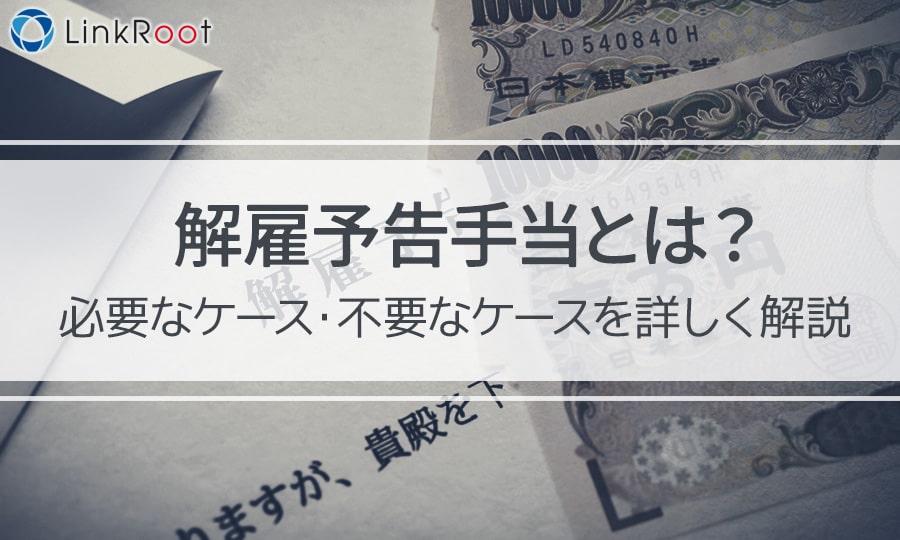
退職金とは?
退職金とは、会社を辞める従業員に対して支払うお金のことです。福利厚生のひとつとして導入している企業も多いでしょう。ただし、退職金を支払うことは法律で定められた義務ではないため、退職金制度の有無は企業によって異なります。
退職金制度がある場合は、勤続年数や働いていた期間中の成果などに応じて、支給する金額を決定するケースが一般的です。退職金の計算方法に関する法律上のルールもないため、何年目から支給する、どのような成果に対して増額する、といった決まりは企業が自由に設定できます。退職金制度を設けていない場合は、基本的に従業員に対して退職金を支払う必要はありません。
退職金が発生するケース
就業規則に記載されている場合や、慣例的に支給されている場合は、基本的に退職金を支払わなければなりません。以下、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1.就業規則に記載されている場合
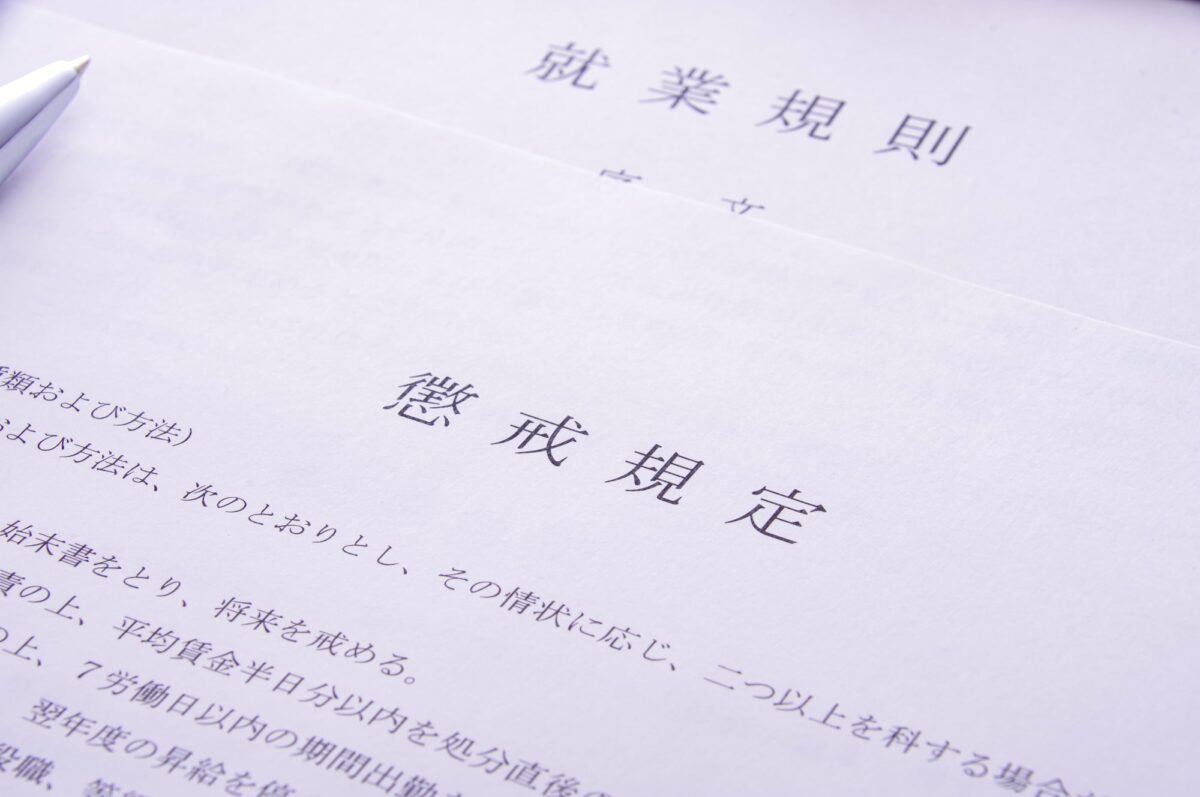
就業規則のなかに退職金を支払うことが明記されている場合は、当然、そのルールに従って支給しなければなりません。常時10人以上の従業員を雇用している場合は、就業規則を作成して労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
退職金制度を導入している場合は、就業規則のなかに、対象となる従業員の範囲や退職金の計算方法、支払い時期などを記載しておくのが一般的です。
企業側は就業規則の内容を確認したうえで、適切な対応をしなければなりません。退職金に関する記載があるなら、従業員の希望により退職する場合はもちろん、何らかの問題が発生したことにより企業側から解雇する場合でも支払う必要があります。
もし、特定のケースにおいては退職金を支払わないことにしたいなら、その旨をルール化して記載しておかなければなりません。退職金を減額・不支給にするための条件については後ほど詳しく解説します。
2.慣例的に支給されている場合
就業規則や賃金規定などに記載がないとしても、慣例的に支給している場合は、退職金の支払い義務があると見なされる可能性が高いでしょう。
たとえば、ほとんどの従業員に対して退職金を支給している場合は、仮に就業規則に記載していなくても、退職金制度を導入しているものと判断されます。よって、一部の従業員に対してのみ退職金を支給しないという判断はできず、平等な対応をすることが求められるでしょう。
逆に、在職期間中に一定の成果を出した従業員にのみ退職金を支給している場合は、報奨金のような慣例であると見なされ、全従業員に対する退職金の支払い義務は発生しません。ただし、何人以下であれば報奨金と見なされる、といった明確な基準はなく、裁判に発展した場合は個別の状況をもとに判断されます。
解雇時に退職金は必要?解雇の種類別に解説
解雇時に退職金を支払う必要があるかどうかは、状況によって異なるため注意しましょう。ここでは、以下4つの解雇の種類ごとに退職金の必要性について解説します。
- 普通解雇:一般的な能力不足や勤怠不良の際に行う解雇
- 懲戒解雇:重大なルール違反があった場合に行う解雇
- 整理解雇:経営難や事業縮小の際に行う解雇
- 諭旨解雇:企業側が従業員に退職届を提出させて行う解雇
それぞれの解雇における詳細は以下のとおりです。
1.普通解雇に対する退職金
普通解雇とは、懲戒解雇や整理解雇に該当しない解雇のことです。以下のようなケースにおいて、繰り返し注意や指導をしても状況が改善されない場合に普通解雇が実施されます。
- 勤務態度が悪い
- 無断欠勤・遅刻が多い
- 体調不良が続いている
- 上司・同僚とのトラブルが頻発している
- 協調性がない
- 能力が不足している
従業員に上記のような問題があった場合でも、就業規則に退職金に関する規定がある場合は、ルールに従って退職金を支給しなければなりません。ただし、就業規則のなかで減額や不支給に関する項目を設けている場合は、全額を支給しなくてよいケースもあります。
普通解雇の理由を明確にしたうえで、就業規則の内容と照らし合わせて、退職金支給の是非を判断することが重要です。また、そもそも退職金制度がない場合は、解雇理由がどのようなものであっても、退職金を支給する必要はありません。
2.懲戒解雇に対する退職金

懲戒解雇とは、従業員が犯罪行為に関わったり、重大なルール違反を行ったりした際に実施する解雇方法です。制裁的な意味合いが強く、以下のようなケースで実施されます。
- 会社の金を横領した
- 傷害事件を起こした
- 会社内で盗聴・盗撮を行った
- 職務怠慢により会社に大きな損害を与えた
- 重大な経歴詐称が発覚した
退職金制度を導入する場合、懲戒解雇する際は退職金を支給しない、または減額する、といったルールを設けることが一般的です。懲戒解雇を決定したときは、満額を支払わなくてよい可能性が高いため、就業規則をよく確認してから対応しましょう。
ただし、懲戒解雇は従業員に対する最も重い処分であるため、簡単に実施できるわけではありません。懲戒解雇が妥当であると認められる理由がなければ、処分が無効と判断されたり、解雇した従業員から訴訟を起こされたりする可能性もあるため注意が必要です。
退職金を支払いたくないからといって、無理に懲戒解雇を選択することは避けましょう。
また、懲戒解雇に該当するような理由があったとしても、あえて普通解雇を選ぶケースもあります。普通解雇という穏便な措置にすることで、従業員の功績に配慮したり、訴訟のリスクを回避したりすることが可能です。
3.整理解雇に対する退職金
整理解雇とは、経営難に陥ったときや事業を縮小するときなどに実施する解雇方法です。整理解雇は、以下のようなケースにおいて実施されます。
- 業績不振により従業員を減らす必要がある
- 事業縮小により支店や工場を閉鎖する
- 解雇以外の方法では経営難を解決できない
従業員側に問題があるわけではないため、整理解雇を行うときは就業規則に従って退職金を支給しなければなりません。
また、整理解雇を行う前に退職希望者を募集する場合は、特別退職金を支払うケースもあります。通常の退職金に上乗せして支払うため、一時的に負担が大きくなりますが、長期的に見ると人件費を削減することが可能です。
とはいえ、整理解雇が認められる状況の場合、会社に退職金を支払うほどの余裕がないケースも多いでしょう。逆に会社に資金がある状況の場合は、整理解雇が認められない可能性もあります。整理解雇が認められる場面は限られているため、慎重に判断することが大切です。
4.諭旨解雇に対する退職金
諭旨解雇とは、従業員が何らかの問題を起こしたときに話し合いを行い、従業員に納得してもらったうえで退職届を提出させることです。以下のような問題があったものの、本人が深く反省している場合などに諭旨解雇が実施されます。
- 長期的な無断欠勤
- ハラスメント行為
- 就業規則に関する違反
諭旨解雇は、企業側が強制的に行う懲戒解雇よりも寛大な措置とされていますが、就業規則のなかで退職金の減額や不支給を定めている企業も多いでしょう。ただし、諭旨解雇による退職金の減額や不支給は、簡単に認められるわけではありません。
そもそも諭旨解雇自体が重い処分であるため、行為の悪質性や反省の度合いなどを考慮して慎重に判断することが大切です。無理に退職届を提出させると、懲戒権の濫用と見なされ、解雇が無効となる可能性もあるため注意しましょう。
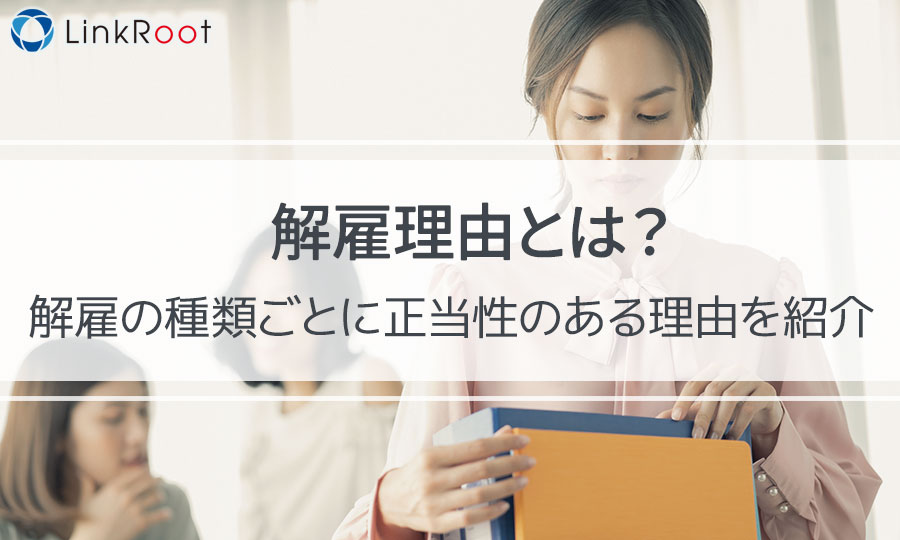
解雇時に発生する退職金の相場はどのくらい?
解雇時に支給する退職金の相場はどのくらいでしょうか。ここでは、退職金制度の導入率などについて詳しく見ていきましょう。
退職金の有無や金額は企業によって異なる

前述のとおり、退職金の支払いを義務付ける法律などは存在しないため、退職金制度を導入していない企業もあります。厚生労働省の調査によると、企業規模ごとの退職金制度の導入率は下表のとおりです。(※2)
| 企業規模 | 退職金制度の導入率 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 90.1% |
| 300 〜 999人 | 88.8% |
| 100 〜 299人 | 84.7% |
| 30 〜 99人 | 70.1% |
調査結果を見ると、大きな企業ほど退職金制度の導入率が高いことがわかります。導入率は業種によっても異なりますが、従業員の満足度を高めるために多くの企業が退職金を支給しているといえるでしょう。
また、退職金の支給対象者や金額の計算方法についても企業側が自由に設定できます。勤続年数が長くなるほど支給金額が増えるというルールを採用している企業が多く、成果に応じてプラスするというケースもあるでしょう。
(※2)厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況(退職給付(一時金・年金)制度)」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/dl/gaiyou03.pdf
不当解雇の場合は解決金が発生する
不当解雇を行うと、退職金だけではなく解決金の支払いが発生するケースもあります。解決金とは、従業員とのトラブルが起きた際、長引く交渉を終えるために支払うお金のことです。
従業員が解雇という処分に納得できない場合、不当解雇であると主張する可能性があります。話し合いによって納得してもらえる場合もありますが、トラブルが長引く場合、解決金を支払って会社を辞めてもらうことは有効な対応策のひとつです。
解決金の金額は状況によって異なりますが、従業員の給与の数ヶ月分を支払うケースが多いでしょう。ただし、大きなトラブルに発展していたり、交渉が長引いたりすると、給与の数年分を支払うことになる可能性もあります。
解決金を支払った場合でも、退職金を支払うべき条件に該当する場合は、解決金と退職金の両方を支給しなければなりません。
解雇はトラブルに対する重い処分であるため、従業員が不満を感じることも多いでしょう。そもそもトラブルが発生した時点で、従業員との関係が悪化しているケースもあります。不当解雇を行うと、会社に対して大きな要求をされる可能性もあるため注意が必要です。
解雇時の退職金を減額・不支給にするための条件
ここまで解説したとおり、解雇時の退職金を減額したり不支給にしたりすることは簡単には行えません。減額や不支給とする場合は、最低でも以下2つの条件を満たすことが必要です。
- 就業規則に明記する
- 労働者に重大な責任がある
それぞれの条件について詳しく確認していきましょう。
1.就業規則に明記する
退職金を支給するルールはもちろん、減額や不支給のルールについても就業規則のなかに明記しておく必要があります。たとえば、「諭旨解雇や懲戒解雇の場合には、退職金の全部または一部を不支給とする」などと記載しておきましょう。
就業規則のなかに減額や不支給の内容を記載することは、とくに違法ではありません。厚生労働省が作成するモデル就業規則においても、第54条に減額・不支給の内容が記載されています。(※3)
減額や不支給の規定を設けていない場合は、仮に懲戒解雇であっても通常のルールに従って退職金を支給することが求められるでしょう。
就業規則の文言は自由に作成できますが、モデル就業規則を参考にしながら自社の状況に合わせて記載することが重要です。悩んだときは、労務問題に詳しい専門家に相談するのもよいでしょう。
(※3)厚生労働省「モデル就業規則」
2.労働者に重大な責任がある

就業規則のなかに規定を設けたからといって、必ず減額や不支給が認められるとは限りません。退職金には、賃金の後払い的な性格と、在職期間中の功労に対する報償的な性格があるからです。
つまり、在職期間中の功労が失われるほどの問題行為や背信行為がある場合でなければ、退職金の減額や不支給は原則認められません。
重大な問題行為や背信行為に該当するかどうかは、個別の事情を含めて総合的に判断されます。一般的には、会社の顧客情報や機密情報をライバル企業に売り渡した、会社の金を横領した、暴行や窃盗などの犯罪行為に関わった、といった場合は重大な背信行為に該当するでしょう。
解雇時の退職金を減額・不支給にするための方法
実際に解雇時の退職金を減額したり不支給にしたりする場合は、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。不当に減額や不支給にすると、従業員とのトラブルに発展する可能性もあります。
具体的には以下のような点に注意しましょう。
1.運用マニュアルを作成する
解雇時の退職金を減額や不支給にする場合、前提条件として就業規則のなかに規定を設けなければなりません。ただし、就業規則を正しく運用しなければ、従業員とのトラブルが発生する可能性が高いため、運用マニュアルを作成しておくとよいでしょう。
運用マニュアルを作成しておけば、たとえば従業員に対する好き嫌いで退職金の支給・不支給を決定するような、恣意的な制度運用を避けることが可能です。就業規則だけではなく、運用マニュアルによる具体的な指針を準備しておくことで、面倒なトラブルを防止できるでしょう。
2.労働者と交渉を行う
労働者との交渉をうまく進めることで、退職金の減額や不支給に納得してもらえるケースもあります。たとえば、労働者が懲戒解雇に該当するような問題を起こした事例を考えてみましょう。
懲戒解雇となると再就職が難しくなる、失業保険の給付制限を受けるなど、労働者側の不利益が大きくなります。そこで、懲戒解雇ではなく普通解雇とする代わりに退職金を不支給とさせてもらう、といった交渉が可能です。
基本的には就業規則の内容に従う必要はありますが、労働者の同意を得ることで退職金を減額や不支給にすることができます。
ただし、退職金を受け取る権利を強制的に放棄させるなど、不当な手段で減額や不支給とすることは避けなければなりません。
3.必要に応じて弁護士に相談する

退職金を減額・不支給としたい場合、必要に応じて弁護士に相談することも大切です。ここまで解説したとおり、従業員側に問題があって懲戒解雇する場合においても、退職金の減額・不支給が認められないケースもあります。
退職金を支払いたくないからといって無理に減額すると、従業員とのトラブルや訴訟に発展する可能性もあるでしょう。無駄な費用や手間が発生することを防ぐためにも、悩んだときは早めに専門家に相談するのがおすすめです。
解雇時の退職金に関する注意点
解雇時の退職金に関して、次のような注意点もあります。
- 退職後の不正発覚についても就業規則に記載しておく
- 解雇する前に正当な理由を明確にしておく
各注意点の詳細は以下のとおりです。
1.退職後の不正発覚についても就業規則に記載しておく
従業員が退職してから、懲戒解雇に該当するような不正が発覚するケースもあります。在職期間中には不正に気付くことができず、すでに退職金を支払っていることもあるでしょう。
退職金を取り戻したい場合でも、就業規則に返還の規定がなければ請求することはできません。時間が経ってから不正に気付くケースもあるため、就業規則には返還の規定を設けておくことが大切です。
2.解雇する前に正当な理由を明確にしておく
退職金の減額や不支給について検討する前に、解雇理由を明確にしておくことも重要です。退職金の減額・不支給が難しいのと同様、解雇についても簡単に実施することはできません。
まずは従業員のどのような行為に対して解雇を行おうとしているのかを明確にする必要があります。また、その理由が就業規則に記載されている解雇事由に該当するのかを確認することも必要です。
不当な理由で解雇すると、従業員から訴えられるケースもあるため注意しましょう。
解雇時の退職金はルールに従って支払おう!
今回は、解雇時に支払うべき退職金について解説しました。退職金制度の導入を義務付ける法律はありませんが、就業規則のなかに規定を設けている場合、ルールに従って退職金を支給しなければなりません。
仮に懲戒解雇や諭旨解雇であっても、退職金を支払うのが基本です。もし一定の条件に該当する場合に減額や不支給としたいなら、その旨を就業規則に記載しておかなければなりません。正当な理由もなく退職金を減額したり不支給としたりすると、従業員とのトラブルに発展する可能性もあります。
退職金に関するルールを明確にしたうえで、全従業員に対して平等な対応をしていきましょう。