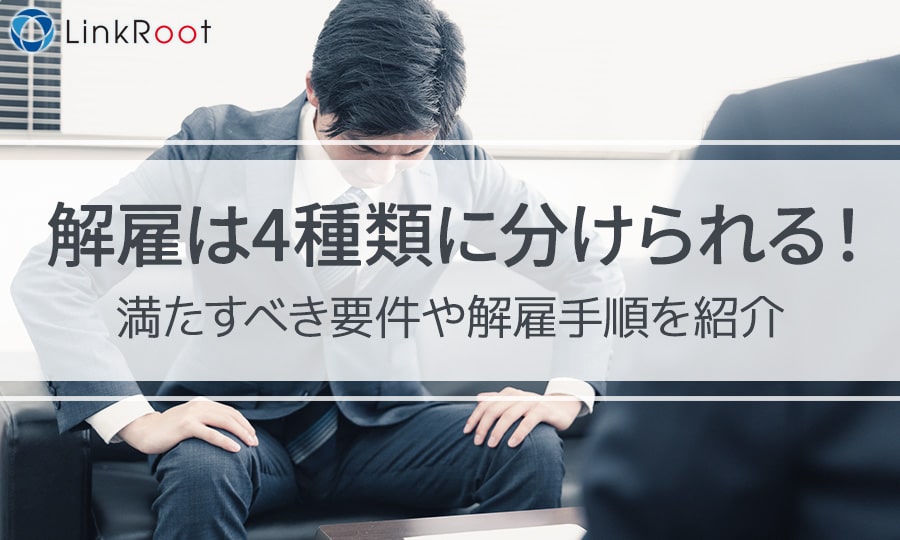解雇にはいくつかの種類があります。解雇を実施するときは、従業員が起こした問題の内容や悪質性に応じて、適切な種類の解雇を選択することが大切です。
この記事では、解雇の種類や、それぞれの解雇において満たすべき要件を詳しく解説します。解雇手順についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
解雇とは?
解雇の種類について解説する前に、解雇の定義や就業規則に記載する必要性について確認しておきましょう。
解雇は労働者の意思に反しても行われる

解雇とは、何らかの問題が発生したときに、従業員との雇用契約を企業側から一方的に解約することです。転職するときなどに従業員が自分の意思で会社を辞める「辞職」とは異なり、解雇は従業員の意思に反しても行われます。
従業員が仕事を続けたいと考えていたとしても、一定の要件を満たしていれば企業側から雇用契約を解約することが可能です。
解雇の種類について就業規則に記載する必要がある
解雇の種類については就業規則に記載し、従業員へ周知しなければなりません。解雇に関する項目は、就業規則に必ず記載すべき絶対的必要記載事項に該当します。(※1)
普通解雇や懲戒解雇といった解雇の種類はもちろん、それぞれの解雇がどのような場合に実施されるのか、解雇理由についても明記しておくことが重要です。解雇理由の記載がない場合、解雇が認められない可能性もあるため注意しましょう。
また、懲戒解雇などの一部のケースにおいて退職金を支給しない場合は、その旨を記載しておかなければなりません。退職金に関する内容は、制度がある場合に記載すべき相対的必要記載事項に該当します。
退職金の支給についてのみ記載していると、懲戒解雇の場合でも支給する必要が出てくるため、減額や不支給に関するルールについても記載しておきましょう。
(※1)厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
解雇に関する法律
解雇に関する主な法律は以下の3つです。
民法
民法の第627条には、期間の定めのない雇用契約を締結している場合、企業と従業員どちらからでも契約解除の申し入れができると記載されています。(※2)
また、解約の申し入れから2週間が経つと、雇用契約は終了します。
(※2)e-GOV法令検索「民法」第六百二十七条1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
労働基準法
解雇に関する条文は、労働基準法のなかにも存在します。従業員を解雇しようとする場合、労働基準法の第20条に従って、30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければなりません。(※3)解雇は従業員の仕事を奪うという行為であるため、不利益が大きくなりすぎないよう配慮することが求められているのです。
(※3)e-GOV法令検索「労働基準法」第二十条(解雇の予告)
労働契約法
従業員を解雇するときは、労働契約法にも注意しなければなりません。労働契約法の第16条には、客観的に合理的な理由がない場合は、解雇が認められないことが記載されています。(※4)
また、解雇理由が社会通念上相当であることも必要です。仕事上の軽いミスだけで解雇という重い処分を与えると、解雇の権利を濫用したと見なされるケースもあるため注意しましょう。
(※4)e-GOV法令検索「労働契約法」第十六条(解雇)
4種類の解雇について詳しく解説
解雇には次の4種類があります。
- 普通解雇
- 整理解雇
- 懲戒解雇
- 諭旨解雇
それぞれの解雇について詳しく見ていきましょう。
1.普通解雇

普通解雇とは、整理解雇・懲戒解雇・諭旨解雇以外の解雇のことです。従業員に以下のような問題があるときに、普通解雇をすることが検討されます。
- 勤務態度が悪い
- 能力が不足している
- 無断欠勤や遅刻が続いている
- 体調不良により継続した勤務が難しい
- 同僚とのトラブルが多い
- 協調性がない
- 業務命令違反を繰り返している
懲戒解雇に該当するほどの重大な規則違反はないものの、会社のルールを無視した働き方をしていたり、上司や同僚とのトラブルが多かったりする場合は、普通解雇を検討することになるでしょう。
ただし、「普通」という名前ではあるものの、簡単に解雇できるわけではありません。従業員に何らかの問題がある場合、まずは注意や指導を行う必要があります。また、解雇予告を行うことや、就業規則に記載されている解雇理由に該当するかどうかをチェックすることなども必要です。解雇の要件については後ほど詳しく解説しますので、参考にしてください。
2.整理解雇
整理解雇とは、業績不振のために事業を縮小する場合など、経営上の理由から従業員を解雇することです。整理解雇においては、従業員側の問題はありません。整理解雇は、企業側に以下のような課題がある場合に行われます。
- 経営難のために事業を縮小する
- 人件費を削減するために従業員を減らさなければならない
- 収支計画の悪化により事業所を閉鎖する
ただし、事業を縮小するからといって、簡単に整理解雇を実施できるわけではありません。解雇以外の方法では経営難を解決できないなど、一定の要件を満たさなければ、解雇は認められないため注意しましょう。
3.懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員が会社に大きな損害を与えたり、重大な犯罪行為があったりしたときの解雇方法です。従業員に対する制裁としての意味合いがあり、懲戒処分のひとつとして就業規則のなかに記載されているケースが多いでしょう。
懲戒処分は、主に次のような場合に実施されます。
- 会社の資金を横領した
- 飲酒運転により交通事故を起こした
- ハラスメント行為を繰り返している
- 重大な職歴詐称や学歴詐称が発覚した
- 会社に大きな損害を与えた
懲戒解雇は、出勤停止・減給・降格といった懲戒処分のなかで最も重い制裁です。会社のルールによっては退職金が支給されなかったり、再就職において不利になったりするため、ほかの解雇方法よりも厳しい基準が設けられています。
要件を満たしていないのに懲戒解雇を行うと、労使間のトラブルが発生したり、不当解雇として訴えられたりする可能性もあるため、慎重に実施しなければなりません。
4.諭旨解雇
諭旨解雇とは、従業員が懲戒解雇に該当するような問題を起こしたときに話し合いを行い、従業員から自主的に退職届を提出してもらう解雇方法です。
懲戒処分のひとつではありますが、在職期間中の従業員の功績や反省の度合いを考慮して、懲戒解雇を避けるときに選択されます。従業員が退職届の提出を拒否した場合は、懲戒解雇を検討することになるでしょう。
諭旨解雇は、懲戒解雇より軽い制裁ではありますが、従業員の生活に大きな影響を与える処分であるため、簡単に実施できるわけではありません。また、従業員が納得していないのに無理に退職届を提出させると、処分が無効となる可能性があります。
解雇時は種類ごとの要件を満たす必要がある
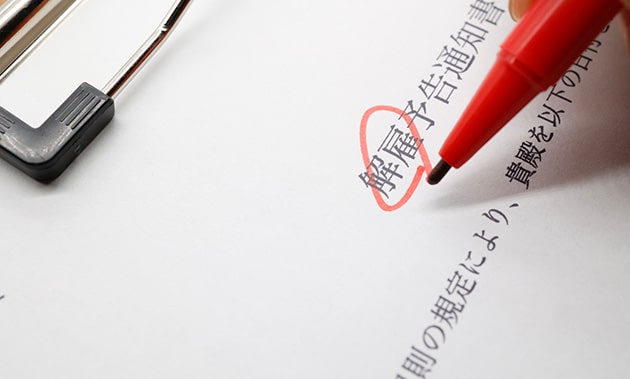
ここまで紹介したように、解雇には4つの種類があります。さらに、種類ごとに満たすべき要件があるため注意しましょう。
解雇の種類ごとの要件は以下のとおりです。
1.普通解雇の要件
普通解雇を実施するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 解雇予告を行う
- 就業規則に記載された解雇理由に該当する
- 客観的に合理的な理由がある
- 解雇が社会通念上相当である
普通解雇を行う場合、まずは労働基準法に従って、30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければなりません。また、解雇理由を明確にしたうえで、その理由が就業規則に記載されているかを確認することも必要です。
就業規則に記載された解雇理由に該当しない場合、普通解雇が認められない可能性が高いため注意しましょう。
さらに解雇理由は、客観的に合理的なものであり、解雇が社会通念上相当であると認められる必要があります。解雇という重い処分が適切でない場合は、処分が無効となるでしょう。
2.整理解雇の要件
整理解雇を実施するための要件は以下のとおりです。
- 人員を削減する必要がある
- 解雇以外の方法を検討し尽くしている
- 人選の合理性がある
- 従業員への説明や協議が済んでいる
整理解雇が認められるのは、経営状態の悪化などによって人員を削減する必要がある場合に限られます。ただし、経営状態が悪いとしても解雇は最後の手段であるため、解雇以外の方法をしっかりと検討しなければなりません。
新しい人材を採用するなど、矛盾した行為があると整理解雇が認められないため注意しましょう。
また、人選の合理性があることも重要です。なぜ特定の従業員を解雇するのか、事前に基準を作成しておき、恣意的にならないよう適切な人選を行いましょう。さらに整理解雇について従業員へ説明し、協議を済ませておくことも必要です。
3.懲戒解雇の要件
懲戒解雇を行うためには、次の要件を満たす必要があります。
- 就業規則に懲戒解雇の項目がある
- 懲戒解雇を行うための理由に該当する
- 客観的に合理的な理由があり、懲戒解雇が社会通念上相当である
- 従業員に弁明の機会を与えている
懲戒解雇を実施する前提として、就業規則のなかに記載しておかなければなりません。懲戒解雇を含めた懲戒処分の内容を明確にし、どのような理由で懲戒解雇が行われるかを記載しておきましょう。
実際に懲戒解雇を行うときは、普通解雇と同様、客観的に合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当であると認められる必要があります。問題の程度によっては、減給や降格などの懲戒処分が適切なケースもあるため注意が必要です。
また、従業員に弁明の機会を与えなければ、処分が無効となる可能性もあります。
4.諭旨解雇の要件
諭旨解雇は、懲戒解雇と同じく懲戒処分のひとつであるため、同様の要件を満たす必要があります。就業規則を作成するときは、諭旨解雇を行えることや、諭旨解雇に該当する理由を明記しておきましょう。
また、懲戒解雇と同様に、従業員に弁明の機会を与えなければなりません。
解雇の種類を検討するときの一般的な流れ
ここでは、解雇の種類を検討するときの一般的な流れを紹介します。正しい手順で解雇を進めなければ、労使間のトラブルに発展する可能性もあるため注意しましょう。
1.解雇が妥当か検討する
解雇は従業員の生活に関わる重い処分であるため、慎重に実施しなければなりません。問題への対応として解雇が妥当かどうか、しっかりと検討しましょう。1回目の問題行動であれば厳重注意にとどめる、減給や出勤停止の処分も検討するなど、解雇という重い処分が適切かどうか、慎重に判断することが重要です。
2.解雇の種類を検討する
解雇することに決めたら、種類を検討しましょう。前述のとおり、解雇には4つの種類があります。経営上の理由がある場合は整理解雇、従業員に重大な問題がある場合は懲戒解雇や諭旨解雇、それ以外の場合は普通解雇を選択するのが基本です。
3.解雇理由を明確にする
解雇の種類だけではなく、解雇理由も明確にしなければなりません。どのような理由でその解雇を実施するのかを明確にしましょう。当然、客観的で合理的な理由が求められます。
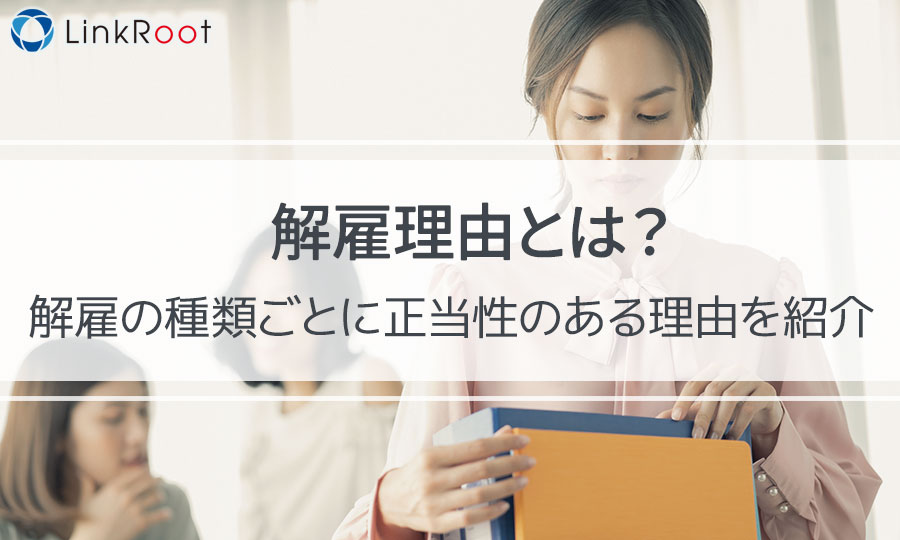
4.就業規則を確認する
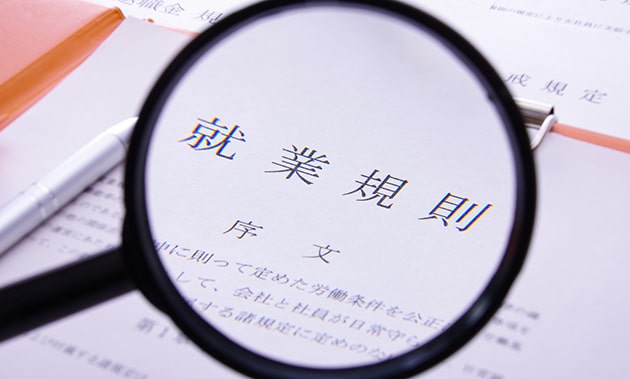
解雇を実施するときは、必ず就業規則を確認しましょう。そもそも就業規則には、解雇理由を明記しておく必要があります。
解雇理由を明確にしたら、就業規則に記載されている内容に該当するかどうかをチェックしましょう。該当しない場合は、解雇が認められない可能性もあるため注意が必要です。
5.必要に応じて退職勧奨を行う
解雇の前に、必要に応じて退職勧奨を行いましょう。退職勧奨とは、従業員に退職をしてもらうよう促し、同意を得たうえで退職届を提出してもらうことです。
解雇という処分を避けられるため、従業員にとってもメリットがあります。ただし、従業員が納得していないのに無理に退職届を提出させることは避けましょう。
6.解雇予告を行う
30日以上前に解雇予告を行いましょう。解雇予告が遅れた場合や、即日解雇したい場合は、解雇予告手当を支払う必要があります。
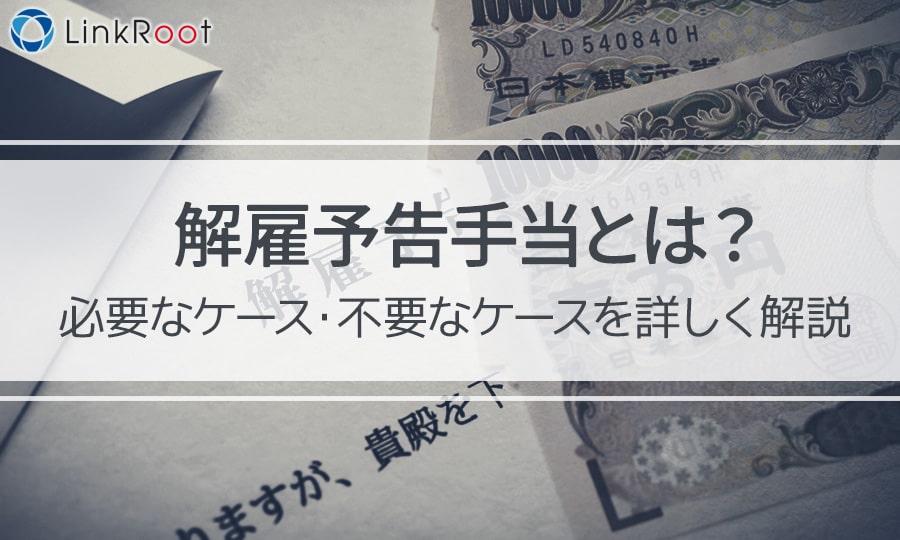
7.解雇通知書を交付する
解雇通知書とは、雇用契約を解約することを従業員へ伝えるための書類です。解雇通知書には、解雇理由や解雇日などを記載します。
また、従業員からの申請があった場合は、解雇理由証明書を発行しなければなりません。この書類には、解雇理由だけを簡潔に記載します。従業員が次の職場や裁判所へ提出する可能性があるため、従業員の不利益にならないよう配慮することが必要です。
8.解雇について発表する
誰がどのような理由で解雇されたのか、社内で発表します。ただし公表する際は、従業員や関係者の名誉やプライバシーに配慮しなければなりません。適切な公表を行うことで、社内の秩序維持やトラブルの再発防止につながるでしょう。
9.社会保険などの手続きを行う
解雇に伴って、健康保険や雇用保険に関する手続きを行う必要があります。期限が決められている手続きもあるため、遅れないように注意しましょう。
試用期間中の解雇が認められるケース
試用期間中の従業員を解雇することは可能ですが、簡単に実施できるわけではありません。一般的な解雇と同様、合理的な理由が求められるため注意が必要です。
以下、試用期間中の解雇が認められるケースについて解説します。
1.能力が不足している

能力が不足していることは解雇を検討する理由のひとつです。ただし、入社してすぐに能力を発揮できるとは限らないため、まずは指導を行うことが必要です。適切なサポートや注意を行うことなく解雇すると、不当解雇と見なされる可能性もあります。
2.勤務態度が悪い
業務命令に従わない、正当な理由のない遅刻や欠勤が多い、といった場合も解雇を検討することになるでしょう。ただし、能力不足の場合と同様、まずは注意や指導を行わなければなりません。繰り返し指導しても状況が改善されない場合は、解雇が認められやすくなります。
3.重大な経歴詐称がある
重大な経歴詐称がある場合も、解雇を検討することになります。とはいえ、軽微な詐称に対して、解雇を実施することは原則認められません。詐称を知っていたら採用しなかった場合などは、解雇が認められやすいでしょう。
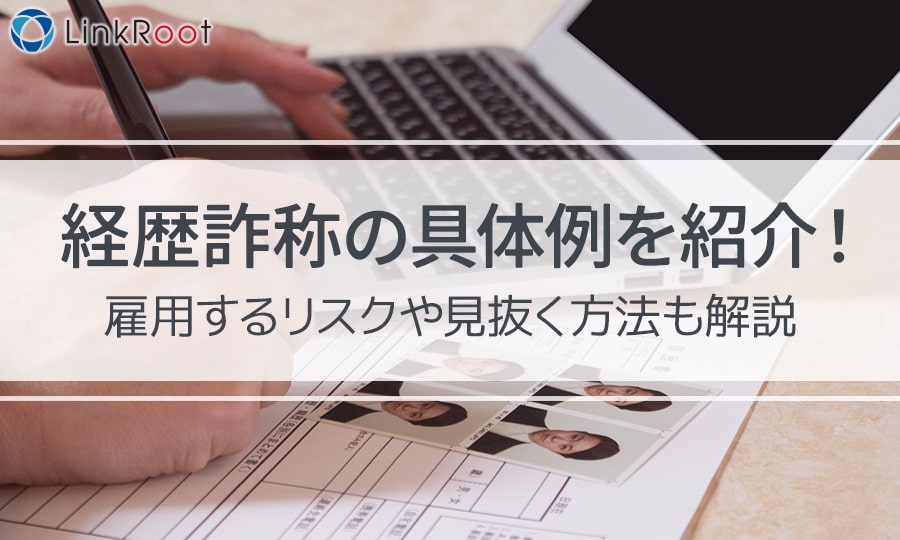
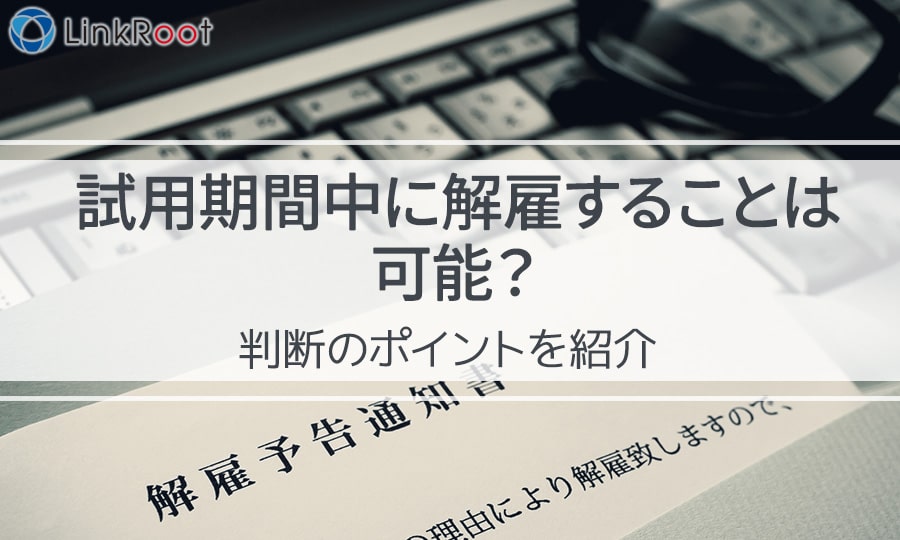
解雇の種類や理由によっては失業保険がもらえない
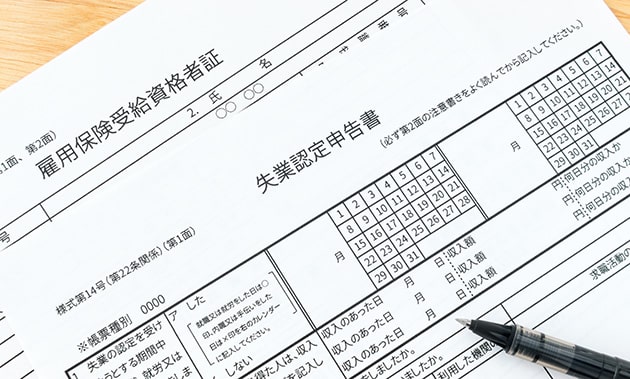
退職する際、一定期間、雇用保険料を支払っていれば、従業員は失業保険を受給することが可能です。ただし、解雇の種類や理由によっては、失業保険がもらえないケースもあります。
また、自己都合か会社都合かによって、失業保険を受給するまでの期間が長くなったり、金額が増減したりするため注意が必要です。とくに犯罪行為が理由の懲戒解雇の場合、失業保険を受け取れない可能性もあります。従業員の生活に大きく関わる問題であるため、解雇は慎重に行いましょう。
トラブルの内容に応じて適切な解雇の種類を選ぶことが重要!
今回は、解雇の種類や、それぞれの解雇において満たすべき要件について解説しました。解雇は、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・諭旨解雇の4種類に分けられます。それぞれの解雇において、満たすべき要件が異なるため注意しましょう。
要件を満たしていないのに解雇を実施すると、不当解雇と見なされて処分が無効となったり、裁判に発展したりする可能性もあります。トラブルの内容に応じて、適切な解雇を実施することが大切です。