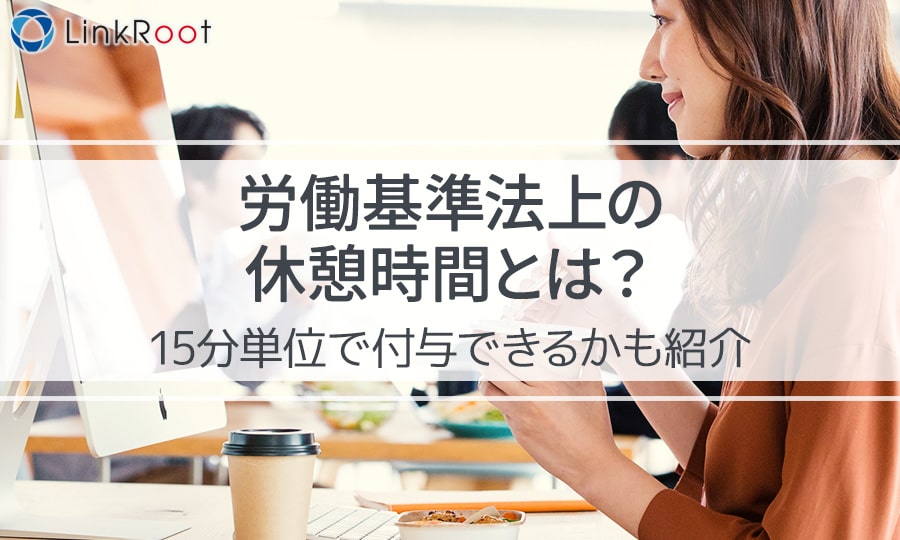従業員を労働させる場合、労働時間に応じて休憩を付与しなければなりません。付与すべき休憩時間の長さは、労働基準法によって明確に定められているため、違反しないように注意しましょう。また、全従業員に対して一斉に付与するなどのルールも存在します。
この記事では、労働基準法による休憩時間の付与ルールについて詳しく解説します。15分単位など、分割して付与できるのかについても解説しますので、ぜひチェックしておきましょう。
労働基準法で定められた休憩時間
休憩時間とは、仕事から完全に離れ、リフレッシュのために自由に過ごせる時間のことです。昼食を食べる、仮眠を取る、同僚と会話するなど、従業員は休憩時間を自由に使えます。休憩時間は、疲労によって労働災害が発生することを防止するために必要な存在です。また、生産性や集中力の低下を防ぐうえでも重要な時間といえるでしょう。
休憩時間に関するルールは、労働基準法の第34条に記載されています。(※1)付与すべき休憩時間の長さだけではなく、与え方に関するルールもあるため、しっかりと理解しておかなければなりません。
たとえば、休憩しながら電話番をするような場合は、休憩時間としてカウントできないため注意が必要です。休憩時間の付与ルールについては、後ほど詳しく解説します。まずは、労働時間に対する休憩時間の長さについて確認しておきましょう。
(※1)e-GOV法令検索「労働基準法」第三十四条(休憩)
1.労働時間が6時間以内の場合
労働時間が6時間以内の場合、休憩時間を付与する必要はありません。6時間ちょうどの場合も休憩は不要です。ただし、仕事内容によっては肉体的・精神的な疲労が蓄積して、生産性や集中力が低下してしまうケースもあるでしょう。労働災害につながる可能性もあるため、労働基準法上の義務ではありませんが、状況に応じて適切な休憩を与えることも重要です。
2.労働時間が6時間を超え8時間以内の場合
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は、最低でも45分の休憩を与える必要があります。労働基準法で決められている数値は最低基準であるため、労使協定を結んで45分より長い休憩を付与しても問題ありません。たとえば休憩時間を管理しやすくするため、労働時間に関係なく、全従業員に1時間の休憩を与える企業もあるでしょう。
3.労働時間が8時間を超える場合
労働時間が8時間を超える場合は、最低でも1時間の休憩を与える必要があります。先ほど解説したとおり、基準以上の休憩を与えても問題ないため、極端には2時間などの長い休憩を与えることも可能です。なお、休憩時間には労働が発生しないため、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、賃金を支払う必要はありません。
4.夜勤が発生した場合
夜勤に対する休憩時間の付与ルールは、一般勤務の場合と同様です。労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えましょう。
夜勤が2暦日にまたがる場合でも考え方は変わりません。たとえば、5月10日の22時から翌5月11日の7時まで勤務する場合、継続して9時間働くことになるため、1時間以上の休憩を付与する必要があります。労働時間は暦日単位でカウントするわけではないため注意しましょう。
休憩時間を15分単位で付与することも可能

従業員に対して、休憩時間を15分単位で与えることも可能です。前述のとおり、労働基準法によって休憩時間の最低基準は定められていますが、分割して付与することは禁止されていません。仮に10分や30分といった短い休憩であっても、合計して最低基準を超えていれば問題ないのです。
たとえば労働時間が9時間の場合は、1時間の休憩を与える必要があります。1時間まとめて付与してもよいのですが、15分の休憩を4回付与することも可能です。ただし、15分の休憩を3回付与するだけでは1時間に満たないため、労働基準法に違反することになります。
休憩時間の分割付与は、シフトなどの都合でまとまった休憩を付与することが難しい場合に役立つ方法です。合計時間をしっかりと管理することは重要ですが、業務内容や勤務形態に合わせて、分割して休ませることも検討しましょう。
極端に短い休憩はNG
休憩時間を分割して与えることは可能ですが、極端に短い休憩は認められない可能性もあります。たとえば、5分休憩を12回付与すると1時間になりますが、5分の休憩では昼食を食べたりリフレッシュしたりすることは難しいでしょう。
基本的に休憩時間中は、従業員の自由を確保しなければなりません。5分という短い休憩では自由に行動できないため、労働基準法違反と見なされる可能性もあります。昼食時の休憩は30分以上まとめて与えるなど、しっかりと休めるように配慮することが重要です。
休憩時間の分割については就業規則に記載しておく
休憩時間の分割や付与するタイミングについては、就業規則に記載しておく必要があります。休憩時間に関する内容は、就業規則における絶対的必要記載事項に該当するからです。(※2)
どのタイミングでどの程度の休憩を取れるのかは、従業員にとって大切な労働条件です。従業員へ周知せずに勝手に分割すると、違法と見なされる可能性もあるため、忘れずに記載しておきましょう。
(※2)厚生労働省「就業規則を作成しよう」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf p1
休憩時間の分割については労働条件通知書に記載しておく
休憩時間の分割については、労働条件通知書にも記載しなければなりません。労働条件通知書とは、契約期間や賃金などの条件を記載した書類のことです。労働条件通知書には、必ず記載すべき絶対的明示事項が定められており、休憩時間もそこに含まれます。就業規則と同様に、忘れずに記載しておくことが重要です。
残業時に15分休憩を追加する必要があるケース
残業が発生した場合、15分休憩を追加すべきケースもあります。たとえば、8時間勤務の従業員について、すでに45分の休憩を与えているケースを考えてみましょう。
8時間勤務であれば、労働基準法に従って45分の休憩を付与すれば問題ありません。しかし、1時間の残業が発生すると合計9時間勤務となるため、1時間の休憩が必要です。この場合、不足している15分の休憩を追加で与えなければなりません。すでに1時間の休憩を付与している場合は、追加で与えることは不要です。
労働基準法による休憩時間のルールに違反した場合の罰則

労働基準法による休憩時間の付与ルールに違反した場合は、同法119条により、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。労働時間に対して休憩時間が不足していると罰則の対象となるため、勤怠管理を徹底するように気をつけましょう。
また、罰則の対象となるのは、休憩時間が不足しているときだけではありません。全従業員に一斉に付与する、休憩時間を自由に利用させるなどのルールに違反した場合も罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
とはいえ、すぐに罰則が科せられるわけではありません。軽微な違反については労働基準監督署による是正勧告が行われ、改善が見られない場合に罰則が科せられるのが一般的です。罰則を受けると企業のイメージが悪くなったり、採用活動がうまく進まなくなったりするため、適切に休憩を付与するようにしましょう。
労働基準法に従って休憩時間を付与するときの注意点
休憩時間を付与するときの注意点は、以下のとおりです。
- 一斉に付与する
- 労働時間の途中に付与する
- 休憩中は仕事をさせない
- アルバイトにも同じ基準で付与する
- 従業員から休憩は不要だと言われた場合でも付与する
- 実際の労働時間に応じて付与する
それぞれの注意点について順番に見ていきましょう。
1.一斉に付与する

休憩時間は、基本的に全従業員に対して一斉に付与しなければなりません。すべての従業員に対して、公平かつ確実に休憩を取ってもらうためです。従業員や部署ごとに休憩時間を変更することは、基本的に認められないため注意しなければなりません。12〜13時など、昼食の時間に合わせて休憩時間を設定することが多いでしょう。
ただし、労使協定を締結している場合は、従業員や部署ごとに休憩時間を与えることも可能です。接客やシフトなどの都合で、休憩を一斉に付与することが難しい場合は、事前に労使協定を締結しておきましょう。また、特定の業種については一斉付与が免除されています。詳しくは後述しますので、参考にしてください。
2.労働時間の途中に付与する
休憩時間は、労働時間の途中に付与しなければなりません。休憩時間は、従業員が仕事の途中でリフレッシュするための時間だからです。出勤した直後や退勤する直前に付与することは認められないため注意しましょう。
また、残業が発生し、追加の休憩が必要となった場合は、早いタイミングで付与することが大切です。たとえば、8時間勤務で45分の休憩を付与していた場合、残業が発生すると15分の休憩を追加しなければなりません。この15分の休憩も労働時間の途中で付与する必要があります。付与するタイミングが遅くなると退勤直前に休憩することになったり、拘束時間が長くなったりするため、早めに休ませるようにしましょう。
3.休憩中に仕事をさせるのはNG
休憩時間中は、従業員の自由を確保しなければなりません。自分の席にいるように指示したり、仕事を依頼したりすると、休憩時間の付与ルールに違反することになるため注意しましょう。
たとえば、休憩時間中に電話対応をさせることや、来客に備えて自席で待機させることなどは違法です。手待ち時間として労働時間と見なされるため、休憩時間としてはカウントできません。手待ち時間となった場合は、別途、休憩を与える必要があります。
会社側が休憩時間として設定していたとしても、実質的に休めていない場合は、違法と見なされる可能性が高いでしょう。従業員がしっかりとリフレッシュできるよう、労働から解放される時間を確保することが重要です。
4.アルバイトにも同じ基準で付与する

労働基準法による休憩時間の付与ルールは、雇用形態に関係なく適用されます。正社員はもちろん、パートやアルバイトにも、法律のルールに従って休憩を付与する必要があります。もちろん、労働時間が6時間以内の場合は、休憩時間を付与する必要はありません。
5.従業員から休憩は不要だと言われた場合でも付与する
従業員から「休憩は不要だから早く帰りたい」といった申し出があった場合でも、労働基準法に従って休憩を付与しなければなりません。従業員へ適切な休憩を与えることは企業の義務です。仮に双方の合意があったとしても法律違反と見なされる可能性が高いため、正しく付与しましょう。
残業時に追加の休憩が発生する場合は、とくに注意が必要です。「追加の15分休憩は不要だから早く帰りたい」と言われる可能性もあるでしょう。確かに早く退社できたほうが従業員にとってメリットがあるように感じられますが、違法と見なされる可能性が高いため、ルールに従って休憩を付与することが重要です。
6.実際の労働時間に応じて付与する
休憩時間は、所定労働時間ではなく、実際の労働時間に応じて付与する必要があります。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載された、始業から終業までの時間のことです。
仮に所定労働時間が5時間であったとしても、実際の労働時間が7時間になった場合は45分、9時間になった場合は1時間の休憩を付与しなければなりません。知らないうちに法律に違反してしまうケースもあるため、従業員ごとの労働時間はしっかりと管理しておきましょう。
休憩時間に関する特例
休憩時間については、いくつかの特例が設けられています。一斉付与をしなくてもよいケースや休憩時間の自由を確保しなくてよいケースもあるため、しっかりと把握しておきましょう。
1.一斉付与をする必要がないケース
休憩時間は、基本的に全従業員に対して一斉に付与しなければなりませんが、以下のような事業では、一斉付与する必要はありません。
- 運輸交通業
- 通信業
- 商業
- 金融保険業
- 保健衛生業
- 旅館・飲食業
- 官公署の事業
たとえば、店舗や旅館などでは常に誰かが接客する必要があるため、一斉に休むことは難しいでしょう。一斉に休憩を取ることで業務上の問題が発生する業種については特例が設けられており、シフト制などで順番に休ませることが可能です。
2.休憩を与えなくてもよいケース
労働基準法施行規則の第32条によると、以下のような従業員に対しては休憩を与える必要はありません。(※3)
- 電車や自動車などの乗務員で、長距離にわたり継続して乗務するもの
- 屋内勤務者30人未満の郵便局で、郵便業務を担当するもの
(※3)e-GOV法令検索「労働基準法施行規則」第三十二条
3.休憩時間の自由を確保しなくてよいケース

基本的には休憩時間中の自由を確保する必要がありますが、以下のような従業員は例外です。
- 警察官
- 消防吏員
- 常勤の消防団員
- 乳児院・児童養護施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもの
- 居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち家庭的保育者として保育を行うもの
上記のような職種は、休憩時間であっても事件や事故、緊急事態などに対応する必要があるため、自由利用の原則の例外とされています。
4.労使協定を締結しているケース
先ほど紹介した運輸交通業や通信業以外の業種であっても、労使協定を締結している場合は、一斉付与の原則に従う必要はありません。たとえば、担当部署やシフトによって休憩時間のタイミングを変える、といった労使間の合意がある場合は、労使協定の内容が優先されます。
ただし、全従業員が平等に休憩時間を確保できるように配慮することは必要です。また、休憩時間が短すぎたり、細かく分割しすぎたりすると、不適切な労使協定と見なされるケースもあるため注意しましょう。
5.従業員が管理監督者に該当するケース
従業員が管理監督者に該当する場合、休憩時間のルールは適用されません。管理監督者とは、相応の地位や権限が与えられており、経営者と一体的な立場で業務にあたる従業員のことです。過重労働に注意することは必要ですが、管理監督者については本人の判断で、ある程度自由に休憩を取ってもらうことができます。
ただし、部長や課長などの肩書きがあるからといって、管理監督者に該当するとは限りません。法律上の管理監督者に該当するかどうかは、権限や職務内容などから判断されます。いわゆる「名ばかり管理職」と見なされる場合は、一般的なルールに従って休憩を付与しなければなりません。
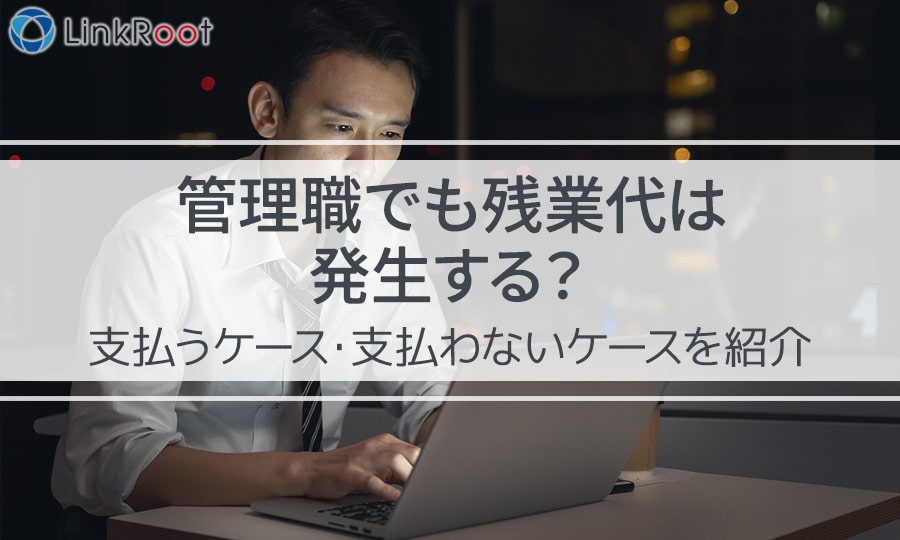
労働基準法による休憩時間の付与ルールを理解しておこう!
今回は、労働基準法による休憩時間の付与ルールや特例について解説しました。休憩時間は、15分単位など、分割して付与することも可能です。ただし、あまりに短い時間では、従業員がしっかりと休むことができません。
休憩時間は、集中力や仕事の生産性を高めるために重要な存在であるため、適切に付与することが重要です。また、一斉付与の原則や自由利用の原則などにも違反しないように注意しましょう。