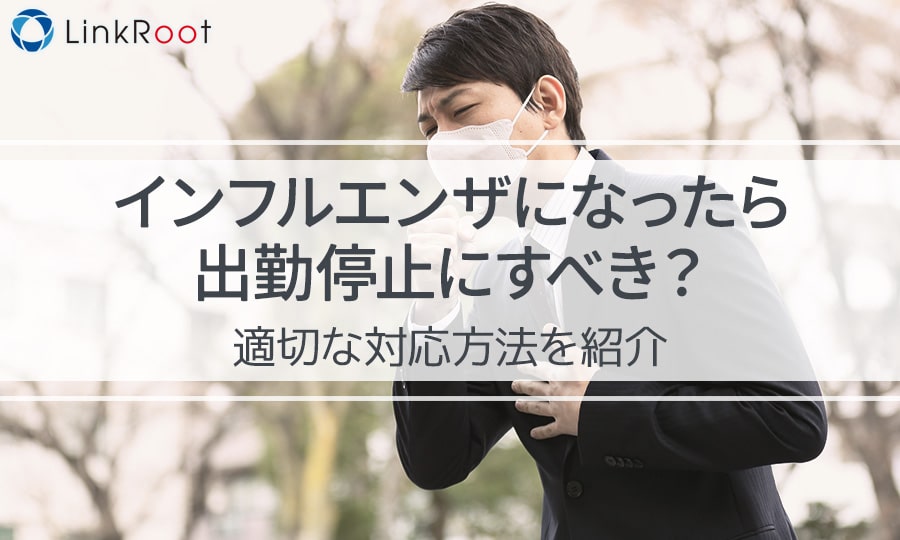従業員がインフルエンザになったとき、出勤停止にすべきか悩むケースも多いでしょう。労働関連の法律では、インフルエンザでの出勤停止に関してとくに規定されていないため、基本的には企業ごとのルールに従って対応することになります。
ただし、安全配慮義務に従うことや状況に応じて休業手当を支払うことは必要です。安全配慮義務や休業手当は、法律によって定められたものであるため、正しく対応しなければなりません。
この記事では、従業員がインフルエンザになったときの適切な対応方法を紹介しますので、チェックしておきましょう。
従業員がインフルエンザになったら出勤停止にすべき?

従業員がインフルエンザになったときに出勤停止にするかどうかは、企業の判断に委ねられます。季節性インフルエンザについては法律上の特別なルールはないため、仮に出勤させたとしても、それだけで法律違反とはなりません。ただし、インフルエンザの従業員を出勤させることにはリスクもあるため注意しましょう。
インフルエンザの従業員を出勤させるリスク
インフルエンザの従業員を出勤させることには、次のような問題やリスクがあります。
- 体調が悪化して回復が遅れる
- 仕事に集中できず生産性が低下する
- 他の従業員へ感染が広がる
体調の悪い従業員を無理に出勤させても効率は上がらないため、避けるべきでしょう。また、インフルエンザの感染が会社全体に広がると、業務が大幅に遅れてしまう可能性もあります。会議などに出席することで、取引先やクライアントに迷惑がかかるケースもあるでしょう。必要に応じて出勤停止や在宅勤務を命じるなど、慎重に対応することが重要です。
インフルエンザによる出勤停止を定めた労働関連の法律はない
労働基準法など、労働関連の法律ではインフルエンザによる出勤停止は定められていません。基本的に働くことは従業員の権利であり、働けなくなると収入が減ってしまうため、特別な事情がない限りは働くことを制限できないのです。ただし、以下のように出勤停止が定められているケースもあります。
学校保健安全法施行規則では出勤停止が定められている
学校保健安全法施行規則の第19条では、インフルエンザになった場合の出勤停止期間が定められています。学校の場合はこの法律に従う必要があり、インフルエンザの発症後5日経過するまで、かつ解熱してから2日経過するまでは、出勤することはできません。(※1)
この基準は学校に関するものですが、企業によっては出勤停止期間について学校と同様の基準を採用しているケースもあるでしょう。
(※1)e-GOV法令検索「学校保健安全法施行規則」第十九条(出席停止の期間の基準)
新型インフルエンザについては法律の規制がある
季節性のインフルエンザに関する法律上の規制はありませんが、新型インフルエンザについては「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第18条による規制があります。(※2)
新型インフルエンザは感染力が高いため、感染拡大を防止するために別の基準が設けられているのです。従業員が新型インフルエンザにかかった場合は、法律に従って一定期間休ませるようにしましょう。
(※2)e-GOV法令検索「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第十八条(就業制限)
https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114/20230607_505AC0000000047#Mp-Ch_4-At_18
安全配慮義務に従う必要はある
季節性インフルエンザに関する法律上の規制はないものの、安全配慮義務に従う必要はあります。安全配慮義務とは、従業員の健康や安全を守るために、職場環境を整備する義務のことです。安全配慮義務は労働契約法によって定められているため、インフルエンザに対しても適切な対応を取ることが求められます。(※3)
体調の悪い従業員に出勤を強要すると、法律違反と見なされる可能性もあるため注意が必要です。最悪の場合、6ヶ月以下の懲役や50万円以下の罰金が科せられることもあります。
(※3)e-GOV法令検索「労働契約法」第五条(労働者の安全への配慮)
インフルエンザで出勤できないときの対応方法
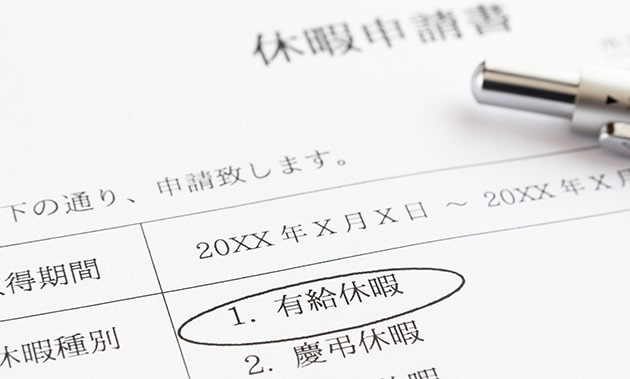
インフルエンザになった従業員を休ませる場合、以下のような方法が考えられます。
- 出勤停止を命じる
- 有給休暇を取得させる
- 通常の欠勤扱いとする
- 会社独自の休暇制度を使う
どのような対応をすべきかは、状況によって異なります。以下、それぞれの対応方法について詳しく見ていきましょう。
1.出勤停止を命じる場合
会社側から出勤停止命令を出す場合は、就業規則の内容に従うのが基本です。就業規則に記載された手続き方法や出勤停止期間について確認したうえで、従業員へ正しく指示を出しましょう。
なお、会社側から出勤停止を命じると、休業手当の支払いが必要となるケースもあるため注意しなければなりません。休業手当の必要性については、後ほど詳しく解説します。
2.有給休暇を取得させる場合
従業員側から有給休暇の申請があった場合は、希望どおりに処理しましょう。有給休暇を取得することは従業員の権利であり、基本的には希望するタイミングで取得させなければなりません。当然、インフルエンザを理由として有給休暇を取得することも可能です。
有給休暇として処理する場合は、賃金を支払う必要があります。また、従業員に対して有給休暇の取得を強要したり、申請がないのに勝手に有給休暇として処理したりすることは法律違反となるため避けましょう。有給休暇の申請を出すかどうかは、従業員本人が決めなければなりません。
3.欠勤扱いとする場合
従業員が有給休暇の申請を出さずに休んだ場合は、通常の欠勤扱いとなります。有給休暇が残っていない場合も同様です。通常の欠勤として扱う場合は、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、賃金を支払う必要はありません。
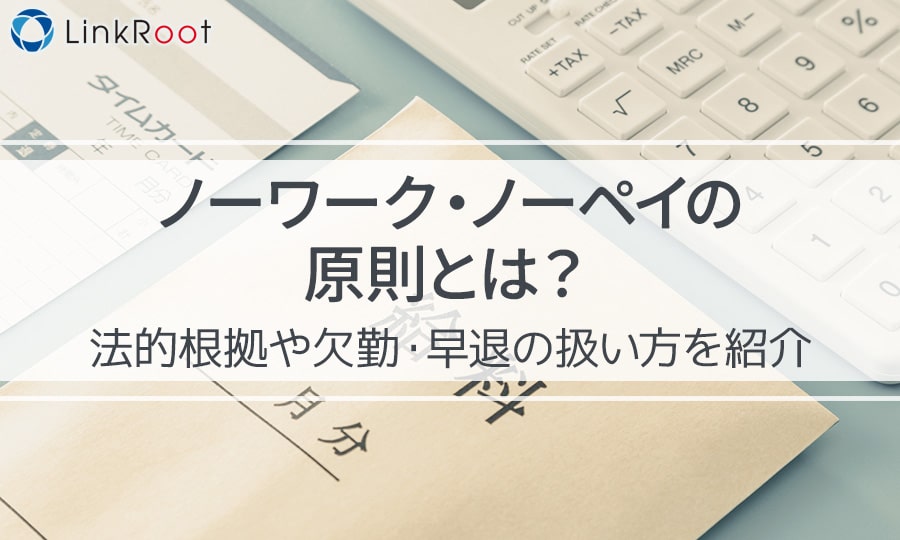
4.会社独自の休暇制度を使う場合
傷病休暇など、独自の休暇制度を導入している企業もあるかもしれません。就業規則を確認し、インフルエンザの際に適用できる場合は、適切に処理しましょう。休暇制度の存在や申請方法などについて、事前に従業員へ周知しておくことも大切です。
インフルエンザを理由に出勤停止を命じると休業手当は必要?
インフルエンザを理由に出勤停止を命じた場合、労働基準法に従って休業手当の支払いが必要なケースもあります。以下、休業手当が必要なケース・不要なケースについて解説しますので、チェックしておきましょう。
休業手当が必要なケース
企業の判断で出勤停止を命じた場合は、労働基準法の第26条に記載されている「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するため、休業手当を支払わなければなりません。(※4)
前述のとおり、季節性インフルエンザについては出勤停止にするための法的な根拠がないため、企業の判断で休ませたことになり、休業手当の支払いが必要です。休業手当の金額は、平均賃金の60%以上と決められているため注意しましょう。
(※4)e-GOV法令検索「労働基準法」第二十六条(休業手当)
休業手当が不要なケース
新型インフルエンザの場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、一定期間の出勤停止が義務付けられています。つまり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当を支払う必要はありません。
また、従業員側から欠勤の連絡があった場合や、有給休暇を取得する場合も休業手当は不要です。
インフルエンザによる出勤停止にうまく対応するためのポイント

インフルエンザによる出勤停止に適切に対応するためには、就業規則を整備したり、社内ルールについて従業員へ周知したりすることが大切です。また、ワクチン接種を推奨するなど、予防に努めることで感染の拡大を防止できます。ここでは、インフルエンザにうまく対応するためのポイントを解説します。
1.出勤停止に関して就業規則に記載しておく
インフルエンザを理由に出勤停止にするかどうかは、基本的に企業の判断に委ねられるため、就業規則を整備しておくことが重要です。社内ルールを明確にしておかないと、従業員がインフルエンザになったときにどのように対応すべきか、判断に迷ってしまいます。就業規則には、対応の手順や出勤停止にする期間などを明記しておきましょう。
ただし、治癒証明書などを提出させることについては、慎重に判断しなければなりません。従業員に対して治癒証明書や陰性証明書を提出させる企業もありますが、厚生労働省は各種の証明書を提出させることは望ましくないとの見解を出しています。(※5)インフルエンザの陰性を証明することは難しく、医療機関に大きな負担をかけてしまう可能性があるからです。
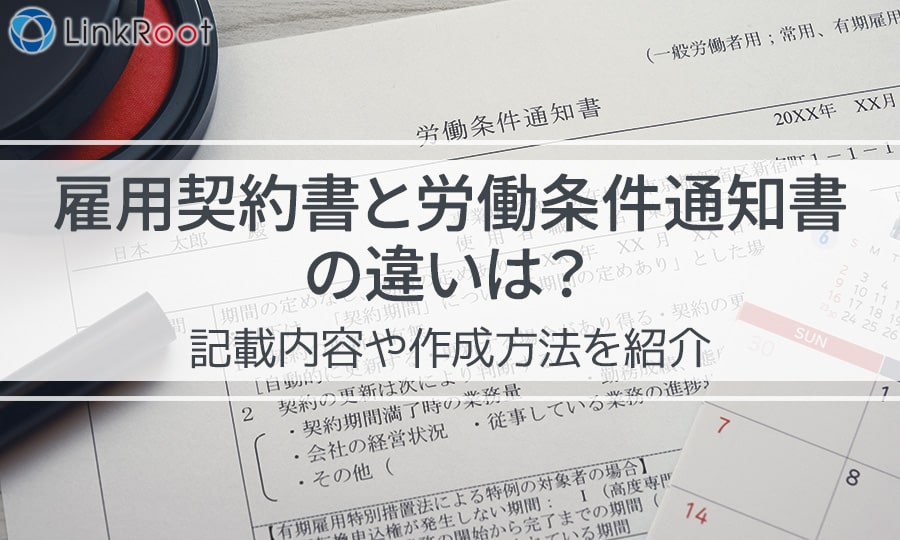
(※5)厚生労働省「インフルエンザQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
2.適切に有給休暇を取得させる
従業員がインフルエンザになったときは、適切に有給休暇を取得させることが大切です。インフルエンザに感染した場合に限らず、基本的には従業員が希望するタイミングで有給休暇を取得させなければなりません。
また、有給休暇の取得を促すことは可能ですが、強要することは避けましょう。有給休暇を使うかどうかは、あくまでも従業員本人に判断してもらう必要があります。
3.休むべきことを従業員へ周知しておく
仕事がたまっている、休みにくいなどの理由で、無理にでも出勤しようと考える従業員もいるかもしれません。しかし、インフルエンザになったときに出勤すると、他の従業員へ感染が広がったり、取引先へ迷惑がかかったりするため、基本的には休んでもらうべきです。
インフルエンザにかかったまま出勤するリスクを伝え、感染が疑われる場合は自主的に休む意識をもってもらうようにしましょう。とくにインフルエンザにかかりやすい冬場には、朝礼で周知したり、掲示板で注意喚起したりすることが重要です。また、従業員が休みやすい雰囲気をつくるためには、上司が積極的に休みを取るとよいでしょう。
4.ワクチン接種を推奨する
インフルエンザへの感染を予防することも大切です。インフルエンザワクチンを接種しておけば、ウイルスに感染した場合に発症する可能性を減らしたり、発症したときの重症化を防いだりする効果を期待できます。
帰宅した際に手洗い・うがいを徹底すること、十分な休養を取ること、バランスのよい食事を心がけることなど、日常生活における対策も効果的です。従業員へインフルエンザワクチンの接種や日常生活における感染予防対策を促し、感染拡大を防ぎましょう。会社に加湿器を置き、適度な湿度を保つことも感染予防につながります。
5.バックアップ体制を整える
従業員が安心して休めるようなバックアップ体制を整えておくことも重要です。自分が休むと仕事がストップしてしまう、同僚に迷惑がかかってしまうという気持ちから、休むことを躊躇する従業員もいるでしょう。
特定の従業員に仕事の負担が集中していると、とくに休みにくい雰囲気になってしまいます。業務の再配分を検討する、人員を補充する、休んだ場合の代わりの担当者を決めておくなど、バックアップ体制を整え、休みやすい環境を構築しましょう。
インフルエンザによる出勤停止に関する注意点

従業員がインフルエンザになったときは、無理やり働かせないようにしましょう。また、状況に応じて在宅勤務を検討することも大切です。ここでは、インフルエンザによる出勤停止に関する注意点を紹介します。
1.無理やり働かせないようにする
前述のとおり、インフルエンザの従業員を出勤させることには、さまざまなリスクがあります。とくに、従業員本人が休みを希望しているのに出勤を強制することは避けましょう。悪質な場合、パワーハラスメントと見なされる可能性もあるため注意が必要です。
また、インフルエンザで欠勤したことを理由として、不当に人事評価を下げたり、降格や減給の処分を与えたりすることも避けましょう。
2.在宅勤務を検討する
従業員側からどうしても働きたいとの申し出があった場合は、在宅勤務を検討しましょう。在宅勤務であれば、感染拡大のリスクを抑えつつ、業務を進めてもらえます。ただし無理はさせず、体調を優先してもらうよう指示しておくことが大切です。
インフルエンザによる出勤停止は慎重に判断しよう!
今回は、インフルエンザを理由とした出勤停止命令の可否や、出勤停止にするときの注意点について解説しました。季節性インフルエンザの場合は、出勤停止にする法律上の義務はありません。基本的には会社の判断に委ねられているため、就業規則に従って適切に対応しましょう。
インフルエンザを理由に出勤停止を命じる場合は、状況に応じて休業手当を支払わなければなりません。休業手当の支払いは労働基準法によって定められた義務であるため、忘れないようにしましょう。