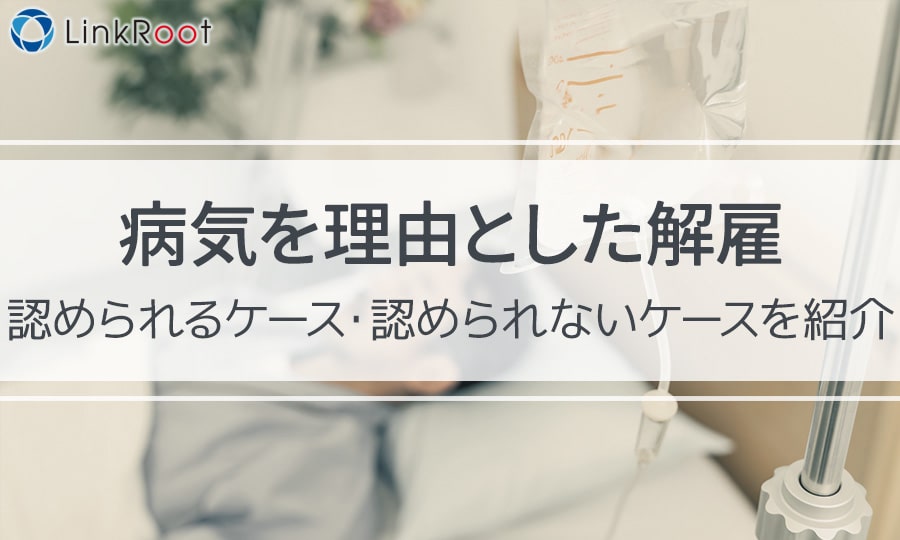従業員を解雇することは法律によって厳しく制限されているため、仮に病気で働けない状態であっても簡単に実施することはできません。不当解雇と判断されると罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。
この記事では、病気を理由とした解雇が認められるケース・認められないケースを紹介します。解雇するときの注意点や解雇された従業員が利用できる保険についても解説しますので、ぜひチェックしておきましょう。
病気を理由とした解雇は認められる?

従業員が病気になり、担当していた仕事を継続できなくなったり、長期的に入院する必要が出てきたりした場合、解雇を検討することもあるでしょう。しかし、病気で働けない状態だからといって、すぐに解雇できるわけではありません。
解雇を実施するためには合理的な理由が必要であり、病気を理由とした解雇が正当と認められるかどうかは状況によって異なります。解雇の正当性は、以下のような事柄を考慮して総合的に判断されます。
- 業務に起因する病気かどうか
- 継続して働ける状態であるか
- 就業規則に病気を理由とした解雇について記載されているか
- 休職制度を利用できるか
以下、病気を理由とした解雇が認められるケース・認められないケースを紹介しますので、不当解雇とならないよう理解を深めておきましょう。
解雇が認められるケース
まずは、病気を理由とした解雇が認められる具体的な事例を紹介します。
私傷病で休職し、期間満了時に解雇する場合
業務とは関係のない原因で生じた病気のことを私傷病といいます。私傷病の場合は、就業規則の内容を確認しなければなりません。就業規則のなかに休職制度に関する規定がある場合は、ルールに従って従業員を休職させることが必要です。
休職期間満了時の扱いについても確認しておきましょう。休職規定のなかに「休職期間が満了した際、傷病が治癒せず就業が困難な場合は退職(または解雇)とする」といった規定がある場合は、ルールに従って退職させたり解雇したりすることが可能です。
休職制度を設けることは義務ではないため、規定の有無や休職期間、期間満了時の扱いは企業によって異なります。間違った対応をしないよう、社内のルールをしっかりと把握しておきましょう。
解雇事由に照らし合わせて解雇する場合
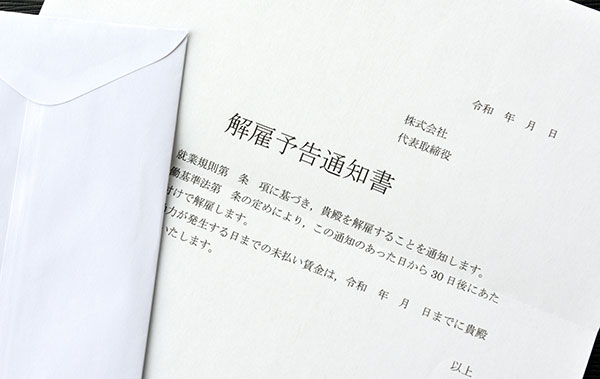
休職制度を設けていない場合は、就業規則のなかの解雇に関する規定を確認しましょう。解雇できる事由として「精神・身体の傷病・障害により業務に耐えられないとき」といった記載がある場合は、私傷病を理由として普通解雇できる可能性があります。
ただし、業務に起因する病気の場合や復職できる場合などは、解雇することはできません。解雇は従業員に対する重い処分であり、仕事を失った従業員は生活できなくなる可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。また、解雇予告も忘れないようにしましょう。
打切補償を支払って解雇する場合
業務が原因で病気になった場合は、療養のための休業期間と、その後の30日間は従業員を解雇することができません。ただし、療養をスタートしてから3年を経過しても病気が治らない場合は、打切補償を支払って解雇することが可能です。労働基準法の第81条により、打切補償の金額は平均賃金の1200日分とされています。(※1)
(※1)e-GOV法令検索「労働基準法」第八十一条(打切補償)
解雇が認められないケース
ここまで病気を理由に解雇できるケースを紹介しましたが、以下のような場合は解雇が認められないため注意しましょう。
休職制度を利用していない場合
休職制度があり、適用条件を満たしているにもかかわらず利用していない場合、基本的に解雇は認められません。就業規則に従って、適切に休職させるようにしましょう。また、休職期間の途中での解雇もできないため注意が必要です。
業務上の理由で病気になった場合
長時間労働や劣悪な環境下での労働など、業務上の理由で病気になった場合、療養のための休業期間はもちろん、その後の30日間は解雇が認められません。
病気であっても働ける場合
病気であっても継続して働ける場合は、正当な解雇事由には該当しないと判断される可能性があります。また、病気で休職していたとしても、医師が復職可能と判断している場合は解雇できません。
業務調整により病気の従業員の負担を減らす、部署移動を検討するなど、解雇を回避する努力も必要です。何の対応もせずに解雇すると、不当解雇と見なされる可能性が高いため注意しましょう。
病気を理由に解雇するときの流れ
病気を理由に従業員を解雇するときは、次のような流れで進めましょう。
- 病気の原因を明確にする
- 休職させる
- 解雇を検討する
以下、それぞれのポイントを解説します。
1.病気の原因を明確にする

従業員が病気になったときは、まず原因を明確にしなければなりません。前述のとおり、私傷病なのか業務に起因する病気なのかによって、取るべき対応が異なるからです。
従業員本人や関係者からヒアリングして、病気になるまでの経緯などを把握しましょう。また、会社側で病名や原因を判断することは難しいため、必要に応じて病院を受診させ、医師が作成する診断書を提出してもらうことも重要です。
2.休職させる
私傷病であり、休職制度を設けている場合は、ルールに従って従業員を休職させる必要があります。就業規則で規定されている休職期間や給与の計算方法を確認し、適切に休ませることが大切です。
また、業務に起因する病気の場合、療養のために休職させるだけではなく、治療のための費用を会社側が負担しなければなりません。どのような原因であっても、休職期間中に解雇することはできないため注意しましょう。
3.解雇を検討する
休職期間が満了しても復職できない場合は、解雇を検討することになります。就業規則を見て、休職期間満了時の扱いについて確認しましょう。復職できない場合に退職や解雇にできる規定があれば、就業規則に従って対応します。
ただし、復職できる状態かどうかは慎重に判断しなければなりません。業務調整をすれば働ける場合や、医師が復職可能と判断しており、本人も復職を希望している場合は、解雇できないため注意しましょう。
また解雇を行う前に、退職勧奨を検討することも大切です。退職勧奨とは、会社側と従業員で話し合いを行い、自主的に退職してもらう方法です。病気により継続して働けないことに納得したうえで退職届を提出してもらえるため、不当解雇のようなトラブルを防止しやすいでしょう。ただし、退職届の提出を強制することはできないため、話し合いに応じてもらえない場合は解雇を検討することになります。
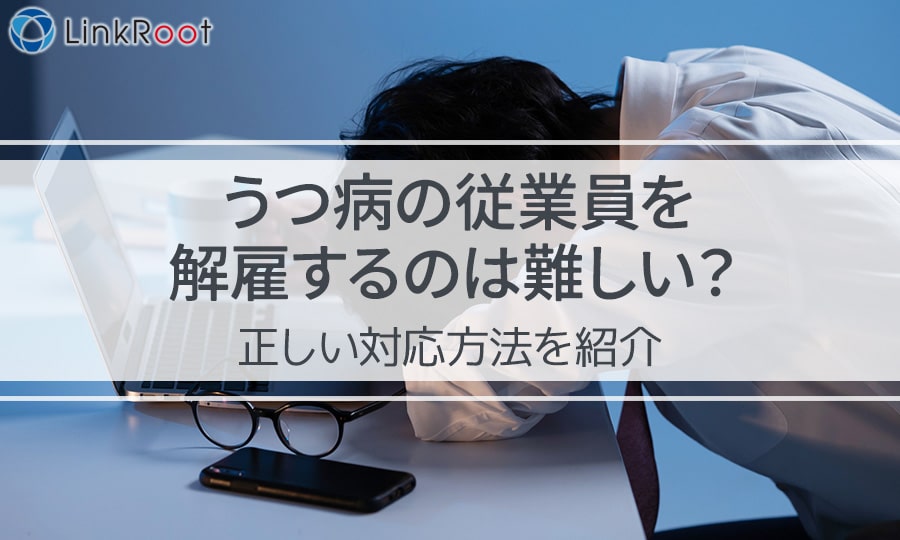
病気の従業員を解雇するときの注意点

病気の従業員を解雇するときは、就業規則の内容や退職金の規定について確認しておきましょう。また、解雇できるかどうかの判断に悩むときは、弁護士に相談することも大切です。
以下、解雇時の注意点を紹介しますので、チェックしておきましょう。
1.就業規則を確認する
病気の従業員を解雇するときは、就業規則の内容を確認しなければなりません。基本的には就業規則に従って休職させたり、解雇事由に該当するかどうかを判断したりする必要があるからです。
就業規則の内容を無視した対応を行うと、従業員とのトラブルが発生し、訴えられたり不当解雇による慰謝料を請求されたりする可能性もあります。また、不当解雇を行うと会社のイメージが低下し、取引先との関係が悪化するケースもあるため注意しましょう。
2.会社都合か自己都合かを慎重に検討する
従業員を解雇するときは、会社都合か自己都合かを慎重に判断しなければなりません。会社都合か自己都合かによって、失業保険の扱いが異なるからです。
会社都合の場合は退職して7日後に給付を受けられますが、自己都合の場合は7日と2ヶ月待たなければなりません。また、自己都合の場合は給付日数も短くなるため、従業員にとっては不利益となります。
会社都合に該当する主なケースは以下のとおりです。
- 病気で働けないことを理由として従業員を解雇する場合
- 退職勧奨により従業員が退職届を提出した場合
一方、以下のようなケースは自己都合に該当します。
- 病気で働けないことを理由として従業員が退職届を提出した場合
- 休職期間満了時に復職できず自然退職となった場合
状況に応じて、会社都合か自己都合かを適切に判断しましょう。
3.退職金に関する規定を確認する
退職金に関する規定にも注意しなければなりません。そもそも退職金制度を導入することは義務ではないため、制度の有無や支給金額などは企業によって異なります。
制度がない場合は退職金を支払う必要はありませんが、制度を導入しているなら、就業規則や退職金規定に従って正しく支給する必要があります。病気を理由とした退職の場合、会社都合か自己都合かによって支給金額が変わるという企業もあるでしょう。会社のルールをしっかりと確認したうえで対応することが重要です。
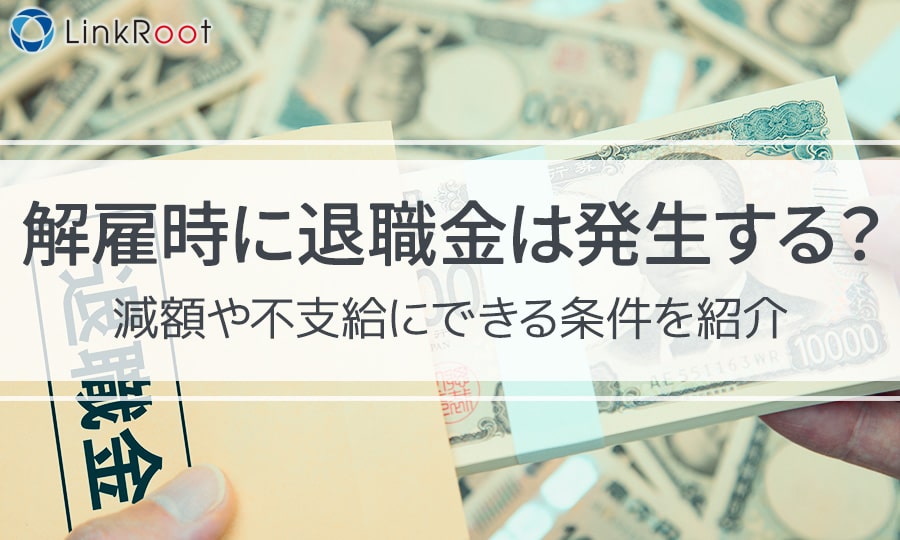
4.必要に応じて弁護士に相談する
病気による解雇が認められるかどうか、判断に迷うときは事前に弁護士に相談するとよいでしょう。労働者を保護するという観点から、解雇については法律で厳しく制限されています。
解雇を行うことで法律に違反すると、罰則が科せられるのはもちろん、解雇した従業員が戻ってくる、未払いの賃金や慰謝料を請求される、会社の信用が低下する、といったリスクがあります。適切な解雇を実施するためにも、専門知識のある弁護士に相談しておくことが大切です。
病気による解雇に対して支給される保険や手当
病気を理由に解雇された従業員は、失業保険や傷病手当などの支給を受けられる可能性があります。やむを得ず解雇するときは、従業員の生活を少しでもサポートできるよう、利用できる制度について伝えてあげるとよいでしょう。
1.失業保険
雇用保険に一定期間加入していれば、失業保険による給付を受けることが可能です。病気を理由とした離職であり、特定理由離職者に該当する場合は、6ヶ月以上の被保険者期間があれば給付を受けられます。
ただし、働きたいという意志や働くための能力を有していることが条件となるため、病気によりまったく働けない状態である場合は給付を受けられません。逆に仕事内容を変更すれば働けるといった場合は、給付を受けられます。
2.傷病手当

健康保険に一定期間加入していれば、傷病手当を受給できます。傷病手当とは、病気や怪我で働けなくなったときに支給される手当です。在職期間中はもちろん、以下の条件を満たしていれば退職後も支給を受けられます。
- 退職日に就労不能である
- 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入している
- 退職日前日までに連続した3日以上の就労不能期間がある
ただし、傷病手当は支給開始日から1年6ヶ月しか受給できません。期間の限りがあることには注意しましょう。(※2)
(※2)全国委健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
3.労災保険
業務に起因する病気の場合、労災保険による給付を受けられます。以下の条件を満たしていれば、休業補償給付を受けることが可能です。
- 業務に起因する病気や怪我で療養している
- 療養のために就労不能な状態である
- 賃金の支払いを受けていない
療養中の従業員が自ら退職を選んだ場合でも、条件を満たしていれば継続して休業補償給付を受けられます。
4.生活保護
病気による解雇や退職で仕事を失い、生活に困っている場合は、生活保護を受けられます。生活保護とは、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度のことです。
保険への加入期間などは必要なく、誰でも利用できるため、生活に困っている場合は申請するとよいでしょう。ただし、保護基準を超える収入があるときは、生活保護を受けられません。
病気を理由とした解雇は慎重に進めよう!
今回は、病気を理由とした解雇が認められるケース・認められないケースや、解雇時の注意点を紹介しました。従業員が病気で働けなくなったからといって、簡単に解雇することはできません。業務上の理由で病気になった場合や、休職制度があるにもかかわらず制度を利用していない場合などは解雇できないため注意しましょう。
また、解雇を行うときは、病気の理由を明確にする、就業規則の内容を確認する、退職勧奨を検討するなど、適切な手順で進めることが大切です。不当解雇と見なされると、裁判に発展したり慰謝料を請求されたりするため慎重に進めましょう。