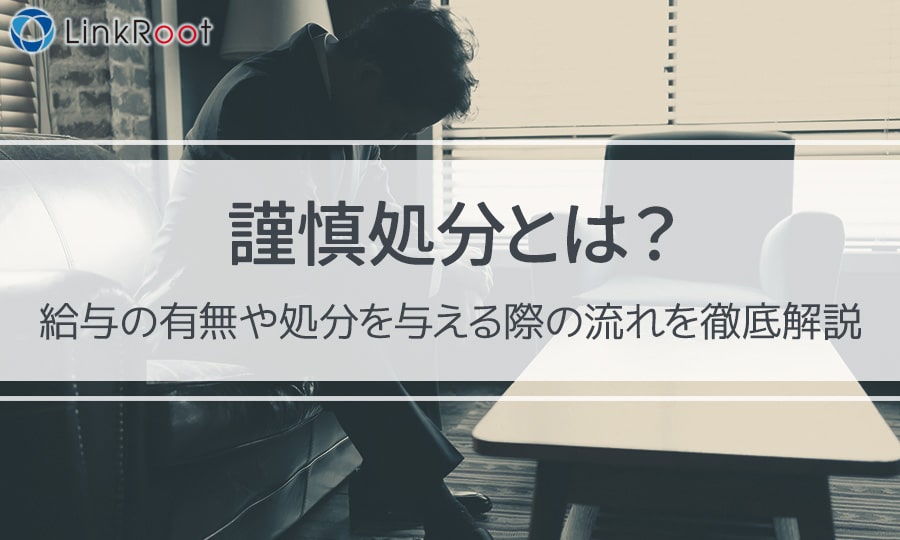謹慎処分は、従業員が違反行為に関わった場合や、感染症に罹患した場合などに与える処分です。謹慎処分を受けた従業員は、自宅で待機するなど、一定期間働けない状態となります。会社側は状況に応じて謹慎処分を与えることは可能ですが、従業員の生活に大きな影響を与える処分であるため、慎重に実施することが重要です。
この記事では、謹慎処分の意味や実施するときの流れについて解説します。法律に違反しないよう、しっかりと理解しておきましょう。
謹慎処分とは?

謹慎処分とは、労働契約を解消することなく一定期間働くことを禁止し、自宅で待機させる処分のことです。自宅謹慎や自宅待機などと呼ばれることもあります。謹慎処分は、従業員が何らかの問題行動を起こしたり、感染症に罹患したりした場合に与えることが多いでしょう。謹慎処分には、以下の2種類が存在します。
1.懲戒処分としての謹慎処分
懲戒処分としての謹慎処分は、「出勤停止」という名称で就業規則のなかに規定されていることが多いでしょう。懲戒処分とは、会社のルールに違反した従業員に対して与える制裁的な処分のことです。戒告・減給・降格・懲戒解雇など、さまざまな種類があります。
出勤停止も懲戒処分のひとつであり、その期間中は一般的に無給となるため、戒告や減給よりも重い処分として位置付けられます。従業員の生活に大きな影響を与える処分であるため、会社に大きな損害を与えた場合や重大な違反行為に関わった場合などに実施するのが一般的です。
懲戒処分としての出勤停止を実施するためには、該当する事由や出勤停止期間などについて就業規則に規定しておく必要があります。また、合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければ、処分が無効となるため注意しましょう。
2.業務命令としての謹慎処分
懲戒処分ではなく、業務命令として謹慎処分を与えるケースもあります。業務命令としての謹慎処分は、懲戒処分を与えるかどうか検討している場合や、業務上の理由で自宅待機させることが必要となった場合などに実施されます。
業務命令であるため、懲戒処分のような制裁的な意味合いはありません。また、就業規則に記載しておく必要はなく、状況に応じて命令を発することが可能です。
ただし、業務上の理由がない場合や、不当な目的によって発せられた場合は、企業側の権利濫用として謹慎処分が無効になるケースもあります。業務命令の有効性については、目的や動機、従業員への影響の度合いなどを含めて総合的に判断されます。
謹慎処分を与えるべきケース
正当な理由のない遅刻や欠勤が多い場合、業務命令に違反して会社に大きな損害を与えた場合などは謹慎処分を検討すべきでしょう。
以下、謹慎処分を与えるべきケースについて詳しく解説します。
1.正当な理由のない欠勤が多い場合

正当な理由のない遅刻や欠勤が多い場合は、懲戒処分としての謹慎処分を検討することになります。無断欠勤や遅刻が頻発すると、仕事が進まなくなったりほかの従業員の負担が増えたりするでしょう。規律の乱れにもつながるため、厳しく対応しなければなりません。
ただし、数回の遅刻や欠勤で謹慎処分を与えることは難しいでしょう。懲戒処分としての謹慎処分は、従業員へ与える影響が大きいため、簡単には認められません。まずは注意や指導を行い、状況が改善されない場合に謹慎処分を検討しましょう。
2.会社に大きな損害を与えた場合
会社に大きな損害を与えた場合は、謹慎処分の対象となります。クライアントに迷惑をかけて契約を破棄されたり、犯罪行為に関わって会社の信用を失墜させたりした場合は、懲戒処分としての謹慎処分を検討しましょう。行為の悪質性や損害の程度によっては、より重い懲戒処分を検討する必要もあります。
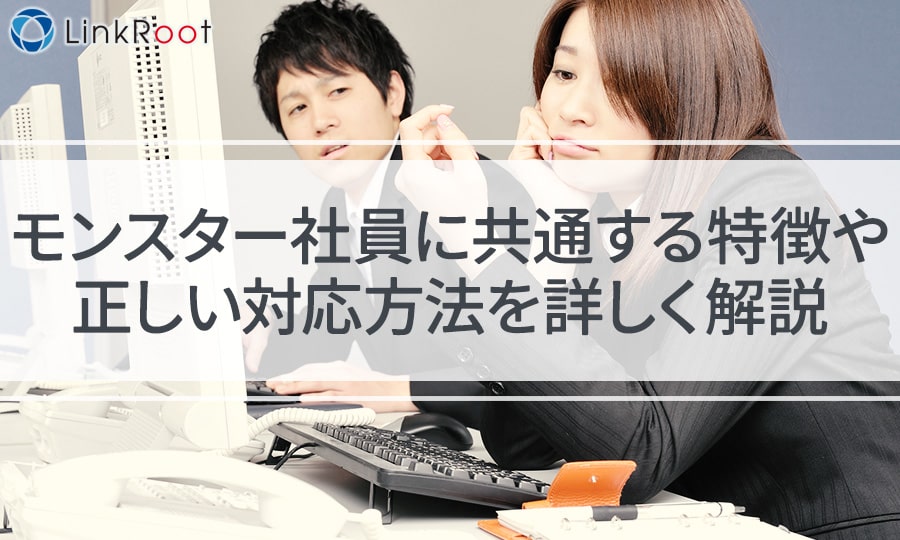
3.ハラスメント行為に関わった場合
パワハラやセクハラなどのハラスメント行為に関わった従業員も謹慎処分の対象です。ハラスメント行為を放置しておくと、行動がエスカレートしたり、ほかの従業員がストレスを感じたりしてしまいます。従業員が働きやすい環境を守るためにも何らかの対応をしなければなりません。
まずは事実関係を確認し、注意や指導などの軽い処分から与えていきましょう。ハラスメント行為がなくならない場合は、減給や出勤停止などの懲戒処分を検討します。
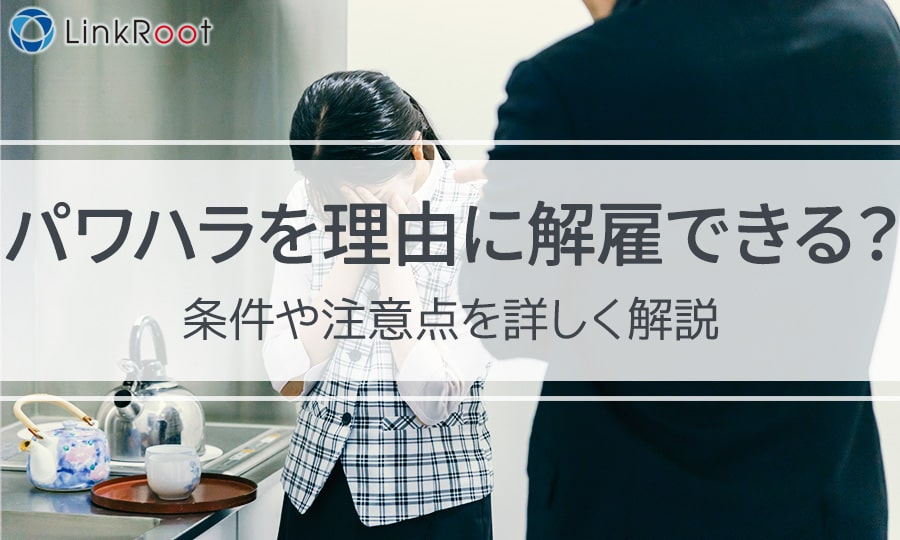
4.業務命令や就業規則に違反した場合
業務命令や就業規則に違反した場合も謹慎処分の対象となるでしょう。上司の指示に従わず大きな損害が発生したときや、就業規則に繰り返し違反したときなどは謹慎処分を検討します。
ただし、軽微な違反に対して謹慎処分を与えることは難しいでしょう。違反の内容や回数、悪質性などを考慮して、謹慎処分が妥当かどうかを検討することが大切です。
5.不正行為に関する調査をする場合

不正行為に関する調査を実施する場合、該当する従業員を謹慎処分とするケースがあります。不正行為に関わった従業員が出勤することで、調査に支障が出る可能性もあるからです。
事実関係を調査したうえで懲戒処分を与えるかどうかを判断したい場合などは、業務命令としての謹慎処分を与えましょう。ただし、基本的には賃金の支払いは必要です。
6.感染症に罹患した場合
感染症に罹患した従業員を出勤させると、会社中に感染が拡大したり、体調が悪化して回復が遅れたりします。取引先にまで迷惑がかかるケースもあるでしょう。
感染症に罹患した従業員に対しては、業務命令による謹慎処分を与えるのが一般的です。体調の悪い従業員を無理に出勤させると、安全配慮義務違反と見なされ、6ヶ月以下の懲役や50万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。(※1)
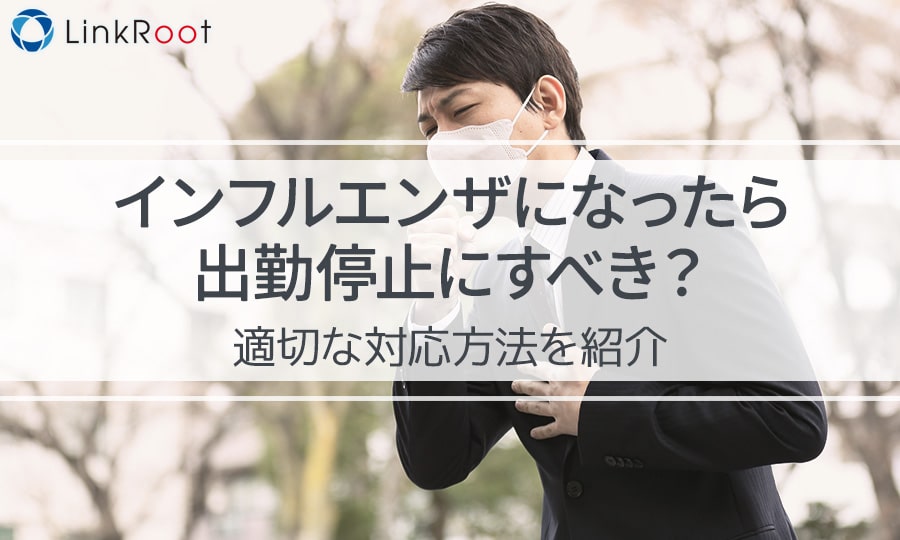
(※1)e-GOV法令検索「労働契約法」
謹慎処分中は給与を支払うべき?
謹慎処分中に給与が発生するかどうかは、懲戒処分か業務命令かによって異なります。以下、給与を支払うべきか否かの基準を解説しますので、チェックしておきましょう。
1.懲戒処分による謹慎処分の場合
懲戒処分による謹慎処分の場合、基本的に給与を支払う必要はありません。謹慎処分の期間中、従業員は働いていないため、ノーワーク・ノーペイの原則により、労働の対価である給与は発生しないのです。
企業側に責任がある場合は給与を支払う必要がありますが、懲戒処分は問題を起こした従業員に対する罰則的な意味合いが強いため、謹慎により働けないのは従業員の責任であると捉えられます。
2.業務命令による謹慎処分の場合

業務命令による謹慎処分の場合は、原則として給与を支払う必要があります。従業員の責任ではなく、会社の都合や指示によって働けない状況になっているからです。
とはいえ給与を支給すべきか否かは、従業員の責任の度合いや就業規則の内容などによっても異なります。たとえば、トラブルに関する調査を行うために関係者を謹慎処分とする場合、会社の都合で働けない状況となっているため、給与の支払いは必要です。
ただし、トラブルの調査期間中は無給の謹慎とする、平均賃金の8割のみを支給する、といった規定を就業規則のなかに設けている場合は、給与の不支給や減額が認められるケースもあります。給与の支払いが必要かどうかは会社のルールによって異なるため、謹慎処分を与える前に確認しておきましょう。
謹慎処分を与えるときのポイント
従業員に対して謹慎処分を与えるときは、次のようなポイントに注意しましょう。
- 期間に関する法律上のルールはない
- 従業員の生活への影響を考慮する
- 有給休暇の申請に応じる必要はない
- 外出禁止などのルールを設けることは難しい
以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
1.期間に関する法律上のルールはない
謹慎処分の期間に関する法律上のルールはありません。ただし、上限がないからといって無制限に謹慎させられるわけではなく、違反行為の悪質性や従業員の責任を考慮して、適切な期間を設定する必要があります。違反行為に対して謹慎期間が長すぎる場合など、社会通念上相当ではないと判断されると、謹慎処分が無効となるケースもあるため注意しましょう。
懲戒処分としての謹慎処分の場合は、1週間〜1ヶ月程度が目安です。1ヶ月以上の謹慎処分を与えるときは、懲戒解雇に相当するような重大な理由が必要となるでしょう。
一方で業務命令による謹慎処分の場合、適切な期間は状況によって異なります。感染症に罹患したときは病気が完治するまで、トラブルに関する調査を行うときはその調査が終了するまでなど、状況に応じて謹慎期間を決めることが重要です。
2.従業員の生活への影響を考慮する
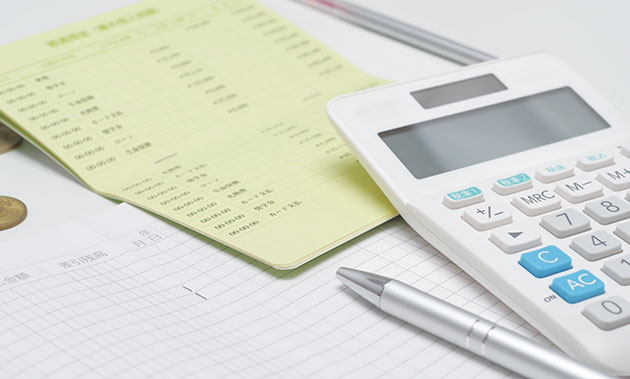
とくに懲戒処分による謹慎処分を実施するときは、従業員の生活への影響を考慮しなければなりません。謹慎期間中は無給となり、収入が大きく減ってしまうからです。制裁的な意味合いはあるものの、違反行為とのバランスを考慮して謹慎期間の長さを設定しましょう。
なお、懲戒処分のひとつである減給の場合は、労働基準法の第91条により、以下のような制限が設けられています。(※2)
- 1回の減給額が平均賃金の半額を超えてはならない
- 減額の総額が賃金の総額の10分の1を超えてはならない
出勤停止の場合、上記の基準は適用されず、謹慎期間に関する制限もないため、長期間にわたり無給とすることも可能です。ただし、違反行為に対して重すぎる処分を下すと、権利の濫用と見なされるため注意しましょう。
(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第九十一条(制裁規定の制限)
3.有給休暇の申請に応じる必要はない
謹慎処分の期間中に従業員から有給休暇を申請されたとしても、応じる必要はありません。有給休暇は、就労の義務がある日において取得できるものだからです。謹慎処分は働くことを禁止する対応であるため、当然、就労の義務はなく、有給休暇を申請することもできません。
4.外出禁止などのルールを設けることは難しい
懲戒処分による謹慎処分の場合、外出禁止などのルールを設けることは原則としてできません。謹慎は就労を禁止する処分であり、それ以上の拘束力はないと考えられるからです。
一方で業務命令による謹慎処分の場合は、外出禁止にすることが認められるケースもあります。たとえば、外出することで証拠隠滅を図る可能性がある場合などは、外出禁止を命じることが認められるでしょう。ただし、通常の勤務時間内に限る、必要性をしっかりと考慮する、といった対応は必要です。
謹慎処分を実施するときの流れ
ここでは、懲戒処分による謹慎処分を実施するときの流れを紹介します。
1.問題行動について調査する

従業員が起こした問題行動や違反行為について調査を行いましょう。関係者にヒアリングしたり、証拠となる書類を集めたりすることが重要です。証拠が不十分な状態で懲戒処分を行うと、処分が無効になるケースもあります。
2.就業規則の内容を確認する
懲戒処分の内容については、事前に就業規則に記載しておかなければなりません。違反行為が出勤停止の事由に該当するかどうかをチェックしてから、処分を与えるようにしましょう。
3.弁明の機会を与える
処分を実施する前に、従業員に弁明の機会を与えましょう。弁明の機会とは、従業員の言い分を聞く場のことです。従業員の話を聞き、反省の度合いなどを確認したうえで、処分を実施するか検討しましょう。
4.謹慎処分を実施するか検討する
問題行動の悪質性や関係者の意見、会社が受けた被害の大きさなどを含めて、本当に謹慎処分を実施するか検討しましょう。場合によっては、より軽い処分やより重い処分が適しているケースもあります。行為と処分のバランスを考慮して、最終的な判断をしましょう。
5.処分通知書を作成する
謹慎処分を与える旨を記載した処分通知書を作成しましょう。処分通知書には、懲戒処分の種類、対象となった違反行為、謹慎処分の期間などを記載します。作成したら従業員に交付して、内容を伝えましょう。
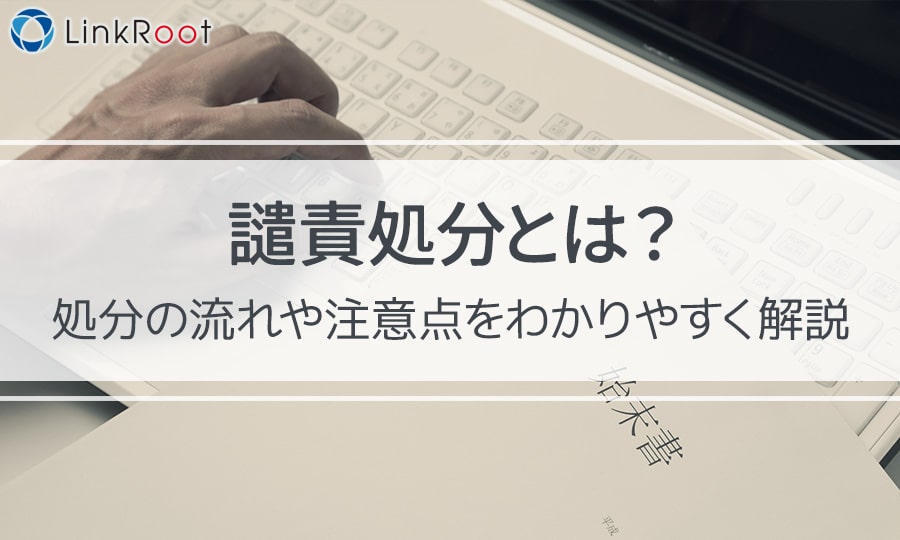
謹慎処分はルールに従って与えよう!
今回は、謹慎処分の意味や実施するときのポイントについて解説しました。謹慎処分には、懲戒処分によるものと業務命令によるものがあります。どちらの処分が適切かは状況によって異なるため、慎重に判断しましょう。
また、謹慎処分を与えるときは、法律に違反しないよう注意しなければなりません。不当に長い期間の謹慎処分を与えると、処分が無効となるケースもあるため、違反行為と処分の重さのバランスを考慮することが大切です。