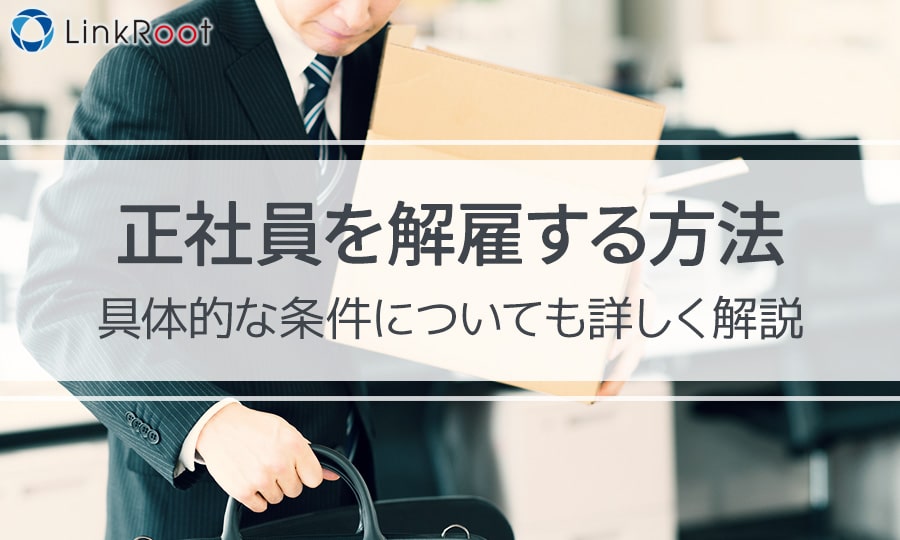正社員として採用したものの、期待していたほどの能力を発揮してくれない場合や、ハラスメント行為などのトラブルが頻発している場合は、解雇を検討することになるでしょう。
特定の条件を満たしていれば正社員を解雇することは可能ですが、解雇は重い処分であるため簡単に実施することはできません。
そこでこの記事では、正社員を解雇する方法や具体的な条件について詳しく解説します。不当解雇のリスクを避けるためにも、解雇が認められる理由や条件について理解を深めておきましょう。
正社員を簡単に解雇することはできない
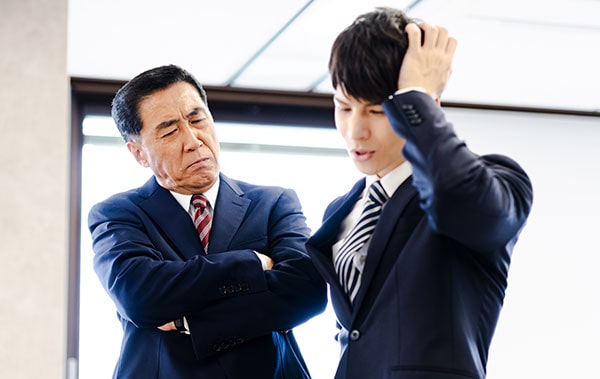
解雇とは、従業員との雇用契約を会社側から一方的に解約することです。民法の第627条には、いつでも契約解除の申し入れができると記載されています。申し入れから2週間が経過すると雇用契約は解除されます。(※1)
しかし、解雇は従業員に対する重い処分であり、急に仕事を失うと生活に困る可能性もあるため、簡単に行うことはできません。労働契約法の第16条によると、解雇が認められるためには、以下2つの要件を満たす必要があります。(※2)
(※1)e-GOV法令検索「民法」第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_8-At_627
(※2)e-GOV法令検索「労働契約法」第十六条(解雇)
1.客観的に合理的な理由があること
正社員を解雇するためには、客観的に合理的な理由が必要です。無断欠勤が多い、仕事を遂行するための能力が不足しているなどの理由があれば、解雇が認められやすいでしょう。
2.解雇が社会通念上相当であること
解雇という重い処分が社会通念上相当でなければ、不当解雇と見なされる可能性もあります。たとえば、数回程度の遅刻を理由に解雇することは、基本的に認められないでしょう。
遅刻や無断欠勤について繰り返し指導しても状況が改善されず、大きな損害が発生しているなど、重い処分が適切である場合に限り、解雇が認められます。
正社員を解雇するための条件については、後ほど詳しく解説します。
正社員を解雇する方法

正社員を解雇する主な方法としては、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つが挙げられます。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
1.普通解雇
普通解雇とは、懲戒解雇や整理解雇に該当しない解雇のことです。「普通」という名前が付いてはいますが、簡単に実施できるわけではありません。普通解雇を行うためには、以下のような客観的に合理的な理由が必要です。
- 職務を果たすための能力が不足している
- 正当な理由のない遅刻や欠勤が多い
- 就業規則に違反している
- ハラスメントやいじめなどのトラブルが頻発している
- 協調性が不足している
- 犯罪行為に関わっている
上記のような解雇理由は、就業規則に記載しておかなければなりません。就業規則に記載がない場合、解雇の正当な理由として認められないため注意しましょう。
また、仮に就業規則に記載があったとしても、社会通念上相当でなければ解雇は認められません。解雇が認められるかどうかは、行為の悪質性や常習性、適切な指導の有無などをもとに総合的に判断されます。
不当解雇と見なされると、未払いの賃金を請求されたり、企業のイメージが悪化したりするため、解雇は慎重に行うことが大切です。
2.懲戒解雇
懲戒解雇とは、重大な犯罪行為やルール違反が発覚したときに行う解雇のことです。従業員に対する制裁的な意味合いが強く、懲戒処分のひとつとして位置付けられます。
懲戒解雇を行うためには、普通解雇と同様、客観的に合理的な理由があることと、社会通念上相当であることが必要です。また、就業規則に懲戒解雇に関する規定を記載しておかなければなりません。
懲戒解雇は従業員に対する最も重い処分であるため、重大な犯罪行為があった場合や会社に大きな損害を与えた場合などに認められます。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 重大な経歴詐称が発覚した
- 無断欠勤が続いており出勤の督促にも応じない
- 横領や窃盗などの犯罪行為に関わった
- 故意や過失により会社に大きな損害を与えた
懲戒解雇を行うハードルは高く、上記のような理由があったとしても、正しい手続きで進めなければ認められないため注意しましょう。
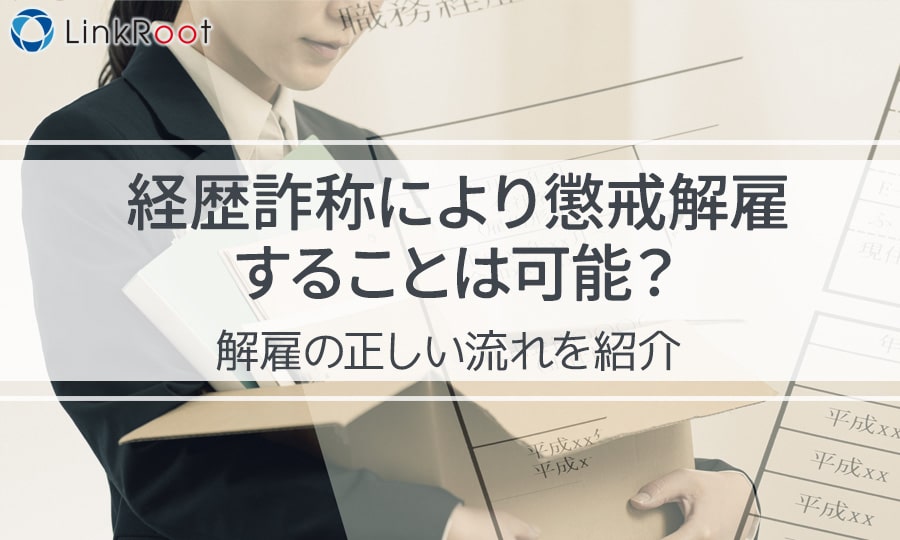
3.整理解雇
整理解雇とは、経営上の都合により雇用契約を解約することです。整理解雇は、以下のような場合に実施されます。
- 経営状況が悪化したために事業を縮小する
- 売上悪化により支店や事業所を閉鎖する
ただし、経営状況が悪いからといって、簡単に整理解雇を行えるわけではありません。整理解雇を実施するためには、人員削減の必要性があるだけではなく、新規採用を中止している、早期退職者を募集しているなど、解雇を回避する努力をすることが求められます。
また、個人的な好き嫌いなどで解雇する従業員を選ぶことはできません。客観的な基準により人選を行い、説明会などを開催して従業員としっかりと協議することが必要です。
正社員を解雇するための条件
ここでは、正社員を解雇するための条件について、解雇理由ごとに解説します。不当解雇にならないよう、それぞれの条件を理解しておきましょう。
1.能力不足を理由として解雇するケース

仕事を進めるためのスキルや知識が不足していることは、解雇を検討する理由のひとつです。能力不足を理由として解雇することは可能ですが、まずは適切な指導やサポートを行う必要があります。
仮にスキルや知識を保有していたとしても、新しい職場ですぐに能力を発揮できるとは限りません。すぐに解雇することは避け、仕事の進め方やコツなどを伝えるようにしましょう。繰り返し指導やサポートをしても仕事が進まない場合は、解雇が認められる可能性が高くなります。
2.無断欠勤を理由として解雇するケース
正当な理由のない無断欠勤が続いている場合、解雇を検討することになります。無断欠勤の日数に関する明確な基準はありませんが、目安として2週間以上続いていれば解雇が認められるでしょう。
ただし、無断欠勤の理由が職場におけるハラスメントやいじめであったり、仕事の影響による精神疾患であったりすると、解雇は認められません。無断欠勤をしていたという証拠も必要です。タイムカードや勤怠管理システムの記録などをしっかりと残しておきましょう。
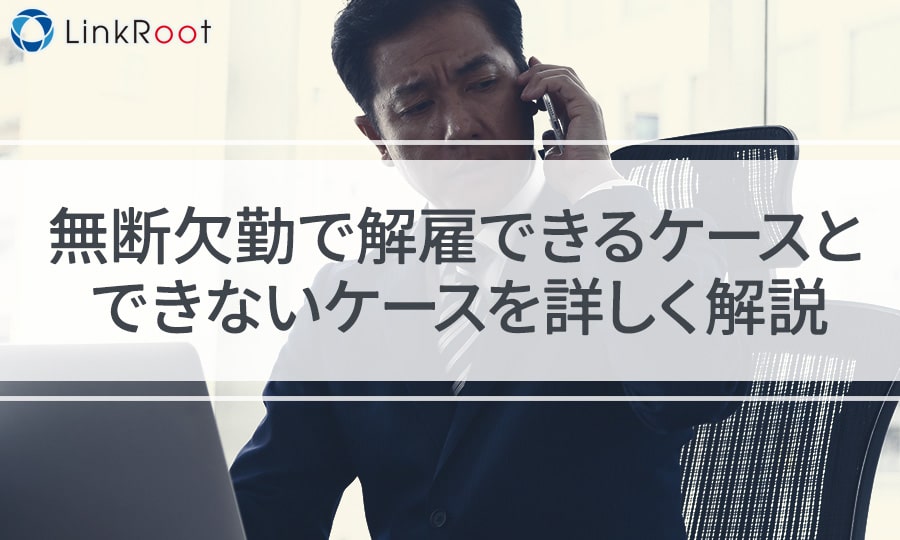
3.勤怠不良を理由として解雇するケース
勤怠不良を理由として解雇するときは、能力不足の場合と同様、まずは適切な指導や注意を行わなければなりません。遅刻が多い、業務上の指示に従わない、クライアントに対する態度が悪い、といった場合でも、指導を怠ると不当解雇と見なされる可能性があります。
指導の記録を残しておくことも重要です。指導をしたときのメールや文書を残しておけば、裁判などで役立つでしょう。また、いきなり解雇せずに、戒告や減給など、段階的に重い処分を与えていく方法もあります。
4.協調性不足を理由として解雇するケース
協調性が不足している場合も解雇を検討することになるでしょう。ただし、会話が少ない、チームになじめないなどの理由で解雇することはできません。
業務を進めるうえで必要なコミュニケーションが取れず、大きな支障が発生しているような場合に限って解雇が認められます。また解雇を検討する前に、コミュニケーションが取れない理由を聞いたり、サポートや指導をしたりするなど、適切な対応を行わなければなりません。
5.病気・怪我を理由として解雇するケース
病気や怪我によって仕事を継続できないことも、解雇を検討する理由のひとつです。ただし、業務が原因で病気になったり怪我をしたりした場合は、休業期間とその後30日間は解雇することができません。
一方で私傷病の場合は、就業規則に従って休職させることが必要です。回復の可能性があれば業務量を調整して復職させるなど、すぐに解雇せずに様子を見ましょう。休職期間が終了するまでに復職できなければ、解雇が認められます。
6.犯罪行為を理由として解雇するケース
犯罪行為が発覚した場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。とはいえ、どのような犯罪行為でも解雇が有効となるわけではありません。たとえば、会社の資金を横領し、大きな損害が発生している場合は、解雇が認められるでしょう。
私生活上の犯罪であっても、会社の信用に関わる場合などは解雇が認められます。具体的には、飲酒運転による事故や暴力行為などにより会社名が報道された場合は、解雇が認められる可能性が高いでしょう。
一方、会社への影響がない場合は、不当解雇と見なされるケースもあります。
7.経営状況を理由として解雇するケース
経営状況の悪化を理由として解雇を行う場合は、以下の条件を満たさなければなりません。
- 人員削減の必要性がある
- 解雇回避の努力をしている
- 人選の合理性がある
- 正しい手続きを行っている
前述のとおり、整理解雇は簡単に行えないため注意しましょう。
正社員の解雇が制限される場面
法律によって解雇が制限される場面もあるため、注意しなければなりません。法律を無視して解雇を進めると、処分が無効となるだけではなく、未払いの賃金や慰謝料を請求されるケースもあります。具体的には、以下のような期間中の解雇が禁止されているため確認しておきましょう。
業務上の怪我・病気による休業期間

仕事が原因で病気になった場合や、通勤中に怪我をした場合、治療のための休業期間は解雇することができません。また、休業期間後30日間も解雇が禁止されているため注意しましょう。
産前産後の休業期間
女性社員については、産前産後の休業期間とその後30日間は解雇が制限されています。従業員側に大きな問題があったとしても解雇できないため注意が必要です。また、妊娠や育児、介護などを理由として解雇することも認められないため覚えておきましょう。
正社員を解雇するときの注意点
正社員を解雇するときは、解雇予告や退職金の支払いに注意しましょう。以下、それぞれの注意点について詳しく解説します。
1.解雇予告を忘れないようにする
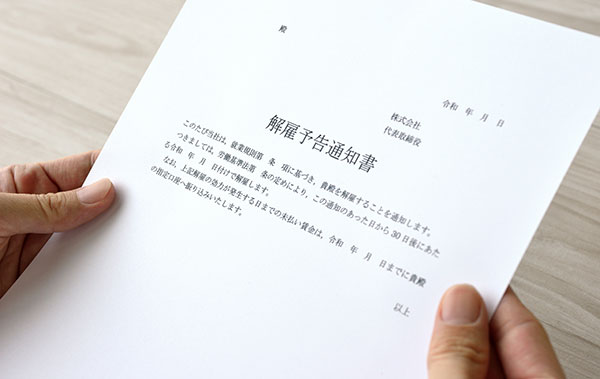
従業員を解雇するときは、30日以上前に解雇予告をしなければなりません。解雇予告とは、雇用契約を解除する日を従業員へ伝えることです。急に仕事を失うと従業員が生活できなくなる可能性もあるため、労働基準法に従って解雇予告をする必要があります。
即日解雇したい場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当の金額は、30日分以上の平均賃金と決められています。(※3)解雇予告や解雇予告手当の支払いを忘れると、30万円以下の罰金、または6ヶ月以下の懲役が科せられる可能性もあるため注意しましょう。(※4)
(※3)厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法20条」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-1.pdf
(※4)e-GOV法令検索「労働基準法」第百十九条の一
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_13-At_119
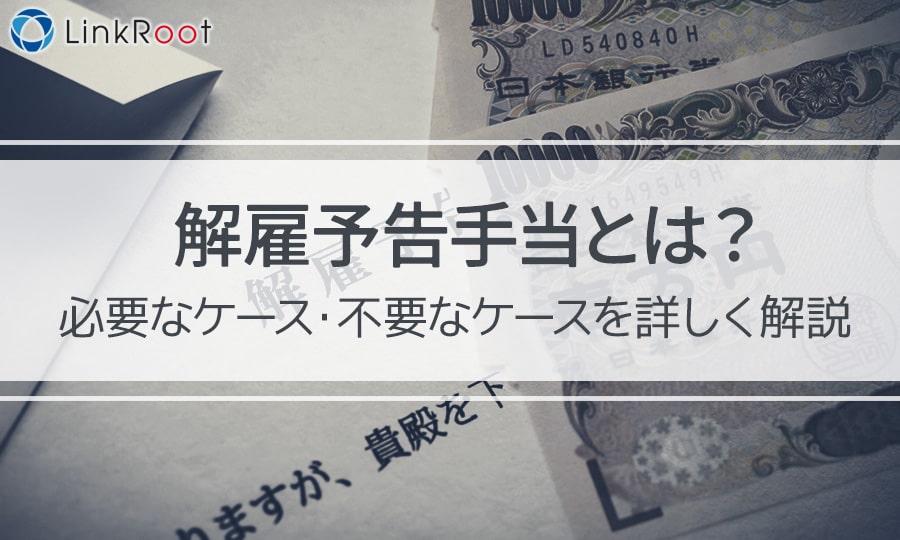
2.退職勧奨を検討する
従業員を解雇する前に、退職勧奨を検討するケースもあります。退職勧奨とは、問題のある従業員に対して退職してほしい旨を伝え、納得してもらったうえで退職届を提出してもらうことです。解雇とは異なり、話し合いにより合意してからの退職を目指すため、比較的スムーズに手続きを進められます。
無理に解雇すると訴えられる可能性もあるため、可能な場合は退職勧奨を検討してみましょう。従業員が納得してくれないのではないかと考えるかもしれませんが、丁寧に理由を説明することで合意形成につながるケースもあります。
解雇に関するトラブルを避けるためにも、まずは退職勧奨を検討することが重要です。
3.退職金の支払いが必要なケースもある
何らかの問題が発生し、従業員を解雇する場合でも、退職金の支払いが必要なケースもあります。たとえば、無断欠勤や能力不足を理由とした解雇が認められる場合でも、就業規則に退職金に関する取り決めが記載されているなら、規定に則って退職金を支払わなければなりません。
犯罪行為や経歴詐称など、懲戒解雇に該当するような大きな問題が発生した場合でも同様です。特定の状況において退職金の支払いを避けたいなら、就業規則のなかに「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」といった規定を設けておく必要があります。解雇を実施する場合は、退職金のルールについて社内の規定を確認しておきましょう。
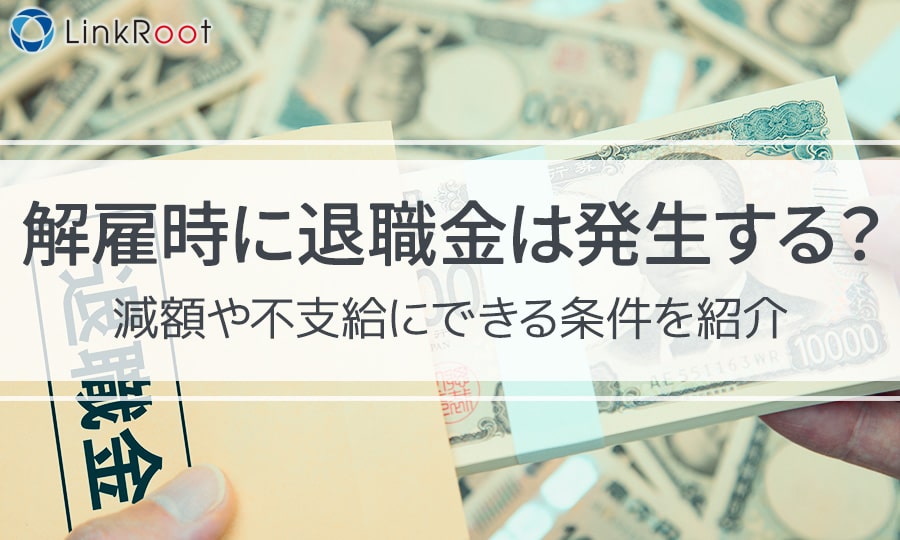
正社員を解雇するときは客観的で合理的な理由が必要!
今回は、正社員を解雇する方法や、解雇が認められる条件について解説しました。正社員を解雇するためには、客観的で合理的な理由が必要です。
また、従業員が起こした問題に対して、解雇が社会通念上相当であると認められなければ、処分は無効と見なされます。
従業員を不当に解雇すると、訴えられたり未払いの賃金を請求されたりするため注意しましょう。まずは解雇理由が就業規則に記載されているかをチェックし、解雇が制限されるケースに該当しないかどうかを慎重に確認することが大切です。