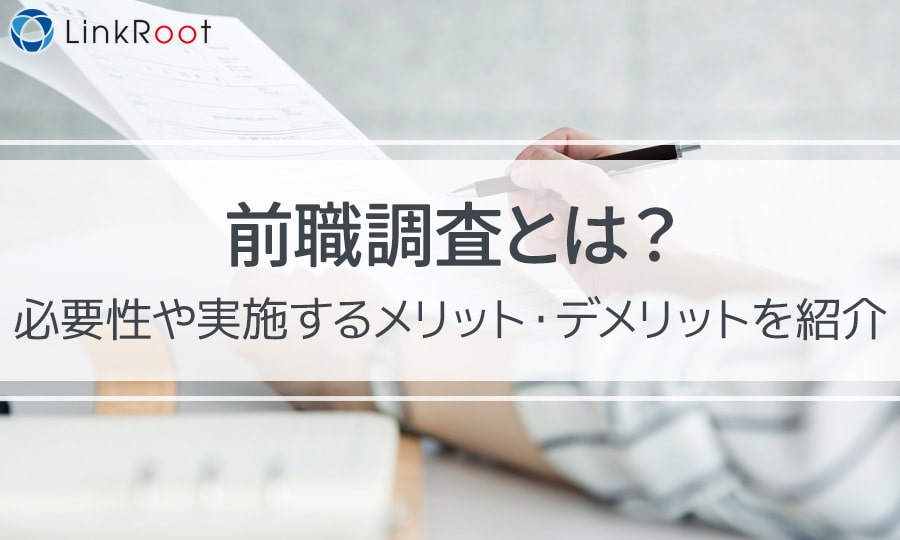少子高齢化による労働力不足が進む状況のなか、優秀な人材を確保して継続的に事業を展開することは企業の大きな課題です。
ただ、新しい人材を採用したものの期待していたほどの能力を発揮してくれない、面接で本人に質問するだけでは正確なスキルを把握できない、といった悩みを抱えている企業も多いでしょう。人材の実力を見極め、採用の精度を高めるためには、前職調査を実施するのがおすすめです。
この記事では、前職調査の意味や行うべきタイミング、実施するメリット・デメリットなどを詳しく解説します。
前職調査とは?
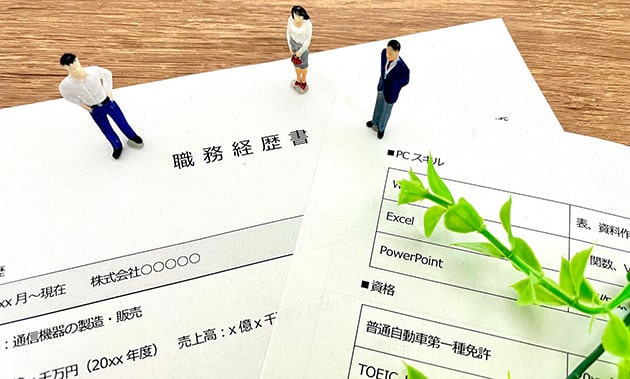
前職調査とは、採用候補者の過去の職歴やスキルを調べることです。一般的に中途採用の場合に行われ、前職が存在しない新卒採用のプロセスで実施されることはありません。
前職調査の大きな目的は、経歴詐称がないかどうかを確認し、採用候補者の能力を正しく評価することです。調査のなかで、前職の上司や同僚などの関係者にヒアリングを行い、履歴書の記載内容や面接での発言内容が正しいかどうかをチェックします。
職歴はもちろん、勤務態度や対人関係などについて幅広く調べることで、自社に必要な人材かどうかを見極め、採用後のミスマッチを防止できるでしょう。
前職調査は誰が行う?
前職調査は、社内の担当者が自分で実施することもありますが、興信所や専門の調査会社へ依頼するケースも増えてきました。アウトソーシングすることで、自分で調査する手間を省き、スムーズに情報を収集できます。
また、強化された個人情報の取り扱い方法に違反することなく、より安全かつ適正な方法で調査を進めることが可能です。
前職調査を行うべきタイミング
前職調査は、選考プロセスがある程度進んだ段階で行いましょう。とくに採用候補者の人数が多い場合、最初の段階から全員に対して前職調査を行うと多額のコストがかかってしまいます。
書類選考や一次面接など、一定の絞り込みをしてから実施すると、コストを抑えつつ必要な情報を得られるでしょう。ただし、内定を出す前には完了させなければなりません。内定を出してから前職調査を実施し、仮に問題が発覚した場合でも、内定を取り消すことはできないからです。
基本的には内定を出したタイミングで労働契約が成立します。前職調査の内容をもとに採用の可否を決めたいなら、内定前の適切なタイミングで実施しましょう。
前職調査は違法?
前職調査を行うこと自体に違法性はありません。ただし、事前に採用候補者から同意を得る必要があります。個人情報保護法により、本人の同意を得ないで個人データを第三者へ提供することは禁止されているからです。(※1)
また、選考とは関係のない事柄まで調査したり、家族関係や出身地を調べることで差別したりすることは避けなければなりません。厚生労働省が定める「公正な採用選考の基本」のなかでも、宗教や人生観、思想に関することなどを面接で質問したり調査したりすることは、就職差別につながる可能性があると注意喚起されています。(※2)
(※1)e-Gov法令検索「 個人情報保護法」第二十七条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057#121
(※2)厚生労働省「公正な採用選考の基本」
前職調査とリファレンスチェックの違い
前職調査と似た手法として、リファレンスチェックが挙げられます。どちらも採用候補者の経歴やスキルを把握するために実施されますが、2つの手法には以下のような違いがあります。
前職調査とは経歴の間違いをチェックすること

前職調査とは、採用候補者が履歴書や面接のなかで申告した内容に間違いがないかチェックすることです。調査内容について明確な決まりはありませんが、主に職歴や担当業務についての事実確認を行います。企業によっては、勤務態度などを一緒に調べるケースもあるでしょう。
企業側がヒアリングする相手を選ぶことも前職調査の大きな特徴です。基本的には、採用候補者のことをよく知る前職の同僚や上司を対象として実施します。
リファレンスチェックとは人物像やコミュニケーションスキルを把握すること
リファレンスチェックにおいても前職調査と同様、前職の上司や同僚などの関係者から採用候補者に関する情報のヒアリングを行います。ただし前職調査とは異なり、採用候補者がヒアリングする相手を指定したうえで、企業側は調査を進めます。
リファレンスチェックを実施する大きな目的は、主に採用候補者の人物像や勤務態度、対人関係やコミュニケーションスキルなど、履歴書や面接だけでは捉えにくい一面を把握することです。
事実関係の確認を主とする前職調査とは異なり、採用候補者の実際の働き方をリアルに把握できるでしょう。リファレンスチェックは対面や電話でのインタビューのほか、関係者から推薦状を提出してもらう、リファレンスチェックツールを活用するなどの方法で実施されます。

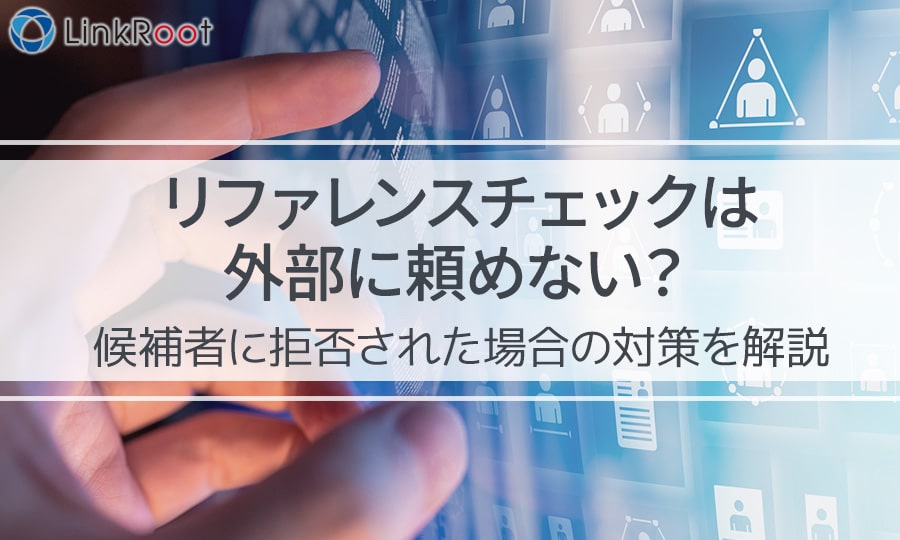
応募者に対して前職調査を実施すべき理由は?
前職調査を実施する目的としては、経歴詐称を見抜くこと、スキルを正確に評価すること、採用後のリスクを把握することなどが挙げられます。
以下、前職調査を実施すべき理由について紹介しますので確認しておきましょう。
1.経歴詐称を見抜くため

前職調査を実施すると、経歴詐称を見抜くことにつながります。経歴詐称とは、学歴や職歴について虚偽の申告をすることです。採用候補者が履歴書に嘘の勤務先名を記載したり、面接で事実とは異なる回答をしたりするケースもあるでしょう。
採用候補者との直接的なやり取りのなかで経歴詐称を見抜けることもありますが、実際に担当していた業務など、細かな内容については事実関係を確認しきれないこともあります。
そこで前職調査を実施すれば、第三者から客観的で正確な情報を得て、経歴の間違いがないかを確認することが可能です。経歴詐称をした人を採用してしまうと、適切な人事配置ができない、適した業務を与えられないなどの問題が発生するため、調査を通して事実を確認しておきましょう。
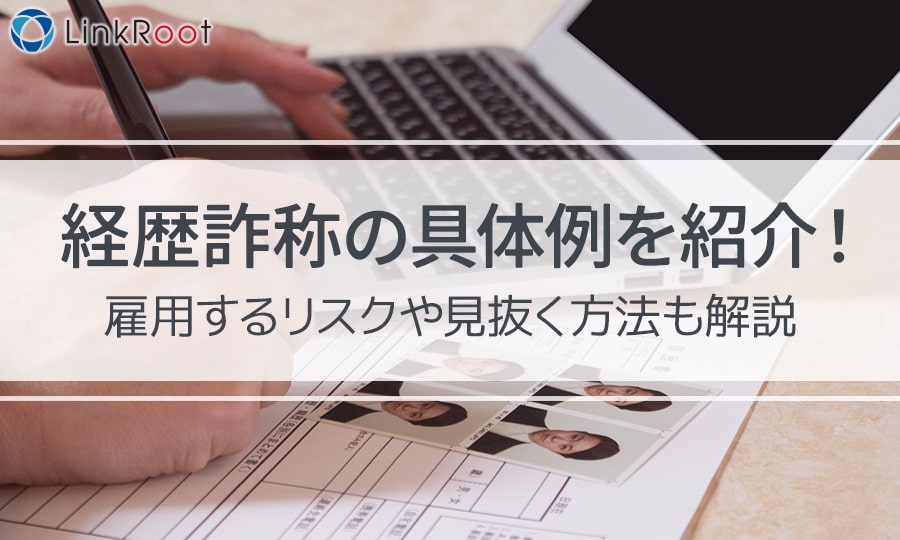
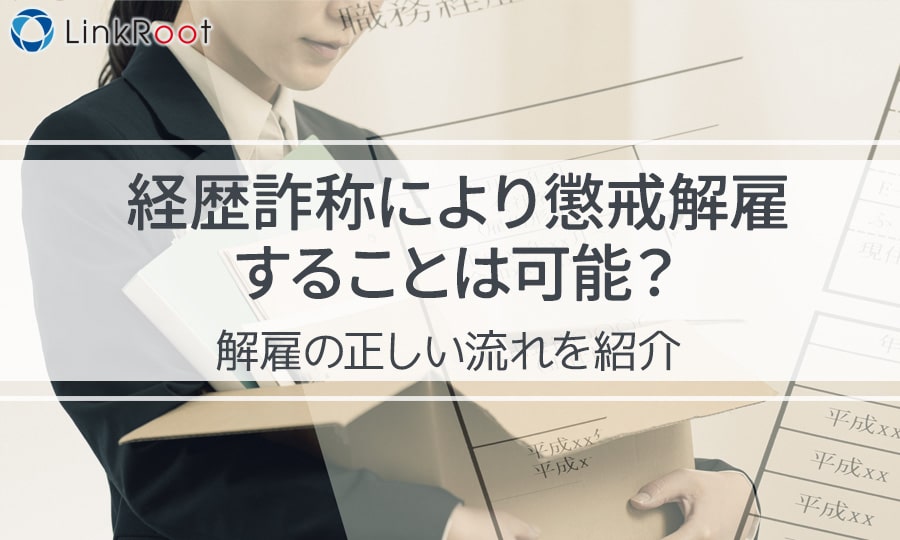
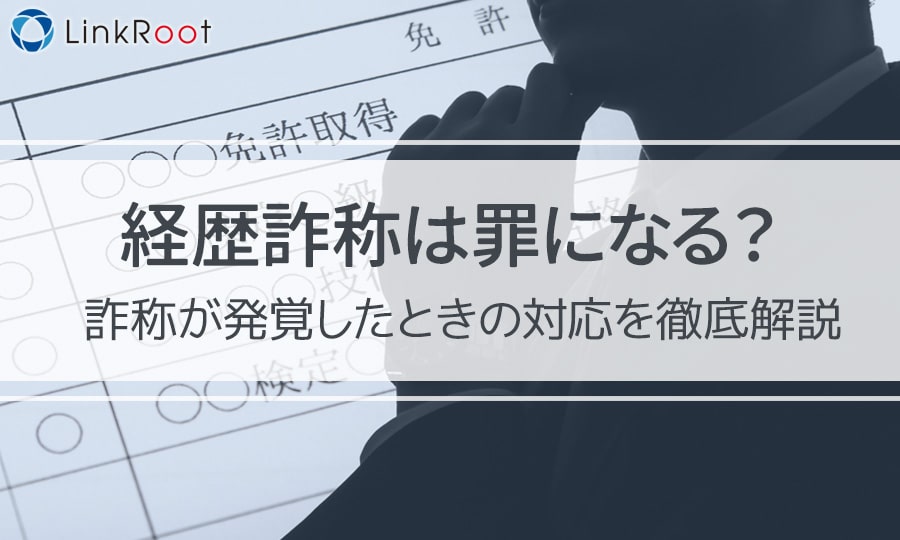
2.正確な能力評価を実施するため
正確な能力評価につなげることも、前職調査の大きな目的です。履歴書に記載された内容や面接でのコミュニケーションを通して、採用候補者のスキルをある程度は把握できます。
ただ、過去の職場でどのように能力を発揮していたのか、実際にどのような成果を出していたのかなど、本当の状況を把握することは簡単ではありません。よくわからないまま採用することで、期待していたほどの能力を発揮してくれないケースもあるでしょう。
前職の関係者から働き方や成果を具体的に聞いておくことで、能力評価の正確性が高まります。適した業務内容や必要なサポートもわかるため、より大きな成果が出ることを期待できるでしょう。
3.履歴書だけではわからない内容を知るため
前職調査を実施すれば、履歴書だけではわからない内容を知ることが可能です。履歴書に記載された学歴や職歴、保有資格だけでは、実際に仕事をこなす能力を把握することは難しいでしょう。
また、自分自身を客観的に評価することは難しいため、面接での回答だけではわからない意外な一面や潜在的な能力もあるものです。前職調査では関係者から客観的な評価を聞くことができるため、面接担当者はもちろん、本人も知らなかった意外な能力を把握できることもあります。
4.リスクを把握するため
採用後のリスクを把握することも前職調査の大きな目的です。採用活動におけるリスクとしては、応募者が経歴の一部を隠している、実際には担当したことのない業務を経験したものとして話している、といったことが挙げられます。
採用候補者は、自分の評価が下がるような内容は積極的に話してくれません。また、入社したいという思いから、誇張した内容を申告してくるケースもあります。
採用候補者が面接や職務経歴書のなかで申告した内容が本当かどうか疑わしい場合は、前職調査によって事実を確認しておくことが大切です。
企業が前職調査を実施するメリット
前職調査を実施することには、応募者の詳しい情報を得られる、面接では把握できないスキルを知れる、適切な人事配置を実現できるなどのメリットがあります。
以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.応募者の詳しい情報を得られる
応募者の詳しい情報を得られることは、前職調査を実施する大きなメリットです。新しい人材を採用したい、即戦力を確保したいと考えていても、採用後に期待どおりに活躍してくれるか不安を感じることもあるでしょう。
企業の文化や雰囲気にうまく馴染めず、すぐに退職してしまう可能性もあります。調査内容にもよりますが、前職調査を通してさまざまな項目をヒアリングすれば、安心して選考プロセスを進めることが可能です。
2.面接では把握できないスキルを知れる

面接では把握できないスキルを知れることも、前職調査のメリットのひとつです。面接ではさまざまな内容の質問をしますが、短い時間のなかで把握できる内容は限られています。
また、緊張感のある雰囲気のなかで、うまくやり取りが進まないケースもあるでしょう。人柄や対人関係、コミュニケーションスキルなどは長く接しないと見えてこないこともあります。前職調査を実施すれば、長期的に接した関係者の意見をもとに、応募者のスキルを多面的に把握できるでしょう。
3.適切な人材配置を実現できる
適切な人材配置につながることも前職調査のメリットです。前述のとおり、前職調査を実施すれば良い面も悪い面も含め、採用候補者のさまざまな側面を把握できます。
それぞれに適した業務を与えられるため、採用後のミスマッチやモチベーションの低下を防げるでしょう。早期離職を減らすことができ、無駄な採用コストが発生することも防止できます。
企業が前職調査を実施するデメリット
さまざまなメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。
1.応募者との信頼関係が悪化する

前職調査を実施することによって、応募者との信頼関係が悪くなってしまう可能性もあります。応募者が自分の過去の職歴が疑われているなどと感じ、選考を辞退されたり、採用後の業務に影響が出たりするケースもあるかもしれません。
前職調査を行うなら、その目的を明確に伝えておくことが大切です。
2.コストが発生する
コストが発生することも前職調査のデメリットのひとつです。専門の調査会社や興信所へ依頼する場合は、予算オーバーとならないよう、しっかりと計画を立てておきましょう。
また、全員に対してではなく、専門職や重要なポジションに就く候補者に対してのみ行うなど、対象者を絞っておくことでコストを抑えられます。
前職調査によりチェックすべき項目
前職調査の項目は、調査の目的や採用候補者の状況、かけられるコストによって異なりますが、過去の担当業務や勤務態度、退職理由などについて調べることが多いでしょう。
以下、各項目について簡単に解説します。
職歴・担当業務
過去の職歴や担当業務は、前職調査における重要なチェック項目です。履歴書に記載されていたとおりの部署に所属していたのか、面接での回答どおりの業務を担当していたのかなどを前職の関係者へヒアリングしましょう。
勤務実績・勤務態度
勤務実績や勤務態度についてもヒアリングしておくことが大切です。実際の働きぶりは、面接や履歴書からはなかなか把握できません。遅刻や無断欠勤はなかったか、真面目に仕事に取り組んでいたかなどを聞いておけば安心して採用できます。
スキル・能力
スキルや職務遂行能力についてもヒアリングしておきましょう。履歴書に記載された内容について確認するだけではなく、同僚や上司、クライアントとのコミュニケーションスキルなどを聞いておくことも重要です。
人柄・対人関係

人柄や対人関係に大きな問題があると、採用後にトラブルが発生する可能性もあります。社内での人間関係を構築できず孤立してしまったり、すでに働いている従業員のモチベーションが低下したりするケースもあるため、注意しなければなりません。
健康状態
採用候補者の健康状態についてもヒアリングしておくことが大切です。業務に支障が出るほど健康状態が悪い場合は、採用を控える必要があるかもしれません。
また、健康状態を正確に把握することで、適切なサポートをすることも可能です。とくに肉体労働など、健康状態が良好でなければ従事できない業務の場合は、しっかりと調査しておきましょう。
退職理由
退職理由については面接のなかで質問するケースも多いのですが、虚偽の回答ではないかチェックしておくことが大切です。退職はネガティブな内容になりがちなため、評価が下がるのを避けたいという思いから嘘をついている可能性もあります。
前職の上司などから本当の理由を聞けば、事実を確認できるのはもちろん、応募者の志望動機や性格を知ることも可能です。
前職調査を実施する3つの方法
前職調査は、自社で行う、調査会社へ依頼する、ツールを活用するなどの方法で実施されます。それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットは以下のとおりです。
1.自社で調査を行う
自社で調査を行う場合は、採用担当者が前職の会社を訪問したり、電話したりして関係者へヒアリングします。自社による調査のメリットは、応募者の同意を得ればすぐにヒアリングを開始できることです。費用もそれほど発生しません。
ただし、慣れていないとどのように連絡を取ってよいのかわからず、手間がかかってしまうケースもあるでしょう。ヒアリング方法をよく知らず、限られた情報しか得られないというデメリットもあります。
また、公正な調査方法や選考基準についても把握しておかなければなりません。
2.調査会社へ依頼する
前職調査は、専門の調査会社へ依頼することも可能です。蓄積されたノウハウを使って、さまざまな情報を収集してくれるでしょう。スムーズに調査を進めてくれるため、採用の可否を決めるまでに時間がない場合に適しています。
調査会社へ依頼するデメリットは、コストが大きくなることです。コストを抑えたい場合は、目的に合わせて調査する項目を必要最低限にしておくとよいでしょう。
担当業務や対人関係など、気になる項目のみの調査にすれば、コストを抑えつつ重要な情報を得ることが可能です。
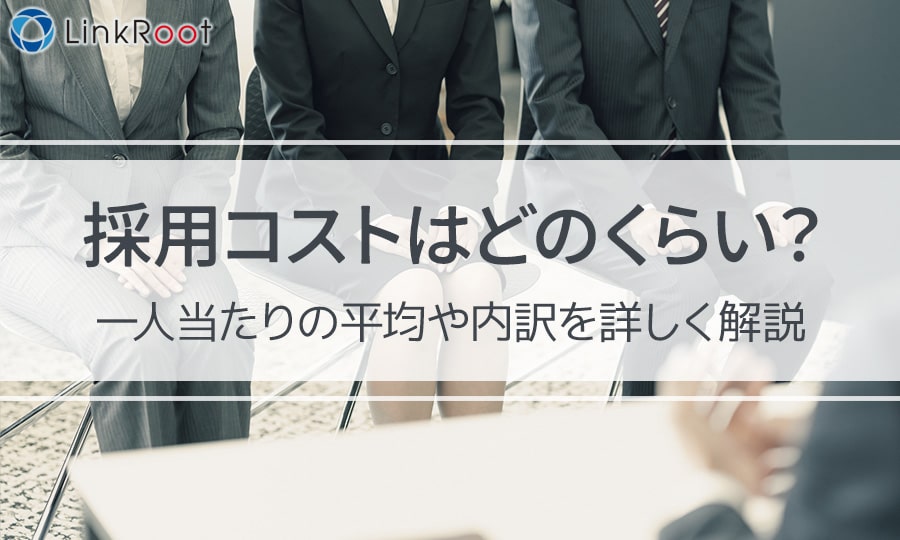
3.ツールを活用する

ツールを使って前職調査を行う方法もあります。前職の上司や同僚にオンラインで情報を入力してもらうタイプのツールも多く、気軽に導入できるでしょう。
前職調査やリファレンスチェックを実施するツールは、数多く提供されています。導入費用や機能、調査できる範囲はツールによって異なるため、自社の予算や目的に合ったものを選ぶことが大切です。
前職調査を実施するときの注意点
前職調査を実施することで採用に関するリスクを減らし、ミスマッチを防止できます。ただし、調査実施のタイミングや個人情報の取り扱いには注意しなければなりません。
ここでは、前職調査を行うときの注意点について解説します。
1.内定を出す前に調査する
前職調査は、内定を出す前に完了させましょう。前述のとおり、内定を出したタイミングで労働契約が成立したと見なされるため、内定後の取り消しは簡単には行えません。前職調査によって採用を見合わせたい事案が見つかったとしても、内定取り消しが認められないケースもあるため注意が必要です。
不当に内定を取り消すと応募者とのトラブルが発生するのはもちろん、企業のイメージが悪化する可能性もあります。これまでのコストを無駄にすることを避けるためにも、適切なタイミングで実施するようにしましょう。
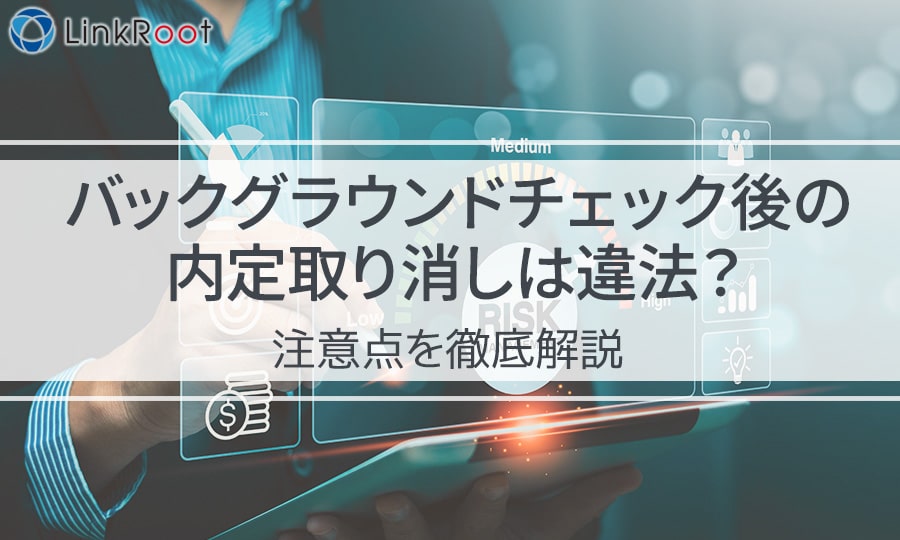
2.事前に応募者の承諾を得る

前職調査を行うときは、事前に応募者の承諾を得ることが大切です。言った・言わないのトラブルを避けるためにも、口頭で伝えるだけではなく、書面にサインしてもらうなど、記録に残る形にするとよいでしょう。
また、プライバシーに配慮し、採用とは関係ない事柄まで調査しないよう注意しなければなりません。応募者が不安を感じる場合は、前職調査を実施する目的を理解してもらい、調査内容は他の用途に利用しないことなどを伝えて安心してもらいましょう。
3.個人情報の取り扱いに注意する
個人情報の取り扱いにも注意しましょう。本人の同意を得ないで個人情報を調査会社などへ提供することは、個人情報保護法に違反します。
個人情報保護法に違反すると、懲役や罰金などの罰則を科せられる可能性もあるため十分に注意しなければなりません。また、企業のイメージが悪くなり、今後の採用活動がうまく進まなくなる可能性もあります。
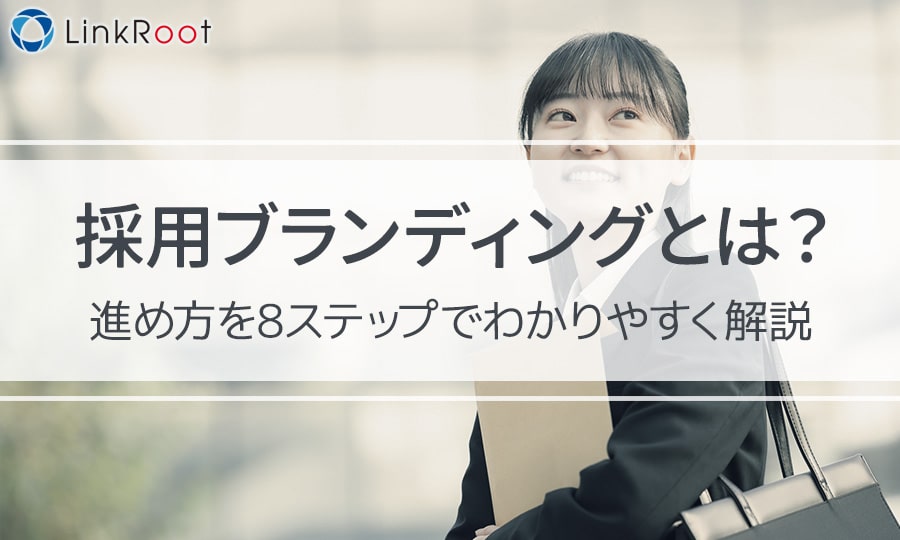
前職調査を実施して応募者の経歴を確認しよう!
今回は、前職調査の必要性や実施するメリット・デメリットを紹介しました。適切な方法で前職調査を行えば、履歴書だけではわからない勤務態度や対人関係のスキルなどを幅広く把握できます。採用すべき人材かどうかを見極めることができ、採用後の人材配置を最適化できるでしょう。
前職調査は自社で行うこともできますが、ノウハウがない場合は、専門会社への依頼やツールの活用を検討するのがおすすめです。
無理に自社で実施しようとすると、手間がかかりすぎてしまったり、求める情報を聞き出せなかったりします。調査の目的や採用活動の予算を明確にしたうえで、自社に最適な方法で調査を進めましょう。