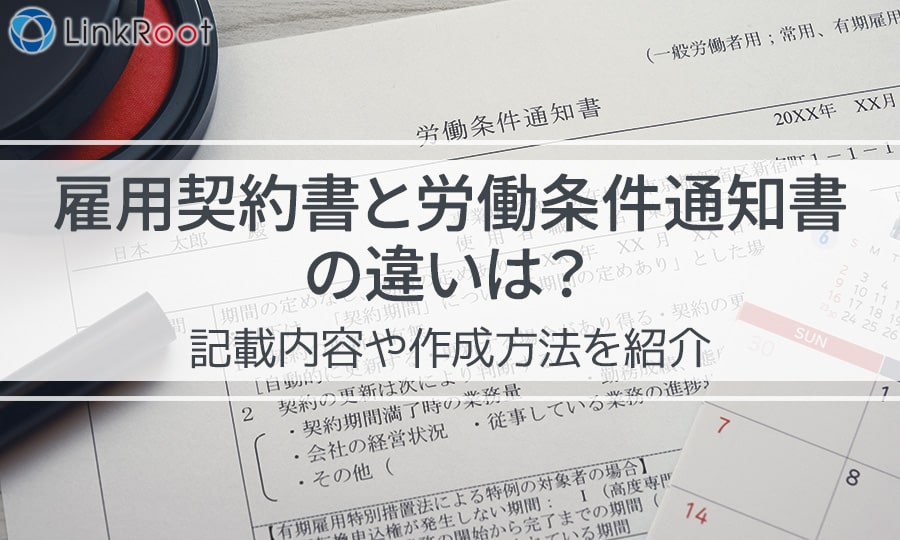新しい従業員を雇い入れる際は、雇用契約書や労働条件通知書を作成して交付するのが一般的です。2つの書類には、契約期間や仕事内容など似たような項目を記載しますが、実は役割や明記すべき事項は異なります。記載すべき項目の抜け漏れがあると労働基準法違反と見なされるケースもあるため、注意しなければなりません。
この記事では、雇用契約書と労働条件通知書の違いや、作成するときのポイントを解説します。労働契約をスムーズに進めるためにも、ぜひ最後までチェックしてください。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも従業員を雇用するタイミングで作成する書類です。就業場所や仕事内容、勤務時間などを記載するという点で似ている書類ですが、さまざまな違いがあります。
以下、雇用契約書と労働条件通知書の違いを4つのポイントで紹介しますので確認しておきましょう。
1.役割の違い

労働条件通知書は、契約期間・仕事内容・所定労働時間・休日など、働くうえで重要な条件を明記した書類です。法律に違反するような労働条件になっていないことを証明し、不利益がないように従業員を守る役割があります。雇用条件通知書や雇用通知書などと呼んでいる企業もあるかもしれませんが、役割としては同じです。
一方の雇用契約書は、労働条件について会社側と従業員がお互いに合意したことを示す書類です。記載内容は労働条件通知書とほとんど同じですが、雇用契約書はお互いの義務や権利を明示する役割をもっています。
会社側から従業員へ一方的に交付する労働条件通知書とは異なり、雇用契約書は2部作成し、従業員が署名や捺印をしたあと、それぞれが1部ずつ保管しておくのが基本です。
2.作成義務の違い
労働条件通知書は、労働基準法の第15条[1]に従って必ず作成しなければなりません。従業員がさまざまな内容を把握したうえで安心して働けるよう、労働条件の明示は法律によって義務付けられています。違反した場合は同法120条[2]によって30万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、新しい従業員を雇い入れる際は忘れずに作成しましょう。(※1)
雇用契約書については、法律上の作成義務はありません。作成しなくても罰則を受けることはありませんが、労使間のトラブルを防止するためにも作成して交付しておくとよいでしょう。後述するように、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として作成することも可能です。
(※1)e-GOV法令検索「労働基準法」第十五条(労働条件の明示)[1],第百二十条[2]
3.記載項目の違い
労働条件通知書には、労働基準法によって定められた項目を記載しなければなりません。必ず記載しなければならない絶対的明示事項と、特定の制度を導入している場合に記載すべき相対的明示事項があるため、抜け漏れのないようにしましょう。記載すべき具体的な内容については、後ほど詳しく解説します。
一方の雇用契約書については、法律上の作成義務がないのと同様、記載項目に関するルールもありません。企業の判断で記載する項目を決めることが可能ですが、契約期間や仕事内容、休日や休憩など、労働条件通知書と同じような内容を記載するのが一般的です。さらに、福利厚生や機密保持など、社内ルールに関する内容を記載するケースもあるでしょう。
4.締結方法の違い
労働条件通知書は会社側から一方的に交付するものであるため、従業員が署名や捺印をする必要はありません。会社側は署名や捺印をするケースもあります。また、書面で交付することもできますが、FAXや電子メールなどで送付することも可能です。
雇用契約書については、会社側と従業員の双方が署名・捺印をする必要があります。交付方法に関するルールはなく、書面・FAX・電子メールなどで締結することが可能です。
雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる
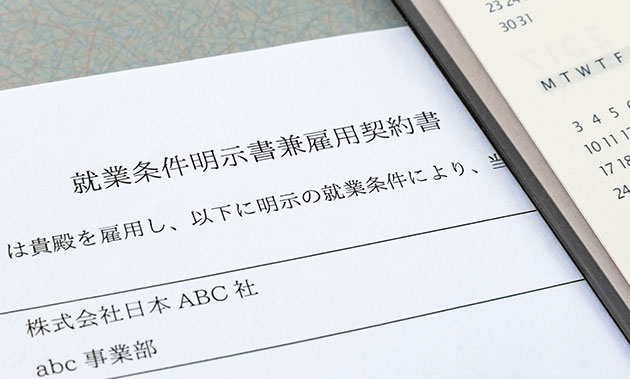
雇用契約書と労働条件通知書には同じような内容を記載するため、兼用できないかと考える人もいるでしょう。ここでは、雇用契約書の必要性や2つの書類の兼用について解説します。
雇用契約書は作成しなくてもよい?
前述のとおり、雇用契約書を作成する義務はないため、交付しなくても法律上の問題はありません。雇用契約は口頭でも成立するため、書類がなくても違法にはならないのです。
ただし、雇用契約書は、労働条件について会社側と従業員の双方が合意したことを示す重要な存在です。雇用契約書を作成していないと、労働条件に合意したことを物理的に証明することができません。従業員から「仕事内容について納得できない」「聞いていた条件と違う」などと主張されたときに根拠をもって説明できないため、事前に作成しておくとよいでしょう。
なお、労働条件通知書は会社側から一方的に交付するものであり、従業員が署名・捺印をすることもないため、労働条件に合意したという証拠としては不十分と見なされます。
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を発行することも可能
労働条件通知書と雇用契約書をそれぞれ発行することも可能ですが、2つの書類を兼用しても問題ありません。とくに書式は決まっていないため、企業が自由に作成できます。2つの書類をまとめて作成することで、事務作業の手間を省け、業務効率化を図れるでしょう。
ただし兼用する場合は、労働条件通知書の絶対的明示事項と相対的明示事項のルールに従う必要があります。また、記載内容が多くなりすぎると確認しにくいため、2つの書類を分けて作成するとよいでしょう。
雇用契約書と労働条件通知書に記載すべき項目

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成するときは、以下のような項目を記載しなければなりません。
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、必ず記載しなければならない項目です。具体的には、次のような内容を明記しましょう。
- 労働契約の期間
- 労働契約を更新するときの基準(期間の定めがある労働契約の場合)
- 就業場所
- 業務内容
- 始業時刻・終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間
- 休日・休暇
- 賃金の決定方法・計算方法・締切日・支払い時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
就業場所や業務内容について変更の可能性がある場合は、その旨も記載しておきましょう。始業時刻や終業時刻に関して、従業員を2組以上に分けて働かせる場合は、転換のタイミングを記載しておきます。
短時間労働者に関する追記事項
アルバイトやパートなどの短時間労働者を雇用する場合は、上記の項目だけではなく、以下の項目を追記しなければなりません。
- 昇給の有無
- 賞与の有無
- 退職手当の有無
- 雇用管理の改善などに関する相談窓口
法律によって記載することが義務付けられた項目であるため、忘れずに明記しましょう。
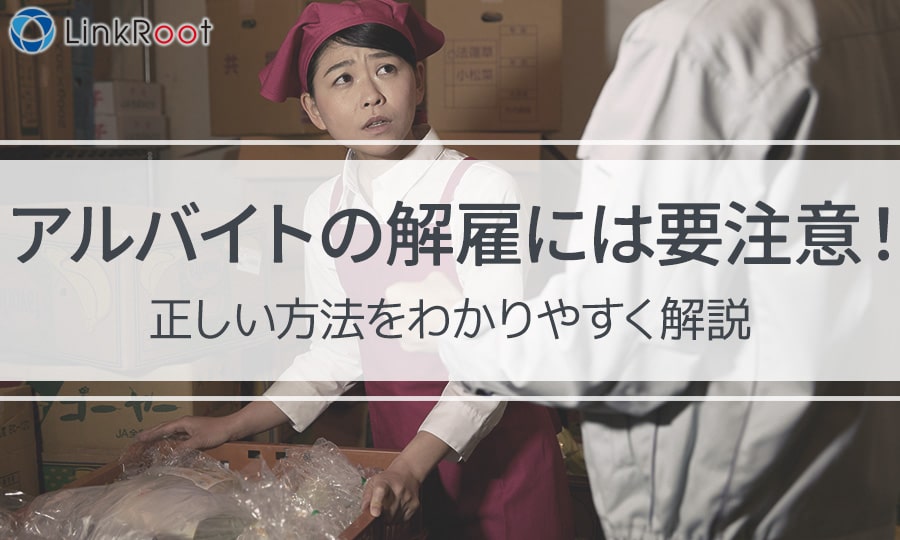
相対的明示事項
相対的明示事項とは、該当する制度を導入している場合に記載すべき項目です。たとえば、退職金制度や休職制度を導入しているかどうかは企業によって異なります。これらの制度を導入している場合は、相対的明示事項に該当するため、労働条件通知書に明記しなければなりません。具体的な項目は以下のとおりです。
- 退職手当の決定方法・計算方法・支払い時期
- 臨時に支払われる賃金・賞与・各種手当・最低賃金
- 安全・衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
- 休職に関する事項
退職金制度を導入している場合は、支給する従業員の範囲についても明記しておきましょう。また、休職制度を導入している場合、休職期間が満了したときに解雇するか退職となるかなど、扱いを明確にしておくことが重要です。
相対的明示事項については口頭での通知でも問題ありませんが、「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性もあるため、絶対的明示事項と一緒に書面で通知しておくとよいでしょう。
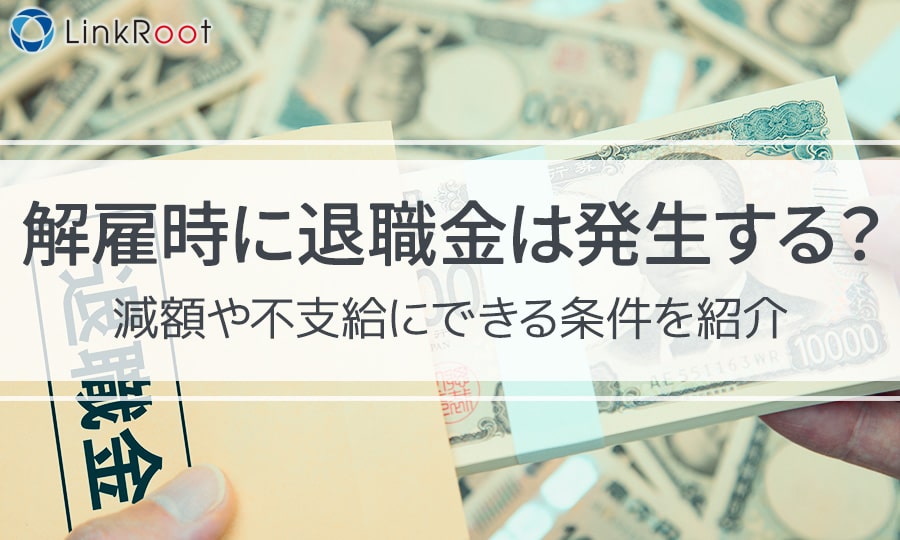
2024年4月以降の変更点
2024年4月の労働基準法改正により、労働条件通知書に記載すべき項目が追加されました。以下の項目が追加されているため、チェックしておきましょう。
すべての従業員が対象となる項目
就業場所や業務内容が変更となる可能性がある場合は、その範囲を記載しなければなりません。すべての従業員が対象となるため、新たに雇用契約を結ぶ際や契約更新のタイミングに記載しましょう。
有期雇用従業員が対象となる項目
有期雇用の従業員については、契約期間だけではなく、更新回数の上限の有無を明記しましょう。また、その理由についても記載しなければなりません。
無期転換申込権が発生する有期雇用従業員が対象となる項目
無期転換申込権とは、同一の企業との間で、有期雇用契約が更新されて通算5年を超えるときに、無期雇用契約への転換を申し込める権利のことです。契約を更新するタイミングで、無期転換申込権があることや無期転換後の労働条件について明示する必要があります。
以上のように、労働基準法の改正により記載すべき項目が追加されるケースもあるため、最新の情報をチェックしておくことが大切です。
雇用契約書と労働条件通知書を作成するときのポイント
雇用契約書と労働条件通知書を作成するときは、次のような点に注意しましょう。
- 労働基準法に違反しないようにする
- 雇用形態に合わせて作成する
- 外国人労働者向けの書類を準備しておく
- テンプレートを活用する
- 最後に内容をチェックする
以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
1.労働基準法に違反しないようにする

雇用契約書や労働条件通知書を作成するときは、労働基準法に違反しないようにしましょう。書式に関するルールはありませんが、絶対的明示事項や相対的明示事項については忘れないように記載しなければなりません。
また、労働契約の内容が労働基準法によって定められた最低基準を下回らないようにしましょう。たとえば、賃金や労働時間に対する休憩時間などについては、法律によって最低基準が定められています。基準を満たしていない場合、労働基準法違反として罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。さらに労働契約の該当する部分は無効となり、法律による最低基準が適用されます。
2.雇用形態に合わせて作成する
雇用契約書や労働条件通知書は、雇用形態に合わせて作成しましょう。正社員や契約社員、パートやアルバイトなどの雇用形態によって、記載すべき内容が異なるからです。
正社員の場合は、賃金や就業場所といった基本的な項目だけではなく、転勤の有無や人事異動の可能性などについても明記しておきましょう。会社全体の基準になるため、正社員に関する書類を作成してから、その他の雇用形態に関する書類を作成するのがおすすめです。
契約社員の場合は、契約更新の有無、更新するかどうかの基準などについて明記する必要があります。パートやアルバイトの場合は、正社員に対する絶対的明示事項だけではなく、昇給・賞与・退職手当の有無や雇用管理の改善に関する相談窓口についても記載しなければなりません。
3.外国人労働者向けの書類を準備しておく
外国人労働者向けの書類を準備しておくことも重要です。外国人労働者を雇い入れることが予想される場合は、日本語と英語が併記された労働条件通知書や雇用契約書を準備しておくとよいでしょう。厚生労働省のホームページにて、外国人労働者向けのモデル労働条件通知書が公開されているため、必要な場合は参考にしてください。(※2)
(※2)厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040325-4.html
4.テンプレートを活用する
記載すべき事項が網羅されていればどのような様式でも問題ありませんが、労働条件通知書の作成を効率化したい場合は、テンプレートを活用するのがおすすめです。厚生労働省のホームページでは、さまざまなタイプのテンプレートが公開されています。
一般労働者用のテンプレートだけではなく、派遣労働者や短時間労働者、林業や建設業で働く労働者に適したテンプレートもあるため、うまく活用しましょう。常用型と日雇型も選べるため、雇用形態に合わせて利用することが可能です。内容をカスタマイズしたい場合は、Word形式でダウンロードして編集しましょう。
5.最後に内容をチェックする
雇用契約書や労働条件通知書を作成したら、従業員へ交付する前に内容をチェックしておきましょう。記載すべき項目に抜け漏れはないか、労働条件に間違いはないか、法律上の最低基準を下回っていないか、必要な捺印はされているか、といった視点から確認することが重要です。
とくに同じ書式を使い回していると、間違いが起こる可能性もあります。労働条件は従業員によって異なることが多いため、思い込みで記載せず、しっかりと確認しなければなりません。必要に応じてダブルチェック体制を整えることも大切です。
雇用契約書や労働条件通知書は電子化できる

雇用契約書や労働条件通知書は電子化することも可能です。以前は、労働条件通知書の絶対的明示事項については書面での通知が義務付けられていましたが、2019年の労働基準法施行規則の改正により、メールやFAX、SNSなどを使った交付方法も認められるようになりました。(※3)
ただし、従業員が電子化を希望した場合に限られます。パソコンやインターネットが普及したとはいえ、自宅で利用できない人もいるため、従業員の意思を確認せずに電子的な方法で交付することはできません。
メールやSNSなど、さまざまな方法が認められていますが、第三者が閲覧できるような形式は避ける必要があります。たとえば、従業員のブログやホームページに投稿するような交付方法は認められません。また、出力して書面を作成できるような形式で交付することも必要です。
(※3)厚生労働省「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」
雇用契約書や労働条件通知書を電子化するメリット
雇用契約書や労働条件通知書を電子化することで、以下のようなメリットを得られます。
- 労働契約の締結を効率化できる
- ペーパーレス化を図れる
各種の書面を電子的な方法で交付すれば、印刷したり郵送したりする手間が省けるため、労働契約に関わる作業を効率化できます。また、ペーパーレス化を図ることで、印刷費や郵送代の削減が可能です。
さらには書類を保存しておく場所が不要になるため、オフィス内のスペースを有効活用できます。従業員数が増えるほど書類作成の手間が増えたり、コストがかかったりするため、ぜひ電子化を検討しましょう。
雇用契約書と労働条件通知書の違いを理解して作成しよう!
今回は、雇用契約書と労働条件通知書の違いや作成するときのポイントなどを紹介しました。2つの書類は、どちらも従業員を雇用するタイミングで作成するものですが、役割や記載すべき事項は異なります。両者の違いをしっかりと把握したうえで作成するようにしましょう。
また、2つの書類をまとめて「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を発行することも可能です。書類をまとめることで、労働契約に関する作業を効率化できます。さらに電子的な方法で交付すれば、よりスピーディーに業務を進められるでしょう。ただし、絶対的明示事項と相対的明示事項を忘れずに記載する、電子化する場合は出力できる形式で交付するなどのルールに従うことは重要です。