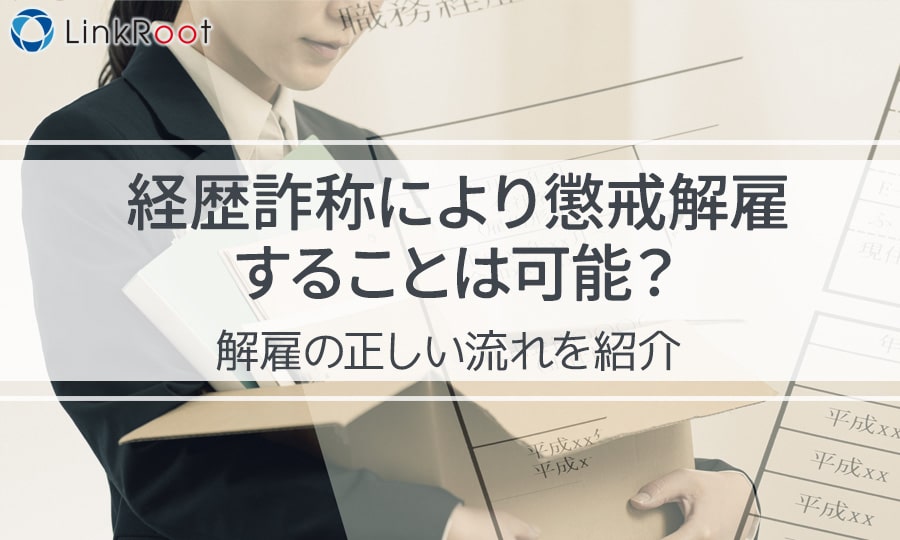経歴詐称は、企業へさまざまな影響を与える重大な問題です。ただ、経歴詐称があったからといって、必ずしも懲戒解雇が認められるとは限りません。経歴詐称を理由に懲戒解雇をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、正しい手続きに沿って実施しなければ解雇が無効となるケースもあるため注意が必要です。
この記事では、懲戒解雇するための要件や解雇の正しい流れを紹介します。経歴詐称による懲戒解雇を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
経歴詐称とは?具体例をもとに解説
経歴詐称とは、採用候補者が企業に対して虚偽の申告をすることです。企業に提出する履歴書に嘘の学歴を書いたり、面接の際に事実とは異なる回答をしたりすることは経歴詐称に該当します。また、学歴や職歴を隠すことも経歴詐称に当たります。
経歴詐称への対応については、会社の就業規則に記載しておくのが一般的です。懲戒解雇の事由のひとつとして、就業規則に記載している企業も多いでしょう。厚生労働省が作成しているモデル就業規則のなかにも、「重要な経歴を詐称して雇用されたときは懲戒解雇とする」という内容が記載されています。(※1)
以下、経歴詐称の具体例を紹介しますので、チェックしておきましょう。
(※1)厚生労働省「モデル就業規則」P86
学歴詐称
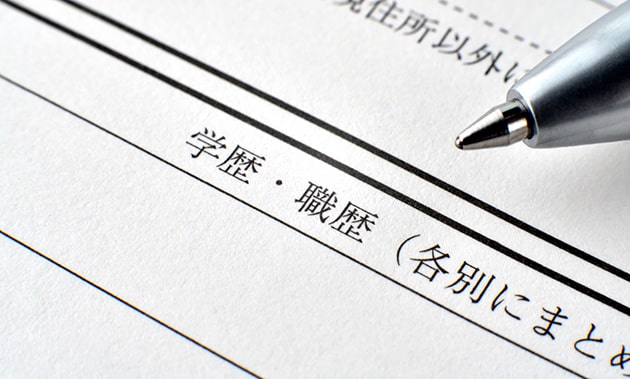
学歴詐称とは、卒業した学校名や学部名について嘘の申告をすることです。たとえば、高校卒業であるにもかかわらず大学卒業と詐称すると、採用後の給与や待遇、人事配置などに大きな影響を与えるため、懲戒解雇の対象となるでしょう。
そのほか、学歴詐称には以下のようなパターンがあります。
- 履歴書に実際とは異なる卒業大学名を記載する
- 入学年度や卒業年度について嘘の申告をする
- 留年や浪人を隠す
- 中退したことを隠して卒業と記載する
- 大学卒業にもかかわらず高校卒業と申告する
自分の評価を高めるために出身大学や卒業学部を偽ることはもちろん、逆に大学卒業を隠して高校卒業と過小申告することなども学歴詐称に該当します。企業によっては、従業員の年齢構成や属性などを考慮して採用計画を進めているケースもあるからです。
企業の方針に大きな影響を与えると判断される場合は、懲戒解雇の対象となります。
職歴詐称
職歴詐称とは、これまで勤めていた企業名や担当した業務内容について虚偽の申告をすることです。とくに中途採用の場合、職歴詐称をされると採用後の給与や仕事内容に大きな影響が出るため、注意しなければなりません。
職歴詐称の具体例は以下のとおりです。
- 過去の勤務先や仕事内容について嘘の申告をする
- 履歴書に実際とは異なる年収や雇用形態を記載する
- 職歴の一部を隠す
- 早期退職した企業について記載しない
- 転職回数を少なく記載する
転職活動を有利に進めたいという気持ちから、実際には経験したことのない業務内容を申告したり、複数の企業の在籍期間を合計して1社分として記載したりするケースもあります。
犯罪歴詐称

犯罪歴詐称とは、過去の犯罪歴について虚偽の申告をすることです。面接で犯罪歴を聞かれた際に嘘の申告をすることや、賞罰欄のある履歴書に前科について記載しないことなどは、犯罪歴詐称に該当します。
ただし、採用候補者側から犯罪歴を自発的に申告する義務はありません。また、犯罪歴を隠したからといって、すべてのケースで懲戒解雇が認められるわけではないため注意しましょう。学歴や職歴の詐称とは異なり、給与や仕事内容に大きな影響がない場合も多いからです。
もちろん、業務や他の従業員への重大な影響が認められる場合は、懲戒解雇の対象となります。
病歴詐称
病歴詐称とは、過去に治療した病気や、現在患っている病気について嘘の報告をすることです。継続して治療しているにもかかわらず健康状態は良好であると回答したり、症状を軽く申告したりすることは病歴詐称に該当します。
採用候補者の健康状態は、採用の可否を決定する重要な要素のひとつです。健康状態が良好でなければ従事できない業務内容もあるため、重大な病歴詐称については懲戒解雇の対象となるでしょう。
保有資格の詐称
採用候補者が保有資格について嘘の申告をしているケースもあります。保有資格の詐称の具体例は、以下のとおりです。
- TOEICの点数を実際より高く申告する
- 実際よりも高い級を記載する
- 保有していない資格名を記載する
- 不合格にもかかわらず合格と申告する
保有資格の詐称は、学歴詐称や職歴詐称と同様、採用後の給与や業務内容に大きく影響するため、懲戒解雇を検討するケースも多いでしょう。
経歴詐称した人を雇用する3つのリスク

経歴詐称した人を雇用することには、適正な人材配置が難しくなる、信頼関係を構築できない、適切な賃金を支給できないなどのリスクや問題があります。
それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
1.適正な人材配置が難しくなる
経歴詐称した人を採用すると、適正な人材配置を実現できません。経歴を詐称されると正確なスキルや経験を把握できず、その人に合った業務を与えられないからです。
実際にはこなすことができない難しい業務を担当させてしまうことで、期待していた成果が出ないことも多いでしょう。その結果、組織全体の生産性やパフォーマンスが低下してしまう可能性もあります。
2.信頼関係を構築できない
信頼関係を構築できないことも経歴詐称した人を雇用するリスクのひとつです。虚偽の申告が発覚したあとも継続して雇用すると、業務上でも嘘の報告をしているのではないかなどと疑ってしまいます。他の従業員との信頼関係が崩れたり、組織の秩序が乱れてしまったりするケースもあるでしょう。
さらに、クライアントとの信頼関係に影響する可能性もあります。企業のルールを無視した取引をする、クライアントに虚偽の報告をするなど、コンプライアンス上の問題が発生することにも注意しなければなりません。
3.適切な賃金を支給できない
経歴詐称した人を雇用すると、適切な賃金を支給できない可能性もあります。学歴や職歴を偽って実際よりも高く申告している場合、その人に見合わない賃金を支給してしまうことになります。
成果が出ていないのに高い賃金を支払い続けると、企業の経営状況に大きな影響を及ぼすため注意が必要です。他の従業員に知られることで、不満が発生したりモチベーションが低下したりするケースもあるでしょう。
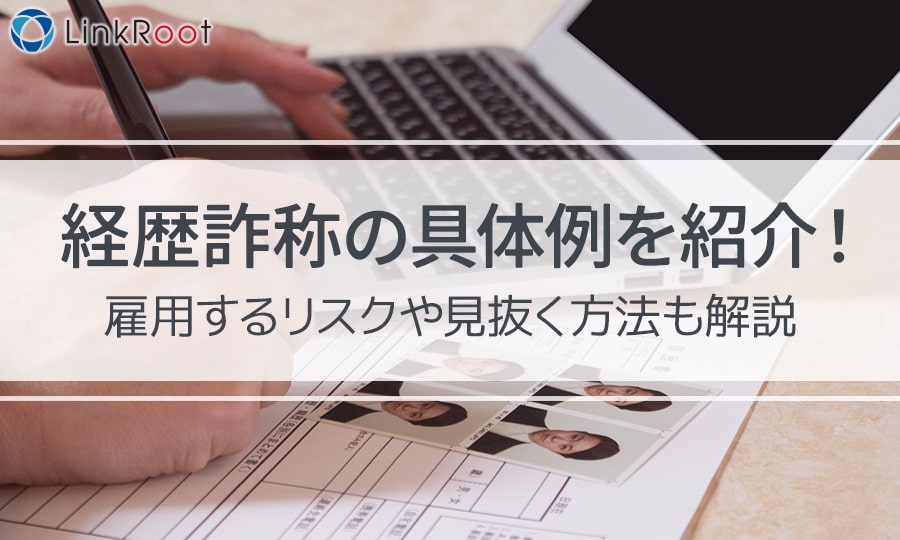
経歴詐称を理由に懲戒解雇することは可能?

経歴詐称をした人を雇用することには、企業にとってさまざまなリスクがあるため注意が必要です。ただし、経歴詐称が発覚したからといって、すべての場面で懲戒解雇できるわけではありません。懲戒解雇が認められるかどうかは、経歴詐称の内容や企業への影響などによって異なります。
以下、懲戒解雇できるケース・できないケースを紹介しますのでチェックしておきましょう。
懲戒解雇できる可能性が高いケース
経歴詐称の内容が重大で企業への影響が大きい場合や、詐称について事前に知っていたら採用しなかった場合などは、懲戒解雇が認められる可能性が高いでしょう。たとえば、高校卒業にもかかわらず大学卒業であると虚偽の申告をしたケースを考えてみます。学歴を考慮して給与額を決める企業の場合、高校卒業の従業員に対して、学歴に見合わない高い給与を支払うことになってしまいます。
そもそも大学卒業を条件としていた場合は、本来であれば採用しなかった候補者を雇用することになるなど、企業の円滑な運営に支障が出るため、懲戒解雇できる可能性は高いでしょう。
職歴詐称についても同様で、給与の決定や人材配置に重大な影響を与える場合は懲戒解雇が認められます。たとえば、実際よりも高いスキルや資格を保有していると虚偽の申告をしたケースを考えてみましょう。企業側は職歴や保有スキルを考慮して、重要な役割を与えたり、高い給与を支払ったりすることも考えられます。しかし実際にはパフォーマンスが上がらず、生産性や売上へ悪影響を与える可能性が高いため、懲戒解雇の対象となるでしょう。
懲戒解雇できない可能性が高いケース
同じような経歴詐称であっても、状況によっては懲戒解雇が認められないケースもあります。
たとえば、大学中退にもかかわらず大学卒業と虚偽の申告をしたとしても、そもそも採用条件に学歴不問と記載していた場合は、懲戒解雇が認められない場合もあります。事前に大学中退であることを知っていたとしても、採用した可能性があるからです。
また、面接時に学歴について質問しなかった、採用後の業務状況や勤務態度に問題がない、といった場合も懲戒解雇が認められないケースもあります。
経歴詐称を理由に懲戒処分するための要件
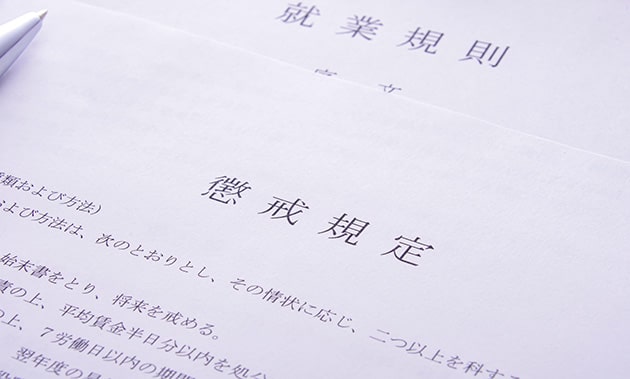
懲戒解雇は、懲戒処分のひとつです。懲戒処分は、従業員が規約や規律に違反した際に制裁として科す罰則を意味します。違反した従業員には自由に罰則を与えられると考えるかもしれませんが、懲戒処分を実施するためには一定の要件を満たさなければなりません。
それぞれの要件の詳細は以下のとおりです。
就業規則に懲戒処分に関する記載がある
懲戒処分を行う場合は、事前に内容を就業規則に記載し、従業員へ周知しておかなければなりません。就業規則には、懲戒処分の対象となる行為や、具体的な処分内容を記載しておきましょう。
経歴詐称により懲戒処分を行う場合は、「学歴や職歴などの重大な経歴について虚偽の申告をした場合は懲戒処分に処する」といった内容を記載しておく必要があります。
従業員数10人以下の企業の場合、就業規則の作成義務はありませんが、就業規則を作成していないと懲戒処分を実施できないため注意しましょう。
合理的な理由がある
懲戒処分が有効であると認められるためには、客観的に合理的な理由とその証拠が必要です。経歴詐称で懲戒処分する場合は、職場関係者からの事情聴取や書類の証拠などによって、詐称であるという事実を認定できなければなりません。
客観的に合理的な理由を欠いている場合は、懲戒処分が無効と判断されるケースもあるため注意しましょう。
社会通念上相当であると認められる
社会通念上相当であると認められることも、懲戒処分を実施するときの重要なポイントです。懲戒処分は従業員に大きな影響を与えるため、行為の内容と処分の重さが合っていなければ認められません。
経歴詐称の場合、詐称の内容が重大でないにもかかわらず、懲戒解雇という重い罰則を与えることはできないのです。
重大な経歴詐称とは、雇用する前にその詐称を知っていたら採用しなかった場合などを指します。ただし、実際に懲戒解雇が認められるかどうかは、企業の採用方針や詐称内容などをもとに個別具体的に判断されます。
適正な手続きが行われている
懲戒処分は、適正な手続きで行わなければなりません。手続きの流れについては、就業規則で定めておくのが一般的です。弁明の機会の付与や懲罰委員会の開催などを定めている場合は、規定に沿って手続きを進めましょう。
具体的な手順については次の項目で詳しく解説します。
経歴詐称により懲戒解雇するときの正しい手順

従業員を懲戒解雇するときは、事実関係の確認や弁明の機会の付与、解雇通知書の作成などを正しい手順で進めなければなりません。以下、具体的な流れを解説しますのでチェックしておきましょう。
事実関係を確認する
懲戒解雇を決定する前に、経歴詐称したという事実を確認しなければなりません。詐称内容を具体的に把握して、間違いがないか証拠を集めて判断する必要があります。事実確認をせず従業員を不当に解雇すると、あとで訴訟を起こされる可能性があるからです。
仮に裁判になったとしても懲戒解雇の正当な理由を立証できるよう、客観的な証拠を十分に確保しておきましょう。具体的には、大学の卒業証明書を提出させる、学校や前職の関係者にヒアリングする、年金記録と職歴を確認するなどの方法が挙げられます。
本人に弁明の機会を与える
事実を確認した結果、経歴詐称したことが明確になった場合は、従業員本人に弁明の機会を与えることが重要です。弁明の機会とは、本人の言い分や反論を聞く機会を意味します。
弁明の機会を与える際は、従業員へ弁明通知書を交付するケースもあります。弁明通知書とは、経歴詐称の事実や懲戒処分の内容を記載した書面のことです。従業員から弁明書を提出してもらうこともあります。弁明の機会を与えない場合、懲戒解雇が無効と判断される可能性もあるため注意しましょう。
懲戒処分を決定する
懲戒処分を決めるときは、経歴詐称の事実や弁明内容を含め、総合的に判断する必要があります。詐称内容や業務への影響に対して重すぎる処分を与えると、認められないケースもあるため注意しましょう。
懲戒解雇は最も重い処分です。状況に合わせて、出勤停止や減給などの処分を検討するようにしましょう。
解雇通知書を作成する
懲戒解雇することを決めた場合は、解雇通知書を作成して交付しなければなりません。懲戒解雇の効力は、その意思表示が従業員へ到達したときから発生します。
直接渡せない場合は、内容証明郵便などで送り、交付したことの証拠が残るように配慮しましょう。
経歴詐称による懲戒解雇を防ぐポイント
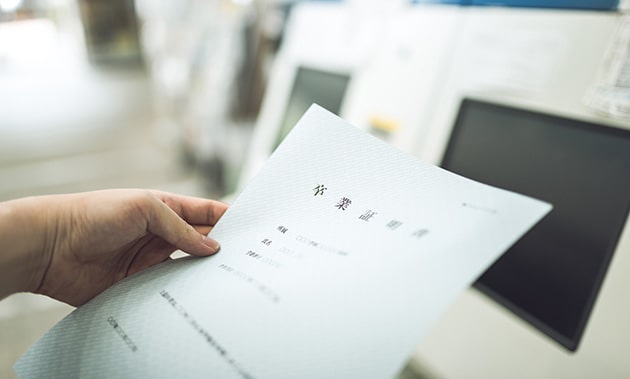
経歴詐称を防ぐためには、採用時の提出書類をしっかりとチェックする、面接時のヒアリングを丁寧に行う、リファレンスチェックを実施するなどのポイントに注意しましょう。
提出書類のチェックを徹底する
選考段階で必要な書類を提出してもらうことは、経歴詐称を防ぐ重要なポイントです。提出書類に関して絶対的なルールはありません。必要に応じて、履歴書に記載されている内容を証明できるような書類を提出してもらいましょう。
具体的には、卒業証書や資格の合格証明書などが挙げられます。
面接時のヒアリングを丁寧に行う
面接時に丁寧にヒアリングすることも大切です。前職での業務内容や成果、卒業論文の内容などを具体的に質問することで、経歴詐称があるかどうかを見抜くヒントを得られます。
気になる点がある場合は、深掘りして聞いてみましょう。
リファレンスチェックを実施する
リファレンスチェックを実施することも経歴詐称を見抜く重要なポイントです。リファレンスチェックとは採用候補者に対する身元照会のことで、前職の同僚や上司などから情報をヒアリングします。
人柄やコミュニケーションスキルなどを把握することが大きな目的ですが、そのなかで業務内容に関する詐称がないかも確認できるでしょう。

経歴詐称で懲戒解雇するときは要件に注意しよう!
今回は、経歴詐称を理由に懲戒解雇するときの要件や正しい手順について解説しました。経歴詐称が発覚した場合、すぐにでも懲戒解雇したいと考えるかもしれませんが、すべてのケースで解雇が認められるわけではありません。
懲戒解雇は従業員にとって最も重い処分であるため、合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合にのみ実施できます。また、事実関係を確認したうえで本人に弁明の機会を与えるなど、正しい手順に沿って進めることも覚えておきましょう。