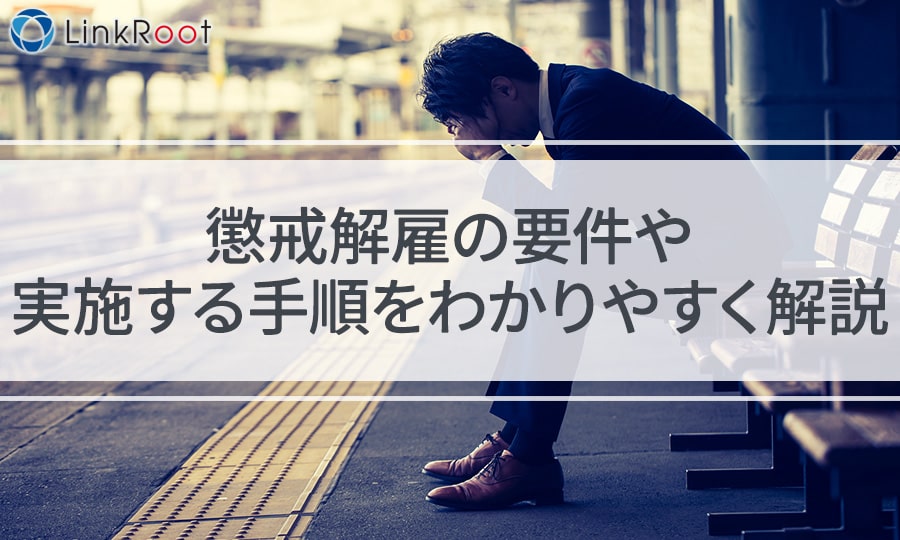従業員が就業規則に違反したり、犯罪行為に関わったりした場合、懲戒解雇を検討することもあるでしょう。しかし、懲戒解雇はいつでも実施できるわけではありません。懲戒解雇は従業員に大きな影響を与える処分であるため、ルールに従って進めることが必要です。
この記事では、懲戒解雇が認められる要件や、具体的な実施手順について詳しく解説します。法律に違反すると労使間のトラブルが発生したり、罰則を受けたりする可能性があるため、しっかりと理解しておきましょう。
懲戒解雇とは?

懲戒解雇とは、従業員が何らかの問題行動を起こしたことを理由として、雇用契約を解約することです。懲戒処分のひとつとして位置付けられ、従業員に対する制裁的な意味合いがあります。懲戒解雇を実施する場合は、事前に就業規則のなかに規定しておかなければなりません。
また、懲戒解雇は懲戒処分のなかで最も重い制裁であるため、犯罪行為に関わった場合や重大な経歴詐称が発覚した場合など、とくに大きな問題行動を起こした従業員に対して与えられます。懲戒解雇された従業員は再就職で不利になったり、会社のルールによっては退職金が不支給となったりするため、実施するかどうか慎重に判断しなければなりません。
懲戒解雇の要件を満たしていない場合は、解雇権の濫用として罰則を受けたり、処分が無効となったりするため注意が必要です。懲戒解雇の要件については後ほど詳しく解説します。
懲戒解雇以外の処分
懲戒解雇以外の懲戒処分としては、以下のようなものが挙げられます。
戒告:文書や口頭で注意を行うこと
譴責:厳重注意したうえで始末書を提出させること
減給:支払う賃金を減らすこと
出勤停止:一定期間の就労を禁止すること
降格:役職やポジションを下げること
諭旨解雇:話し合いにより従業員から退職届を提出させること
さまざまな処分がありますが、罰則の重さや従業員への影響は異なるため、違反行為の程度や悪質性に合わせて適した懲戒処分を与えることが重要です。なかでも懲戒解雇は最も重い処分であるため、簡単には実施できません。まずは軽い処分から実施して、状況が改善されない場合に懲戒解雇を検討するなど、正しいステップで行う必要があります。
懲戒解雇以外の解雇方法
懲戒解雇以外の解雇方法は以下の3つです。
- 普通解雇
- 整理解雇
- 諭旨解雇
普通解雇とは、整理解雇・諭旨解雇・懲戒解雇に該当しない解雇のことです。従業員の勤務態度が悪い、仕事を進めるための能力が不足している、といった場合に実施されます。懲戒解雇を実施するほどの重大な違反行為はないものの、何らかの問題がある場合に普通解雇を検討することになるでしょう。
整理解雇とは、経営上の理由によって雇用契約を解約することです。業績不振のために事業を縮小する場合や人件費の削減が必要な場合などに、整理解雇を行います。
諭旨解雇とは、懲戒解雇に該当するような大きなトラブルが発生した際、従業員と話し合い、納得してもらったうえで自主的に退職届を提出させることです。懲戒処分のひとつですが、懲戒解雇よりは軽い処分であり、従業員に対する恩赦的な対応といえるでしょう。
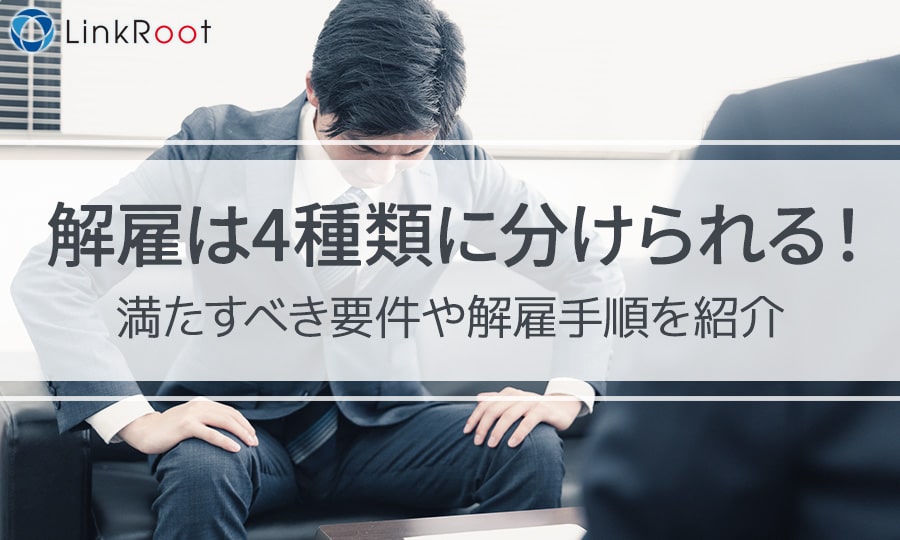
懲戒解雇を行うための要件
懲戒解雇を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 就業規則に規定がある
- 合理的な理由がある
- 社会通念上相当である
- 適正な手続きが行われている
要件を満たしていない場合は懲戒解雇が無効となるだけではなく、労使間のトラブルが発生したり、未払いの賃金を請求されたりするケースもあるため注意しましょう。それぞれの要件の詳細は以下のとおりです。
1.就業規則に規定がある
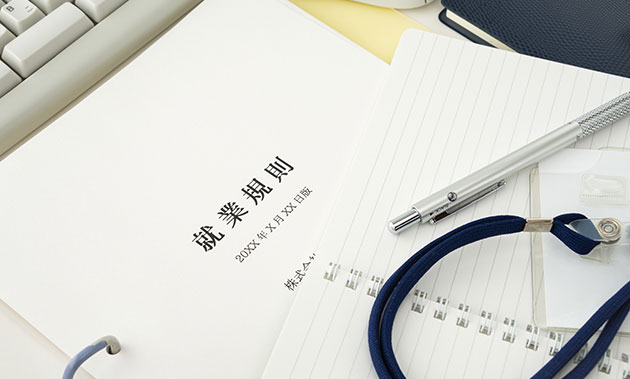
懲戒解雇については、就業規則のなかに記載しておく必要があります。懲戒解雇に関する内容は、就業規則に必ず記載すべき絶対的必要記載事項に該当するからです。(※1)普通解雇など、他の解雇についても同様に明記し、従業員へ周知しておきましょう。
就業規則に記載するときは、解雇の種類だけではなく、それぞれの解雇に該当する事由についても明記しなければなりません。仮に違反行為があったとしても、その行為が就業規則に記載されていない場合は、懲戒解雇が認められない可能性もあるため注意が必要です。
さらに、懲戒解雇の際に退職金を減額したり不支給としたりする場合は、その旨も記載しておく必要があります。明確なルールがないのに減額や不支給にすることは原則として認められないため、退職金制度を導入している場合は忘れずに記載しておきましょう。
(※1)厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
2.合理的な理由がある
懲戒解雇を行うためには、合理的な理由が必要です。労働契約法の第16条(※2)によると、客観的に合理的な理由がない場合、解雇は認められません。重大な経歴詐称が発覚した、注意を繰り返しても勤務態度が改善されないなど、合理的な理由がない場合は懲戒解雇を実施できないため注意しましょう。
(※2)e-GOV法令検索「労働契約法」第十六条(解雇)
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128#Mp-Ch_3-At_16
3.社会通念上相当である
労働契約法の第16条によると、懲戒解雇を実施することが社会通念上相当であることも必要です。懲戒解雇は従業員の生活へ大きな影響を与える処分であるため、違反行為とのバランスを考慮しながら慎重に検討しなければなりません。
遅刻を数回した、仕事において小さなミスをしたなど、軽度のトラブルに対して懲戒解雇という重い処分を与えることは難しいでしょう。社会通念上相当ではないと見なされると、解雇権の濫用として罰則を受けるケースもあるため注意が必要です。
4.適正な手続きが行われている
仮に違反行為が就業規則に記載された処分の事由に該当するとしても、適正な手続きが行われていないと、懲戒解雇が無効になる可能性もあります。たとえば、従業員側の言い分を聞く「弁明の機会」を与えずに、懲戒解雇することは避けましょう。
前述のとおり、いきなり懲戒解雇という重い処分を実施せず、注意や指導から始めることも重要です。また、就業規則のなかに「懲戒委員会を開く」などの手順を明記している場合は、その内容に従う必要があります。
懲戒解雇に該当する行為
従業員が犯罪行為やハラスメント行為に関わったり、重大な経歴詐称が発覚したりした場合は、懲戒解雇を検討することになるでしょう。ここでは、懲戒解雇に該当する行為について紹介します。
1.重大な経歴詐称が発覚した

重大な経歴詐称は、懲戒解雇に該当する行為のひとつです。たとえば、最終学歴を偽っていたり、経験していない仕事を面接でアピールしたりしたことが発覚した場合は、懲戒解雇の対象となるでしょう。
ただし、軽微な経歴詐称に対して懲戒解雇を実施することは、基本的に認められません。事前に嘘であることを知っていたら採用しなかった場合などは、懲戒解雇が認められやすいでしょう。
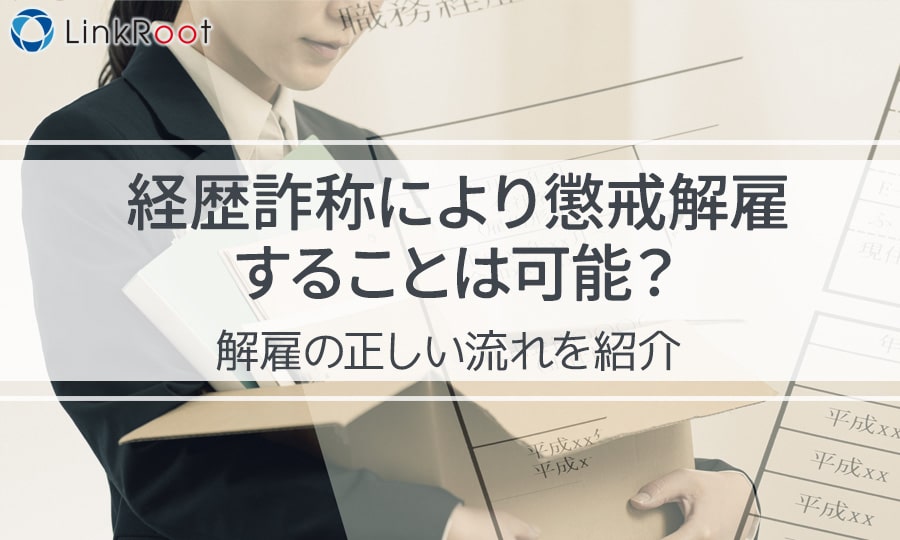
2.業務命令に従わなかった
従業員が業務命令に従わなかった場合、懲戒解雇を検討することになるでしょう。業務命令に従わない従業員がいると社内の秩序が乱れ、仕事がスムーズに進まなくなるため、厳しく対応することが大切です。
とはいえ、経歴詐称と同様、簡単に懲戒解雇を実施できるわけではありません。軽い業務命令違反の場合は、その内容に合わせて減給や出勤停止などの処分を検討することが必要です。繰り返し指導や注意をしても業務命令に従わない場合や、違反行為をしたことで会社に大きな損害を与えた場合などは、懲戒解雇が認められるでしょう。
3.犯罪行為に関わった
会社の資金を横領した、飲酒運転により交通事故を起こしたなど、犯罪行為に関わった場合は、懲戒解雇の対象となります。暴行・脅迫・窃盗・賭博・名誉毀損なども対象となるでしょう。放置しておくと、社内の環境が悪化するだけではなく、社会的なイメージが悪くなるため早急に対応することが重要です。
ただし業務外の犯罪行為は、基本的に懲戒解雇の対象外と判断されます。休日に自家用車による交通事故を起こした場合などは、業務と無関係であるため懲戒解雇は認められないでしょう。一方、犯罪行為が原因で会社の信用が失墜した場合などは、懲戒解雇の対象となります。
4.ハラスメント行為があった

パワハラやセクハラなども懲戒解雇に該当する行為です。ハラスメント行為が横行している職場では、従業員は安心して働くことができません。被害を受けた従業員や同僚から事実関係をヒアリングしたうえで、注意・指導を行ったり、懲戒解雇などの処分を検討したりしましょう。
5.正当な理由のない無断欠勤が多い
正当な理由のない遅刻や無断欠勤が多い場合も、懲戒解雇を検討することになるでしょう。無断欠勤を繰り返す従業員は、雇用契約に従って労務を提供していないことになるため、厳しく対応することが重要です。
ただし、数回の遅刻や欠勤を理由として懲戒解雇することは原則できません。注意や指導をしても無断欠勤が繰り返される場合などは、懲戒解雇の対象となります。
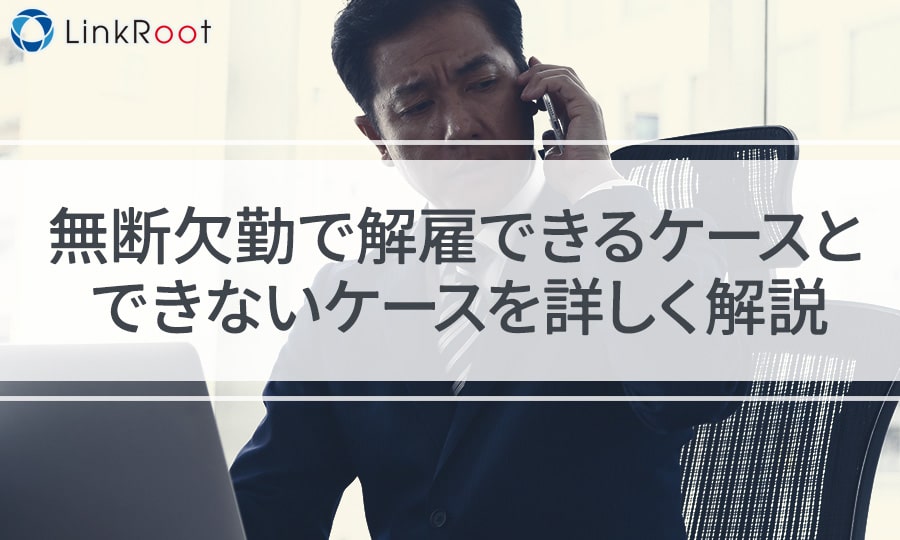
6.就業規則に違反した
就業規則に違反した場合も懲戒解雇の対象です。就業規則は会社が定めたルールであるため、従業員はその内容に従って業務を進める必要があります。就業規則違反を放置しておくと、社内の秩序が乱れるため、早急に対応しなければなりません。
懲戒解雇を行うときの手順
懲戒解雇を行うときは、以下のような手順で進めましょう。
1.注意や指導を行う

従業員が何らかの問題行動を起こした場合、懲戒処分を与える前に、注意や指導を行うことが大切です。処分を与えなくても、注意や指導によって従業員の行動が改善されるケースもあります。まずは上司や先輩など、普段から指導を担当している人から話をしましょう。
また、トラブルが大きくなりそうな場合は、口頭ではなく書面で注意を行い、注意したという記録を残しておくことも重要です。適切な注意を行ったという記録があれば、懲戒解雇が認められやすくなります。
2.軽い懲戒処分を検討する
懲戒処分を与える場合は、軽い処分から検討していきましょう。懲戒処分は、戒告・譴責・減給・出勤停止・降格の順に重くなっていきます。まずは戒告や譴責といった処分を与え、トラブルが解決しない場合は、減給や出勤停止などの重い処分を与えましょう。
懲戒解雇よりは軽いものの、減給・出勤停止・降格を実施すると従業員の収入が減るため、比較的重い処分といえます。違反行為の程度や悪質性と、処分の重さのバランスを考えながら、慎重に検討することが重要です。
3.退職勧奨を行う
さまざまな処分を行っても状況が改善されない場合や、会社に大きな損害を与えるような違反行為があった場合は、懲戒解雇を検討することになります。ただし、懲戒解雇の前に退職勧奨を行うとよいでしょう。
退職勧奨とは、従業員との話し合いを通して退職してもらうよう促し、同意を得たうえで退職届を提出してもらうことです。懲戒解雇という重い処分を避けられるため、会社はもちろん、従業員にとってもメリットがあります。とはいえ、退職届の提出を強制することはできないため注意しましょう。
4.弁明の機会を与える
従業員に対して「弁明の機会」を与えることも必要です。弁明の機会とは、従業員の言い分や反省を聞く場のことです。弁明の内容によっては、他の懲戒処分を検討したり、普通解雇に変更したりすることも検討しましょう。
5.解雇予告を行う
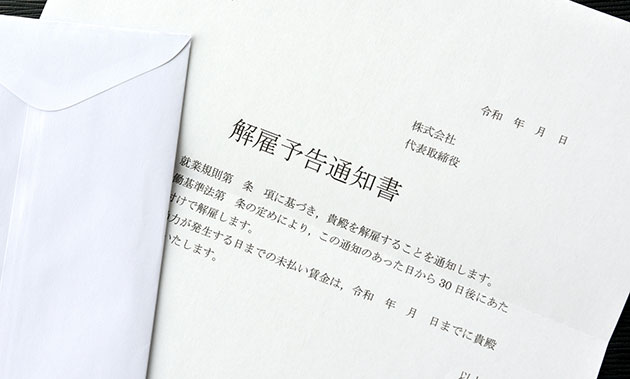
懲戒解雇を行うことを決定した場合は、従業員に対して解雇予告を行いましょう。懲戒解雇を含め、従業員を解雇する場合、労働基準法の第20条に従って30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければなりません。(※3)
解雇予告手当の金額は、30日分以上の平均賃金と定められています。違反行為に対する制裁的な処分であるとはいえ、従業員の不利益が大きくなりすぎないようにルールに従って解雇することが大切です。
(※3)e-GOV法令検索「労働基準法」第二十条(解雇の予告)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_2-At_20
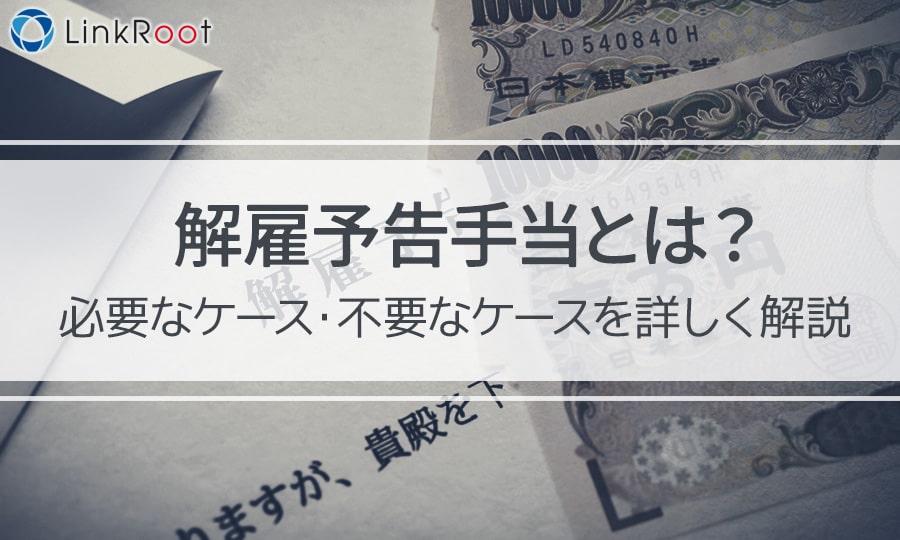
懲戒解雇の要件を把握したうえで正しく実施しよう!
今回は、懲戒解雇が認められる要件や、実施する手順について解説しました。懲戒解雇は、懲戒処分のなかで最も重い処分です。合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければ、処分が無効となるため注意しましょう。
また、懲戒処分については事前に就業規則に記載しておかなければなりません。懲戒処分を検討するときは、就業規則の内容を確認し、ルールに従って手続きを進めましょう。