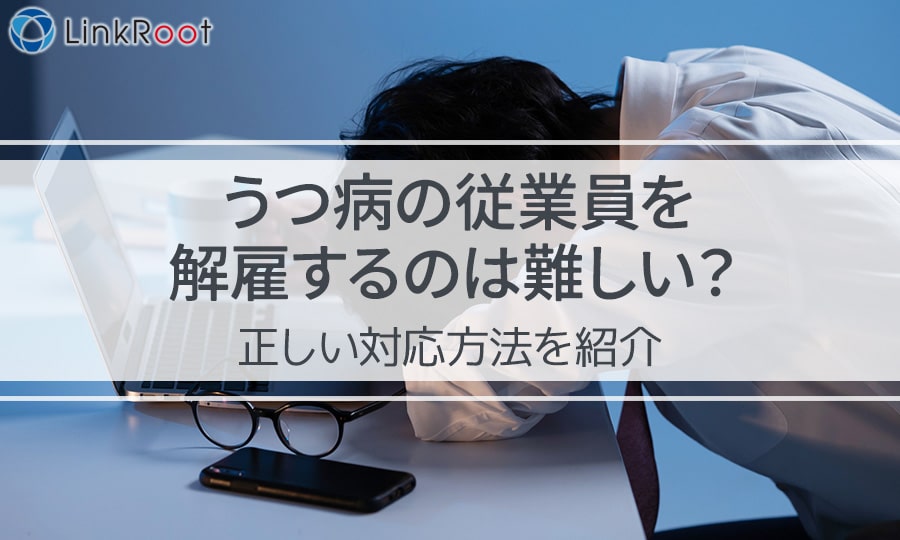うつ病が疑われる従業員がいる場合は、医師の診断を受けさせたり、必要に応じて休職させたりするなど、適切に対応しなければなりません。病気でパフォーマンスが下がっているからといって、すぐに解雇することはできないため注意しましょう。
この記事では、うつ病の従業員を解雇するときの正しい方法や注意点について解説します。間違った対応をすると不当解雇として訴えられる可能性もあるため、正しい対応手順を理解しておくことが大切です。
うつ病の従業員を解雇するのは難しい

従業員がうつ病になると、担当していた業務が進まなくなったり、休職していても人件費がかかったりするため、解雇したいと考えることもあるでしょう。しかし、従業員がうつ病で働けない状態だからといって、簡単に解雇することはできません。
労働契約法の第16条には、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇という処分が無効となることが記載されています。(※1)
従業員がうつ病になったことは、客観的に合理的な理由としては認められにくく、処分が無効となる可能性が高いでしょう。解雇は従業員に対する重い処分であるため、うつ病の場合に限らず、法律によって厳しく制限されているのです。
(※1)e-GOV法令検索「労働契約法」第十六条(解雇)
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128#Mp-Ch_3-At_1
不当解雇に要注意
うつ病を理由として無理に解雇を実行すると、不当解雇と見なされる可能性があります。不当解雇とは、労働基準法や労働契約法などで定められたルールを無視して、会社側の都合で一方的に雇用契約を解約することです。たとえば、国籍や性別を理由として解雇することや、産前産後休業中に解雇することなどは、不当解雇に該当します。
不当解雇と見なされると、処分が無効となり従業員が職場に戻ってくるだけではなく、裁判にまで発展したり、未払いの賃金や慰謝料を請求されたりするケースもあります。不当解雇に該当するかどうかは、うつ病になった原因や職場の状況などをもとに総合的に判断されるため、慎重に対応することが重要です。
うつ病の従業員を放置するリスク
解雇できないからといって、うつ病の従業員を放置したり、そのまま働かせたりすることは避けましょう。無理に働かせると、病状が悪化してしまう可能性もあります。会社が安全配慮義務に違反していると判断されるケースもあるため、医師の指示に従って休業させるなど、適切な対応を行いましょう。
また、他の従業員に対する配慮も必要です。うつ病で働けない従業員がいると、他の従業員の負担が増えてしまいます。その結果、残業や休日出勤が増えてしまい、体調不良や精神疾患で休む従業員が連鎖的に出てきてしまう可能性もあるでしょう。うつ病の従業員をしっかり休ませるだけではなく、業務を再配分したり、新しい人材を確保したりすることも重要です。
打切補償による解雇
ここまで、うつ病を理由とした解雇が難しいことを解説しましたが、まったく解雇が認められないわけではありません。たとえば、病気の治療が3年以上続いている場合は、1200日分の平均賃金を支払うことで解雇することが可能です。このような処置は労働基準法の第81条に規定されており、打切補償と呼ばれます。(※2)
そもそも業務上の理由で怪我をしたり病気になったりした場合は、同法第75条に従って、会社側が費用を負担しなければなりません。(※3)第81条の規定は、治療開始から3年が経過した場合、この費用負担を打ち切れることを示しており、一般的には解雇も認められます。
そのほか、うつ病の従業員に退職してもらう方法については後述しますので、参考にしてください。
(※2)e-GOV法令検索「労働基準法」第八十一条(打切補償)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_8-At_81
(※3)e-GOV法令検索「労働基準法」第七十五条(療養補償)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_8-At_75
うつ病の従業員を解雇することが認められないケース
従業員がうつ病で働けない状態であっても、次のようなケースにおいては解雇することが認められません。
- うつ病の原因が会社にある場合
- 復職可能な場合
- 別の部署でなら働ける場合
- 休職期間が残っている場合
それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。
1.うつ病の原因が会社にある場合
うつ病の原因が会社にある場合は、従業員を解雇することはできません。労働基準法の第19条には、業務上の理由により怪我や病気をした場合は、治療のための休業期間中とその後の30日間は解雇ができないと記載されています。つまり、業務上の理由でうつ病を発症したときは、従業員が回復するまで一定期間待たなければなりません。
うつ病の原因としては、過剰な残業、職場における人間関係、ハラスメントなどが挙げられます。問題を放置しておくと、うつ病になる従業員が増える可能性もあるため、早急に原因を把握して適切な対策を講じることも大切です。
2.復職可能な場合
うつ病を発症したとしても復職可能な状況であり、従業員本人が復職を希望している場合、解雇することは認められません。復職が可能かどうかは、基本的に医師の診断に従って判断する必要があります。医師が作成する診断書に復職可能と記載されている場合は、原則として復職を認めなければなりません。
無理に解雇したり自然退職という扱いにしたりすると、トラブルに発展するため絶対に避けましょう。ただし、医師の診断に疑問を感じるときは、別の医師に状況を説明して意見を聞いてみることも必要です。また、本当に復職できるのか試す期間を設けることや、必要に応じて業務を調整することも検討しましょう。
3.別の部署でなら働ける場合
うつ病の従業員が復職した際に、休職前と同じような能力を発揮できなかったとしても、簡単に解雇することはできません。負担の少ない別の仕事がある場合や、別の部署に異動できる場合は、継続して雇用することが求められます。
人事異動や業務の再配分などの配慮をすれば継続して働けるという場合は、解雇が認められない可能性が高いため注意しましょう。
4.休職期間が残っている場合
休職期間が残っている場合も従業員を解雇することはできません。会社の就業規則のなかに休職制度を設けているときは、正しい期間や期間満了時の扱いを把握しておきましょう。
「休職期間満了時に復職できない場合は退職となる」といった規定がある場合は、就業規則に従って退職してもらうことが可能です。ただし、基本的に休職期間の途中で解雇することはできず、期間中は治療に専念させ、回復を待つ必要があります。
休職制度の有無や期間の設定は、企業によって異なります。就業規則で決められた計算方法を把握しておらず、本来よりも短い休職期間を与えてしまうというケースもあるため、ルールをしっかりと確認しておきましょう。
うつ病の従業員に退職してもらう方法

うつ病の従業員を退職させる方法としては、退職勧奨、自然退職、普通解雇が挙げられます。以下、それぞれの方法について詳しく解説しますのでチェックしておきましょう。
1.退職勧奨
退職勧奨とは、会社側と従業員で話し合いを行い、納得してもらったうえで自主的に退職届を提出してもらうことです。退職することへの合意が得られるため、トラブルを防止しやすいというメリットがあります。また、退職届の提出を促す行為であるため、会社側から一方的に雇用契約を解約する解雇とは異なり、法律による厳しい制限はありません。
ただし、退職届を提出するように必要以上の心理的圧力を加えたり、名誉感情を害するような態度を取ったりすると、違法と見なされる可能性があります。うつ病で働けない事実を双方で確認し、転職や休養を検討させるなど、丁寧な対応を心がけましょう。
退職勧奨を行う場合はプライバシーに配慮し、会議室などの場所を確保することが大切です。話し合いのなかでは、病気の現状や退職するメリット、退職金の有無などについて説明し、退職届の提出を促します。
2.自然退職
うつ病の原因が会社にない場合は、休職期間満了後に自然退職させることが可能です。まずは就業規則に従って休職させる必要がありますが、休職期間が満了しても復職できない場合は退職させることができます。ただし、「休職期間満了時に復職できない場合は退職扱いとなる(または解雇する)」といった規定を設けておくことが重要です。
また前述のとおり、うつ病の原因が会社にある場合、休職期間はもちろん、満了後の30日間も解雇ができないため注意しましょう。
3.普通解雇
退職勧奨に応じてもらえない場合や、就業規則に規定がなく自然退職が難しい場合は、普通解雇を検討することになります。ただし、普通解雇は従業員に対する重い処分であるため、うつ病で働けない状態であっても簡単に認められるわけではありません。
従業員がうつ病になった原因が会社側にないか、解雇が禁止されている期間に該当しないかなど、さまざまな観点から慎重に検討することが必要です。トラブルを防止するためにも、判断に悩む場合は無理に解雇せず、弁護士などに相談するとよいでしょう。
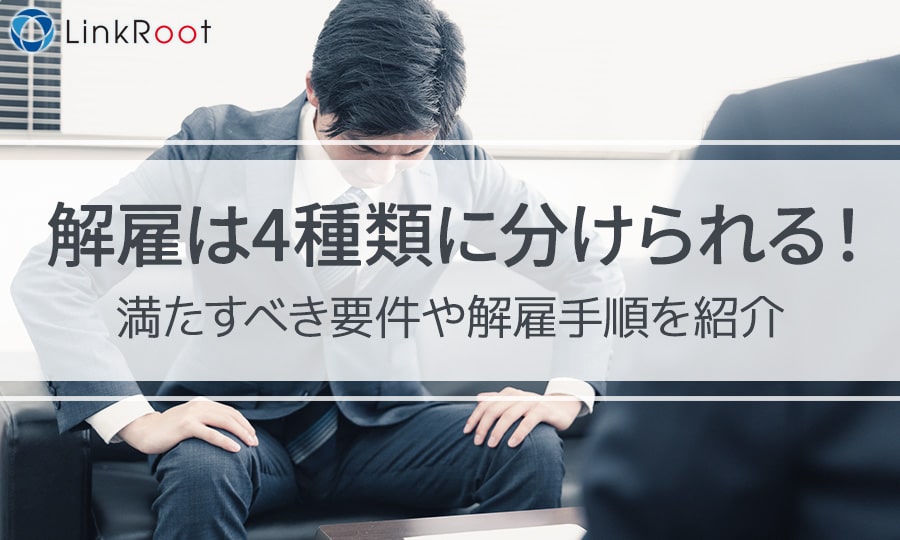
うつ病の従業員への正しい対応方法

ここまで解説したとおり、うつ病の従業員をすぐに解雇することは避け、診断書を提出してもらう、休職させるなど、状況に応じて適切な対応を行うことが大切です。
以下、正しい対応方法を紹介しますので、トラブルを防止するためにも確認しておきましょう。
1.診断書を提出してもらう
仕事中の集中力が低下している、遅刻や欠勤が増えているなど、うつ病が疑われる場合は、医師の診察を受けさせ診断書を提出してもらいましょう。放置しておくと症状が悪化する可能性もあるため、できるだけ早めに対応する必要があります。
ただし、うつ病かどうかを判断するのは、あくまでも医師です。うつ病だと決めつけるような発言は避け、仕事に対する具体的な影響を伝えて受診を促すようにしましょう。今後の対応を検討するため、医師が作成する診断書を提出してもらうことも重要です。
2.業務の再配分を検討する
仮にうつ病ではないという診断であっても、過剰な残業や長時間労働が発生している場合は、業務の再配分や人員の確保を検討しましょう。うつ病ではないとしても、集中力が低下していたり、体調不良による遅刻や欠勤が多かったりすると業務の効率が低下してしまいます。
また、他の従業員も同じような不調を感じているかもしれません。今後、うつ病を発症する従業員が出てくる可能性もあるため、職場環境を見直すことが大切です。
3.必要に応じて休職させる
「うつ病であるため自宅療養が必要である」などの診断が下された場合は、すぐに従業員を休職させましょう。ただし、無理やり休ませると従業員が負い目を感じる可能性もあるため、話し合いを通して納得してもらったうえで、休職を申し出てもらうのがおすすめです。
休職制度を利用するときは、就業規則の内容を確認し、休職可能な期間や休職中の給与などについて丁寧に説明しましょう。健康保険による傷病手当など、従業員が利用できる制度について説明することも大切です。
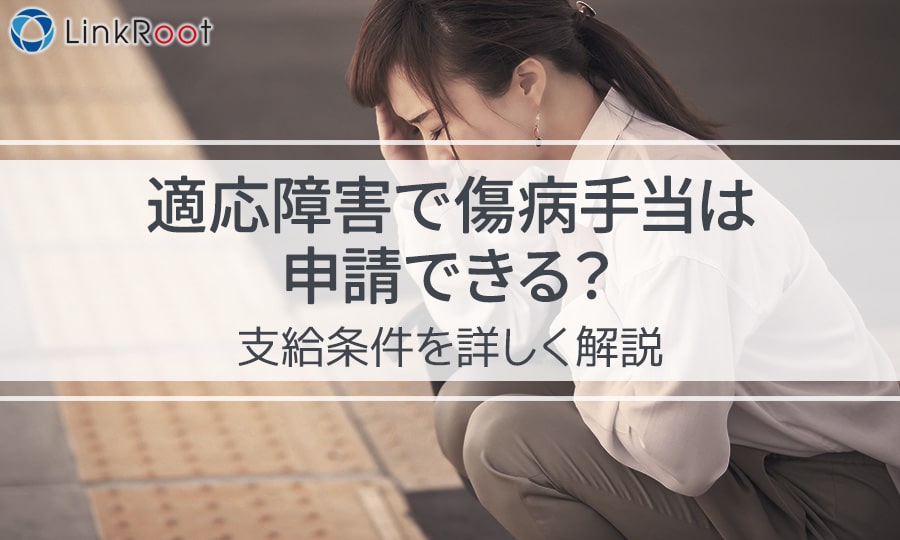
4.復職の可否を判断する

休職期間が満了したら、復職が可能かどうかを判断します。働ける状態まで回復したかどうかの判断は難しいため、基本的には医師の指示に従いましょう。
前述のとおり、医師が復職可能と判断し、従業員本人が復職を希望している場合、解雇することはできません。必要に応じて業務量を減らしたり、部署異動を検討したりして、復職できる状態を整える必要があります。
5.退職勧奨を検討する
うつ病の従業員を復職させることが難しい場合は、何らかの方法で退職させることになります。できる限り解雇することは避け、まずは退職勧奨を検討するとよいでしょう。話し合いを通して、継続して働くことが難しいと納得してもらい、退職届の提出を促します。
退職勧奨に応じてもらえない場合は、休職期間満了による自然退職や普通解雇を検討しましょう。無理な解雇を行うとトラブルにつながるため、判断に悩む場合は弁護士などに相談することも大切です。
うつ病の従業員を簡単に解雇することはできない!
今回は、うつ病の従業員を解雇するときの注意点や具体的な方法について解説しました。従業員がうつ病で働けない状況だからといって、簡単に解雇することはできません。とくにうつ病の原因が会社側にあるときは、不当解雇と見なされるため注意しましょう。
うつ病が疑われる従業員がいるときは、まずは医師の診断を受けさせることが重要です。医師が作成した診断書を提出してもらい、休職や業務調整の必要があるのかなど、今後の対応を慎重に検討しましょう。