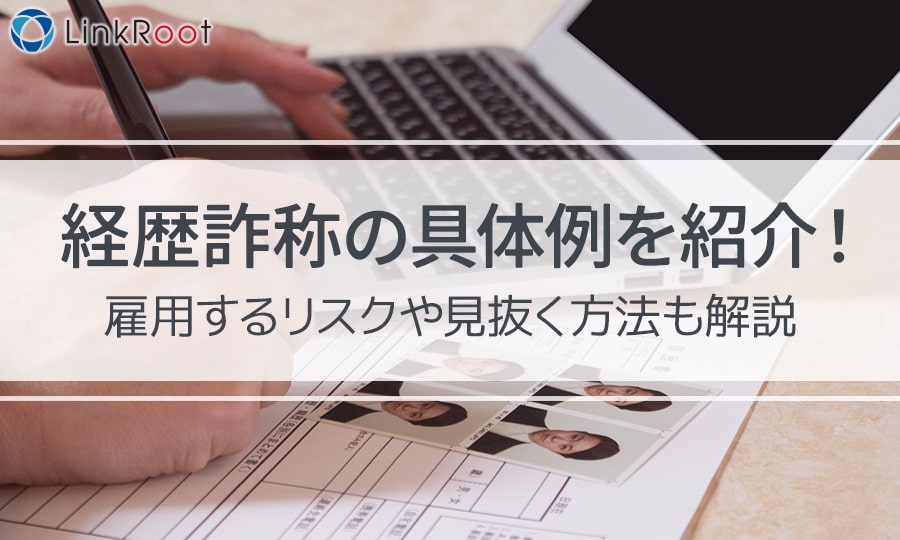企業が求人募集を出した際、一般的に面接や履歴書、職務経歴書に基づいて採用候補者のスキルや経歴を判断します。本来であれば、採用候補者が適切に履歴書や職務経歴書を作成するべきです。しかし、採用候補者によっては履歴書や職務経歴書を詐称するケースがあります。
採用候補者の経歴詐称に気付かずに採用してしまうと、さまざまなトラブルになりかねません。そのため、経歴詐称の例や見抜く方法を把握しておきましょう。この記事では経歴詐称の具体例や雇用するリスク、見抜く方法などを解説します。
経歴詐称の7つの具体例
自社で採用しようとしている採用候補者が経歴詐称していないかどうかを見抜くには、事前に詐称の具体例を把握しておきましょう。詐称の内容によっては支払う給与にも影響してきます。
ここでは次の7つの経歴詐称の具体例を解説します。
- 学歴を偽る
- 雇用形態を偽る
- 在籍していた期間を偽る
- 転職回数を偽る
- 年収を偽る
- 前職の役職を偽る
- 免許や資格を偽る
学歴を偽る
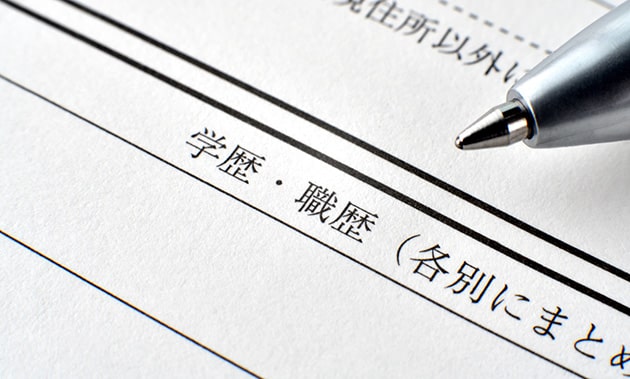
経歴詐称の代表例として学歴を偽るケースが挙げられます。例えば次のような学歴詐称が考えられます。
- 最終学歴が高校卒業にも関わらず大学卒業と詐称する
- 浪人・留年したにも関わらず卒業年を詐称する
- 卒業した学校名を詐称する
高学歴を装うことで面接官の印象を良くしようと、経歴を詐称してしまいます。学歴は収入にも影響を及ぼします。厚生労働省が発表した『令和4年賃金構造基本統計調査』によれば、学歴によって次のような収入が異なります。
| 最終学歴 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 高校 | 27万3,800円 | 29万7,500円 | 22万2,900円 |
| 専門学校 | 29万4,200円 | 31万6,000円 | 26万9,400円 |
| 高専・短大 | 29万2,500円 | 34万8,300円 | 26万9,300円 |
| 大学 | 36万2,800円 | 39万2,100円 | 29万4,000円 |
| 大学院 | 46万4,200円 | 47万8,400円 | 40万4,300円 |
最終学歴が高校卒業の場合、男女合計の月収は平均27万3,800円なのに対して、大学卒業の場合は男女合計の月収は36万2,800円と約9万円も差がありました。(※1)
このように学歴によって収入に大きな差が発生する可能性があるため、収入を上げようと学歴を偽るケースもあるでしょう。
(※1)厚生労働省:令和4年賃金構造基本統計調査https://drive.google.com/drive/folders/1sabY_qcM78Aryq_m0CEAUPT57ChNvqRg
雇用形態を偽る
企業に勤務していたとしても、雇用形態はさまざまです。正社員として雇用されている人もいれば、契約社員として雇用されている人もいます。転職活動している人のなかには、雇用形態を偽ろうとする人がいます。例えば契約社員として勤務していたのに、職務経歴書には正社員とするケースが挙げられます。
雇用形態は学歴と同じく収入に影響を及ぼす要素のひとつです。『令和4年賃金構造基本統計調査』によれば次のとおり雇用形態によって収入は異なります。
| 雇用形態 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 正社員・正職員 | 32万8,000円 | 35万3,600円 | 27万6,400円 |
| 正社員・正職員以外 | 22万1,300円 | 24万7,500円 | 19万8,900円 |
正社員・正職員以外の男女合計の収入は22万1,300円なのに対して、正社員・正職員の男女合計は32万8,000円でした。約10万円もの差が出ています。(※1)
正社員として雇用されていたと経歴を詐称することで、転職先でも高い収入が期待できるため、職務経歴書を偽ってしまう人もいるでしょう。
在籍していた期間を偽る
前職に在籍していた年数を偽る人もいます。在籍していた期間が短いと、面接官から何かしらのトラブルがあったのか、就職しても長続きしないのかなどと思われてしまう可能性があります。
そのため、在籍していた期間は短かったとしても何年も在籍していたかのように偽る人もいるでしょう。
転職回数を偽る
最近は転職をキャリアアップの一環として捉える傾向があるものの、あまりに転職回数が多いと内定が難しくなります。転職回数が多いと就職先に長く在籍していなかったともいえるため、面接官から難色を示されるでしょう。
このようなリスクを軽減しようと転職回数を偽ってしまいます。
年収を偽る
転職する際、収入をはじめとした条件は前職と同等、もしくはそれ以上を提示されるケースがあります。そのため、年収を高く偽ることで前職よりも収入を高められます。
年収を偽るケースでは毎月の固定給を偽るだけでなく、ボーナスの額や有無を詐称するケースもあるでしょう。
前職の役職を偽る

転職にあたって自身が前職で担っていた役職を偽るケースがあります。例えば、マネジメント経験がないのにマネージャー職を担っていたと経歴を詐称するといった事例が挙げられます。
求人内容によっては、マネージャー経験者に限るといったように応募者を限定しているケースがあります。このような求人であっても、採用されるために前職の役職を偽ってしまいます。
役職も当然、収入に影響を及ぼす要素です。『令和4年賃金構造基本統計調査』では次のとおり役職ごとの平均収入を発表しています。
| 役職 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 部長級 | 58万6,200円 | 59万3,100円 | 52万100円 |
| 課長級 | 48万6,900円 | 49万5,600円 | 43万5,000円 |
| 係長級 | 36万9,000円 | 37万9,100円 | 33万7,600円 |
| 非役職 | 28万1,600円 | 30万1,000円 | 25万3,200円 |
非役職者の男女合計の平均収入は28万円ほどです。一方、部長級になると30万円も収入が増加します。部長級でなく係長級であっても非役職者よりも8万円も収入が増えます。(※1)
転職先からよく見られたいという思いだけでなく、収入を増やしたいという思いから経歴を詐称する人もいるでしょう。
免許や資格を偽る
企業にとっては採用候補者がどのような免許、資格を持っているかは採用にあたっての大きな要素です。業種によっては、免許や資格を持っていることを応募要件として定めていることもあるでしょう。
採用候補者のなかには自分を良く見せようと、取得していない免許や資格を持っていると偽る可能性があります。
経歴詐称している人を雇用する3つのリスク
職歴や学歴を詐称している人を雇用してしまうと、次のようなリスクにつながりかねません。
- 期待したスキルを発揮できない
- 企業の秩序が崩れる
- コンプライアンスに反する行動を取られる
それぞれのリスクについて解説します。
期待したスキルを発揮できない
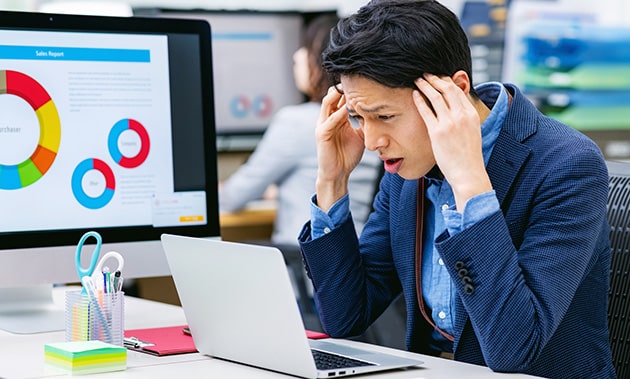
履歴書や職務経歴書を鵜呑みして経歴詐称している人を雇用してしまうと、期待したスキルを発揮してもらえない可能性があります。
例えば、マネージメント経験があると詐称していた人にマネージャーとしてのスキルを期待しても、能力を発揮できないでしょう。期待したスキルを発揮できなければ、新たに従業員を採用する必要があり、採用にかかるコストがかさんでしまいます。
企業の秩序が崩れる
経歴を詐称している人を採用してしまうと、企業の秩序が乱れる原因になります。ほかの従業員が経歴を詐称したにも関わらず採用された従業員がいると知ってしまうと、モチベーションや会社への帰属意識が低下しかねません。
モチベーションや帰属意識の低下は企業の秩序の乱れにつながるでしょう。企業の秩序が崩れてしまうと、レギュレーションが守られないなど、自社の売上低下につながりかねない結果になってしまいます。
コンプライアンスに反する行動を取られる
経歴を詐称する人は入社後の行動も懸念されます。例えば社内で定めたルールを守らず、コンプライアンスに反する行動を取ってしまうかもしれません。
また、経歴を詐称している従業員を雇用し続けるということは、社外から経歴詐称を容認していると捉えられかねません。その結果、取引先の信用が低下してしまう恐れがあります。
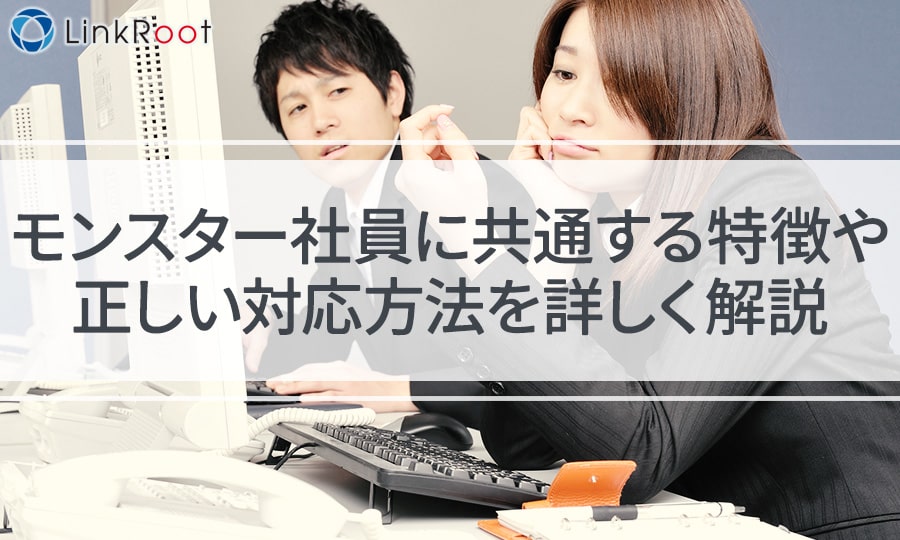
経歴詐称を見抜く4つのポイント
経歴詐称をしていないか、見抜く際のポイントは次のとおりです。
- 資料を提出してもらう
- 面接で質問する
- リファレンスチェックを実施する
- バックグラウンドチェックを依頼する
履歴書や職務経歴書をみて疑わしい人にのみ実施するのではなく、採用候補者全員を対象に実施しましょう。
資料を提出してもらう

大学の卒業証書や取得した免許の証書など、客観的に事実であると判断できる資料を提出してもらいましょう。例えば次のような資料が学歴、スキルなどの証明として機能します。
- 学歴:卒業証書
- スキル:認定証、各種合格証明書
資料は採用候補者が自発的に持参することは少ないでしょう。そのため、募集要項などに資料を持参してもらう旨を記載しましょう。資料の提出を事前に募集要項に記載しておけば、経歴詐称の防止にもつながります。
面接で質問する
資料の提出に加えて面接の際に経歴について質問することも効果的です。特に職歴やスキルによっては資料の提出が難しいケースがあります。例えばマネジメント経験についての証明書を提出するのは困難でしょう。
そのため、面接時にマネジメントで苦労したことや、心がけていることなどを質問すれば、実際に経験しているのかどうかを判断できます。
リファレンスチェックを実施する

リファレンスチェックとは、採用候補者と一緒に働いたことのある人物(主に前職の上司や同僚)から聞き取りを行う調査方法です。候補者の働きぶりや人物像など、履歴書や職務経歴書、面接では知りえない情報を取得することで採用ミスマッチや早期離職といったリスクを軽減できます。
リファレンスチェックを依頼する第三者を「推薦者」とし、協力してもらうには採用候補者(採用候補者)と推薦者双方の合意が必要です。
推薦者の選定は採用候補者自身、または企業が探すかのどちらかです。企業が推薦者を探す場合、事前に採用候補者の承諾を得たあと、候補者の現職または前職の会社に直接連絡して選定するのが一般的です。企業によってはSNSなどのWebサービスを利用して探す場合もあります。
リファレンスチェックでは、応募書類や面接での申請内容について改めて推薦者に確認することで、経歴や実績、スキルに虚偽や誇張がないかを確認できます。

バックグラウンドチェックを依頼する
バックグラウンドチェックとは、候補者の経歴や実績を調査し、虚偽や不祥事(犯罪例など)がないか確認することです。企業の採用担当者が直接行うことはほとんどなく、探偵や調査会社に依頼するのが一般的です。
経歴や実績、勤務態度のほか、反社会的勢力との関係がないか、破産歴や民事訴訟歴はないか、過去にSNSやインターネット掲示板で不適切な発言や行為をしていないかなど、リファレンスチェックではカバーできない調査も可能です。
バックグラウンドチェック、リファレンスチェックともに、採用候補者の個人情報を取り扱う調査です。プライバシー保護のためにも徹底した情報管理が求められます。候補者の承諾を得ない調査や情報漏洩は個人情報保護法などの法律に抵触し、企業の信用問題にも関わります。
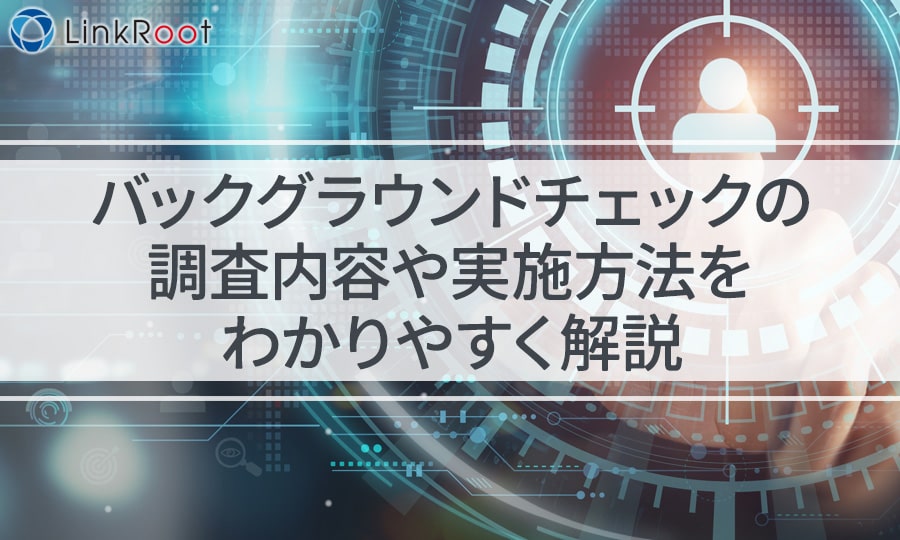
経歴詐称を理由に処分はできる?

採用候補者や採用した従業員が経歴詐称していた場合、状況によって処分は可能です。例えば経歴を詐称していなかったのであれば採用していなかったというケースでは、経歴詐称を理由にした処分が認められるでしょう。
懲戒処分できる経歴詐称のケースを解説
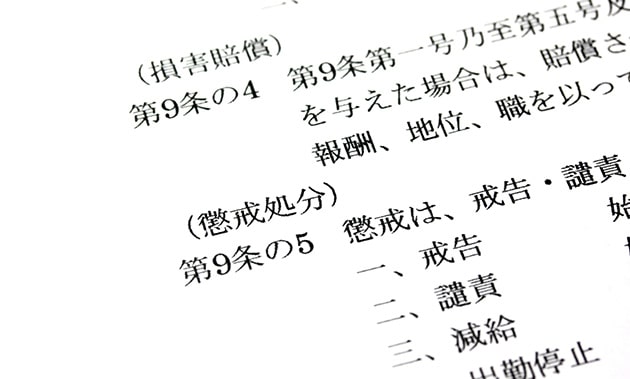
経歴詐称を理由に懲戒処分できるケースとして以下が挙げられます。
- 学歴を詐称していた
- 犯罪歴を詐称していた
- 職歴を詐称していた
学歴を詐称していた
学歴を詐称していたことを理由に、懲戒処分が認められる可能性があります。企業の中には学歴を重視するところもあるため、つい学歴を詐称していたという従業員もいるでしょう。
特に最終学歴は給与にも影響する要素であるため、詐称していると本来よりも多くの給与を支払っていたことになります。例えば募集条件を大学卒業者としていたにも関わらず、経歴を詐称して応募、入社した従業員は懲戒処分の対象となり得るでしょう。
しかし、募集要項に学歴不問と記載していた、学歴について記載していなかったという場合、学歴詐称を理由に懲戒処分をするのは認められない可能性があります。
犯罪歴を詐称していた
履歴書によっては賞罰欄が設けられています。犯罪歴がある場合、賞罰欄に記載が必要です。犯罪歴を詐称していた場合、企業のコンプライアンスや業務に影響を及ぼしかねないため、懲戒処分の対象になり得るでしょう。
しかし、終了した執行猶予をはじめとして、効力が消滅ししている前科や前歴については記載は不要です。
職歴を詐称していた
職歴の詐称も入社後のパフォーマンスに影響するため、重たい懲戒処分が可能になるでしょう。例えば前職の職歴を期待して採用したにも関わらず、職歴が嘘であれば期待した働き方をしてもらえません。
なお、募集要項で職歴不問などと記載していた場合は懲戒処分が認められない可能性があるでしょう。
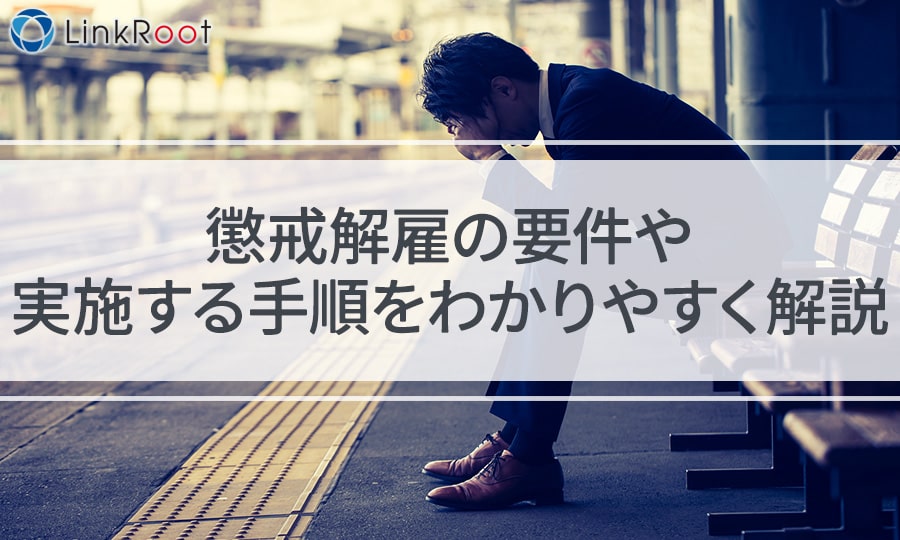
内定取り消しは慎重に検討する

経歴詐称した採用候補者に内定を出してしまった場合、必ずしも取り消しできるわけではありません。内定取り消しが認められるのは、客観的にみても取り消しが妥当で社会通念上においても相当と認められるケースのみです。
そのため、ケースによっては内定取り消しができない可能性もあります。内定取り消しをするかどうかは、弁護士や社会保険労務士など専門家の意見を参考にしてみましょう。
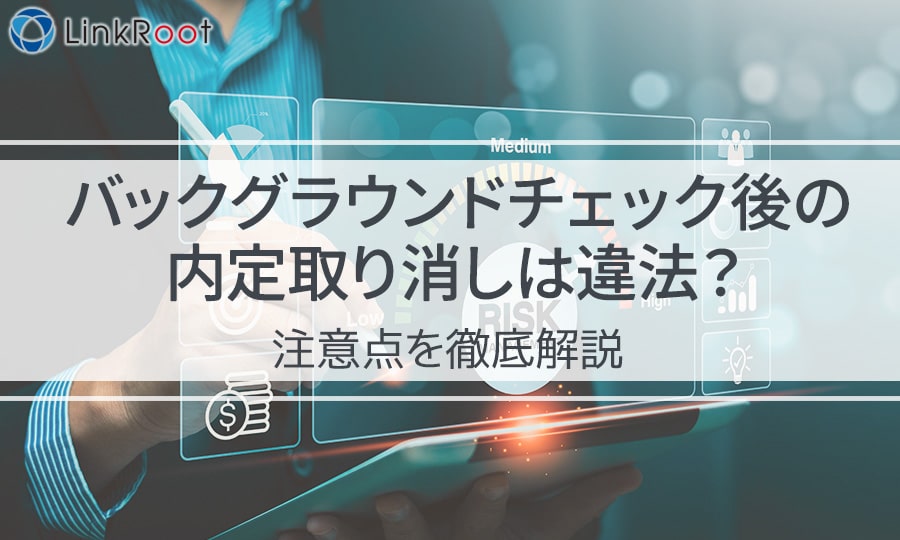
経歴詐称を見抜くにはリファレンスチェックが有効
求人に応募してきた採用候補者のなかには、学歴や職歴、保有資格などを偽っているケースがあります。経歴を詐称している人を採用してしまうと社内の秩序が乱れる、期待していたスキルを発揮してくれないなどのデメリットにつながります。
リファレンスチェックで候補者の経歴や実績に偽りがないかを確認できれば、雇用の際のリスクヘッジにつながります。
リファレンスチェックサービスやツールを利用すれば、採用候補者のデータを一元管理し、採用担当の業務負荷を軽減できます。