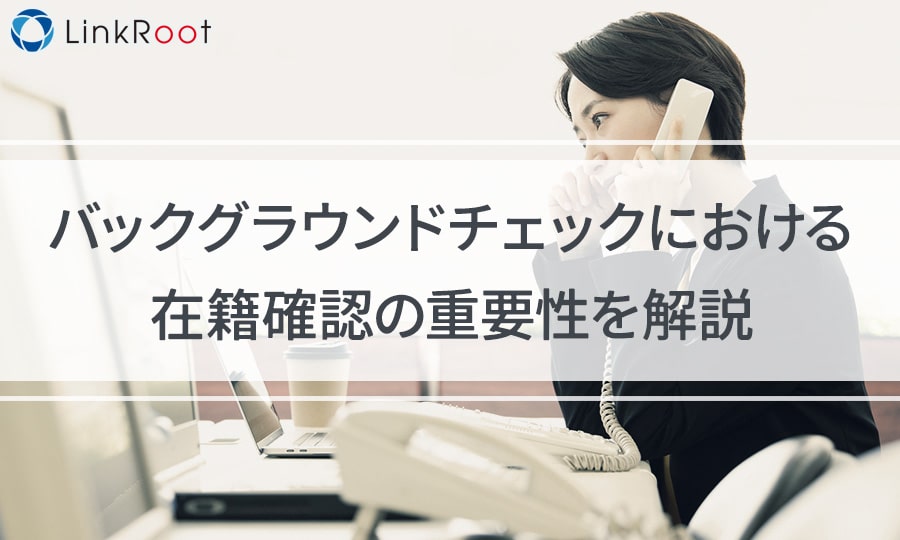優秀な人材を確保することや、コンプライアンス上のリスクを回避することを目的として、バックグラウンドチェックや在籍確認を行う企業が増えてきました。適切なタイミングで調査を行うことで、経歴詐称を見抜き、自社が求める人材を採用することができます。
この記事では、バックグラウンドチェックにおける在籍確認の重要性や、調査の実施手順などを解説します。調査を行う際の注意点についても解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
バックグラウンドチェックとは?
バックグラウンドチェックとは、採用候補者が自己申告した経歴に間違いがないか、重大な犯罪歴や反社会的勢力との関わりはないか、といった点を調査することです。雇用調査や採用調査とも呼ばれます。
採用候補者が履歴書に嘘の内容を記載していたり、面接で事実とは異なる回答をしたりした場合、短い採用プロセスのなかで詐称を見抜くことは簡単ではありません。そこでバックグラウンドチェックを実施して、申告内容に詐称がないかを確認することが重要視されています。
もともとは外資系企業において多く実施されていましたが、採用リスクを避けるために日系企業においても導入されるケースが増えてきました。バックグラウンドチェックは自社で行うこともできますが、効率よく情報収集するために専門の調査会社に依頼するケースも多いでしょう。
バックグラウンドチェックを実施する目的

バックグラウンドチェックを実施する大きな目的は、採用の精度を高めることです。採用プロセスのなかで、企業側は採用候補者の経歴やスキルを正確に把握する必要がありますが、採用候補者は不都合な事実を隠し、簡単に嘘の申告ができてしまいます。
面接だけでは詐称を見抜けないことも多いため、バックグラウンドチェックを通して本当の経歴を把握し、公平かつ精度の高い採用活動を行うことが重要視されているのです。
採用に関するリスクを避けることもバックグラウンドチェックの目的のひとつです。
企業の不利益となるような人物を採用すると、社内の人間関係のトラブルが発生したり、取引先との関係が悪化したりする可能性もあります。重大な犯罪歴や反社会的勢力との関わりがあると、企業のイメージが悪くなる可能性もあるでしょう。
優秀な人材を確保して継続的に事業を展開していくためには、バックグラウンドチェックをしっかりと行い、リスクのありそうな採用候補者を排除することが重要です。
バックグラウンドチェックはいつ実施すべき?
バックグラウンドチェックの実施タイミングについて絶対的なルールはありませんが、基本的には内定を出す前に行うとよいでしょう。内定を出すと労働契約が成立していると見なされるため、仮に調査によって採用を見送りたい事実が判明した場合でも、簡単に内定を取り消すことはできません。
採用の可否を慎重に判断したい場合は、最終面接の前後などで実施しましょう。
また、採用プロセスの早い段階では採用候補者の人数が多く、実施するためのコストや手間がかかってしまいます。
効率よく調査を行いたい場合は、採用プロセスがある程度進んでから実施するのがおすすめです。専門職や重要なポジションに就く人に絞って、調査を実施するのもよい方法です。
バックグラウンドチェックにおける在籍確認とは?
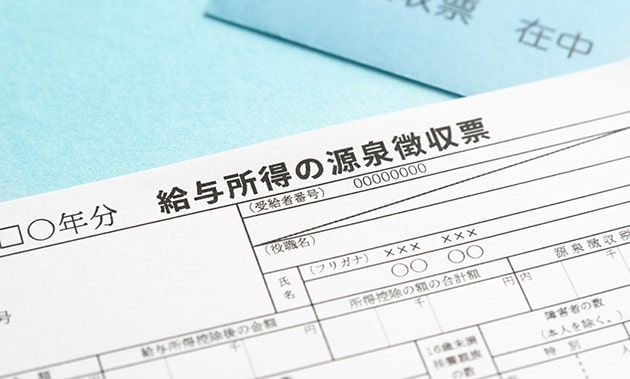
バックグラウンドチェックでは、学歴や職歴、破産歴や犯罪歴など、さまざまな項目について調査します。在籍確認は職歴の調査に含まれ、採用候補者が申告したとおりの会社や部署に所属していたか、どのくらいの期間在籍していたかをチェックします。少し踏み込んで、具体的な仕事内容や休職期間の有無などを含めて調査するケースもあるでしょう。
在籍確認は、前職の会社へ電話したり訪問したりして行います。在籍確認をしっかりと実施することで、履歴書や職務経歴書の内容に間違いがないかをチェックでき、採用後のミスマッチを防止することが可能です。在籍確認を行う代わりに、源泉徴収票の内容や社会保険の加入履歴を調べることもあります。
バックグラウンドチェックとリファレンスチェックの違い
バックグラウンドチェックと似た言葉として、リファレンスチェックが挙げられます。リファレンスチェックとは、前職の上司や部下などから、採用候補者の職歴や人物像をヒアリングすることです。ヒアリング相手として同僚や取引先の関係者が選ばれることもあり、実績やスキルはもちろん、人間関係や勤務態度などを幅広くチェックすることもあります。
一方のバックグラウンドチェックでは職歴を含め、学歴や犯罪歴、インターネット上のトラブルなど、さまざまな項目を調査するため、リファレンスチェックよりも大きな概念といえるでしょう。
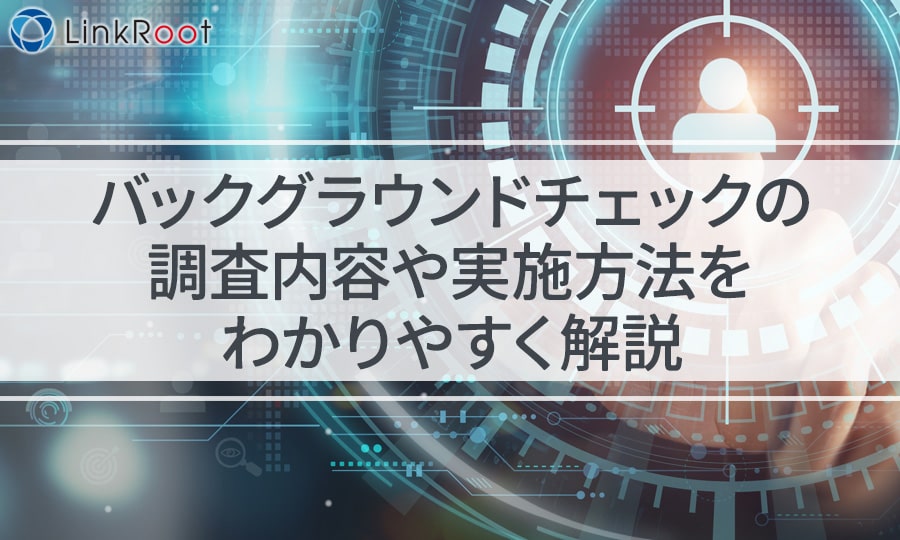

バックグラウンドチェックや在籍確認が重要な理由
バックグラウンドチェックや在籍確認を実施することで、経歴詐称がないかを把握でき、採用候補者を多面的に評価できます。採用後のミスマッチを防止して、適材適所を実現することにもつながるでしょう。
ここでは、バックグラウンドチェックや在籍確認が重要視されている理由を紹介します。
1.経歴詐称がないかをチェックするため
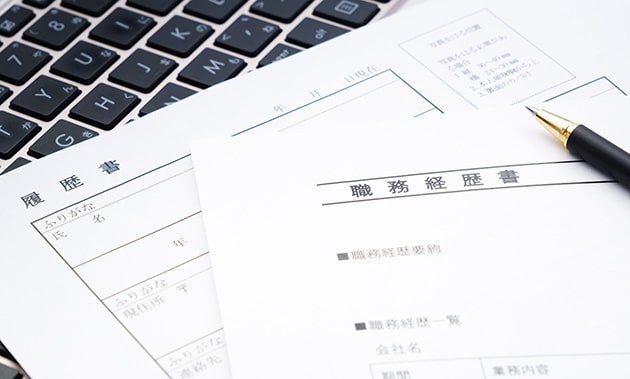
経歴詐称の有無を見抜くことは、バックグラウンドチェックや在籍確認を実施する大きな目的です。
「嘘の内容を記載しても指摘されることはないだろう」
「不利になる要素を隠して選考を有利に進めたい」
といった考えから、採用候補者が嘘の学歴や職歴を申告しているケースもあります。あからさまな嘘については面接での質問で見抜けることもありますが、前職での実績や在籍期間、担当していた業務などを短い時間で正確に把握することは簡単ではありません。
経歴詐称をした人物を採用することには、業務上でも虚偽の報告をする、取引先との関係が悪化する、といったリスクがあります。そのため、バックグラウンドチェックや在籍確認を徹底することが大切です。
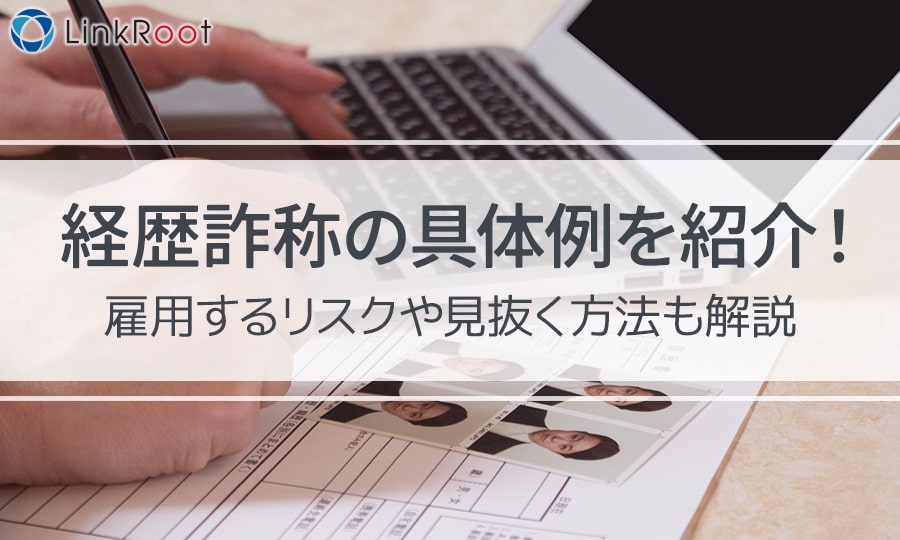
2.採用候補者を多面的に評価するため
バックグラウンドチェックや在籍確認には、採用候補者を多面的に評価するという前向きな目的もあります。履歴書や職務経歴書を提出してもらったり、数時間の面接のなかで会話をしたりするだけでは、採用候補者の全体像を把握することは難しいでしょう。
バックグラウンドチェックを実施すれば、学歴や職歴、スキルや経験などを細かく把握できます。とくに在籍確認のなかで、前職の上司や部下にヒアリングすれば、第三者からの客観的な意見を得ることが可能です。
せっかく在籍確認を実施するなら、所属部署や在籍期間だけではなく、人柄や取引先との関係、遅刻の有無や評価できる点など、さまざまなポイントを聞いておきましょう。
3.ミスマッチを防止するため
採用後のミスマッチを防止することも、バックグラウンドチェックを実施する目的のひとつです。
コストと手間をかけて新しい人材を採用しても、自社に合わなければ意味がありません。期待していたほどの能力を発揮してくれない、採用候補者が得意とするような業務がない、といった理由で早期離職してしまうと、採用や教育にかけたコストが無駄になってしまいます。
バックグラウンドチェックや在籍確認を行えば、採用候補者の得意とする業務や性格などを把握できます。自社の雰囲気や業務内容に合うかどうかを確認したうえで採用の是非を判断できるため、ミスマッチによる早期離職を防げるでしょう。
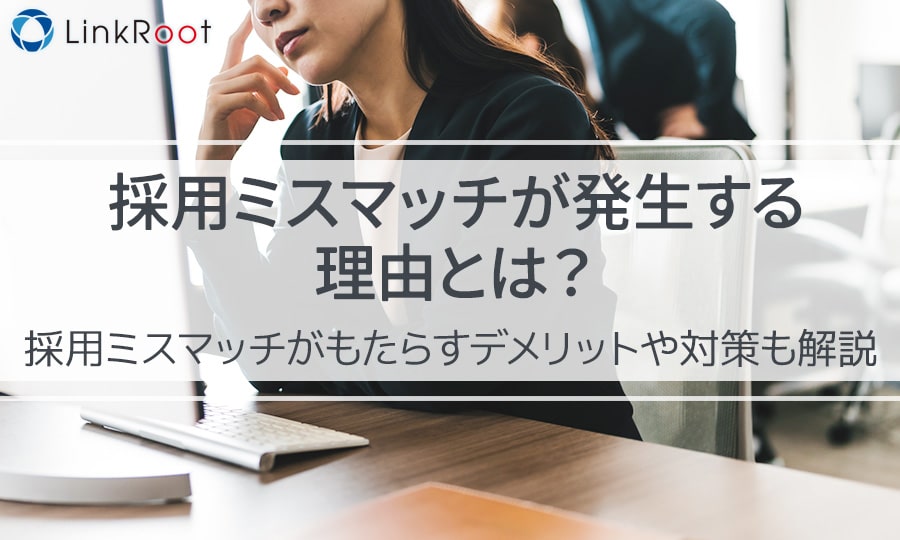
バックグラウンドチェックにおける在籍確認以外の調査項目
バックグラウンドチェックでは、在籍確認以外に次のような項目を調査しましょう。自社の採用プロセスや求める人材に合わせて、必要な項目を選択することが大切です。
- 学歴
- 勤務状況・勤務態度
- 破産歴
- 犯罪歴・民事訴訟歴
- 反社会的勢力との関係
- インターネット・SNSでのトラブル
ここでは、それぞれの調査項目について簡単に解説します。
1.学歴
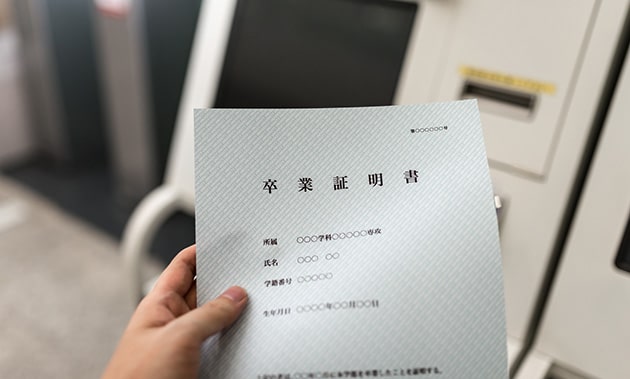
学歴詐称があると専門領域や得意分野を把握できず、適した仕事を与えられなくなるため、しっかりと調査しておくことが大切です。調査の際は、卒業証明書を提出してもらったり、必要に応じて学校関係者への聞き取りを行ったりします。
主な確認事項は以下のとおりです。
- 入学年度
- 卒業年度
- 所属学部・学科
- 専攻分野
- 取得した学位
履歴書の内容や面接での回答と相違がある場合は、本人へ確認したうえで適切な対応を取りましょう。
2.勤務状況・勤務態度
前職での勤務状況や勤務態度については、在籍確認のなかで調査するケースが一般的です。どのような姿勢で仕事に取り組んでいたか、どのような態度で同僚やクライアントと接していたか、といった点を自己申告のみから正確に把握することは難しいでしょう。
勤務態度が悪い人材を採用すると、生産性やチームのモチベーションが低下してしまいます。在籍状況を確認するとともに、仕事へ向かう姿勢や人間関係、人柄などをヒアリングしておくことが大切です。
3.破産歴
気になる場合は、破産歴についても確認しておきましょう。官報に掲載されている情報をもとに、以前に自己破産をしたことがないかを確認します。直近90日分の内容は、インターネットにて無料で閲覧可能です。そのほか、一部の図書館でも公開されているためチェックしておきましょう。
4.犯罪歴・民事訴訟歴
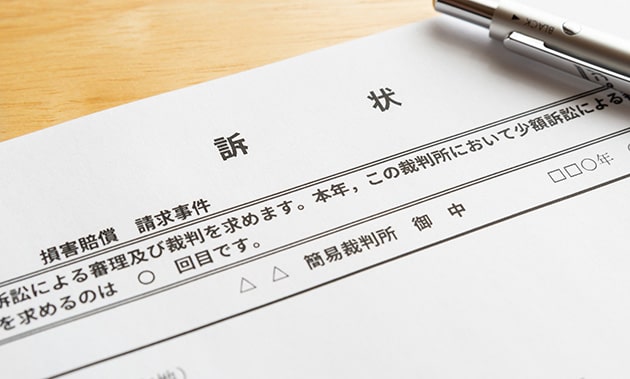
犯罪歴も重要なチェックポイントのひとつです。採用候補者が重大な犯罪歴を隠していないかチェックします。重大な犯罪歴のある人物を採用すると、入社後にトラブルが発生したり、社会的な信用が低下したりするため、しっかりと確認しておきましょう。
ただ、日本においては犯罪歴が公開されていないため、過去の新聞やインターネット上の情報から調べるしかありません。民事訴訟歴については、専門の調査会社に依頼してデータベースでチェックしてもらうのが一般的です。
5.反社会的勢力との関係
反社会的勢力との関わりについても確認しておきましょう。インターネットや新聞で情報を探すほか、反社チェックツールを活用する、警察や暴追センターへ問い合わせる、といった方法もあります。
犯罪歴と同様、反社会的勢力との関係がある人物を採用すると企業イメージの失墜につながるため、しっかりと確認しておくことが重要です。
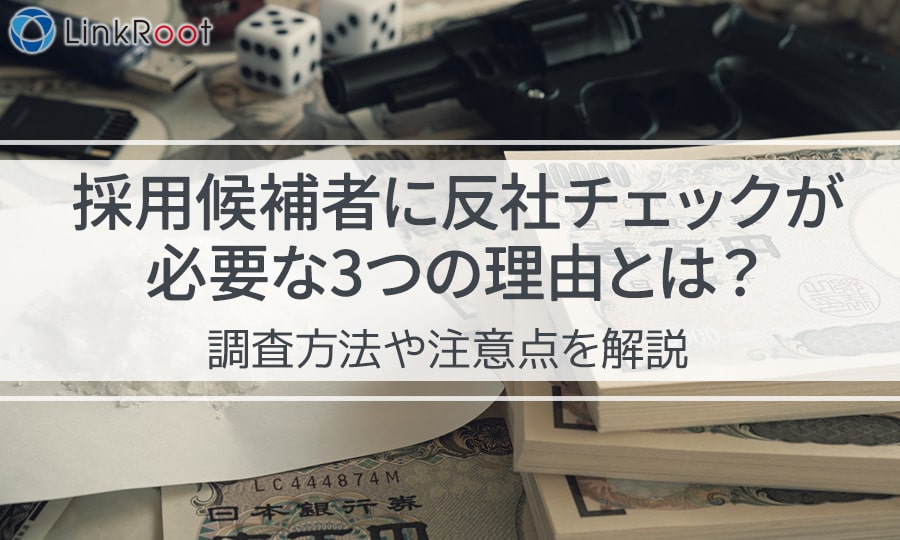
6.インターネット・SNSでのトラブル
インターネットやSNSでのトラブルの有無も重要な確認事項です。差別的な発言や誹謗中傷などをしていないか、確認しておきましょう。FacebookやInstagramで名前を検索すると、過去のトラブルが発覚することもあります。
バックグラウンドチェックや在籍確認を行う流れ
バックグラウンドチェックや在籍確認は、正しい手順で行わなければなりません。とくに採用候補者の同意を得ずにスタートすると、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。以下、調査を進めるときの流れについて詳しく解説しますので、理解を深めておきましょう。
1.採用候補者の同意を得る
バックグラウンドチェックや在籍確認を実施することは法律で禁止されているわけではありませんが、個人情報を扱うため、採用候補者に対して目的や取得する情報などを伝え、同意を得る必要があります。同意を得ずに調査を進めると、個人情報保護法に違反する可能性もあるため注意しなければなりません。
専門の調査会社へ依頼する場合は、取得する情報について事前に打ち合わせを行い、違法な調査とならないよう気を付けましょう。コンプライアンス体制が整った会社を選ぶことも重要です。
オンラインのチェックツールなどを使う場合は、個人情報の取得や保存について配慮されているか確認しておきましょう。
2.ヒアリングを実施する

採用候補者の同意を得られたら、調査を進めます。本人から卒業証明書を提出してもらったり、前職の関係者へヒアリングを行ったりして、虚偽の申告がないかを確認しましょう。
求める人物像や調査の目的にもよりますが、ヒアリングのなかでは勤務態度や人柄など、幅広い項目を聞いておくことが大切です。在籍確認にとどまらず、さまざまな情報を聞き出すことで、より自社に合う人物の採用につながります。
3.採用すべきかを総合的に判断する
調査が完了したら内容をまとめ、採用すべきかどうかを検討しましょう。調査会社へ依頼した場合は、レポートのような形式で情報共有されることが一般的です。履歴書の内容や面接時の印象なども含め、自社が求めている人材なのかを総合的に判断します。
バックグラウンドチェックや在籍確認を行うときの注意点
バックグラウンドチェックや在籍確認を行うときは、実施タイミングや辞退される可能性に注意しましょう。ここでは、調査を進めるときの注意点について詳しく解説します。
1.採用候補者から拒否されることもある
前述のとおり、調査やヒアリングを実施する前に採用候補者の同意を得る必要がありますが、その際、拒否されることもあります。拒否する理由としては、以下のようなことが考えられます。
- 虚偽の申告をしている
- 隠しておきたい経歴がある
- 前職の関係者へのヒアリングを避けたい
拒否する理由に納得できない場合は、その段階で不採用にすることを検討してもよいでしょう。
2.内定を出す前に実施する
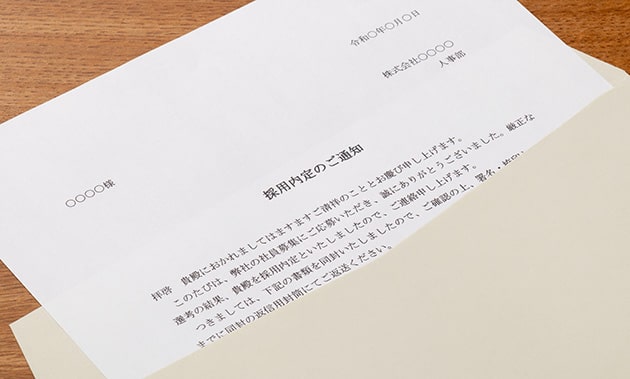
内定を出したタイミングで労働契約が成立したと見なされるため、基本的には内定前に実施しましょう。内定後に調査を行うことも可能ですが、調査結果をもとに内定を取り消すことは簡単ではありません。合理的な理由で内定取り消しを行わなければ、不当解雇と見なされるため注意が必要です。
3.辞退される可能性もある
採用候補者が途中で選考を辞退してしまう可能性があることにも注意しましょう。経歴詐称をしていないとしても、前職の関係者に迷惑をかけたくない、転職活動をしていることを知られたくないなどの理由で、調査を嫌がられるケースもあります。選考を辞退されてしまうと、それまでのプロセスが無駄になってしまうため慎重に進めることが大切です。
4.実施する目的を明確に伝えておく
調査をスタートする前に、採用候補者に目的を伝えておきましょう。バックグラウンドチェックの認知度が低いこともあり、経歴を調べられることに疑問を感じる人もいます。採用における公平性を確保すること、コンプライアンス上のリスクを避けることなど、調査を実施する目的をわかりやすく伝え、同意を得ることが重要です。
バックグラウンドチェックと在籍確認を実施してミスマッチを防止しよう!
今回は、バックグラウンドチェックと在籍確認の重要性や実施手順などについて解説しました。採用候補者は不利になるような情報を隠し、嘘の申告をしているケースもあります。適切な調査や聞き取りを行うことで採用の精度を高め、自社が求める人材を採用できるでしょう。
ただし、調査を実施する際は本人の同意を得る、選考に関係ない情報まで入手しないなど、個人情報やプライバシーに配慮する必要があります。採用候補者とのトラブルが発生しないよう慎重に調査を進めることが重要です。