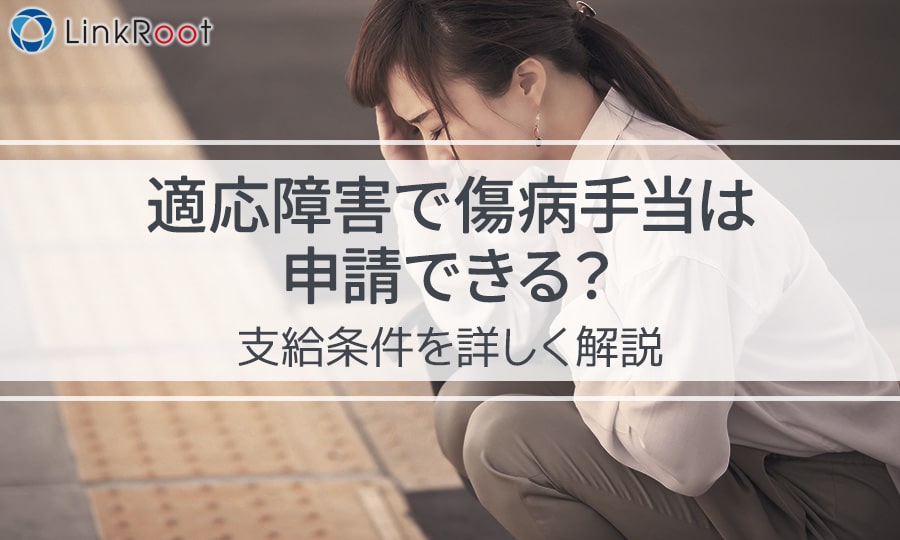適応障害で働けなくなったとき、傷病手当の申請を検討することもあるでしょう。傷病手当の支給を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
この記事では、適応障害で傷病手当を受給するための要件、傷病手当の金額や支給期間などについて解説します。労働災害と認定された場合に受けられる休業補償給付についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
適応障害と診断されたら傷病手当を申請できる?
適応障害と診断された場合、傷病手当や休業補償給付を申請できるのでしょうか。ここでは、適応障害の概要や傷病手当申請の可否について解説します。
適応障害とは?
適応障害とは、強いストレスにより、通常どおりの日常生活ができなくなる病気のことです。誰でも不快な出来事に対して怒りや悲しみを感じるものですが、一般的な範囲を超えて日常生活に影響が出ている場合に、適応障害と診断されます。
適応障害の原因としては、仕事上の大きな失敗や度重なる叱責などが挙げられます。離婚や家族との死別など、プライベートな出来事が原因となって適応障害になるケースもあるでしょう。
適応障害になると、情緒面や行動面にさまざまな症状が出ます。情緒面の一般的な症状は、抑うつ感や不安感、集中力の低下などです。コミュニケーションが減る、無断欠勤が増えるなどの行動面の症状が現れるケースも多いでしょう。適応障害は誰でもなり得る病気であり、薬物療法やカウンセリングにより、しっかりと治療することが重要です。
要件を満たせば傷病手当の申請ができる

適応障害により働けなくなった場合、一定の要件を満たせば、傷病手当を申請できます。傷病手当とは、健康保険の被保険者とその家族の生活を維持するために支給される手当です。(※1)病気や怪我で働けなくなり、会社から十分な賃金が支給されないときに申請できます。傷病手当の支給を受けるための要件については、後ほど詳しく解説します。
(※1)全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
傷病手当の金額
傷病手当の1日当たりの金額は、以下のとおりです。
1日当たりの金額 =(支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3
支給開始日とは、傷病手当の支給がスタートした日のことです。また、標準報酬月額とは、従業員の賃金をもとに決定される金額で、一定の幅で区分された等級表によって決められます。標準報酬月額を決定するための賃金には、基本給だけではなく、残業手当・通勤手当・家族手当・住宅手当なども含まれるため注意しましょう。
傷病手当の支給期間
傷病手当は、病気や怪我で会社を休んだ期間に支給されます。ただし、最初の3日間は除き、4日目から支給がスタートするため注意しましょう。
支給期間は、支給が始まった日から通算して1年6ヶ月です。たとえば途中で数日間出勤したような場合、その日数は支給期間にはカウントされず、後ろ倒して支給を受けられます。
労働災害の場合は休業補償給付を受けられる

業務上の事由により適応障害となり、労働災害と認定された場合は、労災保険による休業補償給付を受けられます。(※2)たとえば、過度の長時間労働やパワーハラスメント、職場の人間関係などが原因で適応障害となった場合は、労働災害と認定される可能性が高いでしょう。適応障害で休業補償給付を受けるための要件については、後ほど詳しく解説します。
休業補償給付の金額
休業補償給付の金額は以下のとおりです。
- 休業補償給付 = 給付基礎日額 × 60% × 休業日数
- 休業特別支給金 = 給付基礎日額× 20% × 休業日数
2つを合計して、給付基礎日額の80%の金額が支給されます。給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金のことです。給付基礎日額は、労働災害が発生した日の直前3ヶ月間に支払われた賃金の合計を、その期間の暦日数で割って算出します。
休業補償給付の支給期間
休業補償給付は、労働災害により働けなくなって4日目から支給されます。休業して最初の3日間は待機期間となりますが、この3日は連続している必要はありません。
また、休業補償給付の支給期間の上限はなく、休業している場合は継続的に給付を受けられます。ただし、休業開始から1年6ヶ月経っても回復せず、そのタイミングで一定の傷病等級に該当すると認められるときは、休業補償給付が打ち切られ、傷病補償年金に変更されます。
適応障害で傷病手当金の支給を受けるための要件
適応障害で傷病手当金の支給を受けるためには、以下4つの要件を満たす必要があります。
- 療養のために仕事を休んだこと
- 就労不能であること
- 連続する3日間を含み4日以上就労できなかったこと
- 療養期間中に傷病手当金の額より多い賃金の支払いがないこと
それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
1.療養のために仕事を休んだこと

適応障害など、病気や怪我の療養のために仕事を休んでいる場合は、傷病手当金の対象となります。健康保険給付としての療養はもちろん、自費で診察を受けた場合や自宅で療養している場合でも支給対象となります。ただし、働けないことの証明は必要です。
また、業務上の事由により適応障害になった場合は、労災保険による給付対象となるため、傷病手当金を受給することはできません。
2.就労不能であること
就労不能であることも傷病手当金を受給するための要件のひとつです。労務不能とは、被保険者がそれまで担当していた仕事ができない状態のことを意味します。
労務不能な状態に該当するかどうかは、医師による診察や担当していた仕事内容、職場環境など、さまざまな条件を考慮して総合的に判断されます。
3.連続する3日間を含み4日以上就労できなかったこと
傷病手当金は、適応障害などにより仕事を休んだ日から連続して3日間休業したあと、4日目以降の休業日に対して支給されます。この最初の3日間のことを待機期間と呼びます。待機期間には、土日や有給休暇も含まれるため注意しましょう。
たとえば、3日間連続して休み、4日目は出勤、5日目以降は休み、というケースでは、5日目以降の休業日に対して傷病手当金が支給されます。仮に2日間しか連続して休んでいない場合は、待機完成とならず、傷病手当金は支給されません。
4.療養期間中に傷病手当金の額より多い賃金の支払いがないこと
療養期間中に賃金が支払われている場合は、基本的に傷病手当金は支給されません。傷病手当金は、病気や怪我で収入がなくなったときに、生活を保障するための制度だからです。
ただし、賃金が支払われていたとしても、傷病手当金の額を超えない場合は、その差額が支給されます。会社の休職制度によっては、療養期間中に賃金を支払うケースもあるでしょう。休職期間中の賃金の額によっては、傷病手当金を受給できない可能性や減額される可能性もあります。なお、任意継続による被保険者に対しては、傷病手当金は支給されません。
適応障害で休業補償給付を受けるための要件
適応障害で休業補償給付を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 業務上の事由で適応障害になったこと
- 適応障害により就労できないこと
- 賃金の支払いを受けていないこと
以下、それぞれの要件について詳しく解説します。
1.業務上の事由で適応障害になったこと
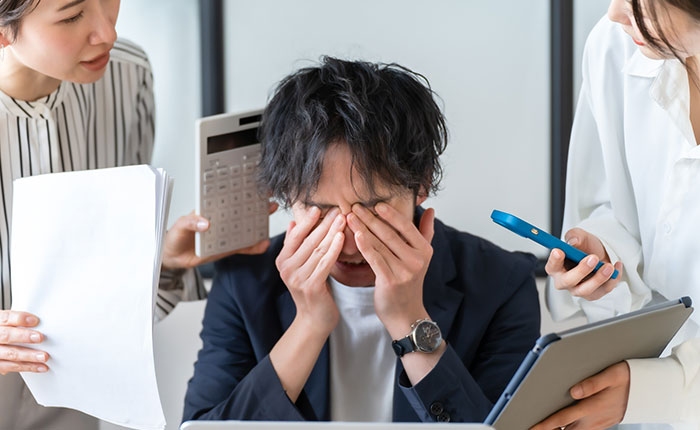
休業補償給付を受けるためには、適応障害になったことが労働災害として認定されなければなりません。業務上の事由で適応障害になったのか、労働災害と認められるかどうかは、労働基準監督署が判断します。
業務上のストレスや長時間労働が原因と考えられる場合は、労働災害として認定される可能性があります。労働災害と認められない場合は休業補償給付を受けられないため、前述の傷病手当金の申請を検討しましょう。
2.適応障害により就労できないこと
休業補償給付を受けるためには、就労できない状態でなければなりません。適応障害になる前に従事していた仕事を継続できない場合は、就労できない状態であると見なされるでしょう。
ただし、本当に就労できない状態であるかどうかは、医師の所見をもとに労働基準監督署が調査を行ったうえで判断します。就労できない状態であると判断されると、休業補償給付を受けることが可能です。
3.賃金の支払いを受けていないこと
賃金の支払いを受けていないことも、休業補償給付を受けるための要件のひとつです。まったく賃金が支払われていないケースはもちろん、1日当たりの賃金が平均賃金の6割以下であるケースにおいても、休業補償給付を受けることができます。
適応障害で休職させるときの注意点
従業員が適応障害になったときは、休職させることを検討するケースが多いでしょう。ただし、休職制度の有無や内容、給与の支払い方法について事前に確認しておくことが重要です。ここでは、適応障害で休職させるときの注意点について解説しますのでチェックしておきましょう。
1.休職制度の有無は企業によって異なる
休職制度とは、従業員が何らかの事情で働けなくなったときに、一定期間就労する義務を免除して、療養させる仕組みのことです。休職期間中は病気や怪我の治療に専念してもらい、早期の復職を目指します。休職制度は会社と従業員の双方にとってメリットのある制度ですが、法律によって定められたものではないため、制度の有無は企業によって異なります。
また、休職制度を導入していたとしても、どのようなケースで利用できるのか、どのくらいの期間休めるのかなどは、企業によって異なるでしょう。従業員が適応障害になったからといって、必ず休職制度を利用できるとは限らないため、事前に就業規則の内容を確認しておくことが大切です。
2.給与の支払い方法は就業規則に従う
前述のとおり、休職制度の内容は企業によって異なります。当然、休職期間中の給与の支払い方法も企業ごとに異なるため、就業規則に従うことが重要です。
基本的に給与は労働の対価として支払われるものであるため、休職期間中は給与を支給しない企業もあるでしょう。ノーワーク・ノーペイの原則により、休職期間中に給与を支払わなくても法律上の問題はありません。ただし、労使間のトラブルを防止するため、休職期間中は無給とする旨を明記しておくのが一般的です。
逆に、休職期間中であっても従業員の生活を守るために、一定の給与を支払うルールにしている企業もあるでしょう。どちらにしても就業規則に従う必要があるため、従業員を休職させる際はルールをしっかりと確認しなければなりません。
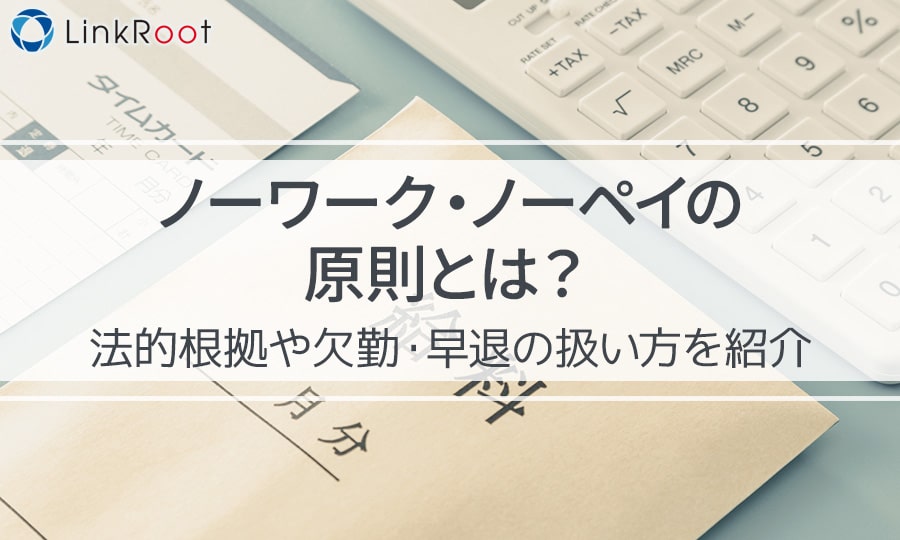
3.復職できないときの対応を確認する
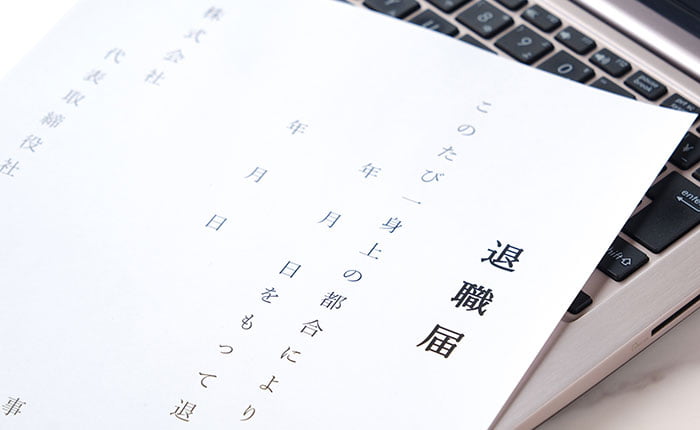
適応障害となった従業員を休職させるときは、復職できないときの対応についても確認しておきましょう。休職制度を導入するときは、休職期間満了時の対応について就業規則に記載しておくのが一般的です。
休職期間満了時に復職できる程度まで回復していない場合は、自然退職や解雇となるようなルールを設定するケースが多いでしょう。また、休職期間を延長できる制度を導入している企業もあるかもしれません。就業規則に従って適切な対応をしなければ労使間のトラブルにつながるため、事前に確認しておきましょう。
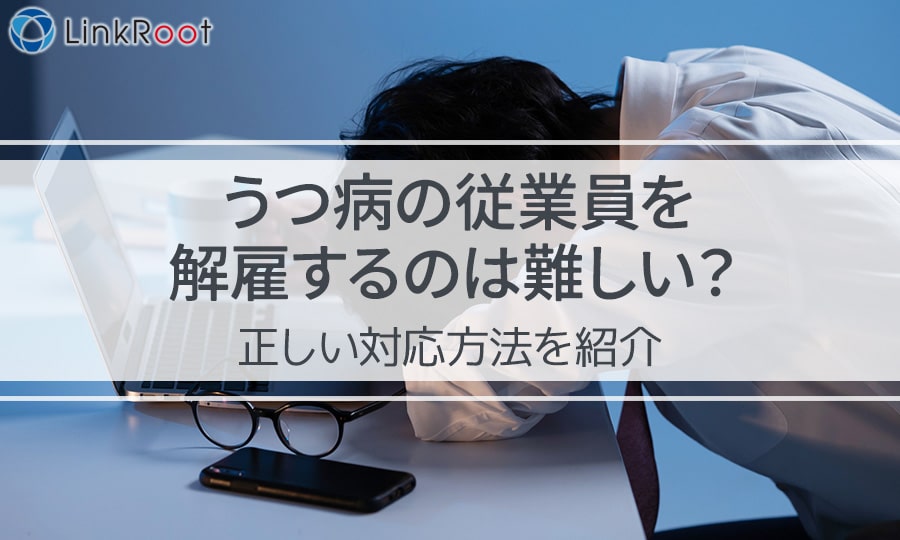
4.必要に応じて職場環境を見直す
従業員が適応障害になった場合、職場環境に問題があるかもしれません。長時間労働が当たり前になっていたり、ハラスメント行為が横行していたりすると、適応障害になる従業員が増える可能性もあります。
適応障害になった原因をしっかりと把握して、適切な対応を取ることが重要です。具体的には、人員の確保や業務の再配分を検討する、ハラスメント対策を徹底する、定期的なストレスチェックを実施するなどの対応が挙げられます。
一定の要件を満たせば適応障害で傷病手当を申請できる!
今回は、適応障害により傷病手当や休業補償給付を受けるときの要件について解説しました。一定の要件を満たしていれば、適応障害で傷病手当や休業補償給付を受給することは可能です。それぞれ要件が異なるため、支給の対象となるかどうか事前に確認しておきましょう。
また、適応障害により従業員を休職させるときは、就業規則の内容を確認することが大切です。休職制度の有無や内容は企業によって異なります。給与の支払い方法や復職できないときの対応についても把握したうえで、従業員を休職させるようにしましょう。