専門的なスキルや知識をもつ人材を採用するため、ジョブ型雇用を取り入れる企業が増えてきました。ジョブ型雇用を導入すれば、職務遂行のために必要な能力をもつ人材を効率よく採用できます。
ただし、従来のメンバーシップ型雇用とは異なり、人事異動などを行いにくくなるため注意しましょう。
この記事では、ジョブ型雇用の特徴やメリット・デメリットなどを詳しく解説します。導入を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
ジョブ型雇用とは?

ジョブ型雇用とは、職務内容を明確に定義したうえで、その職務を担当するために必要なスキルや経験を有する人材を採用する方法です。ジョブ型雇用においては多くの場合、担当する仕事や勤務エリア、労働時間などについて労使間で個別に協議し、職務内容に合わせた雇用契約を結びます。
職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成して、職務ごとの業務範囲や必要なスキルを明確にすることもジョブ型雇用の大きな特徴です。職務記述書をもとに採用活動を進め、採用後に職務を変更するような人事異動を実施することは基本的にありません。逆に、雇用契約の内容によっては、職務がなくなったタイミングで解雇するケースもあります。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
メンバーシップ型雇用とは、職務や勤務エリアを限定せず、幅広い人材を採用する方法です。職務が先にあり、担当する人材を探し出すジョブ型雇用とは異なり、採用した人材にさまざまな職務を担当させるのがメンバーシップ型雇用といえるでしょう。
日本においては、終身雇用制度における長期的なキャリア形成を前提として、多くの企業がメンバーシップ型雇用を実施してきました。メンバーシップ型雇用では、ジョブローテーションによりさまざまな部署を経験させたり、人材配置を最適化するために定期的に人事異動を実施したりするのが一般的です。
メンバーシップ型雇用の場合、従業員は必ずしも希望する職種に就けるとは限りません。一方でジョブ型雇用とは異なり、仮に最初に担当していた職務がなくなったとしても、簡単に解雇されることはないでしょう。
そのほか、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用には下表のような違いがあります。
| ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 主に中途採用 | 主に新卒採用 |
| 担当する職務 | 限定されている | さまざまな職務を担当する |
| 転勤・部署異動 | 基本的に異動はない | 定期的に異動することが多い |
| 給与・評価の基準 | 主に成果・職務の難易度 | 主に年齢・勤続年数 |
| 雇用契約の内容 | 職務に合わせて契約する | 企業のルールに従うことが多い |
| 解雇の可能性 | 雇用契約によっては解雇の可能性がある | 簡単に解雇されることはない |
| 教育方針 | 主に自己研鑽 | 主に社内研修 |
ジョブ型雇用に注目が集まっている理由
ジョブ型雇用は主に欧米で行われていた採用手法ですが、働き方の多様化や専門職の不足などを背景として、日本でも取り入れる企業が増えてきました。ここでは、日本においてジョブ型雇用に注目が集まっている理由を紹介します。
1.働き方の多様化

働き方の多様化が進んでいることは、ジョブ型雇用に注目が集まる大きな理由です。新型コロナウイルス感染症への対策やワークライフバランスの確保を目的として、テレワークや在宅勤務を導入する企業も増えてきました。
テレワークや在宅勤務の大きなメリットは、柔軟な働き方を実現でき、育児・介護と仕事の両立が容易になることです。一方で、業務の進捗状況を管理したり、従業員を評価したりする際に苦労するケースもあります。
従業員の様子を近くで見ることができないため、従来のように労働時間や仕事の進め方で評価することは難しいでしょう。そこでジョブ型雇用を取り入れ、従業員の職務を明確にしつつ、労働時間ではなく、仕事の成果によって評価しようとする企業が増えてきています。
2.経団連による提言
経団連(日本経済団体連合会)による提言があったことも、ジョブ型雇用に注目が集まる理由のひとつです。2020年頃から経団連は、各種の報告書や協議のなかで、メンバーシップ型雇用の見直しやジョブ型雇用の推奨に関する提言を行っています。(※1)
経団連は、雇用面での安心感や効率的な人材育成など、メンバーシップ型雇用のメリットを挙げつつも、就労ニーズや働き方の多様化に伴い、課題が顕在化しつつあることも指摘しています。また、社会の変化に対応するため、従業員の職務を明確にして評価を行うジョブ型雇用を推奨したこともあり、注目が集まるようになりました。
3.専門職の不足
専門職の不足を補うために、ジョブ型雇用を取り入れる企業も増えてきました。ITシステムの導入による業務効率化や、DX推進によるコスト削減などが求められるなか、AIやIoTに強い人材の確保に苦労している企業も多いでしょう。
従来のようなメンバーシップ型雇用では専門的なスキルをもつ人材を見つけられず、困るケースもあるかもしれません。そこでジョブ型雇用に切り替え、職務ごとに求めるスキルを明確にしたうえで、採用活動を進める企業も増えてきています。
4.大手企業によるジョブ型雇用の導入
日立製作所、富士通、資生堂、KDDIなどの大手企業では、ジョブ型雇用の導入が進んでいます。たとえば日立製作所では、グローバルな事業環境の変化や従業員のライフスタイルの多様化などに対応するため、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への変更を推進しています。(※2)
有名な企業の取り組みがメディアで報道されると、他の企業も追従するような形でジョブ型雇用に注目するようになりました。ただし、すべてのケースにおいてジョブ型雇用が適しているわけではありません。次に紹介するようなメリット・デメリットがあるため、目的や企業の状況に応じて適した採用手法を選択しましょう。
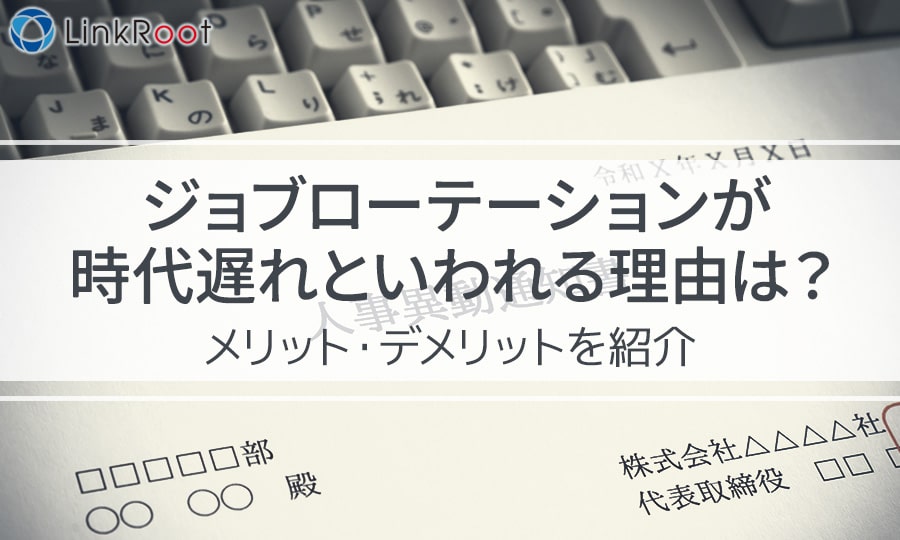
ジョブ型雇用を導入するメリット
ジョブ型雇用を導入することで、以下のようなメリットを得られます。
- 専門的なスキルをもつ人材を採用できる
- ミスマッチを防止できる
- 正当な評価を実現しやすい
- 効率的に教育できる
- 仕事の成果が出やすい
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.専門的なスキルをもつ人材を採用できる

ジョブ型雇用の大きなメリットは、専門的なスキルや知識をもつ人材を採用できることです。従来のメンバーシップ型雇用の場合は、仕事内容や求めるスキルを特定せずに採用を進めることが多く、必ずしも求めるスキルを有している人材に出会えるとは限りません。入社後に必要なスキルや知識を習得させることになるため、教育にも時間がかかるでしょう。
一方のジョブ型雇用においては、職務記述書のなかで求める能力や経験を明確にするため、特定の職務に適した人材と効率よく出会えます。入社後の教育も最低限でよく、即戦力としてすぐに活躍してくれるでしょう。
2.ミスマッチを防止できる
ミスマッチを防止できることもジョブ型雇用のメリットのひとつです。メンバーシップ型雇用の場合は、ジョブローテーションや人事異動により、さまざまな部署を経験させることが多く、従業員にとって負担になるケースもあります。希望していた職務に就けないことに不満を感じ、離職してしまう従業員もいるかもしれません。
ジョブ型雇用の場合は、雇用契約のなかで職務を固定することが一般的です。事前に仕事内容や勤務エリアについて合意したうえで入社してもらうため、ミスマッチを防止しやすいでしょう。定着率の向上につながり、無駄な採用コストや教育コストの発生を抑制できます。
3.正当な評価を実現しやすい
ジョブ型雇用を導入すれば、従業員に対する正当な評価を実現できるでしょう。ジョブ型雇用では、職務ごとの役割や責任、評価基準を明確に設定するからです。事前に設定された項目と基準に沿って客観的な評価を行うため、評価者の主観を排除できます。
その結果、評価の公平性や正確性が高まり、従業員も評価内容に納得しやすいでしょう。評価と給与が連動していることもジョブ型雇用の特徴です。一般的には成果に応じて給与を決定するため、年功序列の解消や従業員のモチベーションアップを期待できます。
4.効率的に教育できる
効率的な教育ができることもジョブ型雇用のメリットのひとつです。ジョブ型雇用においては、担当する職務が固定されているため、関連するスキルや専門知識だけを習得させれば問題ありません。メンバーシップ型雇用のように、部署異動後に新たなスキルや知識を習得する必要がないため、従業員は効率よくレベルアップできるでしょう。
ジョブ型雇用では、幅広いスキルや知識を習得することは難しいのですが、専門分野についてはより理解が深まります。エンジニアやデザイナーなど、深い専門知識が必要となる職種には、ジョブ型雇用が適しているでしょう。
5.仕事の成果が出やすい
ジョブ型雇用ではそれぞれの従業員が得意分野で働くため、自身の能力を発揮しやすく、仕事の成果が出やすいでしょう。成果を出すことで評価も高まるため、従業員のモチベーションアップや生産性向上も期待できます。また、会社全体の意欲や組織力が高まることで、業績アップや売上アップ、業務効率化にもつながるでしょう。
ジョブ型雇用を導入するデメリット

さまざまなメリットがある一方、人事異動が難しい、定着率が低下するなどのデメリットもあります。ジョブ型雇用を導入する前に、しっかりと確認しておきましょう。
1.人事異動が難しい
人事異動が難しいことはジョブ型雇用の大きなデメリットです。ジョブ型雇用の場合、職務記述書や雇用契約のなかで職務や業務範囲を明確に規定していることが多く、簡単に人事異動を行うことはできません。仮に職務がなくなったり、他部署で人材の不足が出たりしたときでも、流動的な人材活用ができずに困る場面もあるでしょう。
流動的な人材活用を行いたい場合は、メンバーシップ型雇用のほうが適しています。メンバーシップ型雇用の場合は職務を限定せず、部署異動があることを前提としているため、業務内容の変更や欠員の補充にも対応しやすいでしょう。
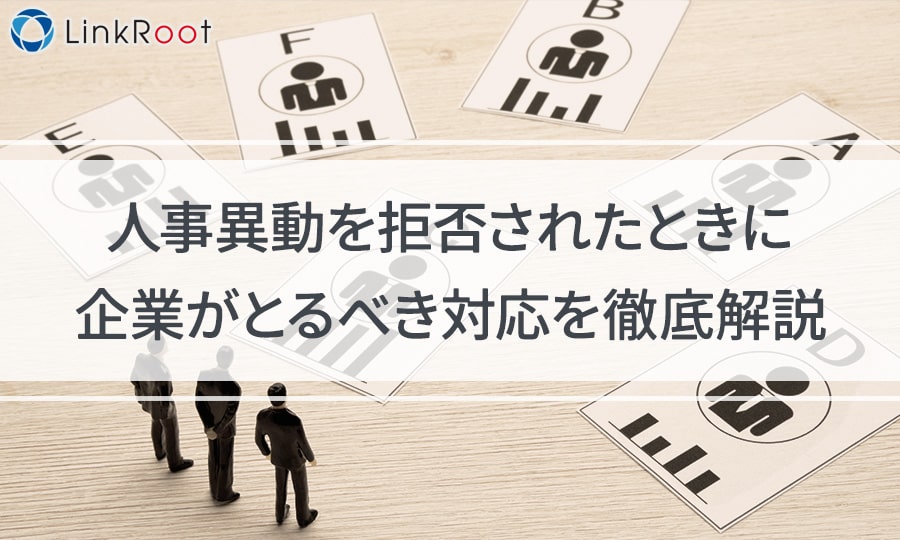
2.定着率が低下する可能性もある
ジョブ型雇用を導入すると、定着率が低下する可能性もあります。同じ職務で自社より好条件の職場があった場合に、転職してしまうケースもあるからです。また、ジョブ型雇用で採用する従業員は、高度な専門スキルを有しています。他の企業が採用したいと考え、高い給与を提示して引き抜こうとする可能性もあるでしょう。
先ほど紹介したように、人事異動が難しいことも定着率が低下する要因です。他の部署で人材が不足していたとしても人事異動を実施できず、優秀な人材が流出してしまうケースもあります。
3.社内制度の見直しが必要となる
ジョブ型雇用を取り入れるなら、さまざまな社内制度を見直さなければなりません。採用プロセスはもちろん、評価制度や給与体系についてもジョブ型雇用に合わせて変更することが必要です。これまでメンバーシップ型雇用を行っていた場合は、抜本的な改革が必要となるでしょう。
また、新しい採用手法や制度の変更について社内に周知する必要もあります。とくにメンバーシップ型雇用で採用された従業員が不満や疑問を感じないよう、目的や仕組みを丁寧に説明しなければなりません。導入までに時間がかかることも多いため、スケジュールを立てて進めるようにしましょう。
ジョブ型雇用を導入するときの手順
ジョブ型雇用を導入するときは、適用範囲を決め、職務記述書を作成しなければなりません。状況に応じて評価制度の見直しも必要です。具体的には、以下のような手順で進めましょう。
1.適用範囲を決める
ジョブ型雇用を適用する範囲を検討しましょう。メンバーシップ型雇用のほうが適しているケースもあるため、すべての職務に対してジョブ型雇用を適用する必要はありません。
まずは、社内に存在する職務や求める人材像を明確にしておくことが大切です。職務を担当するために高度なスキルや専門知識が必要な場合は、ジョブ型雇用を適用するとよいでしょう。事務的な職務については、人事異動を行いやすくするためにメンバーシップ型雇用を適用したほうがよい場合もあります。
2.職務記述書を作成する
ジョブ型雇用を適用する場合、職務ごとに職務記述書を作成しましょう。職務記述書には、主に以下のような項目を記載します。
- 職務名
- 職務内容
- 雇用形態
- 勤務エリア
- 勤務時間
- 責任範囲
- 達成すべき目標・求められる成果
- 必要なスキル・知識・資格
- 待遇
職務記述書をもとに採用活動を進めるため、必要な内容を簡潔に記載しておくことが重要です。ミスマッチを防止しつつ、求める人材を採用するためにも、とくに必要なスキルや知識については明確に記載しておきましょう。
3.評価制度を見直す

ジョブ型雇用を導入するなら、評価制度を見直すことも必要です。とくにメンバーシップ型雇用を行っていた場合、年齢や勤続年数などを重視して評価するような制度になっていることが多いでしょう。
しかし、ジョブ型雇用では職務ごとの難易度や成果を重視して評価するのが一般的であるため、評価制度を見直す必要があります。客観的な評価項目や評価基準を設定し、成果をしっかりと見極められる仕組みにしましょう。評価制度と給与体系の連動について見直すことも重要です。
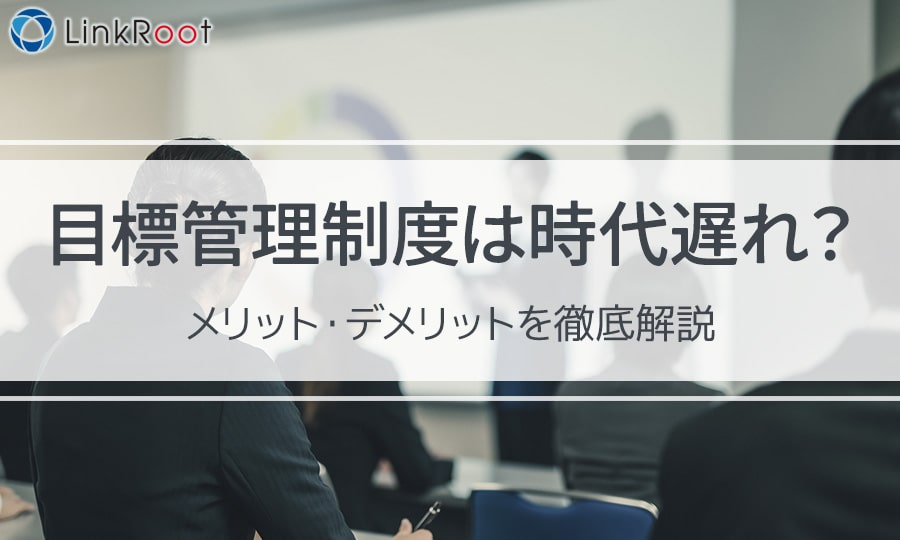
4.定期的に制度を改善する
ジョブ型雇用を運用していくなかで、課題がある場合は制度を改善していきましょう。たとえば、ジョブ型雇用を導入したのに専門的なスキルをもつ人材を採用できていない場合や、ミスマッチによる離職が頻発している場合は、仕組みを見直すことが必要です。
職務記述書の内容に不備がある、そもそもジョブ型雇用が適していない職務である、といった可能性もあります。採用担当者や現場の上司の意見なども参考にしながら、採用手法を改善していきましょう。また、従業員が評価制度や働き方に対して不満を感じている場合も制度の改善が必要です。
ジョブ型雇用の特徴を理解したうえで導入を検討しよう!
今回は、ジョブ型雇用の特徴やメリット・デメリットを紹介しました。ジョブ型雇用は、メンバーシップ型雇用とは異なり、職務ごとの役割や業務範囲を明確にしたうえで人材を採用する手法です。ジョブ型雇用を導入することで、専門的なスキルをもつ人材を採用できる、仕事の成果が出やすくなるなどのメリットを得られるでしょう。
ただし、流動的な人材活用が難しい、社内制度の見直しが必要になるなどのデメリットもあります。すべての職務にジョブ型雇用が適しているわけではないため、特徴やメリット・デメリットを把握したうえで、導入するかどうかを検討しましょう。必要に応じてメンバーシップ型雇用を併用することも重要です。
(※1)一般社団法人 日本経済団体連合会「春季労使交渉・協議の焦点」
(※2)日立製作所「日立が進める「ジョブ型」とは? わかりやすく解説」
https://social-innovation.hitachi/ja-jp/article/job_type_employment




