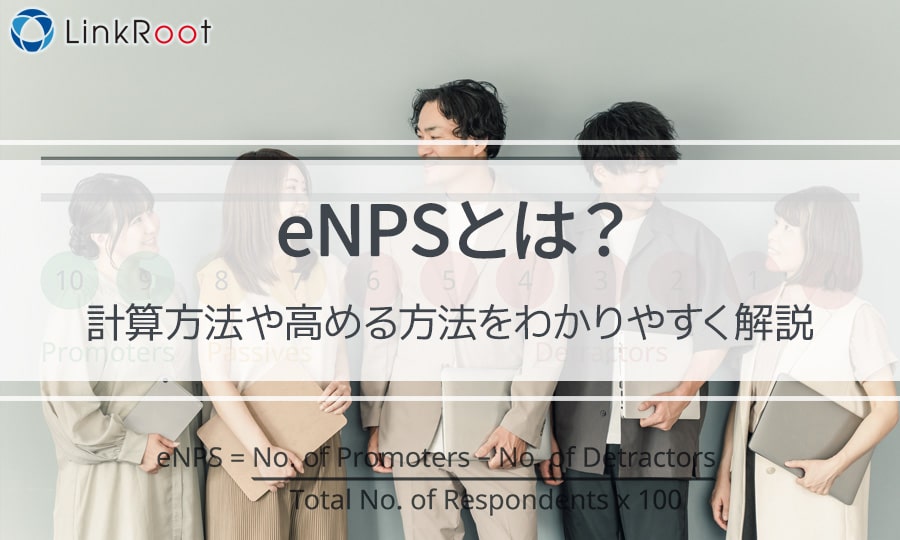少子高齢化による労働力不足が進むなか、従業員の定着率を高めることは多くの企業が抱えている課題です。従業員の職場に対する感情を把握し、適切な対策を検討することで、定着率を高めようとする企業も増えてきました。
この記事では、従業員の状態を把握する指標であるeNPSについて解説します。計算方法や高める方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
eNPSとは?
eNPS(Employee Net Promoter Score)は、従業員の職場に対する愛着や満足度を把握するための指標のひとつです。ここでは、eNPSの意味や調査するときの質問項目について解説します。
eNPSは職場の推奨度を数値化したもの

eNPSとは、自分が働いている職場の推奨度を数値化した指標です。従業員に対して「あなたの職場を知人や友人にどの程度勧めたいですか?」といった質問をし、その回答から職場に対する満足度や愛着、エンゲージメントなどを把握します。
eNPS調査の大きな特徴は、単純に従業員自身の満足度について質問するのではなく、大切な友人や家族に勧めたいかを聞くことです。回答する際、慎重かつ真剣に考えてくれることを期待できるため、従業員の職場に対する気持ちをより正確に把握できます。
eNPS調査における質問項目
eNPS調査を実施するときは、職場の推奨度に関する質問だけではなく、以下のような質問を通して従業員の状況を詳しく把握するとよいでしょう。
- 職場に気軽に話せる同僚はいますか?
- 仕事に関するサポートは受けられますか?
- 仕事を通してキャリアアップできていますか?
- 自分の意見を発信する機会はありますか?
- 仕事のやりがいを感じていますか?
- 評価内容について満足していますか?
どのような質問をすべきかは、調査の目的によっても異なります。まずは、eNPS調査の目的や把握したい項目を明確にしたうえで、適切な質問を選びましょう。
eNPSとNPSの違い
NPSは、顧客満足度を把握するための指標のひとつです。NPS調査では、顧客に対して「自社のブランドを知人や友人にどの程度勧めたいですか?」といった質問をして、その回答を数値化します。
一方のeNPSは、従業員の満足度や自社への愛着を把握するための指標です。NPSから派生した指標ですが、調査対象が異なるため注意しましょう。
eNPS調査と従業員満足度調査の違い
従業員満足度調査とは、仕事のやりがいやモチベーションを把握するための調査です。基本的には従業員自身の気持ちや考え方を把握する調査であり、本音を聞き出すために多くの質問を準備するケースが多いでしょう。
eNPS調査も従業員の気持ちを把握する調査ですが、知人や友人への推奨度を質問するため、安易に高い点数や低い点数を付けにくくなります。従業員満足度調査と比較すると、少ない質問数でも従業員の状態を的確に把握できる調査といえるでしょう。
eNPSの計算方法

eNPSを計算するためには、従業員に対して職場の推奨度を質問し、0〜10の11段階で回答してもらうことが必要です。0点は「まったく勧めたくない」、10点は「とても勧めたい」ことを意味します。
回答が集まったら、0〜6点を批判者、7〜8点を中立者、9〜10点を推奨者と分類しましょう。eNPSは、分類結果から以下の式により算出できます。
eNPS = 推奨者の割合(%)– 批判者の割合(%)
たとえば、推奨者の割合が70%、中立者の割合が20%、批判者の割合が10%だった場合、eNPSは60となります。
eNPSの最大値は100、最小値は–100です。eNPSが高い場合は推奨者が多いことを意味するため、職場環境は比較的良好であると考えられるでしょう。一方でeNPSが低い場合は、仕事に対する満足度や職場への愛着が低下している可能性もあるため、何らかの対策を講じる必要があります。
eNPSの平均スコアはどのくらい?
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が2023年に実施した調査によると、eNPSの平均スコアは「–62.5」でした。この調査は自動車メーカーや銀行など、10業界を対象として実施されており、業界ごとのeNPSは以下の通りです。(※1)
- エネルギー:–64.1
- 銀行:–58.4
- クレジットカード:–70.8
- 航空・トラベル:–60.1
- 自動車メーカー:–59.8
- スーパーマーケット・GMS:–69.8
- 生命保険:–63.6
- 製薬:–55.4
- 損害保険:–66.8
- 通信キャリア:–56.1
eNPSが最も高いのは製薬業界で「–55.4」、逆に最も低いのはクレジットカード業界で「–70.8」という結果でした。すべての業界のeNPSがマイナスとなっていることについて不思議に感じるかもしれませんが、eNPSでは「友人や知人に勧めたいか」という視点で自社を厳しく評価するため、一般的に数値は低くなります。
また、0〜6点という広い範囲を批判者と見なすこと、7〜8点を付けた中立者を計算時に除外することなども、eNPSが低くなる理由といえるでしょう。
eNPSが高い企業のメリット
eNPSを高めるメリットとして、定着率アップや業務効率の向上などが挙げられます。以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.定着率が向上する

eNPSを高めることで、従業員の定着率アップを図ることが可能です。eNPSが高いことは、多くの従業員が友人や家族に勧めたいほど自社に対する愛着をもっていることを意味します。居心地のよい職場環境であると感じている可能性も高く、長く働いてくれることを期待できるでしょう。
逆にeNPSが低い場合、会社に対する愛着や仕事の満足度が低下しているかもしれません。早期に離職してしまう従業員が増える可能性もあるため、何らかの対策が必要です。
2.業務効率がアップする
業務効率がアップすることもeNPSを高めるメリットのひとつです。eNPSが高い場合、多くの従業員が会社に貢献したいと考えており、成果を出そうと積極的に働いてくれる状態といえます。その結果、組織力が高まり、業務の効率や生産性も向上するでしょう。
逆にeNPSが低下すると、従業員のモチベーションや業務効率も下がってしまいます。無駄な残業代が増えたり、利益率が低下したりするケースもあるため、事業を継続的に展開していくうえでもeNPSを高めることは重要です。
3.採用活動がスムーズに進む
eNPSを高めることで、採用活動がスムーズに進むことを期待できます。とくに、従業員から知人を紹介してもらうリファラル採用が効率よく進むようになるでしょう。
リファラル採用の大きなメリットは、自社にマッチした人材と出会いやすいことです。自社の仕事内容や求める人材像をよく知る従業員からの紹介であるため、ミスマッチを防止でき、定着率の向上を図れます。
eNPSを高めておけば、従業員が優秀な人材を積極的に紹介してくれるため、採用活動を効率化できるでしょう。また、自社のよい印象を広めてくれる従業員が増えるため、通常の採用活動における応募者増加にもつながります。
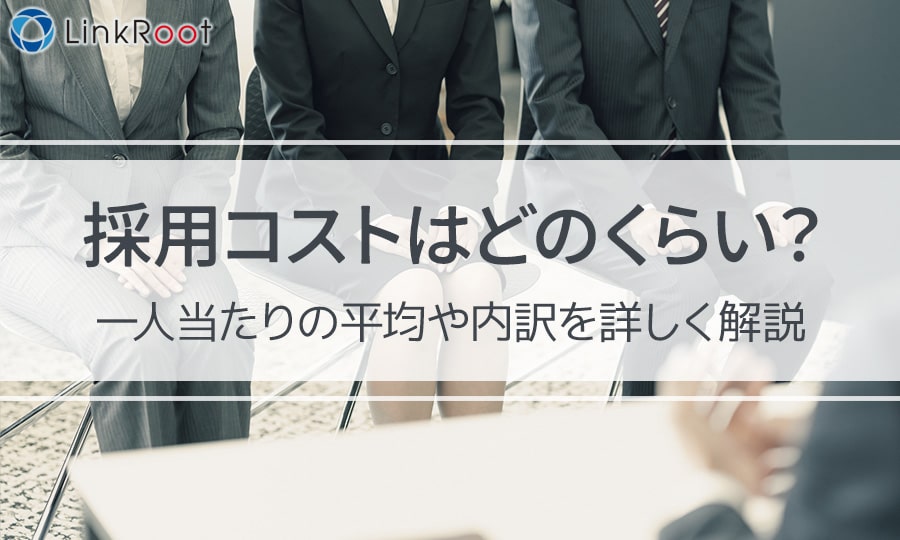
eNPSを測定する手順

eNPSを測定するときは、以下のような手順で進めましょう。
- 調査計画を立案する
- 調査を実施する
- 調査結果を分析する
- eNPSを向上させる施策を検討する
- 定期的に調査を実施する
各手順の詳細は以下のとおりです。
1.調査計画を立案する
まずは、eNPSを測定する目的を明確にしなければなりません。従業員の状況を把握して定着率の悪化を防ぎたいなど、現状の課題をもとに調査の目的を設定しましょう。
目的が明確になったら、調査計画を立案します。具体的には、調査チームの立ち上げ、スケジュール調整、予算の確保、調査ツールの選定、従業員への周知などが必要です。また、調査チーム内で目的を共有し、認識のズレが起きないように配慮しましょう。
2.調査を実施する
準備が整ったら、計画に沿って調査を実施しましょう。従業員に対して「あなたの職場を知人や友人にどの程度勧めたいですか?」という質問をし、点数を付けてもらいます。点数を付けた理由を知りたい場合は、職場環境や給与、評価制度に対する満足度などの質問を追加するとよいでしょう。
調査の進め方としては、紙のアンケート用紙を配布する、メールで回答してもらう、Googleフォームなどのツールを活用する、といった方法が挙げられます。ただし、従業員数が多くなると配布や回収に手間がかかるため、オンラインで質問項目を作成できるツールを利用するのがおすすめです。回収や集計も自動化できるため、効率よく調査を実施できるでしょう。
3.調査結果を分析する
従業員からの回答が集まったら、結果を集計して分析しましょう。先ほど紹介したとおり、批判者・中立者・推奨者の割合を計算してから、eNPSを算出します。eNPSの平均スコアや業界ごとの数値と比較してみると、自社の従業員の状況を把握しやすいでしょう。
また、自社の推奨度以外の質問をした場合は、その結果も集計して分析する必要があります。なぜ自社を推奨できるのか、またはできないのか、さまざまな理由を把握して対策を立案できるケースも多いため、しっかりと分析することが重要です。
4.eNPSを向上させる施策を検討する
eNPSを算出するだけでは意味がないため、結果に合わせて必要な施策を検討しましょう。とくに業界ごとの平均値よりも低かった場合は、従業員が不満を感じていたり、モチベーションが低下していたりする可能性が高いため、適切な対策を講じなければなりません。
eNPSが低い理由を明確にし、調査チームのなかで具体的な改善策を検討していくことが重要です。必要に応じて従業員から意見をヒアリングするなど、追加調査を実施してもよいでしょう。具体的な対策については後ほど詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてください。
5.定期的に調査を実施する
eNPS調査は、定期的に実施することが重要です。eNPSを向上させる取り組みの効果が出ているか、従業員の気持ちに変化があったか、といったポイントを把握するためにも、定期的に実施するとよいでしょう。
期待していたような効果が出ていない場合は、調査結果の分析方法や立案した対策が間違っていた可能性もあります。再度分析を行い、適切な対策に変更していくことが大切です。ただし、あまりに頻繁に調査を実施すると従業員の負担になるため、業務に支障が出ない範囲で行いましょう。
eNPSをうまく測定するためのコツ
eNPS調査をうまく進めるためには、質問項目を追加したり、ターゲットを明確にしたりすることが重要です。以下で詳しく解説しますので、チェックしておきましょう。
1.質問項目を追加する

eNPS調査における質問は、1つだけでも問題ありません。職場の推奨度を測る質問さえ準備しておけば、最低限の調査は実施できるでしょう。ただし、職場を推奨する理由やしない理由についても詳しく分析したい場合は、質問項目を追加するのがおすすめです。
仕事のやりがいや職場の人間関係などに関する質問を準備しておけば、従業員の気持ちや感じ方をより詳しく把握できます。調査を実施する目的に応じて、必要な項目を追加しておきましょう。
とはいえ、質問数が多すぎると回答する従業員の負担が大きくなってしまいます。分析の時間もかかるため、無駄に質問数を増やしすぎないようにすることが大切です。
2.ターゲットを決めて施策を考える
eNPS調査の結果をもとに施策を検討するときは、ターゲットを絞るとよいでしょう。もちろん全従業員を対象に施策を行う方法もありますが、効果が薄くなり、期待していたほどeNPSが向上しないケースもあります。
ターゲットを決めて施策を検討すれば、より大きな効果を期待できます。たとえば、7〜8点を付けた中立者をターゲットにすれば、次回の調査で9〜10点を付けてくれる可能性が高まるでしょう。また、批判者のなかでも5〜6点を付けた従業員をターゲットにすれば、次の調査時には中立者に変わっている可能性もあります。
eNPSを高める方法
最後に、eNPSを高める具体的な方法を紹介します。施策を検討するときの参考にしてください。
1.評価制度を見直す
eNPSを高めるためには、評価制度を見直すことが重要です。とくに、上司の主観で評価される、頑張って成果を出しても待遇に反映されない、といった仕組みになっていると、従業員が不満を感じやすくなります。
評価制度への不満からeNPSが低下するケースもあるため、問題がある場合は制度の見直しを検討してみましょう。たとえば、客観的な評価項目を設定する、評価制度と給与体系を連動させるなどの対策を講じることが大切です。
2.福利厚生を充実させる

福利厚生を充実させることもeNPSの向上に効果があります。福利厚生の導入により、従業員を大切にしていることが伝わるからです。さまざまな福利厚生を取り入れると、従業員の満足度や会社に対する愛着の向上につながります。
住宅手当の支給や社員食堂の設置など、さまざまな福利厚生があるため、予算に合わせて選択しましょう。ただし、従業員のニーズに合っていない福利厚生を導入しても意味がありません。福利厚生を導入するときは、アンケートを取るなど、従業員のニーズを把握したうえで進めることが大切です。
3.働きやすい職場環境を整える
eNPSを高めるためには、働きやすい職場環境を整えることも重要です。たとえば、休憩スペースを設置する、業務効率化につながるシステムを導入するなど、従業員の負担を軽減するような対策を講じると、eNPSが向上するでしょう。
また、テレワークを採用する、フレックスタイム制を導入するなど、多様な働き方を実現することも効果的です。ワークライフバランスを保ちやすい環境を整えることで、従業員の満足度や愛着は高まっていきます。
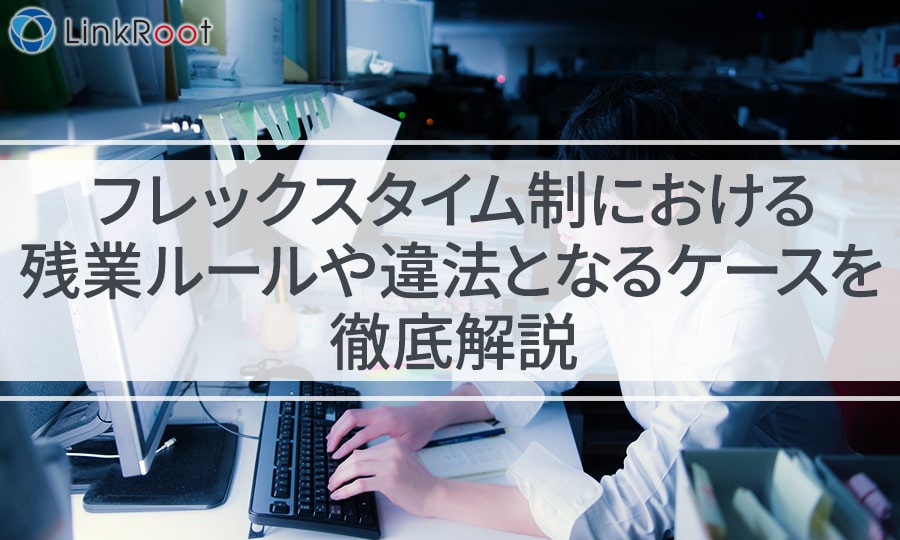
4.会社の目標や理念を共有する
eNPSを向上させるためには、会社の目標や理念を共有することが欠かせません。そもそも従業員にビジョンが浸透していないと、会社への愛着を感じにくくなってしまいます。働く意味を見失い、モチベーションが低下するケースもあるでしょう。朝礼で周知する、ポスターを掲示するなどの方法で、会社のビジョンをしっかりと伝えることが大切です。
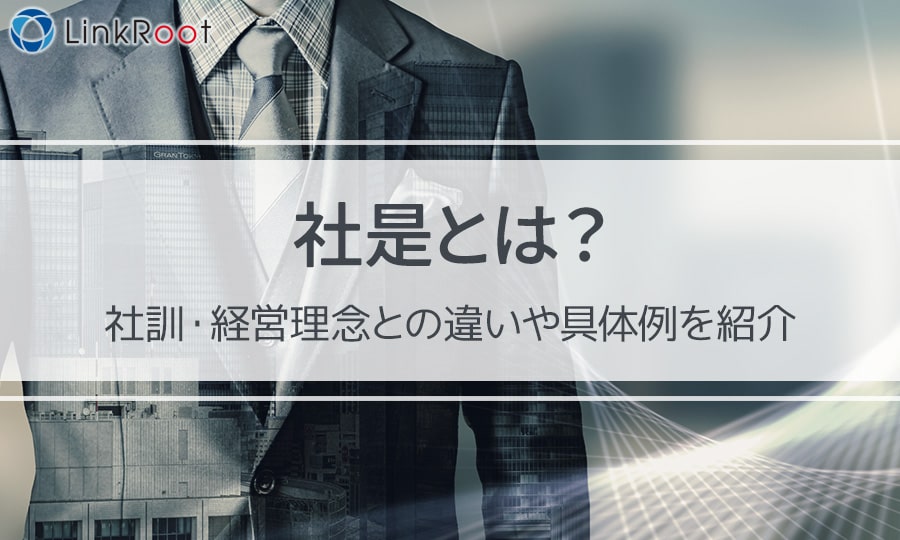
eNPSを測定して必要な対策を検討しよう!
今回は、eNPSの意味や計算方法、高めるための対策などについて解説しました。eNPSを高めることで、定着率の向上や採用活動の効率化を期待できます。会社の推奨度を質問するだけで簡単に測定できるため、従業員の状態を把握したい場合は調査を実施してみましょう。
(※1)NTTコム オンライン「eNPS℠業界別分析レポート」
https://www.nttcoms.com/service/nps/report/employee-engagement-specialreport