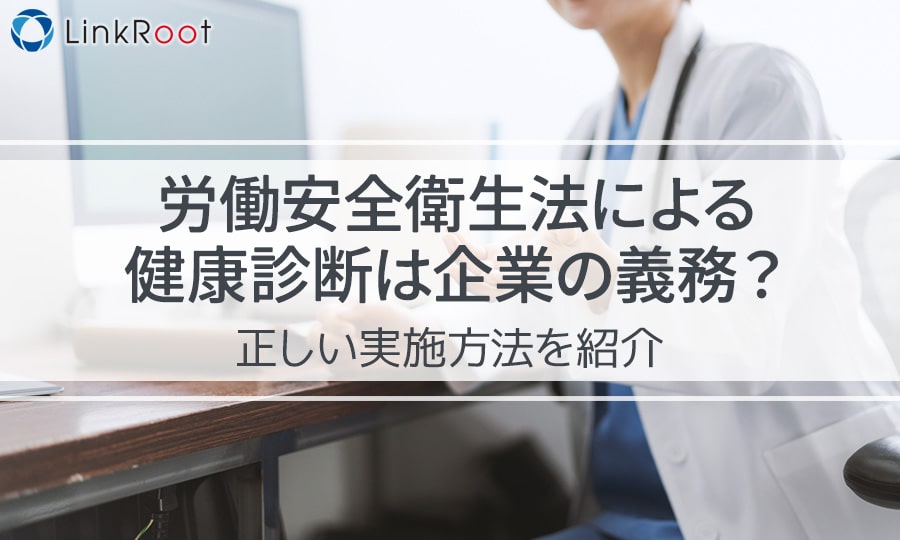大切な従業員に長く働いてもらうため、健康診断を実施することはとても重要です。とはいえ、健康診断を行うことは企業の義務なのか、どのような従業員を対象に実施すればよいのか、理解できていない人も多いでしょう。
そこでこの記事では、労働安全衛生法によって定められた健康診断の実施義務について詳しく解説します。健康診断の種類や対象となる従業員、健康診断を適切に実施するポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
労働安全衛生法による健康診断は企業の義務?
まずは、労働安全衛生法によって定められた健康診断の実施義務について理解しておきましょう。
労働安全衛生法とは?
労働安全衛生法とは、従業員が安全かつ健康に働けるよう、職場環境を整えることを定めた法律です。戦後の劣悪な労働環境を改善するため、1972年に制定されました。
企業は従業員を守るために、労働安全衛生法に従って労働災害の防止に取り組んだり、責任体制を明確化したりしなければなりません。健康診断の実施についても、労働安全衛生法によって定められています。
労働安全衛生法による健康診断は企業の義務

健康診断を実施することは、労働安全衛生法によって定められた企業の義務です。同法の第66条には、企業は従業員に対して医師による健康診断を実施すべきことが記載されています。(※1)[1]
事業規模は関係なく、従業員を雇用しているすべての企業が対象です。従業員がいる場合は、毎年1回の健康診断を必ず実施するようにしましょう。
また、常時50人以上を雇用している企業の場合は、健康診断を実施するだけではなく、その結果を労働基準監督署へ報告しなければなりません。さらに、健康診断の結果を5年間保管しておくことも必要です。健康診断の結果には個人情報が多く含まれているため、漏洩しないようにしっかりと管理しましょう。
健康診断実施の義務に違反したときの罰則
健康診断実施の義務に違反したときは、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。健康診断を実施していない場合や、結果を従業員本人へ通知していない場合は、罰則の対象となるため注意しましょう。罰則を受けるのは、従業員ではなく企業です。従業員の健康を守り、長く活躍してもらうためにも、健康診断を適切に実施しましょう。
労働安全衛生法による健康診断の対象者
企業は労働安全衛生法に従い、常時使用する以下の従業員に健康診断を受けさせる必要があります。
- 正社員
- 契約社員
- 派遣社員
- パート・アルバイト
- 役員
ただし、それぞれ条件が設定されているため確認しておきましょう。
1.正社員

正社員は常時使用する従業員であるため、健康診断の対象となります。年齢や性別などによる例外はないため、全員に一般健康診断を受けさせるようにしましょう。また、特定の有害業務を行う従業員は、特殊健康診断の対象です。健康診断の種類については、後ほど詳しく解説します。
2.契約社員
契約社員の場合、一定の条件を満たすと健康診断の対象となります。具体的には、以下2つの条件を両方とも満たす場合は、健康診断を実施しなければなりません。
- 雇用契約の期間が1年以上である
- 1週間の労働時間が一般従業員の3/4以上である
1つ目の条件には、雇用期間の定めがない場合や、すでに1年以上継続して雇用している場合も含まれます。条件に該当するときは、正社員と同じ健康診断を受けさせましょう。
3.派遣社員
派遣社員も健康診断の対象です。ただし、実施義務があるのは派遣元企業であり、派遣先企業ではありません。派遣先の仕事状況などに配慮しながら、健康診断を受けさせましょう。
粉塵作業や放射線作業など、特定の有害作業を行う場合は、派遣先企業が特殊健康診断を実施する必要があります。
4.パート・アルバイト
パートやアルバイトの従業員も健康診断の対象となります。契約社員と同様、以下2つの条件を満たしている場合は、健康診断を受けさせましょう。
- 雇用契約の期間が1年以上である
- 1週間の労働時間が一般従業員の3/4以上である
5.役員
取締役・会計参与・監査役などの役員は、労働者性の有無によって、健康診断の対象となるかどうかが異なります。代表取締役社長などは労働者性がないと判断されるため、健康診断の対象外です。
一方で、取締役と店長を兼任している場合などは、労働者性があると見なされるため、一般の従業員と同様に健康診断を実施しなければなりません。
労働安全衛生法による健康診断の種類
健康診断には、さまざまな種類があります。それぞれ対象者や実施すべきタイミングが異なるため、しっかりと確認しておきましょう。
1.一般健康診断
一般健康診断には、以下の5つが含まれます。
- 定期健康診断
- 雇入れ時の健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従業員の検便
定期健康診断と雇入れ時の健康診断の対象者は、常時使用する全従業員です。正社員はもちろん、先ほど紹介したように、条件に該当する契約社員やアルバイトなども対象となるため注意しましょう。各健康診断の詳細は以下のとおりです。
定期健康診断
定期健康診断は、1年以内に1回の頻度で実施しなければなりません。検査項目は、労働安全衛生規則(第44条)(※1)[2]にて以下のように定められています。
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
- 胸部エックス線検査・喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
上記の項目のうち、身長・体重の検査や血糖検査などの一部の項目については、医師の判断で省略することが可能です。また、1年以内に受けた項目の一部を省略できるルールもあります。
雇入れ時の健康診断
雇入れ時の健康診断は、労働安全衛生規則(第43条)(※1)[3]に従って、常時使用する従業員を採用するときに実施します。検査項目は、定期健康診断とほぼ同じですが、喀痰検査のみ除外されます。定期健康診断とは異なり、医師の判断で内容を省略することはできません。
また、入社前の3ヶ月以内にすでに健康診断を受けている場合は、その結果を証明する書類を提出してもらうことで検査を省略することが可能です。ただし、指定された検査項目を受けていない場合は、その検査を追加受診させる必要があります。
特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断は、労働安全衛生規則(第45条)(※1)[4]によって規定されています。特定業務とは、深夜業務や坑内業務、高熱物体や重量物を扱う業務など、身体への負担が大きい業務のことです。
特定業務従事者の健康診断は、6ヶ月以内に1回の頻度で実施しなければなりません。また、特定業務へ異動する際にも実施しましょう。検査項目は、定期健康診断と同じです。なお、胸部エックス線検査・喀痰検査については、1年以内に1回で問題ありません。
海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断は、労働安全衛生規則(第45条の2)(※1)[5]によって規定されています。企業は、従業員を海外に6ヶ月以上派遣する際と、帰国した際に健康診断を実施しなければなりません。
検査項目は定期健康診断と同様ですが、医師が必要と判断した場合は、腹部画像検査や血中尿酸値の検査などが追加されるケースもあります。
給食従業員の検便
給食従業員の検便については、労働安全衛生規則(第47条)(※1)[6]に記載されています。給食に関わる従業員を雇い入れる際は、同法に従って検便による健康診断を実施しましょう。
社員食堂のスタッフなども給食従業員に該当します。また、正社員はもちろん、パートやアルバイトも対象となるため注意が必要です。
2.特殊健康診断

特殊健康診断は、特定の有害業務に関わる従業員を対象として実施します。実施頻度は6ヶ月以内に1回です。また、雇い入れ時や配置換え時にも実施しなければなりません。
健康リスクの高い作業に従事する人を守るための健康診断であるため、忘れずに行いましょう。有害業務としては以下のような作業が挙げられます。
- 有機溶剤業務
- 鉛業務
- 粉塵作業
- 高圧室内業務
- 潜水業務
- 放射線作業
- 振動・騒音作業
検査項目は、各有害業務を規定する法律や関連規則によって規定されているため、該当する場合はチェックしておきましょう。
3.じん肺検診
じん肺とは、吸い込んだ粉塵に反応して、肺が変化してしまう病気のことです。じん肺検診は、粉塵を体内に取り込んでしまう可能性が高い従業員を対象として実施します。具体的には、以下のような作業を行う従業員が対象です。
- コンクリートやセメントを扱う建設作業
- 石炭や鉱石の採掘作業
- アスベストを扱う作業
- トンネル掘削
- 解体作業
じん肺検診は、じん肺法(※2)によって義務付けられているため忘れずに実施しましょう。
4.歯科医師による健診
歯科医師による健診は、特定の有害作業を担当する従業員を対象として実施します。具体的には、以下のような作業が対象です。
- 有機溶剤業務
- 鉛業務
- 粉塵作業
化学物質や粉塵に関わる作業は、歯や口腔に大きな影響を与えるため、6ヶ月以内に1回の頻度で健康診断を実施しましょう。
労働安全衛生法の健康診断を正しく実施するためのポイント

健康診断を正しく実施できるよう、以下のようなポイントに注意しましょう。
- 健康診断の費用は企業が負担する
- 健康診断の結果を保管しておく
- 未受診の従業員へ連絡する
- 適切なフォローを行う
各ポイントの詳細は以下のとおりです。
1.健康診断の費用は企業が負担する
健康診断を実施することは企業の義務であるため、その費用は企業が全額負担しなければなりません。社内に担当の医師を招いて実施するか、それぞれの従業員に個別に受けてもらい、領収書を受け取って精算するようにしましょう。
ただし、人間ドックや従業員の希望によるオプション検査などの費用は、企業が負担しなくても問題ありません。
2.健康診断の結果を保管しておく
健康診断の結果は、従業員の了承を得たうえで一定期間保管しておく必要があります。たとえば、定期健康診断の結果については5年間保管しなければなりません。電子データでも紙媒体でも問題ないため、しっかりと管理しておきましょう。
3.未受診の従業員へ連絡する
健康診断を受けていない従業員には、受診を促しましょう。業務が忙しい、健康に対する意識が低いなどの理由で、健康診断を受けようとしない従業員もいます。未受診の従業員に対しては、健康的に長く働いてもらうためにも健康診断の重要性をしっかりと伝え、受診を促すことが大切です。
4.適切なフォローを行う
健康診断の結果に合わせて、適切なフォローを行うことも重要です。健康診断の結果が悪かった従業員に対しては、専門医からリスクを伝えてもらったり、医療機関を紹介したりするとよいでしょう。
また、多くの従業員が不調を感じている場合は、職場環境の見直しが必要かもしれません。残業を減らすような対策を検討する、人員の補充により業務負担を減らすなど、適切な対応を進めましょう。
労働安全衛生法の健康診断を従業員が拒否した場合は?

健康診断を従業員が拒否した場合、まずは受診したくない理由をヒアリングしましょう。そのうえで、企業が健康診断を行うことは義務であることや、健康診断の結果が外部に漏洩することはないことなどを伝えます。健康的に長く活躍してほしいことも伝えるとよいでしょう。
丁寧に説明しても納得してもらえない場合は、懲戒処分を検討します。就業規則の内容をもとに、健康診断を受けないと懲戒処分の対象になることを説明します。
ただし、懲戒処分を実施するためには、事前に就業規則のなかで処分内容などを規定しておかなければなりません。就業規則を無視した対応を行うと、処分が無効となるため注意が必要です。判断に悩む場合は、労働問題に強い弁護士に相談するとよいでしょう。
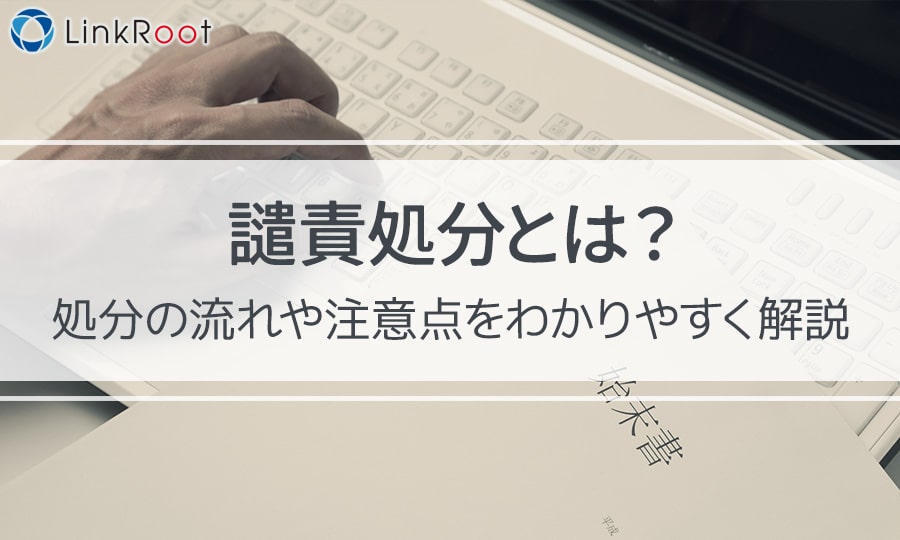
労働安全衛生法に従って正しく健康診断を実施しよう!
今回は、労働安全衛生法によって定められた健康診断について解説しました。条件を満たす従業員に健康診断を受けさせることは企業の義務です。適切に実施しないと罰則の対象となるため注意しましょう。
また、健康診断には、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺検診など、さまざまな種類があります。業種や業務内容によって実施すべき健康診断が異なるため、事前に確認しておきましょう。適切なタイミングで健康診断を実施して、従業員を守ることが大切です。
(※1)e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」第六十六条[1]第四十四条[2]第四十三条[3]第四十五条[4]第四十五条の二[5]第四十七条[6]
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033
(※2)e-GOV法令検索「じん肺法」