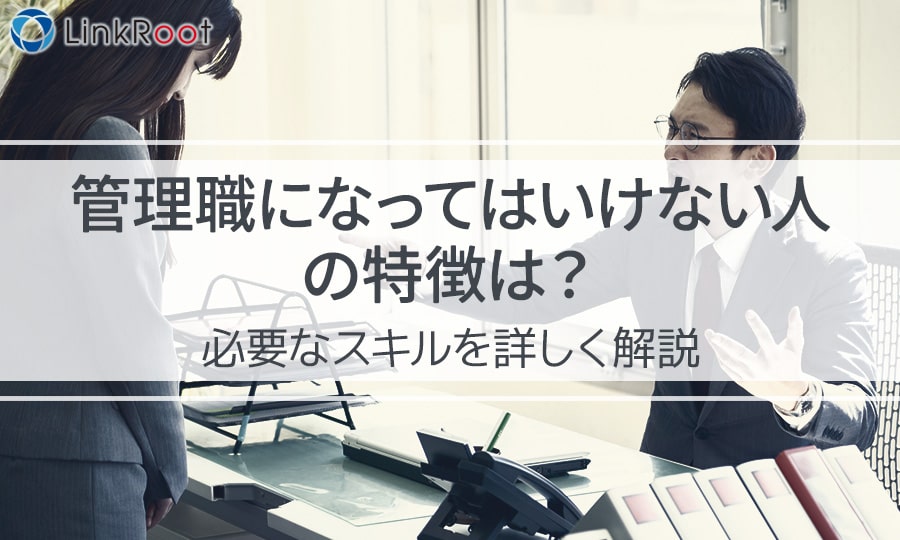どのような人に管理職を任せるべきか、悩むケースも多いでしょう。管理職に向いていない人を任命してしまうと、部下との人間関係が悪化したり、仕事がスムーズに進まなくなったりするため注意が必要です。リーダーシップや指導力など、必要なスキルを保有している人に管理職を任せましょう。
この記事では、管理職になってはいけない人の特徴を詳しく解説します。また、管理職がこなすべき業務内容や、管理職になるために必要なスキルなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
管理職とは?

管理職とは、社内で管理的な業務を担当する従業員のことです。具体的には、部下の指導や作業の進捗管理、人材の採用などを担当します。
役職名は企業によって異なりますが、係長・主任・課長・次長・部長・本部長といった名称が付けられているケースが多いでしょう。また、課長以上を管理職とするのが一般的ですが、絶対的なルールはありません。以下、一般職や役員との違いについて解説します。
管理職と一般職の違い
管理職と一般職の大きな違いは、業務の範囲や評価の対象です。一般職は基本的に与えられた仕事をこなしますが、管理職は一般職へ指示を出したり、経営層とやり取りしたり、幅広い業務を担当します。大きな責任を担っている分、管理職手当が支給されるなど、一般職とは異なる待遇になっているケースが多いでしょう。
また、評価の対象も異なります。一般職の場合、個人のスキルや成果が評価対象ですが、管理職の場合は担当している部署全体の成果が評価対象です。ただし、管理業務と一般作業の両方を担うプレイングマネージャーの場合は、個人と部署の成果が評価対象となります。
管理職と役員の違い
役員とは、経営方針の決定や会計の監査などを行う人のことです。具体的には、会社法で定義されている取締役・会計参与・監査役のほか、専務や常務といった役職も存在します。
管理職と役員の大きな違いは、雇用契約の有無です。役員の場合、雇用契約ではなく任意契約を締結しているため、従業員ではありません。一方の管理職は雇用契約を締結しているため、一般職と同様、従業員に該当します。また役員とは異なり、会社や株主以外の第三者に対して、損賠賠償責任を負う必要はありません。
管理職と管理監督者の違い
管理職と似た言葉として管理監督者がありますが、2つの意味は異なります。管理監督者とは、経営者と同じような立場で業務をこなす従業員のことです。具体的には以下の要件を満たす場合に、管理監督者と見なされます。
- 経営に関わる業務を担当している
- 一般職とは異なる権限と責任を与えられている
- 一般職とは異なる待遇を受けている
- 勤務形態についての裁量が与えられている
管理監督者の定義については、労働基準法の第41条2号に記載されています。(※1)管理監督者に該当する場合は、残業代や休日出勤手当を支払う必要はありません。一方で課長や部長という肩書きがあったとしても、上記の要件を満たしていない場合は管理監督者には該当しないため、一般職と同様に残業代などを支払う必要があります。
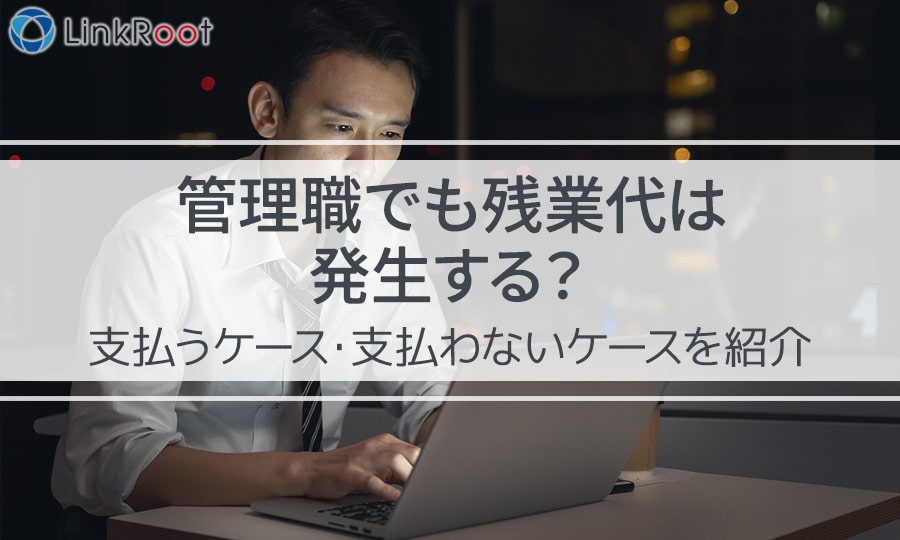
(※1)e-GOV法令検索「労働基準法」第四十一条の二
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_4-At_41_2
管理職を担ってはいけない人の特徴
会社への愛着がない人や自分の利益を優先する人は、管理職には向いていません。また、経営的な視点がないと管理職の業務をこなせないでしょう。具体的には以下のような特徴がある人には、管理職を任せるべきではありません。
1.会社への愛着がない

会社への愛着がなく帰属意識の低い人は、管理職に向いていないでしょう。会社の目標を理解していない、会社に貢献する意思がない、といった人に管理職を任せるのは避けるべきです。
会社の目標やビジョンに共感していない人が管理職になると、進むべき方向が従業員に伝わらず、足並みが乱れてしまいます。管理職のエンゲージメントの低さが従業員にも伝染し、生産性が低下したり離職率が上がったりする可能性もあるでしょう。
2.自分の利益を優先する
自分の利益を優先する人を管理職に任命すべきではありません。会社の利益を無視した行動を取る管理職がいると、損失が大きくなり、事業を展開していけないでしょう。
また、部下の都合や意見を聞かずに、自分が言いたいことばかりを主張するようでは信頼関係を構築できず、組織力が低下してしまいます。他人の意見を無視したり、部下の成果を横取りしたりする人に管理職を任せることは避けましょう。
3.一貫性がない
考えや行動に一貫性がない人も管理職に向いていません。指示内容がコロコロと変わったり、相手によって態度を変えたりするようでは、部下から信頼してもらえないでしょう。
一貫性がなければ、どこに向かっているのかが不明確になってしまい、業務の無駄が増えるケースもあります。組織全体にとってマイナスになるため、一貫した考えをもって前に進める人を管理職に任命すべきです。
4.向上心がない
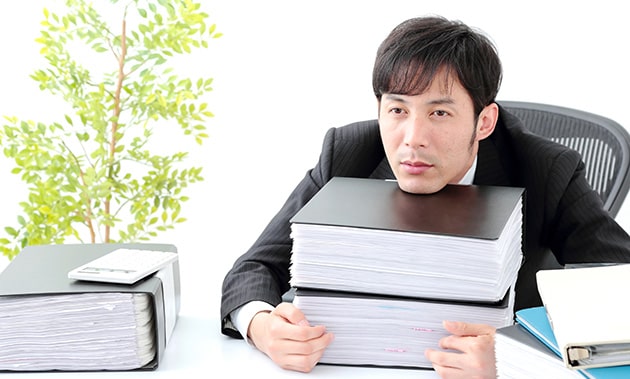
向上心がないことも管理職を担ってはいけない人の特徴です。管理職に昇進すると、自分で仕事をこなす能力だけではなく、部下を指導したり組織全体をマネジメントしたりする能力を身につけなければなりません。
向上心がなく、昇進したことに満足してしまう人には、管理職は務まらないでしょう。向上心がない姿勢は部下にも悪影響を与え、組織全体のモチベーションが低下する可能性もあるため注意が必要です。
5.経営的な視点がない
経営的な視点がない人は、管理職に向かないでしょう。管理職は、経営者と同等の立場で、利益を追求していかなければなりません。市場の変化を分析したり、事業拡大のためのアイデアを出したりする場面も多くあります。
プレーヤーとして優秀だった人が、経営的な視点をもっているとは限りません。自社を取り巻く経済状況を俯瞰的に把握できる人を、管理職に任命しましょう。
6.部下の指導に興味がない
管理職になると、自分の仕事や成長のことだけではなく、部下の指導のことも考えなければなりません。部下に対して適切なアドバイスをしたり、キャリアップを支援したりするのが苦手な人は、管理職に向いていないでしょう。
部下を指導することは簡単ではありません。マネジメント研修を実施するなど、必要に応じて管理職を育成する施策を検討することも大切です。
7.部下に仕事を任せられない
何でも自分でこなそうとしてしまい、部下に仕事を任せられないタイプの人は、管理職に向いていません。管理職になると、部下に仕事を任せながら、必要な指示を出したり、部署全体の進捗状況をチェックしたりする必要があります。
管理職が自分の仕事だけに集中していると、周りが見えなくなり、間違った方向に進んでいってしまう可能性もあります。自分で作業すべき場面もありますが、基本的には部下に仕事を任せつつ、管理職はマネジメントに徹することが重要です。
8.公平な評価ができない
管理職は、部下を公平に評価しなければなりません。管理職の主観で評価してしまうと、低い評価をされた部下が不満を感じてしまうこともあります。好き嫌いで判断することなく、客観的な基準をもとに公平な評価を実施できる人を管理職に任命しましょう。
9.臨機応変な対応ができない
管理職になると、さまざまな状況に対して臨機応変に行動することを求められます。予想外の出来事に対して冷静な判断を下したり、部下の悩みに的確なアドバイスをしたりすることは、管理職の重要な役割です。
臨機応変な対応ができないと、部署全体の動きがストップしてしまう可能性もあります。課題にぶつかっても前に進み続けられるよう、柔軟な対応ができる人を管理職に選ぶことが重要です。
10.感情のコントロールができない
感情のコントロールが苦手な人も管理職に向いていません。管理職は、部署全体の状況を把握し、冷静な判断を下す必要があるからです。
部下のミスに対して感情的に怒鳴ったり、焦って間違った判断をしたりするようでは、管理職は務まらないでしょう。もちろん厳しく指導すべき場面もありますが、感情的に叱責すると、部下のモチベーション低下につながってしまいます。
管理職がこなすべき業務や役割

管理職は、以下のような業務をこなす必要があります。
- 業務の管理
- 部下の指導・教育
- 人材の採用
- 経営層との連携
それぞれの業務について簡単に確認しておきましょう。
1.業務の管理
部署全体の業務管理は、管理職が行うべき重要な業務です。プロジェクトのスケジュールを管理したり、組織目標の達成度を確認したりしながら、従業員全員を導いていかなければなりません。大きなトラブルが発生した場合は先頭に立って解決策を探るなど、常に業務全体を見ておく必要があります。
2.部下の指導・教育
部下の指導や教育も管理職の役割です。従業員ごとの目標を設定し、どのような方法で目標達成を目指すのか、部下と相談しながら決定します。初めて仕事をするような従業員の場合は、作業の進め方を具体的に説明するケースもあるでしょう。
また、仕事の成果や目標の達成度に応じて、部下の評価をする必要もあります。達成できた部分を褒めて伸ばしつつ、達成できなかった部分については適切なフィードバックを行い、成長を促すことが重要です。
3.人材の採用
新しい人材の採用も管理職の業務のひとつです。離職により欠員が出た場合や事業拡大により人員の補充が必要な場合は、人事担当者と連携しながら人材を募集します。
必要なスキルや経験を保有しているか、部署の雰囲気に馴染めそうか、本人のキャリアプランと合っているかなど、さまざまな視点から判断して、採用するかどうかを決定しましょう。
4.経営層との連携
管理職になると、部署内の管理だけではなく、経営層との連携も行わなければなりません。とくに上の役職になると、経営会議に出席したり、経営方針に関する重要な判断を求められたりする場面もあるでしょう。
また、会社のビジョンや経営方針を従業員に伝えることも、管理職の重要な役割です。会社の目標に沿って部署の目標を決めたり、会社が求めるような人材育成に努めたりする必要もあります。
管理職になるために必要なスキル

管理職になるためには、次のようなスキルが必要です。
1.リーダーシップ
管理職は従業員を引っ張っていく立場であるため、リーダーシップが必要です。会社では、さまざまな考え方や価値観をもつ人が働いています。多様化が進んでいるため、幅広い年齢や国籍の従業員を雇っている企業も多いでしょう。管理職がリーダーシップを発揮しなければ、従業員の足並みが乱れてしまい、仕事が進まなくなる可能性もあります。
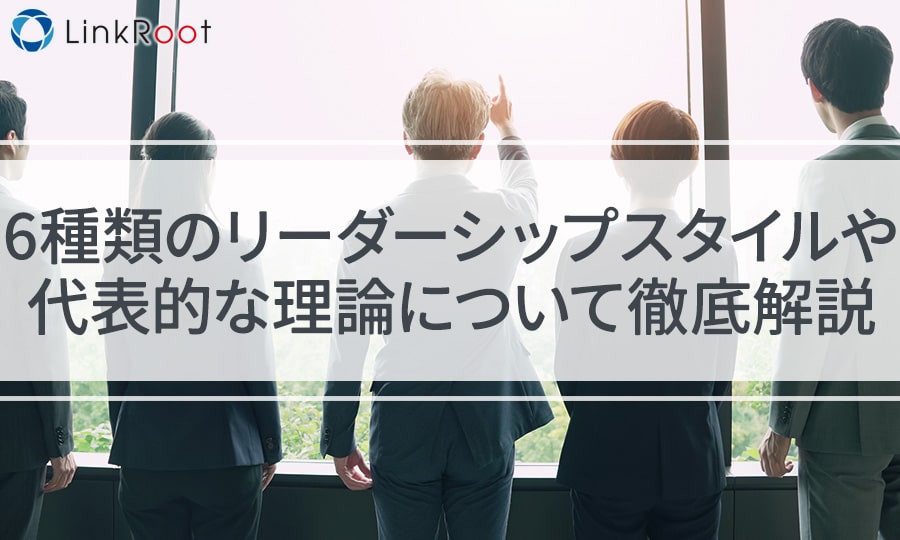
2.指導力
指導力も管理職に求められるスキルのひとつです。管理職は自分の仕事をこなすだけではなく、部下に仕事を割り振り、適切な指導をしなければなりません。
また、目標を達成できるよう適切なアドバイスをしたり、効率よく仕事が進むよう全体をマネジメントしたりすることも必要です。指導力がなければ仕事が遅れ、他の部署やクライアントに迷惑がかかることもあるでしょう。
3.傾聴力
管理職は部下の話を聞く場面が多いため、傾聴力も必要です。部下からの連絡や相談を受け、問題がある場合は的確な指示を出す必要があります。話をしっかりと聞く力がなければ正確な情報を聞き出せず、正しい判断ができないでしょう。また、話を聞いてくれない上司だと思われると、連絡や相談をされなくなってしまいます。
4.自己革新力
自己革新力も管理職に必要な能力です。管理職は部下を引っ張っていくために、マネジメント能力やリーダーシップを身につけなければなりません。また、経営に関わる知識も習得する必要があります。現状に甘んじることなく、常に自分を成長させていく力がなければ、管理職は務まらないでしょう。
管理職になってはいけない人の特徴を把握しておこう!
今回は、管理職になってはいけない人の特徴や、管理職に求められるスキルなどを紹介しました。管理職は、会社のなかで重要な役割を担うことになります。会社への愛着がない人や部下に仕事を任せられない人に、管理職をさせるのは避けるべきです。
また、管理職にはリーダーシップや傾聴力が求められます。管理職を選ぶときは、必要なスキルがあるかどうか、しっかりと見極めることが重要です。管理的なポジションに向いていない人を任命すると、仕事が進まなくなったり、業績が悪化したりするため注意しましょう。