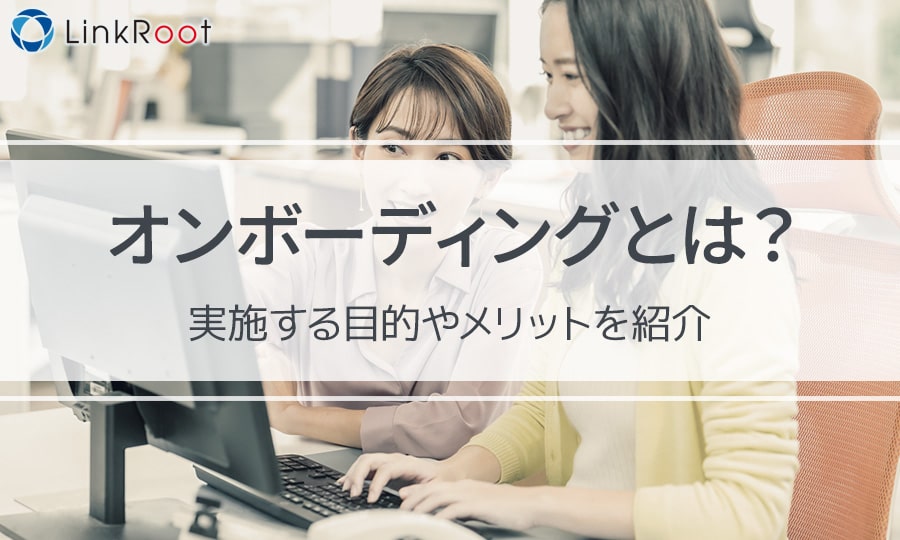新しく入社した従業員にできるだけ早く活躍してもらうため、オンボーディングを実施する企業が増えてきました。オンボーディングをうまく実施すれば、早期離職を防止しつつ、従業員をスムーズに育成することが可能です。
この記事では、オンボーディングの意味や実施する目的、具体的な実施方法などをまとめて解説します。せっかくコストをかけて採用しても定着しない、能力を発揮するまでに時間がかかるなどの悩みを抱えている場合は、ぜひ最後まで読んでみてください。
オンボーディングとは?

オンボーディングとは、新しく会社に入った従業員がスムーズに仕事に馴染めるよう、サポートする取り組みのことです。「on board(乗り物に乗っている状態)」という言葉が由来となっており、会社を乗り物に例え、従業員が乗り込んでいるような状態を示しています。
オンボーディングの大きな目的は、従業員が戦力となるよう早期に育成することです。いくらスキルのある従業員であっても、入社してすぐに活躍できるとは限りません。むしろ社内の人間関係や環境に慣れなければ、能力を発揮することは難しいでしょう。そこで、オンボーディングを通して会社に馴染めるよう支援することで、早期離職を防止しつつ、人材を育成することが重要視されているのです。
オンボーディングとOJTの違い
OJT(On the Job Training:オンザジョブトレーニング)とは、実際の仕事をこなしながら、必要な知識やスキルを習得させる教育方法のことです。主に実務経験のない新入社員や、その業務を初めて担当する従業員を対象として実施されます。先輩社員が作業内容をレクチャーしたり、取引先とのやり取りを見せたりしながら教育するケースが多いでしょう。
オンボーディングとの違いは実施する目的です。オンボーディングは会社に馴染んでもらうことを目的としていますが、OJTは必要なスキルを早期に習得させることを目的としています。同じようなサポートを行うこともありますが、実施する目的が異なることを覚えておきましょう。
オンボーディングとOff-JTの違い
Off-JT(Off the Job Training:オフザジョブトレーニング)とは、通常の仕事から離れて行うセミナーや研修のことです。具体的には、社内・社外の講師が実施する座学や、ほかの従業員とのグループワークなどが挙げられます。新入社員向けのビジネスマナー研修や、中堅社員向けのキャリアアップ研修など、対象となる従業員を選定し、必要なスキルを習得させるケースが多いでしょう。
Off-JTの大きな目的は、OJTと同様、必要な知識やスキルを習得させることです。会社に馴染んでもらうために実施するオンボーディングとは、異なる目的で実施されます。
オンボーディングを実施する目的
オンボーディングは、早期離職の防止や効率的な人事育成を目的として実施されます。また、教育格差の解消にもつながるでしょう。ここでは、オンボーディングを実施する目的について詳しく解説します。
1.早期離職の防止

早期離職を防止することは、オンボーディングを実施する目的のひとつです。厚生労働省の調査によると、令和3年3月に卒業した新入社員の3年以内の離職率は以下のとおりでした。(※1)
- 高卒の新入社員:38.4%
- 大卒の新入社員:34.9%
約3人に1人が3年以内に離職していることがわかります。また同調査によると、事業規模が30人未満の企業では、3年以内の離職率が50%を超えるなど、事業規模が小さくなるほど離職率が高くなるという結果も出ました。
新しい従業員を採用するためには、多額のコストがかかります。卒業したばかりの新入社員がすぐに利益を生んでくれるわけではないため、早期に離職されてしまうと採用コストが無駄になってしまうでしょう。新たに募集する手間がかかったり、離職率が高まることで企業のイメージが低下したりするという問題もあるため、オンボーディングを通して定着率を高めることが重要です。
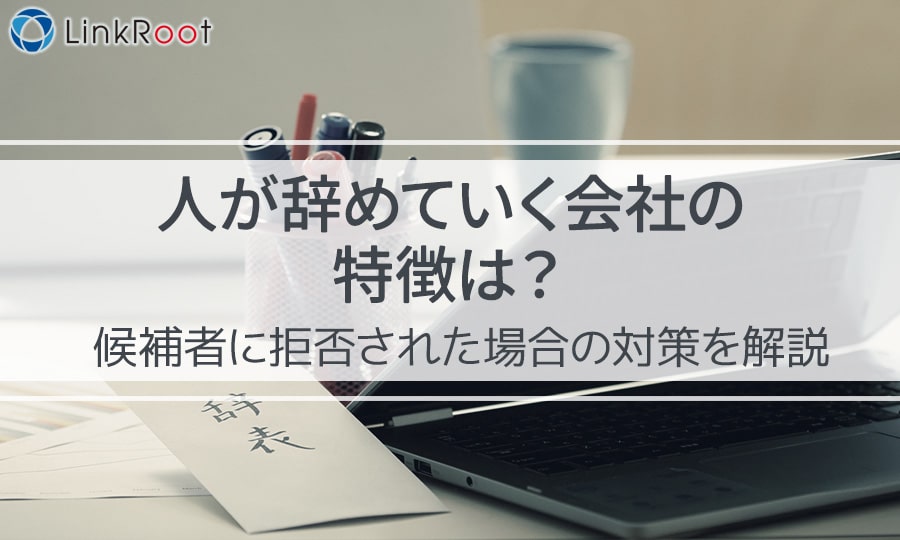
(※1)厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
2.効率的な人材育成
オンボーディングをうまく実施すれば、効率よく人材を育成することが可能です。新しく入社した従業員が自分一人で仕事をこなせるようになるまでには、それなりに時間がかかります。関連する知識や仕事の進め方を学ぶ必要があるのはもちろん、社内のルールや雰囲気、人間関係を知る必要もあるでしょう。
もちろん自分で考える力を身につけさせることも必要ですが、適切なサポートをすることも重要です。教育やサポートをすることが面倒だと感じるかもしれませんが、オンボーディングを通して育成することで早期に独り立ちでき、結果として教育の手間が減るケースも多くあります。
3.教育格差の解消
従業員の教育格差を解消することも、オンボーディングを実施する目的のひとつです。従業員の教育をそれぞれの部署や上司に任せていると、指導内容にバラつきが生じたり、必要なスキルを習得できなかったりするケースもあります。求める知識の獲得やキャリアップが難しくなり、従業員から不満が発生することもあるでしょう。
全社的なオンボーディングを実施すれば、成長するために必要なスキルと知識を体系的に習得できます。必要に応じて集合研修を実施するなど、従業員の成長スピードを揃えたり、遅れている部分をサポートしたりすることが可能です。
オンボーディングを実施するメリット
オンボーディングを実施することには、次のようなメリットがあります。
- 採用コストを削減できる
- 生産性の向上につながる
- 従業員満足度が向上する
- 人材育成施策を一新できる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.採用コストを削減できる
採用コストを削減できることは、オンボーディングを実施する大きなメリットです。従業員を採用するためには、求人サイトを利用して候補者を探したり、書類審査や面接をしたりする必要があり、多くの手間とコストがかかります。前述のとおり、3年程度で離職する従業員も多いため、会社に馴染めるようにサポートしなければ採用コストが無駄になってしまうでしょう。
また、オンボーディングを実施すれば、教育コストを削減することもできます。新卒の従業員はもちろん、中途採用の従業員であっても初期段階のサポートは必要です。コストをかけて入社時研修を行ったり、先輩社員が仕事のサポートをしたりすることも多いでしょう。早期に離職されると教育コストも無駄になってしまうため、定着率を高める対策が重要です。
2.生産性の向上につながる

オンボーディングを実施すれば、生産性の向上を期待できます。従業員が職場環境に馴染めるようサポートすることで、本来の能力を発揮できるようになるからです。
職場環境に馴染めずにいると、コミュニケーションが不足したり、社内のルールを把握できなかったりして、保有している能力を発揮できないケースもあります。オンボーディングを通してすぐに能力を発揮してもらえるよう支援すれば、組織力が強化され、業務効率や生産性が向上するでしょう。
また、早期に戦力として活躍してくれるようになれば、上司や先輩社員が細かく指導する手間を省けます。指導役が自分の仕事に集中できるため、仕事が効率よく進むようになるでしょう。
3.従業員満足度が向上する
オンボーディングを実施することは、従業員満足度の向上にもつながります。従業員満足度とは、職場環境や仕事内容にどのくらい満足しているかを示す指標です。従業員満足度が向上すれば、モチベーションアップや生産性の向上などを期待できます。熱意をもって仕事に取り組むことで、顧客満足度が向上する可能性も高いでしょう。
オンボーディングを通して従業員満足度を向上させるためには、コミュニケーションを活性化させることで人間関係を構築したり、仕事の意義を丁寧に伝えたりすることが重要です。従業員満足度の向上は、定着率アップや採用コストの削減にもつながるため、しっかりと取り組んでいきましょう。
4.人材育成施策を一新できる
人材育成施策を一新できることも、オンボーディングを実施するメリットのひとつです。オンボーディングのなかには、メンター制度の導入、1on1ミーティングの実施、懇親会の開催、相談窓口の設置など、さまざまな施策が含まれます。従来のような新入社員研修の枠に捉われない新しい施策を実施できるでしょう。
また、オンボーディングを実施している企業としてイメージアップを図ることも可能です。入社後のサポートが充実していることで、応募してみようと考える人もいるでしょう。オンボーディングを行っていることを積極的にアピールすることで、優秀な人材確保も期待できます。
オンボーディングを成功させるためのコツ
オンボーディングを成功させるためには、社内の教育体制を整えたり、スモールステップ法を取り入れたりすることが重要です。ここでは、オンボーディングを成功させるためのコツを紹介しますので、チェックしておきましょう。
1.採用担当者と入社予定の従業員の関係性を構築しておく

オンボーディングを行うなら、まず採用担当者と入社する予定の従業員の関係性を構築しておくことが重要です。新しい従業員は、最初に採用担当者と接することになります。採用担当者が窓口となって丁寧に対応することで、従業員が社内に馴染むきっかけになるでしょう。
入社予定の従業員との関係性を構築するためには、従業員が感じている不安を解消したり、疑問に詳しく回答したりすることが重要です。入社までのスケジュールをメールで案内する、先輩社員との交流会を開催するなど、内定後のアフターフォローを徹底しましょう。
2.教育体制を整える
オンボーディングを成功させるためには、社内の教育体制を整えることが欠かせません。配属先の上司や先輩社員はもちろん、人事担当者や研修担当者など、関わる従業員全員で教育に関する情報を共有しておきましょう。
また、リモートワークを実施する予定なら、オンラインで教育できるよう、必要なシステムを整えることも重要です。チャットツールやオンライン会議システムなどを導入し、スムーズに教育できるような環境を整えましょう。ただし、すべてをオンラインで教育するのが難しい場合は、集合研修などを計画する必要があります。
3.スモールステップ法を意識する
オンボーディングをうまく実施するためには、スモールステップ法を取り入れるとよいでしょう。スモールステップ法とは、達成しやすい小さな目標を設定し、少しずつレベルアップを促す教育方法です。
入社したばかりの従業員にとって、大きな目標を達成することは簡単ではありません。売上をアップさせる、新規顧客を獲得する、といった大きな目標を設定すると、達成することが難しくモチベーションが低下してしまう可能性もあります。アポイントを獲得する、営業資料を作成するなどの小さな目標からスタートし、少しずつ大きな目標達成を目指すとよいでしょう。
4.教育方法に関する研修を実施する
教育方法に関する研修を実施することも重要です。オンボーディングを実施しようとしても、具体的な手順や効果的な方法を把握できていないケースもあります。効率のよい指導方法や従業員との適切なコミュニケーション方法がわからないケースも多いでしょう。
せっかく手間とコストをかけてオンボーディングを実施するなら、正しい知識を習得しておくことが大切です。必要に応じて外部の研修を利用するなどして、教育方法について学んでおきましょう。
5.入社前後のギャップを解消する
入社前後のギャップ解消を図ることも、オンボーディングを成功させるポイントのひとつです。入社前後のギャップが大きいと、従業員の早期離職につながってしまいます。
仕事内容や役割などについて、入社前に聞いていた情報と入社後の状態が異なっていると、期待とのズレが大きくなってしまうでしょう。入社してもらいたいという気持ちから、よい情報ばかりを伝えてしまいがちですが、ギャップが大きくなりすぎないよう正しい内容を伝えておくことが大切です。
6.全社的に実施する
オンボーディングを取り入れるなら、特定の部署やチームに限定するのではなく、全社的に実施しましょう。教育格差の解消がオンボーディングの目的のひとつだからです。全従業員を対象として実施することで、平等にキャリアアップを支援でき、不公平感を解消することができるでしょう。
オンボーディングの実施手順を5ステップで解説

オンボーディングを実施するときは、以下のような手順で進めましょう。
1.目標を設定する
まずは従業員が目指すべき方向性や、習得すべきスキルなどを明確にします。目標は所属する部署によっても異なるでしょう。全従業員が共通して習得すべき内容と、部署ごとに習得すべき内容を把握しておくことが大切です。
2.目標達成までのスケジュールを組む
最終的な目標が明確になったら、達成するまでのスケジュールを組みます。1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後など、短い期間ごとに小さな目標を設定しておけば、成長を確認しやすいでしょう。また、全体研修や1on1ミーティングを実施する場合は、タイミングを明確にしておくことが重要です。
3.サポート体制を構築する
従業員をサポートする体制を整えましょう。オンボーディングを成功させるためには、周囲のサポートが欠かせません。採用担当者はもちろん、所属する部署の上司や先輩社員などにも協力してもらえるよう体制を構築しておきましょう。また、メンター制度を導入する場合は、適切な担当者を選ぶ必要があります。
4.教育を実施する
準備が整ったら教育を実施します。早期に仕事に慣れてもらえるよう、適切な指導やアドバイスをしていきましょう。一方的に指示するだけではなく、従業員が感じている疑問や不安をヒアリングすることも大切です。悩んでいることがある場合は、一緒に解決策を考えていきます。
5.振り返りを行う
一通りの教育が終了したら、振り返りを行いましょう。指導内容やサポートは適切であったか振り返ることで、仕組みを改善することが可能です。従業員本人や関わった担当者の意見も聞きながら、仕組みをブラッシュアップしていきましょう。
オンボーディングを実施して従業員の定着率を高めよう!
今回は、オンボーディングの意味や実施する目的、具体的な実施手順などについて解説しました。オンボーディングをうまく行えば、職場環境にスムーズに馴染んでもらえるだけではなく、従業員満足度や定着率の向上を期待できます。離職率が低下することで、採用コストの削減にもつながるでしょう。
オンボーディングを実施するときは、明確な目標を設定したうえで、サポート体制を構築することが重要です。上司や先輩社員の協力を得ることでオンボーディングの効果が高まるため、関係者をうまく巻き込んでいきましょう。