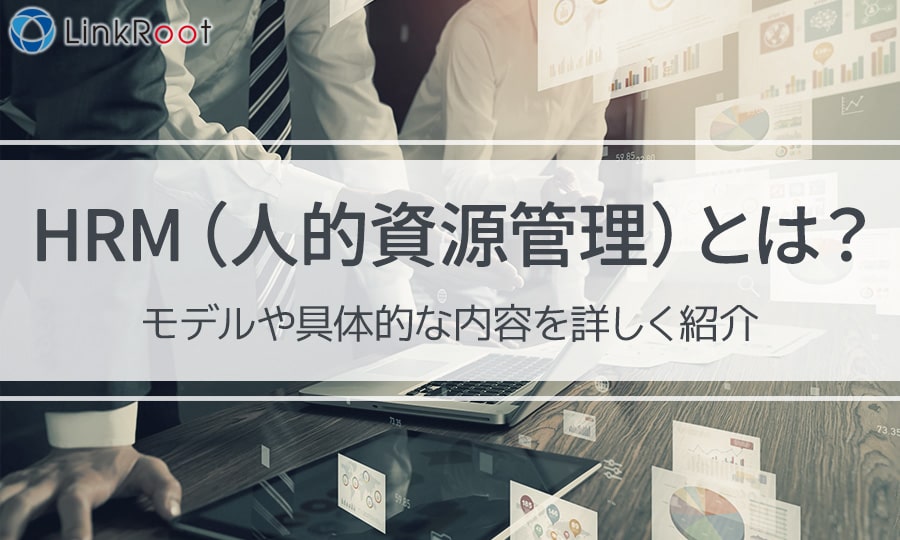組織力強化や目標達成のために、HRM(人的資源管理)に力を入れる企業が増えてきました。HRMは、単なる人事労務管理とは異なります。HRMを通して人材を採用したり、効率よく育成したりすることで、組織のパフォーマンスを向上できるでしょう。
この記事では、HRMの意味や目的、代表的なモデルや具体的な内容などを紹介します。HRMを実施して従業員を有効活用し、目標達成や事業の拡大を図りたい場合は、ぜひ参考にしてください。
HRM(人的資源管理)とは?

HRM(Human Resource Management)とは、従業員を大切な資産と捉え、成果を最大化するために有効活用していく取り組みのことです。日本語では、人的資源管理などと訳されます。
具体的には、人材を育成したり人事配置を最適化したりしながら、組織としての目標達成や事業の拡大を目指します。金(カネ)や物(モノ)だけではなく、人(ヒト)を資産として捉えて大切に扱うことで、結果として大きな利益につながるでしょう。
HRMとPMの違い
PM(Personal Management)とは、従業員に関する情報を管理して、統制していく取り組みのことです。日本語では人事労務管理などと呼ばれ、具体的には勤怠情報を管理することや給与計算を行うことなどが挙げられます。
HRMにおける業務内容と似ている部分もありますが、PMの大きな特徴は、従業員を資産ではなくコストや労働力と捉えることです。PMにおいては、従業員は手間をかけて管理・統制する対象であり、効率よく労働させて事業を展開することに注力します。従業員の育成やモチベーションアップを重視するHRMとは、異なる概念といえるでしょう。
人的資源と人的資本の違い
人的資源と似た言葉として、人的資本があります。人的資源とは、カネ・モノ・情報と同じように、ヒトを重要な経営資源と捉える考え方です。
一方の人的資本とは、ヒトが保有している知識やスキル、経験などを指します。両者の意味は異なりますが、従業員を教育することで人的資本の価値が高まり、大切な人的資源として活用できるなど、関連性は高いといえるでしょう。
HRMと組織マネジメントの違い
組織マネジメントとは、カネ・モノ・ヒト・情報という経営資源をうまく活用して、組織を運営していくことです。会社の予算を管理することや、在庫を把握しながら販売することなど、さまざまな業務が含まれます。経営資源のなかのヒトだけを対象とするHRMとは異なり、幅広い対象について把握して活用することが求められます。
HRMとミクロマネジメントの違い
ミクロマネジメントとは、リーダーがメンバーの仕事内容やスケジュールを細かく確認して指示を出す管理手法です。作業の抜け漏れやスケジュールの遅れを防止することにつながりますが、過干渉によりモチベーションが低下する可能性もあるでしょう。
一方のHRMにおいては、メンバーの育成やモチベーションアップに注力します。もちろん、仕事内容を確認したり指示を出したりする場面もありますが、メンバーの主体性を引き出せるようサポートすることを重視します。
HRMとセルフマネジメントの違い
セルフマネジメントとは、自分自身で仕事の進捗状況やモチベーションを管理することです。メンバーの積極性の向上を期待できますが、壁にぶつかりやすく、成長の限界を感じることも多いでしょう。
HRMにおいては、セルフマネジメントを基本としながらも、適切なサポートを行います。必要に応じてコミュニケーションを取ることで、良好な関係を築きながら成長を促せるでしょう。
HRMが重要視されている理由
近年、多くの企業がHRMに注目し、人材を有効活用しようとしています。HRMに注目が集まっている理由は以下のとおりです。
1.少子高齢化による労働力不足が進んでいるため

少子高齢化による労働力不足が進んでいることは、HRMが重要視されている理由のひとつです。日本の人口は減少傾向を辿っており、2040年には総人口の35%が65歳以上、14歳以下はわずか10%になると推移されています。(※1)
人材の確保が難しくなっているなか、企業は少ない人数で大きな成果を出さなければなりません。
時代遅れの人材育成や人事評価を行っていると、ライバル企業と戦っていけないでしょう。また、従業員が不満を感じて転職してしまう可能性もあります。そこでHRMを通して従業員を大切に育て、定着させようとする企業が増えてきたのです。
(※1)厚生労働省「我が国の人口について」人口の推移、人口構造の変化
2.従業員のキャリアを形成するため
従業員のキャリアを形成するために、HRMに力を入れている企業もあります。従業員により活躍してもらううえでは、キャリアアップを支援することが欠かせません。
また、キャリアアップをサポートすることは、従業員のエンゲージメントや定着率の向上につながります。適切なHRMを行うことで、従業員を育成しつつ離職を防止できるでしょう。
HRMにおける代表的な5つのモデル
HRMには、さまざまなモデルが存在します。ここでは、代表的な5つのモデルを紹介しますのでチェックしておきましょう。
1.ハーバード・グループのモデル

ハーバード・グループのモデルは、1980年代にハーバード大学で実施された研究をもとにしたHRMのモデルです。このモデルのなかでは、HRMを主導するのはトップマネジメントであるとされています。つまり、経営層が中心となって従業員を育成したり、職場環境の改善を図ったりするのです。
また、ハーバード・グループのモデルは以下4つの要素で構成されています。
- 従業員への影響:従業員の意見を聞き、信頼関係を構築する
- 人的資源のフロー:人材のスキルを把握し、将来性を考えながら育成する
- 報酬システム:モチベーションを維持できるような報酬制度や福利厚生を整える
- 職務システム:自発的に行動できるような職場環境を整える
4つの要素の相乗効果によって、従業員のモチベーションアップや生産性の向上を図っていきます。
2.ミシガン・グループのモデル
ミシガン・グループのモデルは、1980年代にミシガン大学で実施された研究をもとにしたHRMのモデルです。このモデルでは、経営方針に沿って人材採用や人事評価、人材育成などを進めていきます。企業の目標を達成するために必要な人材を選抜するなど、計画的な採用・育成を行うことが大きな特徴といえるでしょう。
ミシガン・グループのモデルでは、以下4つの機能をうまく回すことを考えます。
- 採用と選抜
- 人材評価
- 人材開発
- 報酬
ミシガン・グループのモデルを取り入れることで、生産性の向上や計画的な目標達成を期待できます。ただし、経営方針を重視するあまり、従業員のキャリアアップや個人の目標を軽視してしまう可能性もあるため注意しましょう。
3.高業績HRM(PIRK理論)
高業績HRMは、大きな成果を出している企業が採用しているHRMの総称です。PIRK理論は高業績HRMのひとつであり、従業員のモチベーションを高めるために多くの企業で採用されています。
PIRK理論の大きな特徴は、以下4つの要素に注目して従業員のモチベーションや帰属意識を高めることです。
- P:Power(権限の委譲)
- I:Information(情報の共有)
- R:Reward(公平な報酬)
- K:Knowledge(従業員の知識)
権限を委譲したり情報を共有したりすることで、従業員の主体性を高め、業績アップを狙います。また、公平な報酬制度を設計することで、評価に対する納得感や組織への帰属意識が高まるでしょう。
4.高業績HRM(AMO理論)
AMO理論も高業績HRMのひとつです。AMO理論では、以下3つの要素を高めることを目的としています。
- A:Ability(能力)
- M:Motivation(意欲)
- O:Opportunity(機会)
教育や研修、仕事をするうえでのアドバイスなどを通じて、従業員の能力やモチベーションを高めます。さまざまな場面でスキルアップの機会を提供することで、従業員の意欲や帰属意識が高まるでしょう。
5.タレントマネジメント
タレントマネジメントとは、従業員がもつスキルや経験を重要な資産であると考え、有効活用しようとする取り組みのことです。従業員の基本情報はもちろん、能力や資格、得意分野などの情報を一元管理して、人事配置や人材育成の最適化を目指します。タレントマネジメントをうまく進めることで適材適所を実現でき、少ない人数での目標達成を図れるでしょう。
HRMの具体的な内容
HRMの具体的な内容は以下のとおりです。
- 人材を有効活用する
- 人材を育成する
- 組織目標の達成を目指す
- 心理的契約を形成する
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
1.人材を有効活用する

HRMでは、人材を有効活用して組織体制を強化していきます。人材を有効活用するためには、それぞれが保有するスキルや経験などの情報を把握しなければなりません。人材に関するさまざまな情報を集約することで、適材適所を実現したり、不足している人材を新規採用したりできるでしょう。
多くの人材の情報を効率よく管理するために、人事管理システムを導入する企業も増えてきました。人事管理システムを導入すれば、人材ごとの基本属性はもちろん、スキルや保有資格などの情報を一元管理できます。会社全体で情報を共有できるため、人材の有効活用にもつながるでしょう。
2.人材を育成する
人材を育成することもHRMの重要な役割のひとつです。多くの人材を採用したとしても、すぐに活躍してくれるとは限りません。とくに新入社員の場合は、自分で仕事をこなせるようになるまでに時間がかかるでしょう。実務経験のある中途採用社員であっても、自社の仕事に慣れるまでにはそれなりに時間がかかります。
組織を成長させるためには、研修やOJTを通して、採用した人材を育成することが重要です。また、人材ごとのキャリアプランを明確にし、新しい経験ができるようにサポートしていく必要もあります。
3.組織目標の達成を目指す
組織目標の達成を目指すことは、HRMの最終的な目的といえるでしょう。ここまで紹介したような、人材活用や人材育成によって組織力を強化し、売上アップや事業の拡大などを狙います。
HRMを実施することで目標達成を目指す場合、自社に合ったスタイルで進めることが重要です。前述のとおり、ハーバードモデルやミシガンモデルなど、さまざまなスタイルがありますが、自社に合っていなければ意味がありません。目指すべき方向や自社の業種などに合わせて最適な方法を選びましょう。
4.心理的契約を形成する
心理的契約を形成することもHRMの重要な役割です。心理的契約とは、会社と従業員の信頼関係や絆などを意味します。雇用契約などの形式的な関係性を超え、心のつながりを強化することで、従業員のエンゲージメントや定着率の向上を期待できるでしょう。
HRMを通して心理的契約を形成するためには、従業員の意見をヒアリングしたり、働きやすい職場環境を構築したりすることが大切です。また、キャリアアップをサポートすることやコミュニケーションの場を増やすことも心理的契約の形成につながります。
HRMをうまく実施するためのポイント
HRMをうまく実施するためには、従業員個人の事情に配慮したり、多様性を認めたりしながら、協調的な関係を構築することが重要です。ここでは、HRMを実施するときのポイントを紹介します。
1.従業員個人の事情に配慮する

HRMをうまく実施するためには、できる限り従業員個人の事情に配慮しなければなりません。もちろん職場の秩序を維持するために就業規則などに従わせることは大切ですが、個人の事情を無視して同じように働かせることは避けましょう。
たとえば、育児や介護などの都合で長時間勤務ができない従業員に対しては、短時間勤務や在宅勤務など、継続的に働けるような配慮をすべきです。個人の事情に合わせて働けるような仕組みを整えることで、優秀な人材の流出防止やエンゲージメントの向上につながります。
2.多様性を認める
従業員の多様性を認めることも重要です。労働力を確保するために、外国人や障がい者、高齢者など、さまざまな従業員を採用している企業も多いでしょう。年齢や国籍が異なれば、当然、仕事や生活に関する価値観も異なります。
会社の価値観を押し付けたり、従業員同士で価値観を否定したりすると、気持ちよく働けず離職者が増えてしまうでしょう。すべての従業員が同じ気持ちで働いているわけではないため、違いを認め合えるような雰囲気をつくることが大切です。
3.組織と従業員の協調的な関係を構築する
組織と従業員の関係は、協調的なものでなければなりません。組織が一方的に従業員を管理するような仕組みでは、協調的な関係は構築できないでしょう。従業員の不満を聞いて制度を改善したり、福利厚生を充実させたりするなど、対等な関係性になるよう努力することが重要です。
HRMを重視している企業の事例

ここでは、HRMを重視している企業の事例を紹介します。HRMを成功させたい場合は、ぜひ参考にしてください。
1.日産自動車
日産自動車では、グローバルな人材マネジメントや日本人ビジネスリーダーの育成に力を入れています。事業がグローバル化していることを背景として、さまざまな人材を採用し、配置を最適化することで、グループ全体のパフォーマンスを最大化することを目指しています。
また、日本人の後継者が不足してきたことから、国内のビジネスリーダー育成にも注力するようになりました。さまざまな視点から社内の課題を把握することで、HRMをうまく進めています。
2.日立製作所
日立製作所でもHRMを重視して、人材を有効活用しています。日立製作所におけるHRMの大きな特徴は、仕事のやりがいや誇りを感じられるような職場環境を目指していることです。また、価値観を尊重し合えるような雰囲気をつくり、モチベーションの向上を図っています。
具体的な施策としては、リーダー層の育成やジョブ型人財マネジメントなどが挙げられます。ジョブ型人財マネジメントにおいては、職務記述書に従って仕事を進めるため、専門スキルをもつ従業員を育成することが可能です。
3.セブン&アイグループ
セブン&アイグループでは、従業員を会社の大切な資産と考え、育成や評価を行っています。同社におけるHRMの特徴は、従業員ごとの「目標管理カルテ」を作成して、目標や今後の課題を共有することです。
具体的には、従業員のスキルや経験を把握して、上司と一緒に項目ごとのレベルを評価します。目標の設定や達成状況の確認を定期的に実施することで、従業員のモチベーション維持やスキルアップを図っているのです。
HRMをうまく実施して従業員を有効活用しよう!
今回は、HRMの意味やPMとの違い、うまく実施するためのポイントなどを紹介しました。少子高齢化による労働力不足が進むなか、HRMを実施して従業員を有効活用することが重要視されています。人材育成や人事配置を最適化することで組織のパフォーマンスを高めていきましょう。
また、HRMにはハーバードモデルやミシガンモデルなど、さまざまなスタイルがあります。それぞれ特徴が異なるため、自社に合ったスタイルを選ぶことが重要です。他社の事例や従業員の意見なども参考にしながら、HRMをうまく進めていきましょう。